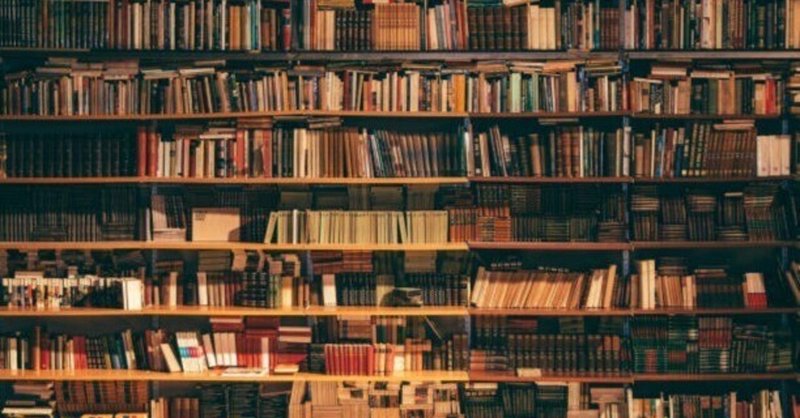
【ソリ死タ雑談】「辞書」について
どうも、ソリ死タです。
今日は箸休めに、「辞書」について少し語るぞコノヤロー!
1.「辞書オタク」、ソリ死タ。
唐突だが、ワシは自他ともに認める辞書オタクだ。
「何を言っているんだコイツ?」と思っただろうか。
だが、本当だ。 ワシは辞書オタクなのだ。
広辞苑は第4版から全部そろえているし、新明解・岩波・三省堂の三大辞書は、特装版やマイナーチェンジ含め、計56冊が本棚にある。
こう書くとコレクターのように見えるが、そうではない。
辞書を読むことが好きなのである。
辞書を「あ」から「わ」まで読むことが楽しくて仕方ない。
改版時に、語釈が変わっているものなどを見つけると幸せで仕方ない。
「どう変えた?」「なぜ変えた?」「背景は?」など、考察する。
時間を忘れるくらい、没頭してしまう。
この話を聞いて「生理的に無理だ」と思った方。
すまない、この話は忘れてくれ。
ちょっとでも興味関心が湧いた方。
少しだけ、この話に付き合ってほしい。
2.塾講師時代の、とある思い出
こう見えてワシは昔、学習塾でアルバイトをしていた。
国語の先生としてだいたい週5コマくらい集団授業を担当していたのだ。
これがまた楽しくて、今まで関わった仕事の中で、最ものめり込んだ記憶がある。
12月のある日。
同じ校舎で仕事をする国語科講師(社員)とワシ(バイト)の間で、生徒におススメする「辞書」について小議論があった。
「新明解国語辞典ってね、説明が長ったるいでしょ。あれがいけ好かんくてね、まだ岩波のほうが・・・」という、”国語科を専門にする講師”の言葉。
その言葉に「作り手の魂の発現たる語釈を『長ったるい』の一言をもって処断するのはなんたる狼藉か」とワシが食いついたのが原因である。
当時自分がレギュラーで勤務する校舎(3校舎)には、生徒への語彙感覚の教授という目的のため、三大辞書(新明解・三省堂・岩波)を置くようにしていた。(その実、ワシ自身が辞書オタクであり、”仕事中に気になった言葉をとことん調べられる環境がない事がストレス”という身勝手な理由で私物を置かせていただいていた。当然ほぼ”塾のもの”という扱いではあるが。)
情けないことに、受験直前期にもかかわらず、最高学年を担当に持つ講師を生徒の面前で散々に批判し、年末特訓国語科チーフたる相手講師の威信を見事失墜させるに至ってしまった運びである。
というのは全くの嘘で、(村上龍風)実際は上記のように食いつきたくなる気持ちをわが胸中でグッと押さえ込み、岩波の丁度よさについて自分からも賛辞の意見を述べるにとどまった。
(後に生徒に聞いたところによると、『相当イラついた顔をしていた』との事なので大分顔色には出ていたようだが)
3.辞書は「生きた語釈」の集合
さて、本題であるが、皆さんは辞書について如何なるイメージをお持ちであろうか。
「普遍的な語釈を述べるにとどまる、つまらない本」
「『辞書的』という言葉の如き、言葉の内実を反映しようとしない堅苦しいもの」
「どれも同じような内容が書かれた、甲斐無いもの」
こういった所だろうか。
残念ながら、それは全て間違いだ。
いろいろな辞書を手にとってみれば分かるが、辞書とは主幹含め編者たちの独特な語彙感覚・偏見・経験、そういった人間臭い部分を色濃く反映する「生きた」語釈に溢れるものなのである。
その権化たるのが「新明解国語辞典」(←超オススメ)だ。
2024年現在で第8版になるこの辞書は、主幹山田忠雄氏を筆頭とした色濃い編者たちによって編まれた、(改訂を重ねるごとにノーマルにはなりつつも)非常にユニークかつ情熱的で、「立った語釈」をすることで有名な辞書である。
ワシも中学生から愛用している。
例えば、新明解の「立った語釈」の代表とされるのが第4版の「動物園」だ。ご覧になられたい。
【動物園】
:生態を公衆に見せ、かたわら保護を加えるためと称し、捕らえて来た多くの鳥獣・魚虫などに対し、狭い空間での生活を余儀なくし、飼い殺しにする、人間中心の施設。
いかがだろうか。
この語釈を見たのち、高村光太郎の「ぼろぼろな駝鳥」という詩を読んで滂沱の涙を流した中学時代の思い出は今なお鮮明に焼き付いている。
(『ぼろぼろな駝鳥』高村光太郎:http://www.design.kyushu-u.ac.jp/~tomotari/boroborona.html )
その他、第7版での「恋愛」についてはどうだろうか。
【恋愛】
:特定の異性に対して他の全てを犠牲にしても悔い無いと思い込むような愛情をいだき、常に相手のことを思っては、二人だけでいたい、二人だけの世界を分かち合いたいと願い、それがかなえられたと言っては喜び、ちょっとでも疑念が生じれば不安になるといった状態に身を置くこと。
4.言葉は『鏡』
いかがだろう?
既に少しなりとも辞書に興味の湧いてきた方もおられるのではなかろうか。
語釈とは、「要するにどういうことか」などといった薄っぺらいものでは無い。
当然、明鏡や岩波といった、簡潔かつ普遍的な語釈こそ辞書の本髄(『辞書は言葉の鑑たれ』)という理念に基づいたものもあるが、言葉は時代・社会・文化を映し取る、(言葉を借りるのであれば)『鏡』でもあるのである。
そして「鏡」としての言葉の使い手たらねばならない我々は、あまりにも言葉に興味がなさすぎるのではあるまいか。(国語科の教員が上記のような台詞を言いだす始末である)
振り返ってみてほしい。
何でもかんでも「ヤバい」で済ませていないか?
そんな言葉の使い方をしていたら、いつか本当に「ヤバい」ものを見た時、それをどんな言葉で表現すればいいのか分からないだろう。
5.辞書読もうぜ!
人生の中で、たった「1回きり」しか使わない言葉も、きっとあるだろう。
その「1回きり」が必要な場面に出くわした時、その言葉が出てくるかどうかで、人生の深みは大きく変わると、ワシは今も信じている。
自信を持って言える。
皆、辞書を読もう!!
さあ、岩波・三省堂・明鏡・旺文社・例解・現代新国語・・・なんでも構わない。
できれば新明解が良い。
一回の飲み会を諦め、3000円を握りしめて自分の辞書を探す旅に出てみてもらいたい。
そこに、多くの人間が出会うことなく一生を終えていくであろう日本語の奥深さを知る入り口があるのだから。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
