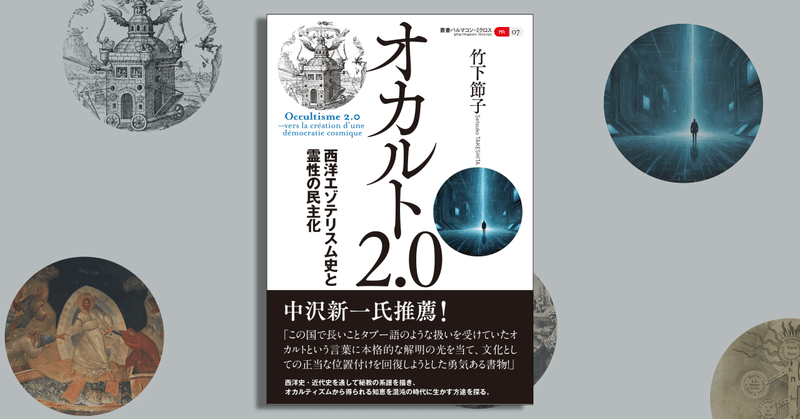
冒頭を無料公開! 竹下節子著『オカルト2.0 西洋エゾテリスム史と霊性の民主化』
中沢新一氏推薦
「この国で長いことタブー語のような扱いを受けていたオカルトという言葉に本格的な解明の光を当て、文化としての正当な位置付けを回復しようとした勇気ある書物!」
メスメルとパラケルスス、エリファス・レヴィとルネ・ゲノンとユリウス・エヴォラ、「ヘルメス文書」とキリスト教、神智学とエニアグラム、エサレン研究所とシュタイナー……。
パリ在住の文明史家が秘教の歴史をたどり、欧米のオカルティズム最新事情を考察を交えてレポートする書籍『オカルト2.0 西洋エゾテリスム史と霊性の民主化』が2024年4月に刊行予定。
刊行に先立ち、本書の「まえがき」を無料公開いたします。
まえがき
私たちの生きている二一世紀は、「近代」が進むべき道を示していた方位磁石が失われた時代だ。二〇世紀の世界大戦と冷戦が一応の終結を遂げた後の世界は、西洋中心の価値観が相対化されたポスト・モダンの時代に入ったといわれていた。非キリスト教文化圏の社会でも、「文明化」が進まない社会でも、それぞれの価値観や習慣を捨てずに「多様性」の名のもとに共生できるという期待が生まれたのだ。けれどもそれは長く続かなかった。経済と資本の力による国境を越えた覇権主義が近代国家や市民社会が立つ基盤を崩したからだ。ポスト・モダンが称揚した自由な「個人」の自己実現といった幻想はかき消されることになった。
その現実を「レトロピア」と分析した社会学者ジグムント・バウマン(一九二五‐二〇一七)の慧眼のことを今さらながら考える。バウマンは「レトロピア」より前に、「リキッド・モダニティ(液状化した社会)」という概念を提唱していた。近代社会では、たとえさまざまな改革や変革によって上にある「建物」が変わろうとも、基盤になる地殻は堅固だったのに、今やその地殻が流動化してもう建物を支えきれないという意味だ。
進歩主義のモダンという高層建築も、ポスト・モダンの多様な集落や一軒家も、同時に足場を失う。世界全体がまさに「液状化」するかのようであり、その中では社会現象を読み解いたり予測したりすることがどんどん複雑で困難になっていった。
その心もとなさを抱えた社会で顕著になってきた傾向をバウマンは「レトロピア」と呼ぶ。トマス・モアの「ユートピア」が理想社会に託す夢という形で五〇〇年も続いてきたのが近代のユートピアだったのに、それがいつしか「未来への帰還(バック・トゥ・ザ・フューチャー)」の流れへと変わっていった。進歩と成長のリレー競争であった西洋近代の「歴史」が少しずつグローバル化した末に社会がノスタルジーへと向かうようになったからだ。
テクノロジーが加速的に進歩するので、人々は、身につけたスキルの市場価値が近い将来に奪われていくと恐れるようになった。安定した身分や階級への帰属感が薄まり、将来の生活の保証も持てないので、先進国の親たちは子供の未来に悲観的になっている。こうして、ユートピアに託される「最終的な完成」という発想がもはや維持できなくなった時、一種の防衛機制として、過去を憧憬し、修正し、承認し、吸収し、組み入れて志向するものとして出現したものが「レトロピア」と呼ばれる。
レトロピアが集合的記憶を持つコミュニティへの憧れを反映しているといっても、実際の民族や国家に根差した復古的なコミュニティだけではない。世界中の民族や部族神話の神々、怪物、勇者から、天使や悪魔や宇宙人までを自由に取り入れた「メタバース」そのものが、もはや新しいノスタルジー共有の場となっている。そうやって、歴史的・文化的・科学的整合性などを問題にしない世界に慣れるうちに、それまで宗教の縛りが比較的強かった社会でも、逆に合理主義が徹底した社会でも、いつのまにか「体制」の建前から自由な「多神教的ゾーン」が生まれていた。
これは新しい形の「オカルト」だ。隠れた世界、裏の世界のオカルトが、レトロピア文化における選択肢の一つとして「表」と隣り合うことになった。
例えば、ピラミッドは宇宙人によって創られたという説を信じるという人がいても、それは「魂の不死を信じる」というタイプの信じ方とは違って、「生き方」とは関係がない。「真理」と「現実性」「実用性」が乖離しているからだ。そのようなレトロピア現象は、ある時は「退行」であって、ある時は液状化した社会におけるレジリエンス(適応の知恵)だともいえるだろう。
家族共同体や地域共同体の縛りがなくなった状況で暮らす世代であれば、たとえ現実が「ひきこもり」状態でも、ヴァーチャル世界のアバター(分身)としてのアイデンティティで十分な満足感を得ることがある。スマートフォンの登場によって、情報へのアクセスだけは「民主化」しているからだ。
といっても、レトロピアであろうとなかろうと、「多様な生き方」をする個人が有機的に連帯して平和で建設的に共生できるというポスト・モダン幻想はすでに潰えている。現実に増大するのは、一部の強者が富や権力を求める欲望ばかりで、地球上で、搾取、争い、テロ、犯罪、憎悪などがやむことはない。
そんな世界で、二〇二〇年はじめに、突如として起こったパンデミー(パンデミック)によって、非現実的な隔離、閉鎖が先進国で広く強制されるという出来事があった。移動を含む「経済活動」の多くが停止し、その期間、人々は一種のメタバースが現実に展開するのを目の当たりにすることになった。
幹線道路は閑散とし、観光地にも繁華街にも人が途絶え、大気や水は澄み渡り、静かな町で鳥がさえずり小動物が現れる姿が次々とスクリーンに映し出された。「現実感」が揺さぶられる異界映像が広く共有されることになった。同時に、目に見えないウィルスの恐怖が煽られ、「専門家」による「予言」が修正され続ける出口の見えない不安の中で、自分や地球の未来や将来、運命を知りたいという若者たちが増えたことは不思議ではない。
ヴァーチャルなゲームによって現実逃避をしたり、無数のインフルエンサーらが発信するその場限りの気晴らしを消費したりという日々は、液状化したモダニティで揺らぐ建物どころか、個人がばらばらに流されて溺れていくかのようなものになった。そんな時期に、ともかくも、非対面・非接触のコミュニケーションを実現するコンタクトレス・テクノロジーを通して、自分や世界の未来を志向しようという人々が増えてきたのだ。
オカルトの世界はすでにゲームやアニメやライトノベルなどで消費されていたが、パンデミーの先の見えない闇の中で一筋の光を求めて手探りをしようとする人々にとっては、オカルトこそが、「忘れられた宗教」、「失われた精神世界」への無意識の郷愁と穴を埋めるものとなっていった。それが「オカルト2・0」だ。
時代の空気が、富と力による支配か、逃避・省略・回避・無関心か、という二つに分かれつつある中で、オカルトへの感性は単なる非合理性への回帰ではない。液状化する足場にしがみつくのではなく、共に見上げることのできる空、個人の枠を超えた居場所を「神秘」に求める動きだ。平時に「共通の大義」を模索するのは容易ではない。パンデミーという「共通の不安」から出発して初めて他者と協働する可能性が探られたことになる。
それだけではない。パンデミー下で孤独や鬱や葬儀、法事の欠如など、さまざまな問題が出てくることで、霊性の欠如が意識されるようになった。家族に会えぬまま亡くなった高齢者や家族を看取ることができなかった人たちが、今まで忘れていた「死」を前に、古来続いていた霊的な直観、「あの世」とのつながりを新たに取り戻そうとしている。
若者のオカルト2・0だけではなく、順境においては「健康長寿」や「遺産相続」などの「終活」ばかりに目が向いていた高齢者自身の意識も変わらざるを得なくなった。一人ひとりが時間と金をかけて「心と体」をマネージメントすればいいと信じていた人々に、「魂」のレトロピアが見えてきた。
ヴァーチャルなメタバースの中でだけ完結するオカルトではなく、魂のレトロピアを通じて実存的な不安から抜け出さない限り、本当の平和は訪れない。どんなに「科学や合理主義」が進歩しても、争いはなくならないしエスカレートさえすると歴史が教えてくれる。
そこから逃避するためにスポーツや暴力やアルコールやドラッグなどへと向かうのが一時的であり解決にならないこともわかっている。既成の宗教や哲学の歴史を敢えて迂回することで、今のオカルトの可能性を問う意義は看過できない。
本書ではその可能性を探るために、秘伝的・難解・深遠だと思われてきた秘教エゾテリスムの歴史を紐解く。
プロローグでは、ブラジルでのSBNR(spiritual but not religious)やエコフェミニズムの問題点に注目しながら、キリスト教文化圏で、「スピリチュアリティ=霊性」について歴史的な変動が起こっていることを見ていく。
第1章では、フランスでの修道院ブームやインフルエンサーの観察を通して、アングロサクソン世界とフランスのオカルトの変遷をたどる。また「カルト的逸脱行為関係省庁警戒対策本部(MIVILUDES/以下、「カルト的逸脱行為警戒対策本部」とする)」の取り組みなどを紹介することで、フランスの「オカルト2・0」現象を明確にする。
第2章では、動物磁気療法で名を成したフランツ・アントン・メスメルとフリーメイスンやイルミナティ、フランス革命とのつながりを紹介しながら、科学とオカルトのはざまで戦い、成功と転落の両方を体験したメスメルの足跡をたどる。
第3章では、ヘルメス文書やフィチーノの新プラトン主義、パラケルススと錬金術・占星術、神智学とエニアグラム、パーマカルチャーとエリファス・レヴィとルネ・ゲノン、魔女とフェミニズムなどを取り上げ、西洋におけるオカルトの歴史を簡単にたどりながら、オカルト2・0について考察を続ける。
第4章では人文科学における「複雑系」のパラダイム転換が、脱構築の「多様性」にあり、ポスト・モダンの相対主義は、今や科学・技術・工学・数学の教育分野まで影響を与えていることを見た上で、その中で脈打つスピリチュアリティにおいて、神やオカルトの占める位置を探り続けることの意味を考える。
さらに終章では、ルネ・ゲノンとユリウス・エヴォラがばらばらだった非西洋の秘教やオカルトを、人類学的な普遍に統合しようとしたこと、西洋と日本でどんな新しいオカルトが生まれたかを紹介し、「オカルト2・0とは何か」という結論に向けて議論を進める。
また第1~3章の後にコラムを挟んでいる。コラムでは著者がパリで開かれているオカルト見本市「パラプシー」を定点観測することで見えてきたフランスのオカルト事情の変化、日本の占い師とのやりとりの中で感じたことなどを綴っているので、気軽に読んでもらえたらと思う。
今のオカルトが秘めているのは「可塑性」だ。一時はカルトやオカルト、超常現象という扱いを受けていた心霊現象なども、二一世紀の最新科学ではすべて「あり得る」ことだとされつつある(超心理学や量子力学などの研究を参照)。オカルトからいったん「離陸」したはずの近代科学が自らの「知の限界」を知ってから、再びオカルトに接近したり、オカルトにインスパイアされたり、オカルトと協働したりする経過を概観する。
また、西洋キリスト教文化圏といっても、ローマ・ギリシャ文化圏に生まれたカトリック世界と、宗教改革で分離したプロテスタント世界、新大陸に渡ったピューリタン世界、共和国主義と政教分離の国、立憲君主国など多様な歴史と文化がある。そこで、それぞれの中でオカルトがどのように醸成したかを観察する。それを踏まえることで、日本の伝統文化とサブカルチャーの間でオカルトがどのように受容され変化したのかが見えてくるだろう。
複眼的な視点なしには、オカルト2・0を「希望」に結びつけて語ることは不可能だ。それは「今、ここ」の不安の解消でもないし、線的な「未来」における欲望達成の「期待」でもない。個々の時や空間を超えて、人と自然が共に育んでいる「全体」を内的に生きる「希望」こそを、オカルト2・0に託してみたい。

●目次
まえがき
プロローグ SBNRとエコフェミニズム
SBNRと「自分仕様」のアマルガム
スーパーノヴァ現象とグノーシス
エコフェミニズムの問題点
第1章 フランス型個人主義とエゾテリスム
仏教と修道院
インフルエンサーとフランス型個人主義
アングロサクソン世界とフランスのオカルトの変遷と比較
ルルドの奇跡とオカルト「探究者」
フランスのカルト的逸脱行為警戒対策本部のスタンス
フランスにおける「エゾテリスム」の定義
コラム1 フランスのオカルト事情の定点観測を始めた理由
パリのパラプシー
「見ただけでわかる」天性の占い師
マダム・Mのタロットカード
第2章 メスメルの磁気療法とオカルトの転換点
今も生き残るメスメルのマグネタイザー療法
メスメルとアウエンブルッガーとパラケルスス
メスメルとイルミナティとモーツァルト
メスメルは癒すのは「手」だと悟った
サウジアラビアの「手当て」療法
ホルカ男爵との出会い
盲目の天才ピアニスト、パラディス嬢の治療
パリでのメスメルとオルバック男爵
ついに治療が成功
ユニヴァーサル・ハーモニー協会
メスメルの転落と神秘主義
メスメルとラ・ファイエットとフランス革命
フランスとドイツのメスメリズム
メスメリズムとMr.マリック
メスメリズムと音楽療法
コラム2 占い師のセラピー効果
笑ってしまう陳腐な答え
サービス業だからセラピー効果がほしい
占い師との「相性」
第3章 西洋オカルト史とオカルト2・0
「ヘルメス文書」とキリスト教
科学とオカルトとエゾテリスム
パラケルススと錬金術・占星術
神智学とエニアグラム
エサレン研究所とシュタイナーとバイオ・エコロジー
パーマカルチャーとエリファス・レヴィとルネ・ゲノン
魔女とフェミニズムとオカルト
オカルトやエゾテリスムから「秘密」がなくなった
コラム3 コーチングから霊媒へ――パラプシーの最新状況
パラプシーに増えた「コーチング」
霊媒に亡くなった友人について聞いてみた
第4章 科学史・科学哲学とオカルト
「科学」が「謎」「ミステリー・ゾーン」を認め始めた
「神の存在」を再度証明しようとしたボロレとボナシー
なぜ聖母出現の奇跡に注目すべきか
ミステールをオカルトから回収する試み
認知神経科学とマインドフルネス
ポスト・モダンは「モダン」の基準を取り払った
クーンの「パラダイム・シフト」理論
ソーカル事件とライン博士の転向
第二のソーカル事件とポスト・「ポスト・モダン」
医師の父親とシャーマンの息子
終章 オカルト2・0総論
ルネ・ゲノンとユリウス・エヴォラ
日本と西洋の「新しいオカルト」
オカルト2・0はアート
あとがき
[著]竹下 節子(タケシタ セツコ)
比較文化史家・バロック音楽奏者。東京大学大学院比較文学比較文化専攻修士課程修了。同博士課程、パリ大学比較文学博士課程を経て、高等研究所でカトリック史、エゾテリスム史を修める。著書に『陰謀論にダマされるな!』(ベスト新書)、『大人のためのスピリチュアル「超」入門』(中央公論新社)、『フリーメイスン もうひとつの近代史』(講談社)、共著に『コンスピリチュアリティ入門 スピリチュアルな人は陰謀論を信じやすいか』など多数。
