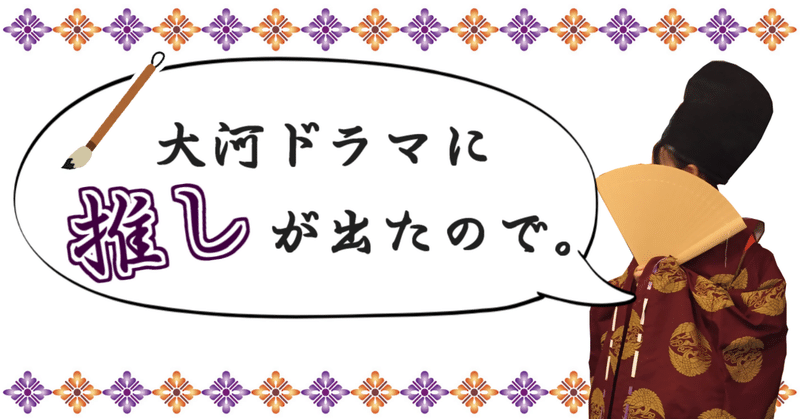
推し、奉職す。(確定)✿第18回|実咲
祝・藤原行成、蔵人頭就任!!!!!!!!
長い実質的な無職期間を経て、無事に行成が蔵人頭へ任官されました。
ここから本格的に、行成の実務派官僚としての道のりがスタートします。
つまり社畜ならぬ宮畜、まさに馬車馬のように休みなく走り続けることになります。
死なないで行成! たまには休んで! 休めないか! ごめん!!
さて、この行成の蔵人頭への任官は、前回でもお話ししたように道長の義兄である源俊賢の後任としてでした。
若手貴族のエリートコースの登竜門というべきポジション。
祖父も父も早くに亡くし後見の手薄な行成は、このエスカレーターに乗るにはなんとも心もとないポジションにいました。
そこへ来てのこの蔵人頭への任官は、文字通り大抜擢と言っていいものでした。
この時代を描いた歴史物語『大鏡』にはこの行成の任官について、つぎのようなエピソードを載せています。
俊賢が参議に昇進する予定になった時、一条天皇が「後任は誰がいいだろうか?」と問いました。
すると俊賢は、「行成がよいでしょう」と推薦します。
一条天皇は、当時の行成が備後権介でしかなく、すこし身分などが足りてないのでは、と躊躇しました。
しかし、俊賢はさらに後押し。
「行成はとても貴重な人物です。位が低くても気にする必要はございません。陛下に末永くお仕えする力量を備えています。あれほど優れた人物を登用しないことは、世のためにもなりません。陛下が君主として物事の道理をわかっているからこそ、皆も心を尽くしてお仕えするというものです。この機会に行成を登用しないのは、大きな損失です」
一条天皇はその言葉に背中を押されたのか、行成は蔵人頭へ任じられたとのことです。
当時の慣例ではありえない大抜擢だったらしく、蔵人頭として参内した行成に驚いて、「我こそは次の蔵人頭!」と思っていた人などは茫然自失だったとも書かれています。
行成は俊賢が推挙してくれた恩を生涯忘れず、自分の位が俊賢を越えた際にも上座には決して座らなかったとか。
どうしても同席する必要がある場合は、向かい合わせに座ったそうです。
さて、蔵人頭が参議へ続くステップの最初であることはお伝えしてきました。
そもそも、「貴族」や「公卿」とは何の事か。いささかいまさらかもしれませんが、今回初めてこの連載を読まれる方もいると思いますので、ここで一度おさらいしておこうと思います。
当時、朝廷に仕える人たちは「位階」をそれぞれ持っていました。「位」ということもあります。
これは地位や身分の序列や等級をあらわすものでした。
一位から八位まであり、さらにその中でも「正>従」、「上>下」という順番がありました。
この「光る君へ」第19話の段階で例えば行成は「従四位下」の位階を持っています。
これは、「従四位上」の下、「正五位上」の上になります。
そして、自分が持っている位階によって、就くことのできる官職が決まっています。
たとえば自衛隊のトップである統合幕僚長になるには、陸将・海将・空将いずれかの位階に達していなくてはならないのと似た話です。
現代でも、社内の等級が上がっていないと上の役職に就けない場合がある企業もあるでしょう。
第19話の中で、まひろ(紫式部)の父為時が「自分は六位だから越前(現在の福井県)の国司(県知事)にはなれない」と言っていたのはこのことです。
それが急に為時は従五位下に任じられます。
これは、為時が後に国司に任じられる越前国は大国というランクになっていて、この大国の国司に相当する官位を先に叙されたということです。
この、六位と五位というのは、たった数字ひとつの違いながら、現実の貴族社会では、天と地の程のとてつもない大きな差がありました。
そもそも、「貴族」と呼ばれるのは従五位下以上の位を持つ者のことを指します。
じつは、為時はそれまで「貴族」ではなかったのです。
前回お話しした蔵人など天皇に直接接する職種の者以外は、基本的に天皇の住まいである清涼殿に行くことはできません 。
そして、特別に清涼殿に昇ること(昇殿)を許された者のことを「殿上人」と呼ぶのですが、殿上人になるのは三位以上(自動的)と四位・五位(許可された場合のみ)となっています。
殿上人のことを、「雲上人」と呼ぶこともある反面、昇殿できない五位より低い位のものを「地下人」と呼ぶのです。(字面がすごい)
為時が長年苦難の末やっと五位にたどり着きましたが、道長のような上級貴族の子弟は元服(成人)した瞬間に従五位下からスタートです。
生まれた環境ですでに決まってしまうのが、この平安京という場所なのです。
また、「公家」という言葉もじつは明確に対象者が決まっています。
さらに位階が上の、三位以上のことを「公卿」と呼びます。
三位ではなくとも、公卿会議に参加できる参議以上も含みます。
中世以降、家の役割が固定化され三位以上になるには決まった家の者だけになります。
そのため、代々三位に昇る家という意味で「公家」という言葉が次第に一般的になるのです。
書いた人:実咲
某大学文学部史学科で日本史を専攻したアラサー社会人。
平安時代が人生最長の推しジャンル。
推しが千年前に亡くなっており誕生日も不明なため、命日を記念日とするしかないタイプのオタク。
