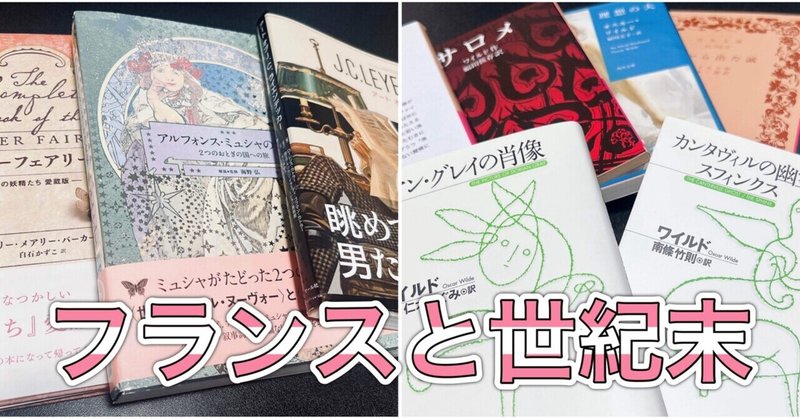
フランスと世紀末[原神][趣味]
芸術界の世紀末「アール・ヌーヴォー」
私が好きなゲーム「原神」には、
幾何学模様が多いアール・デコなデザインの国「フォンテーヌ」が登場します。

だけど、フォンテーヌという国全体のストーリーモチーフは、どちらかといえばアール・デコよりも少し前の、アール・ヌーヴォーやそれ以前の時代が多いというちょっとした矛盾があります。
キャラクターのモチーフも考察していくと全体的に18世紀末から19世紀末当たりが多いです。

恐らくフォンテーヌという国が他の国よりも先進的で明るいというイメージを持たせるために、退廃的なアール・ヌーヴォーは採用されなかったんだろうな…と思う今日この頃。
アール・デコが幾何学模様多めで人工的なのに対し、アール・ヌーヴォーはどことなく退廃的だったり、植物多めで自然なデザインになっています。
私はアール・ヌーヴォーのような植物多めで自然を混ぜ込んだ絵を描く画家が結構好きなので、アール・ヌーヴォーなフォンテーヌも見たかったなぁと思ったり…。
アール・ヌーヴォーの代表というかトップと言えば、私の中ではミュシャ(1860-1939)が上がります。

アール・ヌーヴォーというわけではないと思うけど、同じ感じでシシリー・メアリー・バーカー(1895-1973)も好きです。
シシリーは挿絵画家で植物の妖精を描いたことで有名。
私はパリ留学の際にミュシャに影響を受けたというJ・C・ライエンデッカー(1874-1951)もかなり好き。

ライエンデッカーはミュシャに色々手助けされる形で絵を学んだらしい。
両者ともに当時は商業的な画家だと批判を受けたそうだけど、今でも人気があるという点を踏まえると、時代をある意味先取りした画家と言えるかもしれないですね。

この3人の画集やポストカードを集めていて、暇さえあればいつも眺めています。
シシリーはイギリス人、ミュシャはチェコ人(フランスで活躍したけど)、ライエンデッカーはアメリカ人(フランス留学経験あり)。
画家たちの遍歴を見ていると、やっぱり産業革命でどれだけイギリスの影響が凄かろうと、芸術の最先端はフランスだったんだな…と思う日々。
文学界の世紀末「デカダンス」
文学でよく19世紀末の退廃的な作品をデカダン派といいます。デカダンスdécadenceもフランス語です。
技術の進歩が目覚しい時代ではありましたが、その一方で道徳的な退廃、社会のこれまでの文化・遺産の退廃が嘆かれた時代でもありました。
このデカダンスの根源には古代ローマの繁栄と表裏一体だった道徳的な衰退が手本としてあるようです。
フランスだけではなく、イギリスや他の国でも技術の進歩とその裏側の退廃に関する話が出ています。私が好きなコナン映画(ベイカー街の亡霊)で哀ちゃんがこんなセリフを言います。
「世紀末のロンドンは大英帝国最後の最もよき時代だったと言われているけど、実際は貧富の差が激しくて、犯罪は悪質化し、人々の心がすさんでいった時代よ。」
まさにそう。技術は進歩したけど、本当に人々の生活がよくなり、社会全体として前進していたかと聞かれるとかなりあやしい時代です。
そうした1種の衰退を描いたデカダン派が私は好きです。
以前から私は一番好きな作家としてアイルランド人のオスカー・ワイルドの名前をあげています。
(この時期のアイルランドはイギリスとの関係が複雑でした。オスカー・ワイルドはイギリス文学に分類されがちです。後、芸術の最先端・フランスのパリにも文学の勉強のために滞在しています。)
オスカー・ワイルドのドリアン・グレイの肖像とか、幸福な王子とか、切なげでどちらかといえば退廃的な作品が特に胸に刺さります。

オスカー・ワイルド(1854-1900)も文学界では世紀末文学のトップを走っていたとよく言われていますね。
なんとライエンデッカーもオスカー・ワイルドを愛読していたらしいので、オスカー・ワイルド好きの私がライエンデッカーの作風に惹かれるのも必然なのかもしれないです…。
世紀末やデカダンスという括りから少し外れますが19世紀の文学の流行と言えばなにがあげられるでしょうか。
貧富の差の産物とも言える「孤児小説」や貧しい人に焦点を当てた作品、
科学的なものがどんどん発明されたことによる半分科学・半分ファンタジーな「SF小説」、宗教からの脱却として科学的な思考が問われる「推理小説」などがあがるような気がします。
孤児小説といえばディケンズ(イギリス)やH・マロ(フランス)などの大家が挙げられますし、
孤児に限らず貧しい人に焦点を当てたといえばレ・ミゼラブルやノートルダム・ド・パリで有名なユゴーもこの時代です。
少しだけ遅れて20世紀初頭に活躍したアメリカの小説家・バーネットも、19世紀のイギリスを舞台にした「小公女」「小公子」シリーズを発表しています。
私は本当にこの時代の小説が好きですが、ただこれだけの孤児小説が生まれているということは、それだけたくさんの孤児がいたということなんですね。

一応孤児院もどき(というか孤児に限らず貧しいものを集める場所)も存在したそうですが、ほとんど機能していなかったようです。
そこら辺の話はディケンズの作品で結構出てきます。
推理小説としては19世紀後半にイギリスで「シャーロック・ホームズシリーズ」が誕生しています。
それとよく対比されるのがフランスの怪盗小説「ルパンシリーズ」。こちらはシャーロック・ホームズより少し遅れて20世紀初めの頃に登場します。
「オペラ座の怪人」で有名なガストン・ルルーもこの時代で、ルパンシリーズを書いたモーリス・ルブランとはライバルだったそうです。
(ちなみに名探偵コナンの毛利蘭はモーリス・ルブランから名前をつけたそう。主役のコナンはホームズの作者コナン・ドイルからです。)
イギリスで割と王道な探偵小説(推理小説)が流行ったのに対し、オシャレの国フランスでは、紳士的な怪奇小説が流行るという…国ごとの性質が現れているようで面白いです。

SF小説家としては、フランスで19世紀後半からヴェルヌが登場。彼はSFの開祖と呼ばれます。
ディズニーシーに彼の作品をモチーフとした「海底2万マイル」というアトラクションがあることで有名ですね。
イギリスでは19世紀後半から20世紀前半にかけてウェルズが活躍し、名前が似ていてジャンルも同じでややこしいという…。
フランスのヴェルヌとイギリスのウェルズはSF界の先駆け、巨匠として有名人です。
19世紀前半の目覚しい産業革命以降、こうした科学への憧れを表すSF小説が増えました。
当時、芸術や文化を流行らせるのはフランスとイギリスが中心で、特にフランスが流行を作っています。
アニメ映画界の世紀末(20世紀)
19世紀末の退廃的な雰囲気はフランスから流行りだし、ファン・ド・シエクル(=世紀末)という言葉で流行しました。
こうした19世紀末をテーマにした作品は20世紀末にもいくつか見られます。
例えば名探偵コナンの「世紀末の魔術師」。
この作品は20世紀末に19世紀末の退廃的な雰囲気をリバイバルした作品と言えるかもしれません。
フランスから始まりヨーロッパ全体に影響した王権の衰退、機械化という変化を、ロシアのロマノフ朝をモチーフとして上手く表現しました。
ロマノフ朝も革命の並に逆らえず、最後滅ぶんですけど、古い王権の「記憶」と新しい技術である機械(からくり)を融合させてつくった見事な映画として、私の中では思い出深いです。
同時にもう1つ、名探偵コナンの「ベイカー街の亡霊」も19世紀末のロンドンが舞台でした。
19世紀末ロンドンを20世紀末~21世紀初頭の技術で再現するというテーマで、なかなか重厚な作品構成となっています。
こちらは先日考察した「ベイカー街の亡霊の記事🔗」をご参照ください。孤児の話も結構出てきます。
少し似た流れで、19世紀末の退廃的な雰囲気を、20世紀末の懐かしさに置き換えて作られた映画・クレヨンしんちゃんの「モーレツ!オトナ帝国の逆襲」もあります。
大人たちが20世紀の郷愁溢れる「懐かしさ」に魅了されてしまうという作品なんですけど、アニメ映画界の中でも伝説となる名作になりました。
このように、1990年代後半から2000年代にかけてのアニメ映画って、今のキャラクターを前に押し出す感じの映画とはまた違って、テーマが深くて、考察の幅も広いものが多いように思います。(多分そういったものが流行っていた)
今は今の良さがあり、昔は昔の良さがあり、私は20世紀末の作品も結構好きです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
