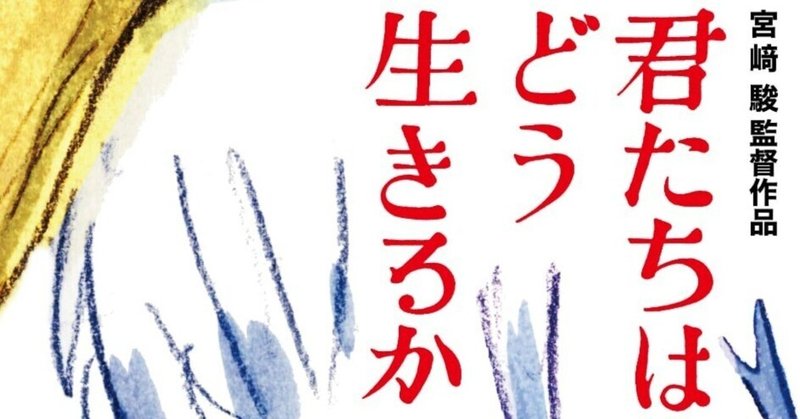
『君たちはどう生きるか』を観て【ネタバレあり】
『君たちはどう生きるか』を友人たちと鑑賞してきた。
ひとことで言えば、延々と他人の夢の話を聞かされるみたいな映画だった。
※以下の感想にはネタバレがあるので映画本編を未見の方はご承知ください。

もちろん天下のスタジオジブリ、それも宮崎駿御大の(おそらくは)生涯最後の長編映画ということもあって、「アニメアベンジャーズ」とでも言うべき日本の最高峰クラスのスタッフが集って制作された画面はゴージャスそのもので、そこから紡ぎ出される映像のダイナミズム、そして画面の細部にまで行き渡った緻密さには感嘆するほかはない、というのは大前提としてはある。
映像と音響で表現するエレガントな「説明」
シーンとして個人的に特に感じ入ったのが、主人公の眞人が父親とともに田舎へ疎開してきて継母となる女性と出会い自室に案内されて、疲れから寝入ってしまうところ。
そこにお茶を持って件の女性、夏子が茶を持って入ってくるが、眠っている眞人を起こさないようにそっと窓辺に茶を乗せた盆を置き、入ってくるときとは全く違って、音を立てないように静かにドアを閉めて出て行く。
ここに至るまで、観客も「継母となるこの女性は眞人に対してどういう対処をする大人なのか」ということを判断する材料があまりなく、その人となりをいわば言外に説明して見せた最初のシーンがこれなのだけれど、その奥ゆかしくも明確な提示の仕方にゾクゾクした。
よくTVアニメを観ていても「ちゃんと説明してほしい」と感じることがあるが、それは何も言葉にしろというのではなくて、「観てわかるようにしてほしい」ということなのだ。
ここではそうした「説明」が最上にエレガントな形で示されている。
モザイク状に役割を受け持つ女性キャラクターの表象
しかし一方で、この映画全体を俯瞰してみると、途中でちょっと意識が飛んだかなと思えるくらいに説明を端折っている部分があまりにも多いのだ。前述のように細やかなディテールを積み上げて説明しようと思えばいくらでもできるにもかかわらず。
それがなぜなのかということを愚考すれば、あえて曖昧にすることによって未分化のイメージとしての母/恋人/伴侶という役割それぞれを、表象の異なるキャラクターたち――それは夏子やヒミ、あるいは向こうの世界で出会う若き日の桐子――にモザイク状に受け持たせるためであったのだろうと思う。
彼女たちは、眞人(そして観ている私たち)の生まれ出ずる源である母親であると同時に、初恋の人であり、初めての性交の相手でもあり(桐子と魚を捌くシーンは初体験する性交のメタファーだし、その「滋養」を得て現世へと旅立っていく「ワラワラ」たちは受精卵そのものだ)、そして最後に還る場所でもある。
自他境界線の曖昧な主人公・眞人の二面性
そうした境界線の曖昧なキャラクターたちに呼応するように、というかそうであるのが自然なこととも思えるが、原作・脚本・監督と全権を振るう宮崎駿その人が投影されるべきキャラクターであるはずの眞人の人物もまた曖昧である。
ある時点までは宮崎駿であるようにも思えるし、特に後半のシークエンスでは宮崎吾朗の似姿であるようにも思えるそのキャラクターの「わからなさ」は、自らの側頭部に石を打ちつけて負傷するシーンに象徴されるだろう。
それは後半で明かされるように何らかの「悪意」の表れであることは間違いないが、実際どういう感情であったのかはついに説明されることはないし、それ自体にはあまり意味がないとも言える。
眞人は田舎での新しい生活にも、そこで得られる可能性のある新たな友人にも、何ら興味を示すことがない。彼が学校で出会う地元の少年たちには全く台詞が与えられず、合理的な理由もなく襲いかかってくる記号的蛮族としてしか意味を持たない。
そうした身の回りの雑事には「倦むべき日々」としての価値しか与えられることがなく、眞人は自身が負傷して伏せってしまったことを転換点として、不思議な振る舞いをするアオサギと謎多き塔へといっそう傾倒していくこととなる。
塔の中の世界で桐子やヒミとの出会いや交流の中でもちょくちょく前提を省いたり意図的に認識をずらしたりしているシーンが散見される(桐子の名を言い当てるシーンやヒミが夏子を妹と呼ぶのに眞人は反応しないシーンなど)のだけれど、大叔父様=殿様に出会ってからの眞人の存在はさらに自他の境界線を曖昧にしていく。
それは物語の担い手としての主語が実は眞人から大叔父様へと移行しているからに他ならない。これは受け継ぐ役割である息子の話であると同時に、次代へ遺産を託す父親の話でもあるからだ。
答えを待たない問い、そして別れの挨拶
「君たちはどう生きるか」というタイトルでもあり主題のひとつでもあるシンプルすぎるテーゼに対する答えは、必然的にこちらもシンプルにならざるを得ない。
庵野秀明は『シン・ゴジラ』で登場人物の一人に「私は好きにした、君らも好きにしろ」と語らせたが、大叔父様からの積み木の継承を固辞して自らの人生へと戻っていった眞人の選択は、それと全く同じではないにせよ、似たものではあるだろうと思う。
子々孫々へと連綿と積み上げてきたものを継承すること、それが「世界」の秩序を維持するものであることは重々承知した上で、積み上げたものを放棄した結果として塔は崩壊し、世界を構成した要素である鳥たちは解き放たれていく。
それは、ある種の自由と秩序との共存には自ずと限界があることを端的に示しているが、同時に「世界」の広がりを予感させるものでもある。
そこには、タイトルの字面から身構えた人も多かった「説教臭さ」はどこにもない。あるのは老境にあって死にゆく人物から我々観客に向けての、突き放した問いかけでしかない。
「俺はこう生きた、お前らはどう生きる?」
彼にとって理解されるべきテーマはすでになく、ただ問いかけただけだ。その答えを聞くつもりも、おそらくないだろう。これは別れの挨拶でもあるのだから。そして、それでいいのだと俺も思っている。さようなら、宮崎駿。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
