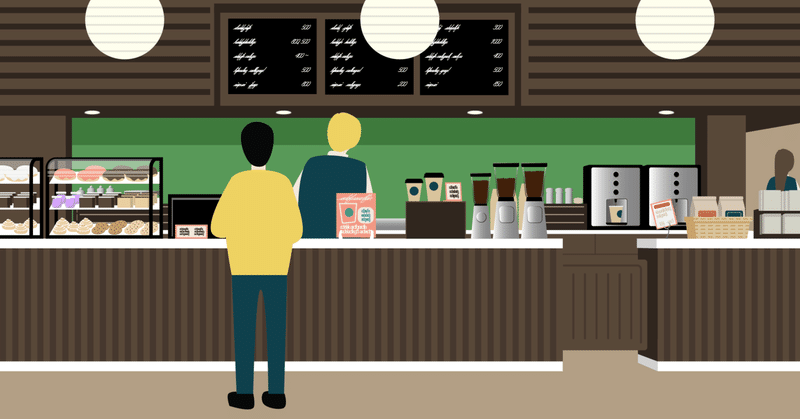
接遇にマニュアルがあることを否定するわけじゃないの。マニュアル通りの接遇しかしないと、お客様だけじゃなくて、本人も辛いだろうに、って話。
先日、コンビニでコーヒーを淹れていたら、直ぐ側のレジから「友達じゃないんだから!」と店員さんがお客さんに怒鳴っていた。なにがあったのかわからない。正直、朝から嫌なものを見てしまった気分だった。
その店員さんは日頃、型にはまった対応をする方で、今ひとつ融通がきかない印象だった。本心はどう考えていようが、まぁコンビニの買い物だしいいか、と思っていたけど、この一件で、本心では顧客を人として見ていないのではないかとの疑念が湧いて、それ以来、その店から足が遠のいている。
最近はコンビニの転院に外国にルーツを持つ方が増えてきた。数年前までは日本語の能力も危ういくらいの人ばかりだったけど、最近は、驚くほど日本語がうまい、というか、むしろ日本人より接遇がうまいと思うことが多い。
異国の文化の中で外国語を覚えて使う時、母国での常識が頼りにならないから、視覚聴覚をフル動員してあらゆる情報を脳内で統合して、目の前の人が何を望んでいるのか想像して、その人に相応しいだろう言葉を紡いで届ける必要がある。コンビニの外国スタッフも同じように接しているならば、接遇が上手くなるのも当たり前だ。
日本はハイコンテキスト文化と言われる。簡単に言うと「空気を読む」文化だ。「察する」というと相手を気遣う方向だが、この文化には同時に「察してほしい」もセットになっている。言わなくても分って当たり前、わからないのはあなたが悪い、とでも言うような姿勢で、言葉を交わすことをまるで避けているような文化になっている。
件のスタッフは、それだけ相手のことを想像していただろうか?周りに居た僕のことまで想像がついていただろうか?ハイコンテキスト文化に慣れすぎて、マニュアルに安心しすぎて、相手を想像する習慣が失われてしまったのではないか?それは辛い。接遇マニュアルも転換期かな。
ハイコンテキスト文化も限界が来ている。ダイバーシティ&インクルーシブな社会には「察する」「察して」は相応しくない。精神社会を取り戻そう。
紳士淑女の皆さん、話そう。想像しよう。
ちょっとここでひと暴れ~にしないでね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
