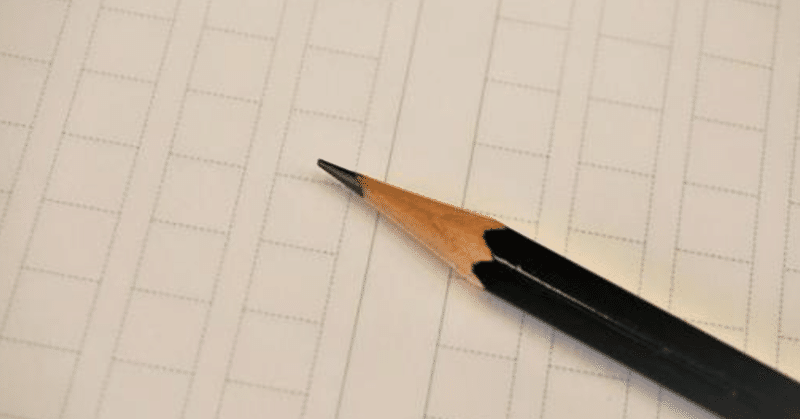
文章を書くことが好きになった話
タイトル通りですが活字がとても好きになり、自分でも書いてみたいと思い続けるようになった原点のお話です。
*
毎月、誕生日を迎える生徒に担任の先生が送ってくれたメッセージカード。私のカードには見慣れた先生の字でこう書かれていました。
「はしのさんの書く文章はとても面白いので、いつも読むのが楽しみです。」
その先生はクラスの生徒全員と定期的に交換日記みたいな物をするくらいには熱心な人でした。30人弱居る生徒に一人一冊ノートを渡してやりとりをするなんて多忙な小学校教員としては面倒だろうに、それぞれのノートに目を通してコメントを書き込んで返却していた先生の事を思い出すと、素直に凄いなぁと感心するばかりです。ただ小学校高学年になり思春期に入りつつある6年生的にはほんの少し熱すぎて、当時の同級生達にはやや面倒に思われていました。かくいう当時の私自身もこの先生面倒だなと思う事は何度かありましたが、冒頭の言葉は今の私にもとても鮮明に残っているほどに嬉しい言葉でした。
その頃の私はまさに本の虫でどこに行くにも本を一冊鞄に忍ばせており、隙あらばどこでも本を広げて読書をする子どもでした。幼少期の私は教室の隅っこが一番落ち着く消極的な子でしたが、人並みに子どもですからやっぱりどこかで主人公になりたいという気持ちも少なからずあったのです。皆の中心に行きたい、でも上手くできない、ていうかそもそもそんな事を急にしはじめたら調子に乗っていると思われる、恥ずかしい、そんな自意識過剰な私は誰にも邪魔をされない本の世界に閉じこもり切りでした。
物語の主人公はいつも何か特別なものを持っていて、周りの皆から愛されている。少しくらい苦手なことがあっても、誰かが助けてくれて最終的にはハッピーエンドを迎える。本を読むことでそんな主人公に感情移入して、まるで自分が主人公になったかのように物語の中で生きることが出来る。この感覚がとても楽しくてますます読書にのめり込んでいきました。けれどもその一方で本を閉じていつもの風景に帰ってくると、クラスの中心にはなれない、言いたいことも何も言えない、思い通りにいかない日々をただ鬱屈と過ごしている。あれ、これってもしかして、自分はどの物語でも見切れているモブキャラに過ぎない...?と気づいてしまいました。
もうすでにお気づきかもしれませんが、当時の私は自己肯定感がどん底でいわゆる”こじらせ”を起こしていました。(なぜどん底なのかはまた別の機会に)物語に登場する主人公みたいになりたいのに自分にはなれない、自分には出来ない事を出来てしまうクラスメイトが羨ましい。そんな私にできる事ってなんだろう。
そう考えた時に「そういえば昔から作文や感想文を書くのが得意だった、ならば自分もこんな素敵な世界を作ってしまえばいい!!」そう思い私はノートに自分の世界を鉛筆で書きなぐり始めました。
思い返せば当時の私は今の私よりも何かを表現する事に貪欲でした。とにかく描きたい、書きたい、あの素敵な世界を作れる人になりたい!!そう思っていました。
夜、お布団に入ってから眠りにつくまで、よく頭の中で自分の物語を想像する事が好きでした。その要領で自分の中にある別の世界の中にはどんな人が居るのか、どんな世界なのかを想像してはメモしていく、そんな作業を繰り返しながら物語を作っていく作業に夢中になりました。
よく短くてもいいから1本の物語を書き切る事が重要だと言いますが、本当にその通りで筋の通った起承転結をしっかりと作るという事が当時の私には物凄く難しい事でした。私の中にある世界を具現化するのに私の表現力が足りず急なワンシーンだけの断片的なものであったり、舞台設定をちまちまと書いていくことの方が多かったのですが、それはそれで楽しんでやっていました。
その後成長して中学生になった頃、相変わらず本が好きだった私は文芸部に入部しました。もちろん部員も大体が本好きで、そして本好きはもれなく自分でも書いてみたことがある人が多かったのです。
文芸部では毎年夏休みの課題が出ます、ある年の夏休みは各自で物語を書くといったもので、久しぶりに自分の世界をまた書くことになりました。
自分がどんな世界を作りたいのか悩みながらも、当時の私が書きたい世界を短いですが1編書きました。その時に書いた物語を読んでくれた友達に「すごい!本当にそういう本がありそう!すごく面白かった!!」と褒めてもらいました。もちろん友達なので贔屓目もあると思うのですが、当時の私は素直に喜びました。
こんな風に書いた文章を読んでもらって褒めてもらうという経験が少なくとも過去に何度かあって、あの時の気持ちが今もまだずっと生きていて私は何かを書きたいと思うのかもしれないとふと思いました。きっと褒めてくれた人達にとっては何気ない言葉でも、言われた方はあの時の喜びをずっと覚えているもので、あの言葉たちに私の人生が少し変えられたと言っても過言ではないのかもしれません。
