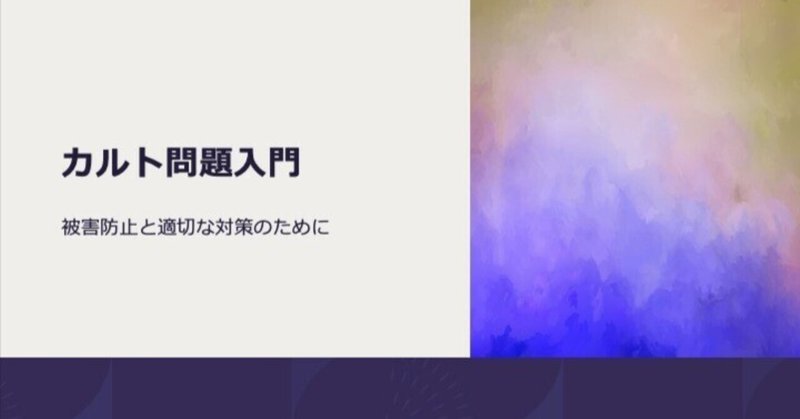
カルト問題入門 〜被害防止と適切な対策のために〜
はじめに
この記事は、破壊的カルトの被害を防止するため、注意喚起に取り組む学校の職員、子どもたちの保護者、諸団体の責任者に向けて、研修用に作成したものです。記事の最後に、スライドのPDFをダウンロードできるようにしてあります。
こちらの資料は、カルト問題やカルト対策の研修に使う目的であれば、出典を示した上で、手続きや問い合わせなしで、自由にお使いいただいて大丈夫です。
カルト対策の前に
今回はカルト問題入門として「カルト(的)集団と言えるもの」「カルト(的)思想と言えるもの」「カルト化していると言えるもの」について、カルト対策の基本と前提を共有しながら話していこうと思います。

まず、カルトという言葉を聞くと、だいたい「カルトと宗教」の話になりやすいと思います。

そして、カルトと宗教の話になると、「カルトと宗教は違う」「カルト団体は宗教じゃない」「宗教をカルトと一緒にしてほしくない」と言われることが多いです。
これは、キリスト教や仏教など、何らかの宗教を信じている人だけでなく、宗教に理解のある人や、宗教者と一緒にカルト問題に取り組んできた弁護士や学者からもそう言われることがあります。
おそらく、普通の宗教まで攻撃されないように、擁護してくれているんだと思いますが、実はこれ、ちょっと注意のいる言葉なんです。

なぜかと言うと、「カルトと宗教は違う」と言いながら、多くの人は、健全な宗教とカルトの違いがちゃんと説明できない、もしくは、曖昧にしか話せないことに無自覚だからです。
そして、健全な集団とカルトの違いがきちんと認識できていないゆえに、実態を隠したカルト団体、カルト化していく身近な集団があるにもかかわらず、気づけない……という事態が発生しています。
今まで、何らかのカルト団体の被害対策に取り組んできた人でも、異なる集団のカルト性やカルト化には気づけないことがあります。
破壊的カルトとは?

じゃあ、「カルトとはいったい何なのか?」というと、広い意味では、「熱狂的崇拝」やそれを行う小団体のことです。短く言うと熱狂的集団、熱狂的な少数派です。よく、一部の層から熱狂的に愛されている映画を「カルト映画」と言ったり、「カルト的人気を誇る」と表現したりしますが、まさにその意味です。
そして、狭い意味でのカルトとは、メンバーをコントロールして人権侵害や社会問題を引き起こす集団のことで、単なる熱狂的集団とは区別して、「破壊的カルト」と呼ばれています。現在、「カルト」という言葉が使われる際は、一般的にこちらの意味で使われています。

この「破壊的カルト」をもう少しちゃんとした言葉で説明すると、「金銭的、身体的、精神的被害をもたらす反社会的集団」です。単に、怪しく見える、おかしい集団を指すのではなく、具体的な被害をもたらす集団だ、ということです。
もう少し補った言い方をすると、「個人の人権を侵害し、公共の福祉を破壊する、社会問題を引き起こす集団」です。加えて、破壊的カルトを表す際に重要になってくるのは、「メンバーをコントロールして、被害者を加害者に変えてしまう」という構造です。私が説明する際には、だいたいこの3つの表現から説明します。

さて、これらの説明を聞いて分かるとおり、破壊的カルトというのは、宗教団体に限りません。
過激派、テロ組織などの思想政治カルト。マルチ商法や信者ビジネスなどを行う商業カルト。自己啓発セミナーや悪質カウンセラーをはじめとする心理療法カルト、そして、霊感商法、霊視商法、高額献金などの被害をもたらす宗教カルトがあります。
大きく分けて、この4つがありますが、必ずしもきれいに分かれているわけではなく、思想政治カルトと宗教カルトが合体していたり、商業カルトと心理療法カルトが合体していたり、複数の要素が重なっているカルトもあります。

つまり、最初に取り上げた「カルトは宗教じゃない」という言葉は、厳密には正しくなくて、商業団体の中に商業カルトがあるように、宗教団体の中に宗教カルトがあります。また、思想政治団体がカルト化したものが思想政治カルトであるように、宗教団体がカルト化したものが宗教カルトです。
「カルトは宗教じゃない」と言ってしまうと、宗教とカルトは、全く別物のように思われてしまいますが、宗教も、他のあらゆる集団と同じように、カルトを内包する、カルト化する可能性を持った集団の一つです。
ミニカルトとは?

最近は、「ミニカルト」という言葉を聞く機会も増えてきたかと思います。ミニカルトとは、「一対一カルト」をはじめとして、世間で広く認識されていない破壊的集団や教祖、リーダーを指します。
「一対一カルト」というのは、占い師やカウンセラー、DV やデートDVなど、一対一の関係でコントロールされ、金銭的・身体的・精神的被害が発生するものです。
カルト問題の話でDVが出てきて、驚く方もいるかもしれませんが、破壊的カルトのメンバーに対するコントロールと、DV 加害者の被害者に対するコントロールは、構造が非常によく似ていて、重なる要素を持っています。後で、カルトのコントロールについて説明する際、もう一度取り上げますが、この点はぜひ、覚えておいてください。
このように、サークル、家族関係、友人関係など、比較的小さな、誰もに身近なコミュニティで、ミニカルトが形成されることもあり、暴行や殺人事件に発展することもあります。

この他にも、カルトはあらゆる集団から生まれ得ます。よく、相談が寄せられるものの中には、スピリチュアル系の団体、陰謀論系の団体、過激な自然派、悪質な代替医療、過激な社会運動や自己啓発系の団体も含まれます。
基本的に、人が集まるコミュニティであれば、どんなものでも「カルトである可能性」「カルト化する可能性」があります。
カルトかどうかの判断基準

じゃあ、あらゆる集団にカルトの可能性があるなら、カルトかどうかの判断基準は何なんだ? という点が気になってくると思います。よく勘違いされますが、ある団体がカルトかどうかを判断する際に基準となるのは、「何を信じているか」「教えがおかしいかどうか」ではありません。
カルトの判断材料になるのは、その集団が「何を行っているか」「不適切な手段を用いるかどうか」です。「メンバーが心の中で信じていること」を問題にするのではなく、「メンバーに被害をもたらす破壊的な行動をさせているか」を問題にします。

ここでよく、カルト問題について議論する際、「信教の自由があるから」「内心の自由があるから」という理由で、問題に踏み込むことができないかのように発言されることがあります。
しかし、先ほども言ったように、カルト問題で問われるのは、「何を信じているか」ではなく「何を行っているか」です。内心の自由を侵す話ではありません。
また、信教の自由とは「宗教を信仰し、宗教上の行為を行う自由」であって、「人権侵害や不法行為を働く自由」ではありません。信教の自由は、宗教を理由にすれば、何でも許されるという権利ではなく、何を信じるか、何を信じないかが尊重される権利です。
自分たちの信仰を広めるために、他の人たちの信仰を蔑ろにしたり、他の人たちの「信じない自由」を侵害することこそ、信教の自由に違反しています。
「何を信じているか」を理由に、宗教団体を取り締まったり、解散させることはできませんが、「何を行っているか」「何を犯しているか」を理由に、宗教団体を取り締まったり、解散請求をすることは、適切な対処の一つです。
カルト問題を信教の自由の問題にすり替える動きは、カルト団体が処罰を免れるための常套手段なので、安易に加担しないようお願いします。
カルトの破壊的要素

それでは、カルトかどうかの判断材料である「何を行っているか」という視点で、カルトの破壊的要素について取り上げたいと思います。ここでは分かりやすく、金銭的被害、身体的被害、精神的被害、関係の破壊、公共の福祉や利益の侵害という5つに分けて説明します。
まず、金銭的被害には、霊感商法、霊視商法、高額献金、詐欺行為などが挙げられます。次に、身体的被害には、性暴力、虐待、奉仕の強要、長時間の拘束などが挙げられます。信者に対する医療拒否の指示や、児童虐待を支持する指導も、ここに含まれます。
精神的被害には、メンバーに対するパワハラ、セクハラ、脅し、批判者に対する誹謗中傷などが挙げられます。関係の破壊は、カルトにおける最も深刻な問題で、家族・友人関係の破壊や制限が挙げられます。
金銭的被害が大きくないところでも、家族との連絡を禁じたり、メンバー以外との関係を切らせることで、深刻な被害が生み出されています。また、いわゆる宗教二世の場合、脱会すると、組織に残った家族や友人とも、一切接触させてもらえない、という被害があります。
最後に、公共の福祉や利益の侵害として、活動による騒音や、施設の無断使用、無許可の貼り紙などが挙げられます。他の集団を装った、正体や目的を隠した勧誘も、ここに含まれます。
カルト問題として取り上げることができるのは、今挙げたような「具体的な被害や具体的な不法行為が、その集団の指導・コントロールによって行われている」と指摘できるところです。

ちなみに、金銭的被害の中に出てきた「霊感商法」は、別名「開運商法」とも呼ばれ、人の不安や信仰心に付け込み、「このままでは不幸になる」「地獄に行く」などと言って恐怖心を煽り、高額な商品を売りつける、悪質商法のことです。
なぜ、開運商法とも呼ばれるかと言うと、「運気を上げるため」「幸運を引き寄せるため」などと謳って、高額な商品を売りつける形もあるからです。
「運気を上げる」と言われるだけだったら、直接、死後や将来の不安を煽っているようには聞こえませんが、実際には言葉巧みに「このままだと運気が下がる」「何もしなければ不幸なままだ」という不安を植え付け、購入しないと幸せになれないかのように誘導していきます。
このように、最近のカルトは、あからさまに「恐怖によるコントロール」が指摘できる言動は避け、ターゲットが自分で、無意識に、恐怖心や不安感を抱いていくよう誘導する傾向が見られます。
そのため、被害を受けた当事者に「脅された」「恐怖心を刷り込まれた」という認識がない場合もあります。

似たような言葉で、霊視商法という用語も出てきましたが、こちらは、「あなたに取り憑いている悪霊を祓わないと死んでしまう」「祈祷しないと家族に災いが降りかかる」などと、不安や悩みに付け込んで、祈祷料・除霊料・供養料などの名目で、高額の寄付や献金を行わせる悪質商法のことです。
霊感商法と違って、商品の販売はしませんが、「献金すれば天国へ行ける(献金しなければ地獄に落ちる)」「献金すればするほど幸せになる(献金しなければ不幸になる)」などといって、高額な献金を行わせる場合もあります。
霊感商法と同じく、あからさまに「恐怖によるコントロール」が指摘できる言動は避け、被害を受けた当事者が「恐怖心から強制された」という自覚を持たないように、「不幸を回避するため、幸せになるため、自ら喜んで献金した」という認識になるよう誘導します。
私は、カルト団体における高額献金は、基本的に霊視商法だと思っています。
カルト(的)思想とは?

さて、ここまで、カルトかどうかの判断基準は「何を信じているか」や「教えがおかしいか」ではなく、「何を行っているか」「不適切な手段が用いられるか」が問われる事柄だと説明してきました。
しかし、いわゆる「カルト思想」「カルト的思想」と呼ばれるものも、カルトの破壊的要素として取り上げられることがあります。いやいや、「思想」や「教え」を問題にしたら、結局のところ、内心の自由や信教の自由にぶつかってしまうじゃないか? と思われるかもしれません。
もちろん基本的には、何を教えとして信じるかは、個々人の自由です。では、「カルト思想」「カルト的思想」と言われるものは何なのかと言うと、不法行為や暴力に直結する教えや思想を指しています。
たとえば、人種差別や民族差別、虐待や医療拒否、暴力的な支配関係を支持する思想です。これらは、特定の人々の人権侵害や虐待の容認、不法行為の指示にも従うなど、様々な被害に直結するため、カルト的思想と言われます。
また、誤った治療法、誤った病気や障害の理解、誤った教育方法など、健康被害や人命やハラスメントに直結する教えも、カルト的思想と言うことがあります。
このように、カルトの思想が問われる場合は、それが反社会的な言動に直結する、健康被害や人命に直結する場合です。単に、誰かから見て「おかしい」「変だ」「受け入れられない」というだけで、カルト的思想と断定することは、避けなければなりません。
どこからカルトと言えるのか?

しかし、多くの人は、自分が快く思わない集団に対して、問題だと感じる要素を一つでも見つけると、その集団に対して、カルトだと言いたくなってしまいます。これは、カルト対策において避けなければならない態度です。
なぜなら、破壊的要素の指摘だけで、すぐにカルトと認定することは、現実に即していないからです。たとえば、日本脱カルト協会、略して、JSCPR というところで作られた「集団健康度チェック表」では、114項目の破壊的要素が挙げられています。
このうち、80項目を超えると「不健康な集団」、さらに、110項目を超えると「非常に不健康な集団」と見なされますが、一般企業やサークルでも、それらの項目を有することは珍しくなく、何か一つの項目が当てはまれば、即「カルト」と言えるわけではありません。

このJSCPRの集団健康度チェックは、ネットで検索すれば、誰でも簡単に見られるので、よかったらご覧になってください。
おそらく、皆さんが所属している会社、学校、サークル、家庭など、試しにチェックしてみたら、自分の属するコミュニティの中で、1つ2つ、3つ4つくらいは、当てはまるところが出てくるのではないかと思います。
忘れてはいけないのは、どんな集団も少なからず、破壊的要素や破壊的傾向を持っているということです。ある時期、あるメンバーに、ある破壊的な要素が見つかっただけで、すぐに「この集団はカルトである」とは言えません。
カルトとは、複数の破壊的要素がいくつも積み重なって、組織的に継続されている状態であり、あらゆる集団と無関係ではないんです。
もともと普通だった会社が、ある上司のパワハラを放置し続けて、だんだんその傾向が広がっていき、いつしか自殺者まで出てしまう悪質企業へ変化してしまうのと同じです。カルトとは、組織的、継続的な破壊的要素の積み重ねなんです。

じゃあ、「どこからカルトと言えるのか」「はっきりカルトと言えるのは、どんな団体なのか」ということが気になってくると思います。一応、「これらを満たせば、カルトと言っても差し支えない」という条件が3つあります。
⑴ 金銭的、身体的、精神的被害が複数訴えられている。
⑵ 刑事裁判や民事裁判が複数起こされている。
⑶ 被害者の会や被害対策弁護団が存在する。
この3つ全てが当てはまれば、ほぼ破壊的カルトと言って差し支えないと言われています。ただ、カルト問題として、しばしば取り上げられる団体の中にも、この3つが満たされるところは、そう多くありません。
つまり、「破壊的要素がいくつ以上当てはまればカルトです」とはっきり言えるわけでも、「これとこれとこれの条件が満たされなければ、カルトとは言えません」と断言できるわけでもないんです。

このように、ある団体が「カルトかどうか」「カルトでないか」を判断することは難しく、それらを認定する機関も、今のところ日本にはありません。そして、カルトと言うほど破壊的傾向が強くない集団でも、個々の破壊的要素を放置し続ければ、反社会的集団へ成長する恐れがあります。
また、被害者が組織の報復を恐れたり、元メンバーであることを明かしたくないなどの理由で、多くのカルトは、実態が知られにくいという現状があります。
そのため、実際には、カルトの破壊的要素を相当有しているにもかかわらず、それを判断できるだけの材料が表に出てこないため、はっきり「カルト」として扱うことができない団体は無数にあります。
カルト(化)対策で重要なこと

したがって、カルト対策で第一にすべきは、その団体が「カルトかどうか」をジャッジすることではありません。その都度、確認された個々の破壊的要素を放置しないで、指摘と改善を進めることです。
また、現段階では「カルトと言うほどでない団体」と判断される場合も、こちらに見えてない破壊的要素が隠れている可能性を踏まえ、警戒しながら、改善が進むかどうか見守っていく必要があります。
そして、確認された破壊的要素が、組織的継続的に放置され、改善が見られない団体であれば、速やかに距離をとって、安全を確保することが大事です。
カルトかどうかのジャッジを第一にしていると、カルト対策はなかなか進みません。かえって二元論的な思考に陥るので、ジャッジは対策の結果であって、目的にするところではないと、心得ておく必要があります。

ちなみに、ここまで「カルト化」という言葉も何度か出てきましたが、これも注意が必要な言葉です。私の方で定義すると、「ある集団の破壊的傾向が組織的・継続的に放置され、積み重なっていくこと」を指します。
ある時期、あるメンバーに、ある破壊的な言動が見られただけで、すぐ「カルト化している」とは言いません。そう言いたくなる人が多いですが、あらゆる集団は、少なからず破壊的要素や破壊的傾向を持ってしまう時期が存在します。
逆に言えば、いくつかの破壊的要素が見られても、「現時点では、カルト化しているとまでは言えない」という判断が多くなります。したがって、カルト化対策で重要なことも、「カルト化しているか」のジャッジではなく、その都度、確認された破壊的要素を放置しないことです。
ある人が、うつ病か、抑鬱状態か、ジャッジすることを第一に考えるよりも、うつ病患者と同じ不調を抱えている、抑鬱状態と同じ症状が見られることを確認したら、休ませる、病院へ行かせる、など、悪化を防ぐ対応を目指す方が、回復に、健康につながるのと同じです。
「うつ病とまでは言えないから、抑鬱状態とは言えないから、今までどおり、仕事をさせ続けよう」となったら、結局悪化するように、「カルトとまでは言えないから、カルト化しているとまでは言えないから、現状維持で放置しよう」としてしまうことも、集団の悪化につながります。
カルト対策は、ジャッジを第一にするのではなくて、個々の破壊的要素への対処を第一にします。
カルトと異端の違い

そして、カルトかどうかを考える際、伝統宗教か異端かどうかは関係ありません。
よく、異端とカルトを混同している人もいますが、異端とは「その宗教一般の共通理解から外れる集団」で、異端であってもカルトでない集団もあります。どんなに不思議な教えを信じていても、人権侵害や不法行為がなければ、破壊的カルトとは言わないからです。
カルトとは「人権侵害や社会問題を引き起こす集団」で、伝統宗教の中にも、金銭的、身体的、精神的被害をもたらすカルト団体は存在します。いわゆる正統的な教義を教えている教会にも、金銭トラブルや性暴力を引き起こしているカルト化した教会があります。
異端の場合は、「何を信じているか」「何を教えているか」が問われますが、カルトの場合は、「何を行っているか」「不適切な手段を用いるか」が問われます。これが、異端とカルトの違いです。
当然、「異端だしカルトでもある」という団体は多いですが、「異端だけどカルトじゃない」「カルトだけど異端じゃない」という団体もたくさんあることを認識しないと、単なる「魔女狩り」になったり、被害を防げなくなったりします。
特に、カルト対策を行っている宗教者の方々は、この点に注意しなければなりません。

このように「私は伝統宗教を信じているから、カルトとは関係ない」と思っている人も、実際には関係してきます。たとえ、その宗教一般における正統的な教義が語られていても、その教会の指導や運営に問題があれば、カルト問題として取り上げられる可能性が出てくるからです。
たとえば、正体や目的を隠した勧誘が行われているか? 適切な会計報告や役員会が行われているか? ハラスメントの常態化や隠蔽があるか? 献金の強要や奉仕の強制が行われているか? 医療拒否や虐待を支持する指導があるか? 進路、職業、転居の自由を侵害しているか?
カルトを扱うところでは、こういった指導や運営の問題が問われます。最近、身内が宗教を信じるようになったけれど、伝統宗教だから大丈夫……と考えてしまう人は、「伝統宗教だからカルトじゃない」とは言えないことを押さえておく必要があります。
また、様々な大学のキャンパスで活動している宣教団体の中にも、キリスト教の背景があることを隠し、リーダーシップの育成や文化交流の目的を看板に掲げ、学生たちを集めて、宣教活動のリーダーに育てようとするところがあります。
現時点では、金銭的・身体的・精神的被害が見られなくても、「正体や目的を隠した活動」という破壊的要素を今後も保持し続けるなら、カルト化していく可能性があります。
各学校関係者の方は、学生たちが被害に巻き込まれないよう、正体や目的を隠した勧誘を取り締まり、注意をはらうようにしてください。
カルト団体と健全化

さて、色々とカルトやカルト化した団体について話してきましたが、もともとカルト的だった団体が、反省して、健全な団体になることはあるのか? という問いも生まれてくると思います。
もちろん、以前はカルト的だった団体が、問題を放置せず、健全化して、社会と共存できる集団になることもあります。
かつては悪質企業(ブラック企業)と呼ばれていた団体が、反省し、対応を重ね、健全な企業へ変わっていくことがあるように、かつてはカルトと呼ばれていた団体が健全な集団へ変わることもあります。

ただし、注意しなければならないのは、過去に金銭トラブルや性被害、正体や目的を隠した勧誘などで問題になった教会が、「自分たちはもう、普通の教会と同じ、クリーンな団体です」とアピールする場合、「健全化した」とは評価できない事例もあることです。
たとえば、「団体名や活動名を変え、過去に起こした問題を隠して健全さをアピールする」「被害者への謝罪表明や継続的な対応を誠実にしなくなる」「問題を繰り返さないための対策より、組織や活動の拡大を優先する」……こういった傾向が見られる団体は、なお危険です。
しかし、信頼されている有名人や著名人が招かれて、組織のイメージアップに利用されているケースがあります。特に、キリスト教会は「悔い改めて、再出発した」というストーリーに弱いので、たとえ、表では被害を聞くことがなくなっても、ここに挙げた傾向が見られる場合は、引き続き、警戒が必要な団体だと思ってください。
カルトに入るメカニズム

ここまで、カルトの破壊的要素について色々説明してきましたが、そんな危ない要素を持った集団に、どうして入ってしまうのか、どうして離れられなくなるのか、一番気になると思います。
実は、ある人がカルトにハマって、離れられなくなる構造は、ある人がDVの加害者に捕まって、離れられなくなる構造と似ています。DVが「一対一カルト」と言われる所以です。
どんな人でも、最初から、理不尽な支配を受けると分かって、パートナーと付き合う人はいないように、最初から、問題のある団体と分かって、カルトに入ろうとする人はいません。
DV の加害者が、本性を隠して、良い人を装って、被害者へ近づいてくるように、破壊的カルトも、正体を隠して、目的を偽って、ターゲットへ近づいてきます。
DV の場合は、加害者と付き合い始めると、まずはとことん好意を伝えられ、大切にされますが、徐々に「お前はダメだ」「何でこんなこともできないんだ」と責められるようになります。急に怒られては、優しくされてを繰り返し、「自分はダメなことばっかりで、この人がいないと生きていけない」と思わされます。
破壊的カルトの場合も、最初はラブシャワーと呼ばれる歓迎を受け、夢や悩みをとことん聞いてもらえますが、徐々に、自分で考えることは間違った常識に基づいていると思わされ、「組織の言うことを聞かないと幸せになれない」「正しく生きることができない」と思わされるようになります。
どちらも、最終的には、他の人の言うことを聞いてはダメだと、周囲の人間関係を制限され、他に居場所をなくされて、離れることができなります。
被害者は、自分の意志で、そこに留まっていると思っていますが、実際には、加害者からコントロールされ、そこに留まる以外の選択ができないようにされています。これが、DV や破壊的カルトに見られるマインドコントロールの構造です。
破壊的カルトの偽装勧誘

このように、カルトに入ってしまう理由の多くは、最初に、正体や目的を隠して接触されることです。そして、多くのカルト団体は、フロント組織やダミーサークルを持っています。
一見、カルトと関係ない、普通のサークルやイベントのように見えますが、後から仲良くなって、メンバーへ取り込むために、連絡先や個人情報を獲得する入り口になっています。たとえば、以下のようなテーマで人集めが行われます。
家庭教育、性教育、子育て、環境問題、社会問題、人権問題、平和運動、ボランティア、SDGs、起業、副業、自己啓発、自己分析、手相、アロマ、ハンドメイド、コンサート、英会話、文化交流、スポーツ、ゲーム、留学、就活、婚活、妊活、心理相談……
これらは実際に、複数のカルト団体で人集めに使われているイベントや集会のテーマです。人を集められるなら、左派に多いテーマでも、右派に多いテーマでも、流行のテーマでも、何でも使います。

そして、大学の場合、公認サークルかどうかだけで、安全を判断することはできません。公認サークルに、カルトのダミーサークルが入っているところもあれば、後から乗っ取られたところもあります。インカレサークルや地域交流サークルとして、複数の大学をまたいで活動している場合もあります。
もちろん、学生に限らず、子育て世代の母親や父親、生活を安定させたい社会人、老後の趣味を探している高齢者など、あらゆる人たちを対象に、カルトは魅力的なテーマを設け、正体を隠して近づいてきます。
そして、注意していただきたいのは、一般的に、右派と呼ばれる人たちは左派と呼ばれる人たちの集まりにカルトが多いと考え、左派と呼ばれる人たちは右派と呼ばれる人たちの集まりにカルトが多いと考える傾向が見られますが、実際にはどちらの層にも様々なカルトが存在します。
右派だからカルトに入りやすいわけでも、左派だからカルトに入りやすいわけでもありません。カルトに入りやすいのは、「自分は入るわけがない」と思っているからです。
保守であろうと、リベラルであろうと、カルトに入ってしまう人、カルト化してしまう人たちは存在します。保守系のカルトが、リベラルっぽいテーマで、人集めを行うこともあります。また、カルトはあらゆるテーマを利用しますが、特定のテーマを扱うだけで「カルト」とは言いません。
右派の勉強会がみんなカルトなわけでも、左派の勉強会がみんなカルトなわけでもありません。そういう安易な捉え方をする人こそ、カルト問題の基本や前提が身についてないので、知らないうちにカルトに囚われやすくなっています。ここもぜひ、押さえていただけると嬉しいです。

加えて、「伝統宗教を信じていれば、何か別の宗教団体のメンバーであれば、おかしなカルト集団に入ることはない」と考えてしまう人もいますが、既存の宗教団体の信者を勧誘するカルトもあります。
たとえば、キリスト教系の破壊的カルトが、一般的なキリスト教会の信者を装って、「私もクリスチャンです」と近づいてくるパターンなどです。教会へ初めてきた人、他の教会から引っ越してきた人を装って、ターゲットの教会へ侵入し、信者の引き抜きや法人の乗っ取りを行うところもあります。
何か、先に宗教団体に入っていれば、カルト信者にならないわけではないので、そう思い込んでいる人は注意してください。

また、カルトから勧誘の即戦力になる人間として狙われる人たちもいます。たとえば、医師、看護師、助産師などの医療従事者です。日々、たくさんの患者さんと接し、世間からも信頼を受け、待合室に関係団体のパンフレットなども置いてもらえるので、けっこう狙われます。
また、保育士や学校の教師、大学教授なども、保護者や学生から信頼されるので、カルトの傘下の講演やセミナー、イベントに案内する者として取り込まれている人たちがいます。PTAの会長なども、PTA主催の講演会や勉強会にカルト団体の講師を呼ぶことができるため、あちこちで即戦力として狙われます。
地域の人たちから相談を受ける立場の民生委員やケアマネージャーも、カルトに取り込まれ、勧誘に加担させられることがあるので、よく注意が必要です。
市議会議員や県議会議員、国会議員なども、カルト傘下の講演にきてもらうと、組織の信頼性を高め、メンバーをコントロールし続けることに役立つため、接触を受けやすいです。
中小企業の会社の社長や料理教室の先生なども、部下や生徒に対してカルト団体が出版している本や販売しているサプリメントなど、ばら撒くのに都合がいいため、あわよくば取り込もうとしてくる人たちがいます。
当然ながら、教会やお寺で信者や檀家さんからの信頼を受けている牧師、司祭、住職なども、上手く取り込めば、教会やお寺ごと乗っ取ることができるため、しばしば接触を受けます。
まさか、自分が狙われることはないだろうと思っている人たちこそ危険なので、自分の大切な人たちを守るためにも、ぜひ注意してください。

では、こういった正体や目的を隠した勧誘がどういう場面で行われるかと言うと、実に多岐にわたります。
外出時であれば、アンケート調査や無料の手相診断ですと声をかけ、悩んでいることや困っていることを自然に聞き出し、連絡先を交換しようと言われます。
ネットであれば、無料で悩みを聞いてもらえる「心の相談室」や資格講座の案内などを介し、教祖が待ち構える組織へ誘導されていきます。
Twitter、Instagram、FacebookなどのSNSであれば、「いいね!』やリツートをしてくれた人へのプレゼント企画などに、商業カルトが紛れています。反応すると、悪質業者のカモリストに入ったり、特殊詐欺の受け子に利用される恐れが出てきます。
また、ある時期から、自分の投稿に「いいね!」をつけたり、シェアしてくれるようになった人が、メッセージを送ってくるようになり、仲良くやりとりをしていたら、カルトのダミーサークルへ誘われた……という手口もあります。
友人から誘われる場合は、最初は目的を隠してお茶や飲み会、ゲーム大会に誘われて、「ぜひ会ってほしい人がいる」と、おしゃれで賢そうな人を紹介され、徐々にサクラのメンバーがいるホームパーティーへ誘導される……というケースもあります。
医師や教師など、先生と呼ばれる立場の人からは、「これ良いよ」と紹介してもらった健康食品や民間療法を試していくうちに、「その分野に関するすごい先生が、今度講演するんだ」というふうに、カルトのイベントへ誘われるようになります。
ちょっと触れるだけでも、あらゆるやり方で、カルト勧誘が行われているのが分かったと思います。そして、正体や目的を隠した勧誘から、メンバーになった被害者は、お金と時間と労力を搾取されながら、自分自身も誰かを勧誘し、加害者へ変えられていきます。
マインドコントロールとは?

こうして、知らず知らずのうちに、カルトのメンバーになった被害者は、種々のコントロールを受けて、自分で考える力を弱められ、その集団に都合の良い人格へ作り替えられてしまいます。
マインドコントロールとは、そこで見られる様々なテクニック、心理現象の総称で、宗教カルトのように、あるリーダーによって、意識的に指示されて進められることもあれば、陰謀論系のコミュニティのように、集団の中で、無意識に、自発的に進んでいくこともあります。
たとえば、不安や正義感をあおって仲間意識を作り、離れたら恐ろしい目に遇うなど恐怖を刷り込む感情コントロール。
あらゆる情報や出来事を特定のパターンで捉えさせ、指示に従わせる思考コントロール。
教えの拡散、メンバーの勧誘、批判者の撃退などに加担させ、周囲や家族から孤立させていく行動コントロール。
都合の悪い情報は見せないか、フェイクとして自ら切り捨てさせる情報コントロール。
といったものが、例として挙げられます。これらのコントロールが進むことで、もともと冷静で、責任感のある人も、周りの意見を聞かなくなって、カルトの言いなりになってしまうんです。

カルトのメンバーになる人は、無責任で身勝手な人のように思われることが多いですが、実際には、真面目で、優しく、責任感のある人も多いです。
カルトの勧誘をしてくる人も、マインドコントロールを受けているため、騙そうという意識はほとんどなく、本気で相手のためになると思って勧誘してきます。悪意100%の人ならともかく、善意と正義感に満ちた人からの勧誘は、なかなか断ることができません。
彼らは、自分が悪者になってでも、家族やみんなを救うんだ、という気持ちで行動しています。組織から離れたら、自分の身内にも不幸が及ぶという恐怖心で、カルトの言うことを聞いています。
そのため、コントロールを解くには、専門家の協力と、周囲の連携が不可欠で、ものすごい時間と労力を要します。だからこそ、社会全体で、被害の予防と注意喚起を続けなくてはなりません。
カルト被害を防ぐには?

被害を予防するために、注意するポイントとしては、以下の点が挙げられます。
まず、主催者、責任者、問い合わせ先の明記がない集会やイベントに行ってはいけません。それらは正体隠しの典型です。次に、団体名が何度も変更されているところも危険です。被害の実態がクチコミで広がり、その度に、以前の名称から変更している可能性があります。
また、「開催日時や会場を知りたい人は、連絡先を記入・入力してください」と案内しているところは、絶対に近づいてはいけません。高確率で危険な団体であるため、安易に連絡先を渡さないようにしてください。
最後に、あまり聞いたことのない団体で、検索しても背景がよく分からない団体は、一旦、参加を考え直しましょう。「団体名」+「別名」や「名称変更」で検索して、正体を偽っているところでないか調べたり、「団体名」+「被害、裁判、訴訟、事件、カルト」などで検索して、問題がヒットしないか確認してください。
一見、どこかにありそうな肩書きや名前の団体でも、カルトが偽装している可能性もあります。知らない団体から、取材協力や寄稿などを求められた場合も、同様に、信頼できる組織かどうか確認してください。

自分からイベントや集会に参加しなくても、SNS などでカルトメンバーから声をかけられ、お茶会や勉強会に誘導される場合もあります。やりとりするうちに仲良くなっても、面識のない人から連絡先を求められたら、まず警戒することが必要です。
そして、目的や用途の分からない、自分に必要性がない場合は、安易に連絡先を渡さないようにしてください。
また、SNS のプロフィール欄に、学生の場合は、自分の学校名、学科名、住んでいる地域などを書いていると、ピンポイントで先輩やOBやOGを名乗るカルトメンバーから接触を受ける可能性があります。
起業、副業、投資に興味があることを書いている人や、クリスチャンであることを書いている人も、商業カルトや乗っ取り型カルトのメンバーから、「私も同じ関心を持っています」とメッセージが来て、接触を受けることがあります。なるべく、そういった個人情報を書かないようにすることが、被害を防ぐポイントになります。
そして、連絡先を教えてしまった場合、やりとりをするようになった場合も、違和感を覚えた時点で、誰かへ「こんな接触を受けたんだ」と話してみてください。誰かに話してみることが、未然に被害を防ぐ最も大きな方法です。
身内がカルトに入ったら?

そして、もし、身内がカルトに入ってしまい、救出を目指す場合には、以下の点に注意して取り組んでください。
まず、カルトに入ったことを怒ったり、叱ったり、説得して、脱会させようとしないことです。多くのカルト団体は、何かあったら事細かく、報告、相談、連絡をするようメンバーに指導しています。家族から脱会するよう言われたことも、すぐに組織へ相談されます。
最悪の場合、家族との接触を切るよう命じられたり、脱会したふりをして、知らないうちに行方をくらまされたりします。そのため、まずは専門の窓口に相談をして、どう対応すればいいか聞いてください。
次に、身内を救出するためには、カルトのコントロールについて詳しく学ぶ必要があります。専門の窓口から紹介された相談会やカウンセラーのもとで、基本的な理解を深めてください。
そして、連携できる他の家族を増やしていくことも、救出に不可欠な要素です。これが一番難しいですが、カウンセラーと相談しながら、家族の連携を進めてください。
カルトからの脱会は、アルコール依存症の身内と向き合うようなもので、短期間で、簡単に進めることはできません。本人との信頼関係を再構築しながら、時間をかけて進めていきます。
「カルトに入っても怪しいと分かったら、すぐに抜けられるだろう、すぐに辞められるだろう」と思っている人は、認識を改め、しっかり予防に取り組んでください。
カルト問題の相談窓口

カルト問題の相談窓口には、次のようなところがあります。全国霊感商法対策弁護士連絡会、統一協会被害者家族の会、国民生活センター、日本基督教団カルト問題連絡会、などです。
ここに挙げている相談機関は、以前から、弁護士、臨床心理士、ジャーナリスト、学者、宗教者などが連携して、被害対策に取り組んできたところです。それぞれの名前で検索すると、ホームページに、電話番号や問い合わせフォームが出てくるので、受付時間を確認した上で相談してください。
相談窓口の中にも、カルト団体が偽装しているものや、適切な対応がされていないところもあるので、必ず、複数の分野の専門家が連携している機関に相談してください。以上で、カルト問題の入門講座を終わります。ご視聴ありがとうございました。
研修・注意喚起コンテンツ紹介
カルト問題研修用スライド
研修用動画(カルト問題入門)
学生向け注意喚起動画(シンプルver)
学生向け注意喚起動画(ドラマ付きver)
学生向け注意喚起パンフレット
家族・保護者向け予防パンフレット
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
