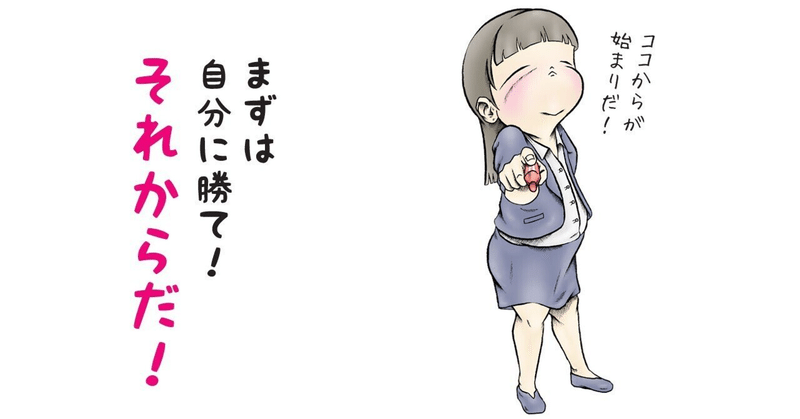
50歳からの中小企業診断士 学びなおしは独学ではじめるがBest
私自身、50代直前から、自分の人生もっと自分の力で変えたりアップデートできるのではと思い、リスキリングやキャリア自律を考えて中小企業診断士を目指すに至りましたが、独学によるリスキリングについての入門書が刊行された紹介記事に基づいて、自分なりの「独学×リスキリング」の有効性を書き留めます。
東京大学経済学部教授の柳川範之氏が著した『東大教授がゆるっと教える 独学リスキリング入門』のリンクは以下となります。
独学の厳しさが自分の覚悟につながる
社会人向けの資格学校は通学タイプや通信教育タイプなど様々用意をしています。日本人は学校や塾など1対Nの講義形式で学ぶタイプが多いですが、これは提供側のビジネス面では効率的ですが、学ぶのに適しているとは言えないです。
私は1対Nの講師がいう「この問題はここ数年出ていないから飛ばしてよい」とか、「これは捨て問としてとばして他に時間を使う」などの合格をGoalにしたテクニックについて違和感を覚えています。
資格学校はKGIが合格数であるが故に、当然ながら合格に向けたテクニックと合格にむけたっ効果的な勉強方法やアプローチを指南することが必須となります。そのため、個人的には、資格取得後にこの知識を最大限得るためのどんな問題が来ても対応できる体系的な学力をあげるというスタンスではないことが、私にとっては「合格をゴールとするのではなく、その後の資格活用をゴールにした学びをしたい」というスタンスと相いれなかったので、資格学校については、模試を活用したり、直前期のまとめを活用するにとどめようと思って独学を選びました。もちろん金銭的にも「お金を投じるのはここではない。体系的に学べる登録養成課程にお金を使おう」と思うに至りました。
独学と決めたからには、「専門雑誌の購読」「問題集の反復利用」などを重ね、最新の情報から体系的な学びの習得に力を注ぐことにして、いまとなっては、よかったと思っています。
社会人が学び、その知識を活用して社会に貢献していくには、スクール形式の学びのみならず、自ら疑問を持ち、自ら調べ、学んでいく必要があります。そのために、以下の3つを指摘しています。
①自分の経験や知見を整理すること
②好奇心や目的意識を呼び起こすこと
③時間がないことを前提にすること
自分の経験や知見を整理し、学ぶ分野、チャレンジする分野を選択し、そのなかから「これなら頑張り切れる」、「学ぶことで自分が楽しいと思える」と感じる分野を絞り込み、「時間が無くても自らスキマ時間を使って学びたいと思える」ものを決定することが大事だと思います。
このプロセスを経て選んだものは、学んでいるというよりも、水とか空気とかと同じように生活のプロセスに入り、生活している中で「学んでいる時間がないと違和感がある」という感覚になり、資格勉強をしている感覚ではなくなって、生活習慣の一部に昇華していました。どんなに忙しくでも「食べる、寝る」と同じレベルです。
そして、体得したあとの「次は大学院に挑戦しよう」とか「資格取得したら独立を真剣に考えよう」とか先の楽しい未来をより具体的に輪郭がはっきりとしてきたことが、また資格の勉強のモチベーションをあげることになりました。
失敗もすべて自分で受け入れてでも学びたいと思える分野や資格に出会えたら、あとは挑戦をしていくことでその思いが膨らみ、将来のその先のSTEPの輪郭がはっきりしてくる良いスパイラルが生まれると、本当のリスキリング、キャリア自律かなと思っています。
私自身、キャリア自律やリスキリングの途中ですし、そもそも終わりはないと思っています。生涯に渡って、学び続ける姿勢と知的好奇心を持つことを前提に、第二ステージとして登録養成課程に臨んでいこうと思います。
最後までご覧くださりありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
