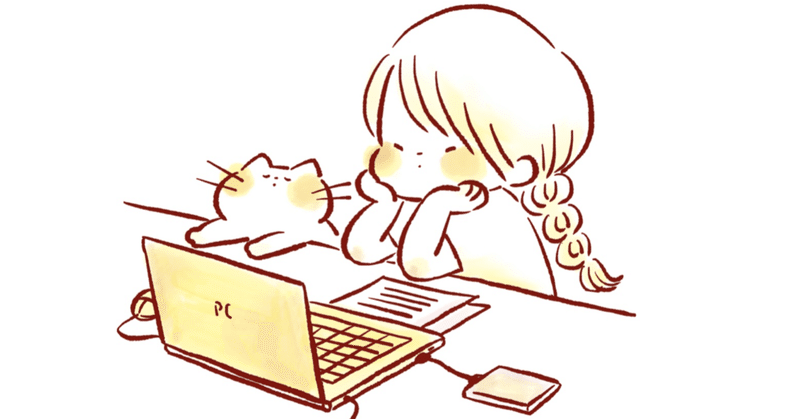
早大入試で不正をした受験生が読み切れなかったもの(2)【「評価」という視点の欠如が与えるダメージの大きさ】
今春の早稲田大創造理工学部の一般入試で、スマートグラスという電子機器を使って入試問題が流出する問題が起きたとのこと。
そのことについて、考えています。
前回はこちら
今回は、「評価」という観点から問題を考えたいと思います。
それはずばり、不正をすることのメリットはあるのかという「評価」の問題です。
ネットの書き込みを見ると、今回の事例は「発覚した事例」であって、水面下ではもっと類例があるのではという見方があるようです。1匹の害虫を見つけたら・・・の論を踏まえると確かにそのような一面はあるかもしれません。
私はそこまで多くはないとみています。
なぜなら、不正をしようという発想は結構トリッキーで、そもそも不正をしようと「思いつかない」のが現実ではと思うからです。
さらに、このラインを突破して不正をしようと思ったとしても、不正をするメリットがあるのかという点を考察した場合、それは「メリットがほとんどない」と結論付けられるのではと思います。
今回の受験生がとった行動は、「手間」という観点からみると、メリットのないことに時間やお金などの受験リソースをつぎ込んだとしか思えません。
ウエアブル端末選びから始まって、操作の練習もあります。さらに、解答を教えてもらう外部委託の算段や解いてもらう人の選定など、やることが多すぎる。
多くの受験生は、ここで、「手間の割には実入りがすくないんじゃないか」と思うのかなと思います。
そうであっても今回の受験生のように「ルビコン川を渡る」人はいるとは思いますが、それは稀なことだと思います。
人間は、何か行動をする際には、無意識であっても「評価」の視点を持って行動していると思っています。不正は心理面のハードルの高さもあり、そう簡単に踏み切れるものではない。
ただ、今回の受験生のように心理的に追い詰められてしまうと、そのような「評価」の視点が抜けてしまうことはあるのかもしれません。
さらに、この受験生が気の毒に思うのが、この方の中に「学歴は不正をしてでも手に入れる価値がある」と思ってしまったことではないかなと思います。
学歴はそこまで絶対的なものではありません。世間には学歴がなくても立派に仕事をしておられる方はたくさんいますし、一方で、高学歴なのに、??という人も少なからずいます。
大卒で入る最初の会社には、学歴は意味を持つとは思いますが、転職によりキャリアアップが一般化している昨今の労働環境では、「転職」のタイミングでは、学歴よりも仕事の実績がものをいう実力社会というのが現実的な考え方でしょう。
また、難関大には、留年を重ねて苦労している人や学力の問題で退学する人もいます。不正をしてまで入学するメリットがあるのかという点まで含めた「評価」では、不正はあまりにも割が合わない。
今回のように発覚してしまうと、ダメージはさらに絶大です。
その意味でも「評価」の視点はとても重要で、思いとどまる抑止の面でも意味があったのではと思っています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
