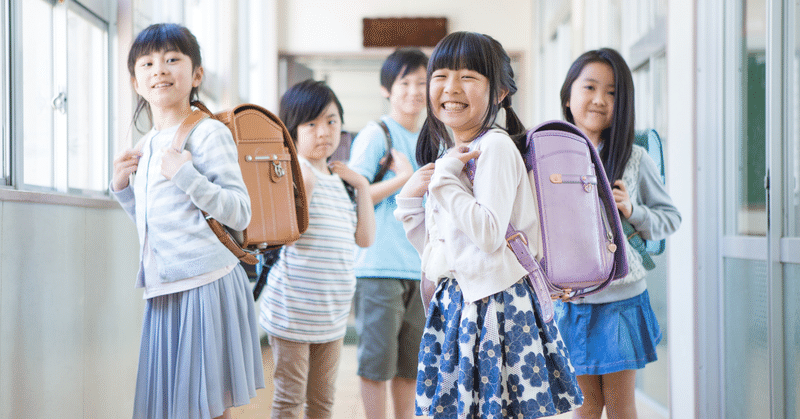
学童クラブに入れたくない
現在、年少の保育園児が我が家にはいます。共働きなので民間の保育園を利用していて、朝8時前から夜6時すぎまで10時間ほど預けています。
このままいくと子供は小学生になるのですが、どうしても学童クラブ(放課後クラブ、児童クラブ、学童保育)に入れることが納得できず、どうしたものかと考えてしまいます。
一般的な共働きの小1の壁
①夏休みなどの長期休暇がある
→学童クラブで解決
②帰宅時間が昼のときもあるがもう時短勤務ができない
→学童クラブで解決
③学童クラブの多くが18時までしか預かってくれない
→延長可能な学童クラブで解決
本当に学童クラブに入れれば「小1の壁」が解決され、みんなハッピーなのでしょうか?私のこの「学童クラブに入れたくない」という気持ちを書きながら掘り下げてみようと思います。
保育園と学童クラブについて思うこと
保育園はすばらしい
保育園では、10時間という長い間預かってもらっているのですが、保育園は本当に良いと思っています。
集団生活に慣れさせるという意味でも必要性を感じています。たくさんのオモチャ、たくさんの遊具、いろんな遊びができ、先生からいろいろと教えてもらえるの保育園は、子供にとって素晴らしいと思います。家庭よりも質の高い保育をしてもらえていると感じています。
留守番は虐待!!ってホントか?
さて小学生になったときのことを考えてみます。現代は鍵っ子は駄目らしく、お留守番は虐待に相当するそうです。たしかに帰宅中にあとをつけられて、誘拐されたとか家に押し入られたといった事件はあります。
専業主婦の家庭の子は安全か?
お母さんが専業主婦でも、友達と分かれたあと一人で家まで歩くこともあります。また、家にランドセルを置いたあと、友達同士で公園で遊んだりします。そういうとき、変質者に遭いませんでしたか?私は遭いました。
留守番していたほうが安全説
1人で鍵を開けるときは周りに注意して、家に入るときは後ろに誰かいないかも注意して、留守番中ピンポンが鳴っても訪問者対応はしない、火事になるようなことはしない、電子レンジに変なものを入れないように教えておく、などの対策は必要だと思いますが…留守番していたほうが安全なこともあるのではないでしょうか。
共働き家庭には学童クラブは必須…
私が「留守番安全説」を唱えても、虐待になってしまう以上、共働き家庭なら、子供が小学生になったら学童クラブに入れなくてはいけません。選択肢はないのです。世間では、保育園の小学生版という認識なのではないでしょうか。果たしてそうでしょうか?
共働きは30年前の20倍になっている
昔の共働き率は2%以上(私調べ)
私が子供の頃は、私の実家も含めて専業主婦のお母さんが多く、1000人くらいいた小学校でも、学童クラブにいっていたのは20人くらいで、学校の敷地内の小さなプレハブで運営していました。鍵っ子もOKだった時代ですが、共働きは本当に珍しい時代&地域でした。
タケノコさんの後ろ姿…
私の通っていた小学校では学童クラブは「タケノコクラブ」と呼ばれていて、「先生さようなら!」のあとはタケノコさん(クラブのメンバー)は、先生と一緒にタケノコクラブのあるほうへ歩いていきました。子供心にその背中がかわいそうに感じていました。
今の共働き率は40%以上(私調べ)
しかし時代は変わりました。共働きのお母さんが増え、うちの子が行く予定の公立小学校は、1600人の児童、1〜3年生800人に対し、複数の民間学童クラブがあって合計300人が収容できるようです。こんなに枠があっても、足りていないというから驚きです。また、塾が高額な学童クラブを兼ねているところもあり、実際には共働きの家庭の割合はもっと高そうです。
学童クラブのなんとなく嫌な印象
思い込みではないです
私は学童クラブに行ったことがなく、タケノコさんの背中しか知らないのですが、学童クラブについて調べて、やることはだいたい分かっています。私の地域の学童クラブは、宿題をする、宿題が終わったらゲームをする、お菓子を食べる、といった過ごし方をするそうです。
嫌いな友達も出てくるでしょう…
保育園は、まだ本人が小さいというのもあり(年長くらいになったら出てくるかもしれませんが)あの子が嫌だとかなんだとかいうのがなく、泣かされても翌日はケロッとした感じで仲良く遊べて、本当にのびのびしています。
しかし、小学生になったらどうでしょうか。嫌な人ができて、そういう人と一緒にいたくないという気持ちも出てくると思います。それなのに、授業中から放課後までずっと一緒にいないといけないというのは、ちょっと酷かなと思ってしまいます。
ぼーっとする時間もなさそう…
もし学童クラブに入ったら、朝から晩まで友達といて、親が迎えにいったあとは慌ただしくお風呂&夕食&就寝となります。今日あったことなどをぼーっと考えて、脳みそを整理する時間が必要に思うのですが、そういう時間がないのはかわいそうかなと思ってしまいます。もし考えようとしたら、寝る時間が遅くなってしまいます。
自分で宿題を考えなくなりそう…
友達と宿題をすると、ぶっちゃけあまり進まかなかった記憶があります。イベントとして、ちょっと変わった宿題は友達とやるのは良いと思いますし、実際私もそういうことをしていました。
しかし、こう毎日毎日学童クラブで友達と宿題をするとなると、自分で考える力がつかなくなりそうです。どうせダラダラと話し合いながら、答えを見せ合ったりして、マジョリティの意見に流されてしまうのではないでしょうか。自分の意見のまま宿題を仕上げることに勇気を持つ、というのも重要なことだと思います。
学童クラブの夏休みは絶対嫌でしょ
朝から晩まで大してやることもなく同じメンバー…
夏休みなど、長期休暇中についてです。朝か晩まで同じメンバーと一緒にいるのです。これは嫌いな友達がいたら耐えられないでしょう。好きな友達といたとしても、朝から晩まで毎日はきついです。心ない友達からは「○○ちゃんと遊ぶの飽きた」と言われ、傷つくことだってあるかもしれません。学童クラブに行ったふりをして、公園で一人で遊ぶ子が出てきてしまうのではないでしょうか。それこそ危ないです。
普通に小学校で授業がある日だったら、いろいろな授業を聞いたり、グループでやったり、いろいろとやることがあるので同じ部屋にいてもべったりではありませんが、学童クラブだと授業もなく朝から晩までべったりです。
ちょっとその状況を想像しただけでも吐き気がします。
毎日同じメンバーと遊びたいか?
小学生のころ、放課後毎日同じ友達と遊んでいる子なんでいなかったでしょう。もしいたら、つまらなくて別の友達と遊ぶようになるはずです。小学生ごときに、毎日楽しいと思わせる引き出しはないはずです。私は週1でクラスの友達、幼馴染、その他複数をローテーションしていた感じで十分でした。
夏休みの学童保育でやること
学童クラブの資料に載っています。
午前中は宿題。
お昼は仕出し弁当。(1食500円)
お昼後はお菓子を食べながらDVD鑑賞会。
午後は自由活動です。
たまに花火で遊びます。
夏休みの宿題なんて、毎日やらなくても終わるでしょう。毎日同じお店の仕出し弁当じゃ飽きるに決まってる!DVD鑑賞会なんて、家でもできるでしょう?自由活動なんて友達でおしゃべりくらいしかすることないのでは…花火なんて1回くらいでしょう…。これは本当に楽しいのでしょうか。楽しいはずはありません。
小学生を犠牲にしてないか?
学童クラブを運営すると、運営費の半分は補助が出て、かつクラブの活動には何の決まりもないため、場所と監視役の放課後児童支援員を配置するだけでもよいようです。学童クラブ運営事業者(ビジネス目的)も絡んでくると、小学生を犠牲にして、大人だけがおいしい蜜を吸うシステムのように感じて仕方ありません。
保育園児と小学生の関係性の違い
どうしてこんなに嫌なイメージが先行してしまうのか、よく考えてみることにしました。そこで大人の感覚で説明すると少ししっくり来ました。
保育園児同士は「昔からの親しい友人」、小学生同士は「会社の同期」といった感じではないでしょうか。そこには恥ずかしさの重みに違いがあると考えます。
ここから先は
¥ 300
家計は火の車です。
