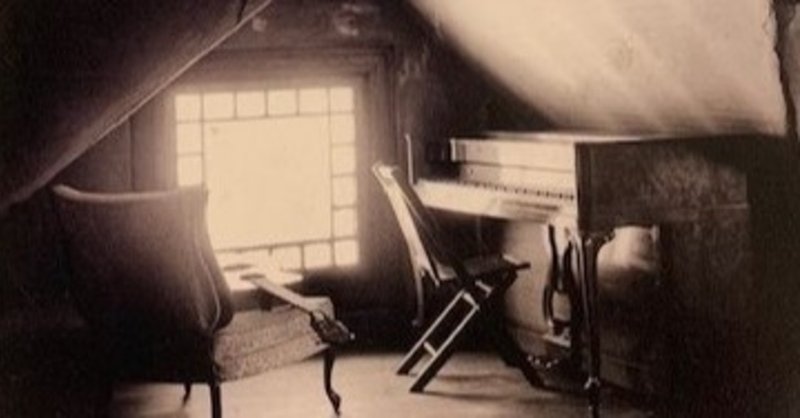
大きな課題がいつの間にか「すり替わって」しまう
河野防衛大臣が、新型迎撃ミサイルシステム「イージス・アショア」の山口県と秋田県への配備計画を停止する考えを表明したのが今月15日。そこからの議論の流れが「おや?」と思わせるものになっています。
このシステム、防衛省によれば「24時間・365日、切れ目なく、長期にわたって」日本を守る柱とされてきたものです。「システム」というだけあり、弾道ミサイルなどの探知から追尾を行うレーダーや、迎撃ミサイルの発射管制までを行う装置などで構成されています。簡単に言えば、「北朝鮮からミサイルを発射されても、察知して撃ち落とすことができる」ようにする仕組みということです。
これを、河野防衛相が「安全性の確保にはお金がかかりすぎることが分かった」として配備計画を停止する考えを表明しました。この報道を聞いた時、私は感心しました。
最近、話題になっているアメリカ・ボルトン前大統領補佐官の回顧録からも明らかですが、トランプ大統領は「アメリカのものを日本に売りつける」ことに熱心です。プロジェクト全体で4500億円とも言われるイージス・アショアがなくなればアメリカから相当クレームが来ることは間違いないですし、よくそれだけの決断ができたな、と。
しかし、ここまでは「自衛」をめぐる話だったのに、その後は急に「相手を攻撃する戦力を持つか」という議論にシフトしています。18日に安倍首相は記者会見でこんなことを言っています。
「相手の能力が上がる中で今までの議論に閉じこもっていいのかという考えのもとに自民党の提案が出されている。そういうものを受け止めなければならない」
自民党が保有を提言している敵基地攻撃能力について、議論を進めるという考えを示したのです。敵基地攻撃能力とは、たとえば北朝鮮が日本への攻撃を示唆してミサイル発射の準備を進めているときに日本が事前に攻撃して発射を止める能力のことです。言うまでもありませんが、アメリカではなく日本の判断で相手を抑止することができる一方で、実際に攻撃すれば間違いなく戦争ですから、非常に大きいリスクを伴います。それに、そこまでするなら自衛のために巨費を投じているイージス艦って何なの?ということにもなります。
安倍首相としては新型コロナもあって政権に翳りが見える中、いままでやりたかったことを実現したいのでしょう。それにしても、こうした重大なことを「イージスアショア断念」という動きの中に混ぜ込んで「防衛の見直しの一環」としてさりげなく進めようというのは、さすが長年トップに座り続けただけのことがあります。都合が悪いことが起こっても「ただでは起きない」というわけです。
私たちとしてはいつの間にか行われている、こうした「議論のすり替え」に注意を払い続けるしかありませんし、安倍首相にはやりたいならもっと正面切って説明してほしいと要求していくしかありません。
「こんな話ではなかった」という印象を持ったところで、今回は逆に「こんな話(解釈)を聴きたかった」という音楽に耳を傾けてみましょう。
フレッド・ハーシュ+ビル・フリーゼルの「ソングス・ウィ・ノウ」です。
フレッド・ハーシュ(p)とビル・フリーゼル(g)はそれぞれの楽器で現代ジャズをけん引するスターだと言っていいでしょう。フレッド・ハーシュは1955年生まれ、ビル・フリーゼルは1951年生まれで同世代です。この2人がデュオでスタンダードを演奏するとなると当然、ビル・エヴァンス(p)とジム・ホール(g)による名作「アンダーカレント」を意識してしまうのは当然です。
しかし、そこはさすがベテランで、フリーゼルの浮遊感あるギターにハーシュが呼応する形でゆったりと会話しているかのような全く別の味わいがある作品が生まれました。しかもよく聴くと曲によってアプローチがかなり異なることも分かり、スリリングな挑戦が盛り込まれているのも嬉しいところです。
1998年、サンフランシスコでの録音。
Fred Hersch(p) Bill Frisell(g)
①It Might as Well Be Spring
以外にも冒頭はスロー・ナンバー。ハーシュの繊細なピアノと共に、フリーゼルがアコースティック・ギターを使っているのが曲想にピタリとはまっています。ほとんどメロディだけの提示で終わる3分ほどの演奏ですが、この始まりで両者がリラックスしていることが窺え、最高のスタートとなっています。
②There Is No Greater Love
こちらは両者が本領発揮(?)。フリーゼルの余韻が伸びるお得意のギター・サウンドでメロディが提示されます。これがやや愛嬌があるというか、ユーモアのあるサウンドでちょっとリラックスさせる効果があります。これに対し、ピアノは硬質なサウンドでメリハリをつけながら寄り添っていきます。ここからなのですが、実はソロに入るとどこまでがギターの持ち分でどこからがピアノのパートなのか分からなくなるぐらい両者がスムーズに移行していくのです。正直、互いのスペースを侵食しあいながら呼吸で入れ替わっているのではないかと思うぐらいです。実際のところは分かりませんが、互いが音楽全体のスペースを意識しながら「入るべきところに入っていく」ような現代らしい、柔軟な演奏です。これを肩ひじ張らずに聴けるのですからすごいですねー。
⑦My Little Suede Shoes
個人的な愛聴曲です。このアルバムの中ではストレートなアプローチが聴けます。まずギターがメロディを提示し、そのままソロへ入っていきます。ここでのフリーゼルはジャズだけではなくロックも消化したアプローチでメロディを巧みに引用しながらリズミカルに楽しいフレーズを弾き続けています。これに対しハーシュのソロもリズムを意識。高音から低音までを駆使することでグルーブを生み出し、音楽に勢いをつけています。2人がいかにこの音楽をエンジョイしていたかがよく分かるトラックです。
⑨I Got Rhythm
有名なエリントン・ナンバーが通常とは全く違うアプローチで演奏されています。メロディとリズムが分解されているのです。最初はピアノとギターの交換(!)でメロディが提示され、次第に混然一体となっていく斬新なアレンジ。ピアノとギターは競い合うのではなく、ほとんどそれぞれを補い合う同じ楽器のごとし、です。やがてギターのリズムをきっかけにピアノ・ソロが始まりますがここではギターがやや攻撃的にスペースを埋めてきます。これに応じて、ギター・ソロの際にはピアノが強めのリズムをつけ緊張感を高めていきます。やがて、ピアノが4ビートを刻む中、ギターがストレートにメロディを奏で出すところは抽象画から具象の世界に入ったように思え、不思議な後味を残します。
この作品、長らくお互いの音楽をチェックしていた2人が、たまたま同じNonesuchレーベルに所属することになったタイミングで制作されました。付け焼刃ではない、互いの音楽に対する理解が円熟の対話を生み出したのでしょう。
アメリカが「世界のトップ」として君臨することを投げ出している時代。
日本とアメリカの関係も変わってくる中で、防衛のあり方も当然、変化していくのは分かります。
ただ、長い日本の国境線を守るのに失敗した過去の戦争の経験から私たちは学ばなくてはいけません。本当に相手を攻撃する能力を持つことで自国を守れるのか。そもそもそんなことにコストをかけられるだけの体力をこの国が持っているのか。周辺国との対話を放棄したリーダーに求めるには難しい課題でしょうが、やるべきことは他にあるように思えます。
この記事は投げ銭です。記事が気に入ったらサポートしていただけるとうれしいです(100円〜)。記事に関するリサーチや書籍・CD代に使わせていただきます。最高の励みになりますのでどうかよろしくお願いします。
