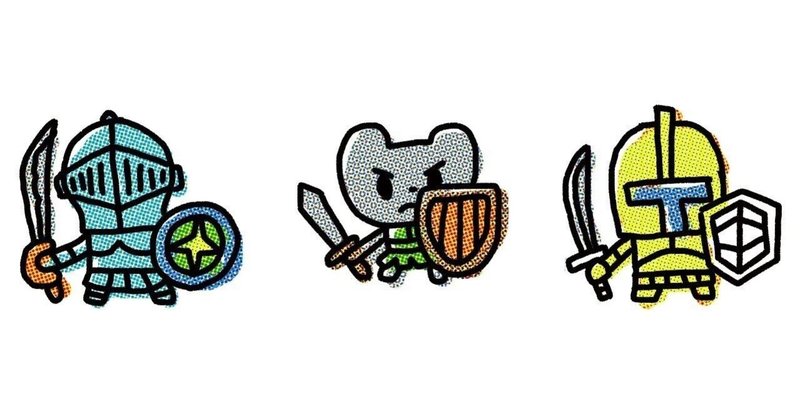
RPGから学ぶグルディス
グルディスとかGDとか呼ばれるグループディスカッション。(以下GD)
参加していてふと、
「RPGみたいだな」
と感じ面白かったので共有。
真面目に頑張りつつも、ゲーム感覚で楽しんで受けて少しでも緊張感を和らげてください。
RPGとGDの基本情報
RPGとは、
ゲームにストーリー性があり、プレイヤーの演じるキャラクターの成長を特徴とするゲームジャンルで、Role-Playing Game(ロールプレイングゲーム)の略称。参加者が各自に割り当てられたキャラクター(プレイヤーキャラクター)を操作し、一般には互いに協力しあい、架空の状況下で与えられる試練(冒険、難題、探索、戦闘など)を乗り越え、経験を通して成長していく過程を楽しみながら目的の達成を目指すゲームである。
引用元:OCA大阪デザイン&IT専門学校「RPG(アールピージー)とは」https://www.oca.ac.jp/glossary/6539/
一方就活におけるGDとは、はじめましてな就活生が4〜6人ほど集められ、決められた時間内に面接官からのお題に関して話し合いを行い結論を導き出すというものだ。
二つには、
✔️ 各自に役割がある
✔️ 協力プレイ
という共通点がある。
GDにおける役割
①ファシリテーター(司会)🗣
議論の進行役。
メンバーが議論に参加しやすい場を作り出す。
②書記✍️
議論のメモを取る役。
オンラインGDではパワーポイントやホワイトボード機能を使って画面共有をしながら行うこともある一方、そういったツールの使用が禁止されているGDもある。
③タイムキーパー⏳
時間管理を行う役。
議論が制限時間内に終わるように時間をチェック。
以上が主な役割だ。
「役割特にないどうしよう😰」となっても大丈夫。
役割に縛られることなく議論が活発になるようにどんどんアイディアを出しちゃいましょう。
タイムキーパーが時間を言うのを忘れていたり、ファシリテーターが議論をまとめるのに苦戦している時等にサポートしてあげると議論が円滑に進みます。
役割に囚われず柔軟に立ち回る必要があるので、全体を俯瞰して見ることができる人の方が力を発揮できそう。
どの役割が評価される?
私がこれまで参加してきたGDはどれも明確に役割決めをしておらず、気がつけば成り行きで決まっていることが多かった。タイムキーパーを決めなくても各々時間を見て、「あと5分なのでそろそろまとめに移った方が良いですかね?」といったように対応できる。
正直、ファシリテーターは評価が高そうという印象があり学生に人気。確かにファシリテーターは目に見えて活躍できるけれど、結局は自分の性格にあった役割を果たしてチームワークに貢献するのが大事なのだと思う。
「クラッシャー」にだけはならないで
GDという名のクエストには障壁が付き物である。
お互いについてあまり知らない状態で議論をしなければならないし、
上手く意見がまとまらないこともあるだろう。
考え方や価値観が異なるのは当たり前のことだし仕方がない。
でも
・自己主張をしまくる
・否定ばかりする
・やたら仕切りたがる
・あまり喋らない
・議論から逸れたことを言う
・とりあえず意見に賛同する
・根拠のない意見、アイデアを出す
のは避けた方が良い。
これらの行為をする人はいわゆる「クラッシャー」認定をされるからだ。
クラッシャーは面接官からの評価が悪くなるだけでない。
他の学生も正しく評価してもらえなくなるリスクがあるため、学生にとっても即追放したくなる。
「あくまでも議論によって結論を導き出すのが学生に課せられたミッションであり、自分がいかに優秀であるかをアピールする場ではない」
ということを常に意識して望まなければならない。
まとめ
RPGでもGDでも、自分の個性を活かしてチームワークに貢献するという点では一緒だ。
GDとはつまり「企業に就職する」というクエストの一つのステージであり、みんなでクリアするという目標を第一に掲げつつ、自分の個性や強みを活かす場であるのだと思う。🛡⚔️
就活は「しんどい」「辛い」「めんどくさい」といったような負のイメージが付き纏いがち。
真面目に取り組みつつも、ちょっとでも楽しめるようにシェアしました。
是非参考にしてみてください🥳
サポートしていただけるなんて飛んで喜びます。ありがとうございます。
