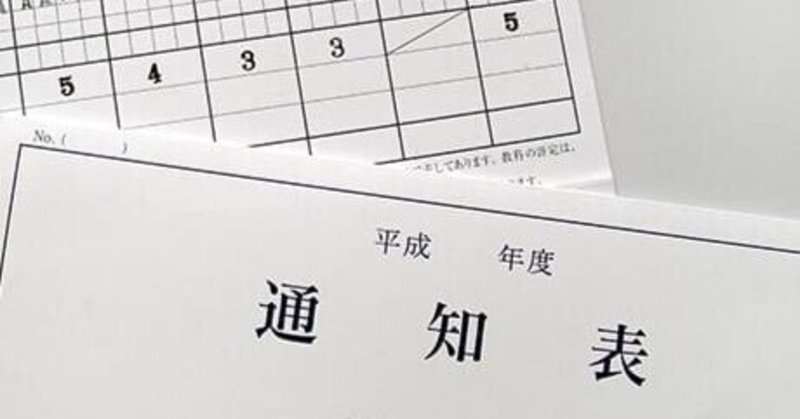
学習のゴールを示そう 評価と成績
はじめに
野球は何回で試合が終わるのでしょうか?サッカーは何分で終了しますか?マラソンのゴールは何キロ先なんでしょうか?全てのスポーツにはルールがあります。そのルールの中で、選手たちは全力を出して競技しています。例えば、陸上競技の100m走と42.195㎞のマラソンでは、練習方法や走り方ももちろん異なります。
学習のゴールを提示しましょう。
学校の成績もスポーツと同じだと思います。学習のゴールや学習評価のルールを生徒に提示しないまま学習をスタートさせていませんか?
教員にとってのゴールとは…
教員にとっては、生徒に身につけてもらいたい学習内容だと考えます。生徒が学習する内容と目標については、指導要領や各教科の解説に示されています。そして、先生方は教えるべき学習単元の内容と目標を踏まえて授業を行っているはずです。学習のゴールを理解した上で、学習計画を立て1時間の授業構成を考えていると思います。ゴールが分かっているので、計画的に授業を進めることができます。
生徒にとってのゴールとは…
批判を恐れずに言えば、それは通信表の成績ではないでしょうか。生徒は通信表で自分の成績を知ります。通信表の各教科の欄には「観点別評価」と「評定」の2つがあります。一般的に観点別評価はA~C、評定は1~5でつけていると思います。生徒は通信表をもらうと一喜一憂します。当然だと思います。それは自分の学習の成果だからです。
教師はその目標をどのようにして評価しているのかを生徒に伝える必要があります。教えないで授業はできません。生徒に失礼です。ゴール地点が何m先なのか、何km先なのかを教えないでスタートラインには立たせる指導者はいるでしょうか?

評価方法と生徒への提示
現在の中学校での評価方法は、各単元での学習内容について、「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」の3つの観点でそれぞれ「A・B・C」で評価します。これを「観点別評価」といいます。そして、この3つの観点をもとに「1・2・3・4・5」の評定を出していると思います。
どうすれば評定が5になるのか。どうすれば観点別評価でAを取れるのか。授業の中でどのように評価していくのか。生徒に提示していますか。
陸上で考えると、ゴールが100m先なのか、24.195㎞先なのか知らないでスタートラインに立つ陸上選手はいません。自分の競技のルールを知り、ゴールがどこにあるのかを知って初めて練習ができるのです。
今学んでいる学習内容のゴールと評価方法を知ることで、生徒は意欲的に前向きな学習活動が行えるようになると思います。
行ってきた評価方法
私の現職時代は、観点別評価は、「知識・理解」「技能・表現」「科学的思考力」「関心・意欲」の4つでした。
生徒には、この1年間どのような場面で評価するのかを授業開きの時間だけではなく、定期テストの返却時や普段の授業で伝えてきました。具体的には、
「知識・理解」は定期テストと小テストで、「技能・表現」は実験レポートの内容や実験時での行動観察で、「科学的思考力」は、定期テスト内での記述問題や実験レポートでの科学的表現や授業中での発言やノートへの記載内容で、「関心・意欲」は実験レポートやプリント・ワーク類の提出状況、授業中の発言等で評価してきました。また、授業中の態度等も参考にしました。
そして、4つの観点を数値化して達成度によって観点別評価を行いました。80%を超えればA、50~80%ではB、50%以下はCとしました。4つの観点別の成績の組み合わせで5段階評価を行いました。また、定期テストでも3つの観点で評価できるようにしました。これについては「指導と評価の一体化」とあわせて記述したいと思います。
そして、この評価方法を生徒に提示しました。実験レポートはすべて評価を加え返却しました。結構大変でした。様々な提出物の提出状況を伝え、締め切り日以降も減点で対応しました。定期テストは3つの観点を別々に採点しました。詳しくは後述したいと思います。授業中の発言や態度については開示しませんでした。
おわりに
どのようにして自分の成績がつけられているのか。生徒は知る権利があります。そして、教師は責任をもって生徒を評価し、自信をもって提示することが大切です。
では、また。
追記:桃だより
桃の選定作業も終了し、最初の消毒も終わりました。
小さな芽吹きが見られます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
