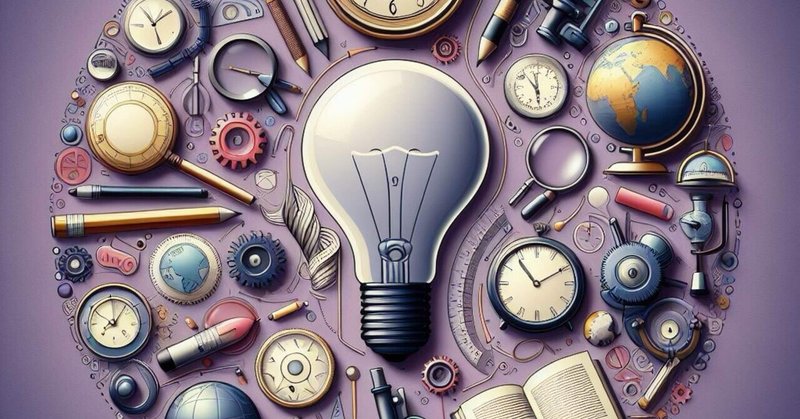
ツールを授業で使うバランス
GoogleforEducation認定トレーナー&コーチの笠原です。
久々の三連休なので積読にしてある本を手にとって読んでいます。本日、読んだ本はこちら。
『「思考ツール×ICT」で実現する探究的な学び』
ICTが教室に入ることで思考ツールもかなり使いやすくなりました。
ロイロノートはもちろん、Canvaなどを利用すると、テンプレートによって簡単に思考ツールを使うことができ、また、様々な教材で思考ツールが紹介されることもあり、体感的には高校に入学する前にかなり多くの生徒が思考ツールに触れたことがあるように感じます。
今日読んでいる『「思考ツール×ICT」で実現する探究的な学び』の中でもまえがきでこのようなことが書かれています。
「思考ツール」はすでにさまざまな書籍や実践が紹介されており、その中では、多くの素晴らしい実践例に触れることができる。
一方で、思考ツールの活用そのものが目的化してしまったり思考ツールを使ったものの、子供の思考がまったく深まっていなかったりするような実践も散見される。
これは「思考ツール」を「ICT」や「生成AI」と置き換えても同じことが言えるでしょう。
今回はツールをうまく授業に取り入れるためのバランスについて考えてみようと思います。
自己目的化を理由にしない
授業で何かを使おうと思うと、常に自己目的化に気をつけなければいけないのです。
ただ、これもICTの導入の時に何度も言われてきたことですが、「自己目的化してはならない」ということが「ツールを使わない理由」にはならないということです。
新しいツールで深い学びを実現しようと思うのであれば、ある意味でマンネリ化してツールを使うことが自己目的化していると言われてしまうくらいに使い込んでいることは必要だろうと思います。
意識して変化を取り入れようとしないと、安定していることを繰り返したいと思うバイアスは必ず働くものです。だからこそ、多少の自己目的化も手段としてツールとは付き合う必要があると考えます。
常に選択肢を用意する
とはいえ、自己目的化した実践は停滞を招きます。ツールを繰り返し利用して習熟することも必要ですが、それでも「使わせる」ことが目的となっているのであれば、修正は必要なのでしょう。
ここでやはりICTの強みを活かしたいところです。
ICTであればプリントのような授業前に大きな手間をかけて準備をしなくても、授業で使えるツールを複数準備しておくことが可能です。
一つの単元において、学習課題を達成するために使えるツールを複数想定しておき、学習者が選べるようになれば良いのだろうと考えています。
使うか使わないかを含めての判断してもらい、様々な見本を用意するのがよいのだろうと思います。
こういう形になると授業準備の仕方自体もかなり変化してくるはずです。子どもたちの思考を想像するということの重要性が増すはずです。
そういう授業準備はハードルは低くないのですが、少しずつ授業での子どもたちの見え方も変わるため、今後、大切になってくるだろうと考えています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
