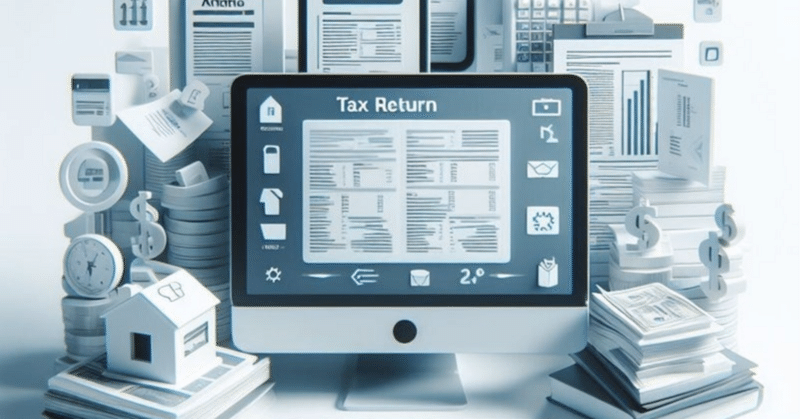
テレビは長命、パソコンは短命
テレビを見ていて何気なく「テレビて壊れないね」と言った。聞いていた家内が頷いたので、やはり壊れないのだろう。それに比べて、コロナ禍が始まる直前に買ったパソコンが去年動かなくなり、買い替えた。この違い不思議だな、と、感じる。
子どもの頃に白黒テレビがわが家に来た。四脚付でカーテンがついていた。おもむろにカーテンを開けて、観る。映画の銀幕のような、家で映画が観られる期待感を感じさせようとしていたのだが、今思えば、子どもだましのような物だった。それからカラーテレビが現れ、次第に大きくなるとともに反対に薄くなっていった。買い替えなくても良いのだが、カラーテレビは欲しい。小さいテレビより大きいほうが見栄えがする。やはり買い替えてしまった。
普及率を見ながら、次の新製品を出していくのは企業戦略なのだろう。テレビの需要を新機能で新たに呼び起こしていた。水がめがいっぱいになったら、新しい水がめを作る。そうして、消費者は新しい水がめに飛びついていった。わが家もそうだった。
これらは、選択的決定だったが、一度だけ、地上波に変わったときに、強制的な買い替えをしなくてはならなかった。この時は、国家政策に乗って、あわてて地デジ対応テレビを買った。テレビの販売数はかなり多かったはずである。それから数年、テレビは異常を来たさずに使われている。たしかにテレビは壊れない。
販売戦略には、①新製品を出すやり方 ②今の機能が使用できなくするやり方の2つがある。
白黒テレビ→カラーテレビ→巨大・薄型テレビ→高画質テレビと新たなモデルに変えて行くのが①だ。②は地デジ化のように旧型を使えなくするやり方だ。経済成長には、需要を喚起する新たなものが必要である。
パソコンは、随分と買い替えた。初期のパソコンはMS―DOSで動いていた。MAC系のパソコンもあったが、マイクロソフトのOSが入ったものが多く出まわっていた。私は、NECの98シリーズを買ったが、Windows3.1やWindows95まではOSを買ってきて、自分でインストールしたが、やはり、スペックを上げるために新しいデスクトップパソコンを買った。ノートパソコンが普及した頃から、OSの進歩と共にパソコンを買い替えなくてはならなくなった。自分の意思でというより、いつの間にかパソコンが重たくなり、また新たなソフトに対応できず、仕方なく買い替えていたようだ。CD―ROMに代わりDVDが出たとき等はそうだった。Windows98で使えたCDアプリは今では全く使えない。OSは、Windows7、8、10、11と変化し、旧式を維持しようとしても、いつの間にかパソコンを買い替えるハメに陥っている。
最近では、コロナ禍になる直前に買ったパソコンが使っているうちに重たくなり、起動に数分かかり、アプリの立ち上げも遅くなったが、我慢して使っているうちにとうとうダウンした。新しいパソコンに買い替えたが、Windows11になったら、確定申告に使っていたICカードリーダーが使えずに買い直しした。デジタル化は出費が多いなとぼやいている。
販売戦略②の呪縛からは消費者は逃れられない。これも国家程に力を持った企業の戦略として、受け入れざるを得ないのか、人類の進歩のためには必要なものなのだろう。
情報分野では、パソコン以外には、今世紀になり、新たにスマホやSNSが生まれたし、新たな技術が全く別の場所から生まれる余地はあるようである。寡占化の中でも切磋琢磨による進歩が行われている。新技術こそが成長の鍵だと改めて思えてくる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
