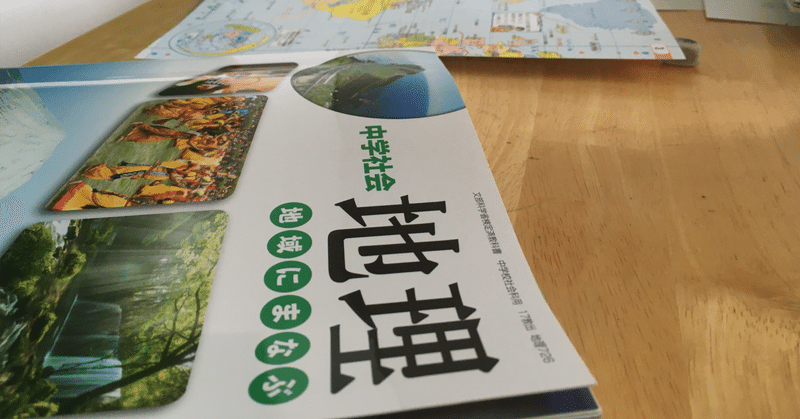
デジタル教科書と学習内容の詰め込み過ぎを思う
子どもが高校に進学するにあたり、これまで学校から支給されていたタブレットPCは返却し、自前で教育用タブレットを購入することになりました。
学校推奨のタブレットを、指定された業者から購入することも検討しましたが、破損保証付きとはいえ、少し割高であったことから、
・OSがChrome OSであること
・画面サイズ11.6インチ以上
・キーボード、カメラが付いていること
の3条件が揃っていれば、別な機種を自前で購入しても良いということなので、要件を満たすタブレットを探し、Lenovoの「 IdeaPad Duet 560 Chromebook/13.3型/Qualcomm Snapdragon 7c Gen2/メモリ4GB/eMMC128GB/Chrome OS/ストームグレー」を購入することにしました。
子どもが機種を選ぶにあたり重視したのは、
・なるべく軽い機種であること
・キーボードの取り外しができること
でした。
これまでの学校支給のタブレットPCは取り外しができないタイプで、おそらく一括発注のタブレットPCにありがちな安普請のため重量もあり(偏見かも)、教科書、副教材などと一緒に持ち歩くと、リュックが脱臼するんじゃないかと思うぐらいの重さになるため、少しでも軽くしたいということのようです。
以前も書いたような気がしますが、僕が中高生の頃に使っていた教科書に比べ、サイズも大きくなり、ページ数も増え、それに加えて、カラーページがデフォルトになったことで、明らかに重くなっています。
少し前のテレビ局の特集でも、16年で教科書の重さが倍になったことが、取り上げられていました。
デジタル教科書の導入は、2024年度に小学5年生から中学3年生までの英語に先行導入され、その後、順次導入を拡大していくようです。ただ、全面的に切り替わるには、しばらく時間がかかるということでしょうか。
教育関連のサイトでこの事実関係を調べた際に、デジタル教科書導入の理由として、より多くの情報量を盛り込むことができて、教科書の内容が充実するようなことが書かれていました。
ただ、実際、今のてんこ盛りの教科書でも、消化しきれているのでしょうか。僕も子供の教科書を一通り見たことがありますが、現在の教科書には「考えてみよう」のようなコーナーや、コラムなどが豊富に盛り込まれていて、正直、本線上のカリキュラムを消化していくだけでも、それなりに大変なはずなのに、こうした学びを深めるコンテンツが、授業でどれだけ使われているのか、疑問です。
これで、デジタル化をすると、ある意味「あれも、これも」入れることが可能になってしまい、フルスペックの電子辞書のように、ほとんど使わないコンテンツが大量にインストールされ、何となくお得な気分になるだけで、実際には使わない、そういったことになるような気がします。
デジタル化により情報量が増えても、人間の認知のスペックは30年前も今もあまり変わらないはずであり、情報過疎は困りますが、情報過多もそこから必要なものを選び取るために、認知を余計に使うことになります。
「精選」という言葉は、何事においても非常に重要な要素であり、学びにおいては、学び手が素人であるほど、精選されたテキストが重宝される。
結局、分厚い参考書を使いこなせるのは、使い手がポイントを理解していることが大前提であり、初心者が、分厚い参考書を1ページから取り掛かれば、確実に挫折します。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
