
2021年間ベストアルバム50選
ワクチンが行き届いてくれたおかげでようやくコロナ禍からアフターコロナのフェーズに一歩進んだか…と思っていたらまた新たな変異株が出てきたりと、相変わらず予断を許さない昨今。まあ去年よりはずっとマシになったかとは思うが、もちろんパンデミック前の状態に戻ることはないだろう。ただ言えるのは、決して悲観的ばかりになる必要はないということだ。野外フェスの開催は今年の夏に散々議論の的となっただけに、来年以降もどのような形になるか定かではないが、様々な経験や教訓を生かしてコロナ以降のライブスタイルは徐々に開拓されてきているはずだ。また音源のリリースに関しても、表現者たちは厳しいコロナ禍をどうにか耐え抜き、何ならこの危機的状況をチャンスとも捉え、今年も数多くの傑作を発表してくれた。やってやれないことはない、ということを様々な形で示してくれた事実に、一介の音楽ファンとしてはただただ感謝、敬意の念しかない。そんな作品群の中から自分が個人的に特に優れていると感じた50枚を以下に羅列し、あまつさえ順位をつけた。このリストが皆さんの音楽ディグの参考になればこれ幸い。
また、この記事を基としたプレイリストを Apple Music と Spotify で作成してあるので、時間のある方はこちらもどうぞチェックを。
50. Patricia Brennan "Maquishti"

メキシコ出身のマリンバ/ビブラフォン奏者。楽曲は完全に本人のみの独奏で、一連の明確なフレーズを構築するのではなく、即興も多く交えながら音の断片を空間的に散りばめたり、深遠な残響音をドローン/アンビエント的に活用したりで、ミステリアスな浮遊感と緊張感が綯交ぜになった独特の音響空間を堪能できる。楽曲ごとに微妙に質感の違う音を使い分けたり、時にはギター用のエフェクターを用いるなどの工夫が成されており、音数が至極シンプルなだけにそういったニュアンスの差異も引き立っている。音が発生してから消失するまでの隅々、そして音の隙間に潜む静寂までもが実に味わい深く、聴き終えた後は頭の中がすっかり浄化された心地に。ジャズや現代音楽の界隈でもここまでマリンバ/ビブラフォンという楽器のみの魅力を端的にパッケージした作品は珍しいのでは。
49. India Jordan "Watch Out!"

イギリス・ロンドン出身のプロデューサー。内容は火の玉ストレートでアドレナリンを噴出させてくるレイブサウンド。性急なスピードで聴き手を鼓舞するブレイクビーツには、例えば The Prodigy などと同様にロック成分も多く加味されているように思う。とにかくビートの即効性が強く、曲開始からすぐさま我を忘れるくらいの熱狂、恍惚から多幸感へと誘われる。この世に涅槃などは存在しないが、もしあるとしたら周囲を完全にシャットアウトするほどの爆音でこの音楽が鳴り響いているダンスフロアだろうし、それは世の中がコロナ禍に入ってから今に至るまで、自分からはそれこそ涅槃のようにすっかり遠い状態になってしまっている。最高の音で最高になれる時間を奪還するべきだ。この音を全身で浴びれば俺は自分の人生を讃美できる。それまで生きたるわ。
48. Chris Corsano & Bill Orcutt "Made Out of Sound"

アメリカ・ニュージャージー出身のドラマーとフロリダ出身のギタリストによるコラボ作。情報によれば今作は実際に顔を突き合わせてのセッションではなく、各々が別の場所で別の時間に録音したものを Bill Orcutt が編集で組み合わせたものなのだと。それで何故こんな丁々発止の臨場感が生み出せるのか、素人の自分などには到底理解できない領域に彼らは到達している。絶え間なく縦横無尽にロールし続ける Chris Corsano のフリージャズ風ドラミングと、鋭い弦の鳴りの隙間に仄かなノスタルジアを滲ませる Bill Orcutt のブルージーなギタープレイ。盛大に感情を爆発させるむせび泣きのようなプレイ同士がぶつかり合い、情感と気迫が倍増されてひとつの荒ぶる大河と化し、聴き手の意識はその波にすっかり飲み込まれ、ただただ固唾を飲んで行く末を見届けるしかできなくなる。カタルシス待ったなし。
47. Genghis Tron "Dream Weapon"
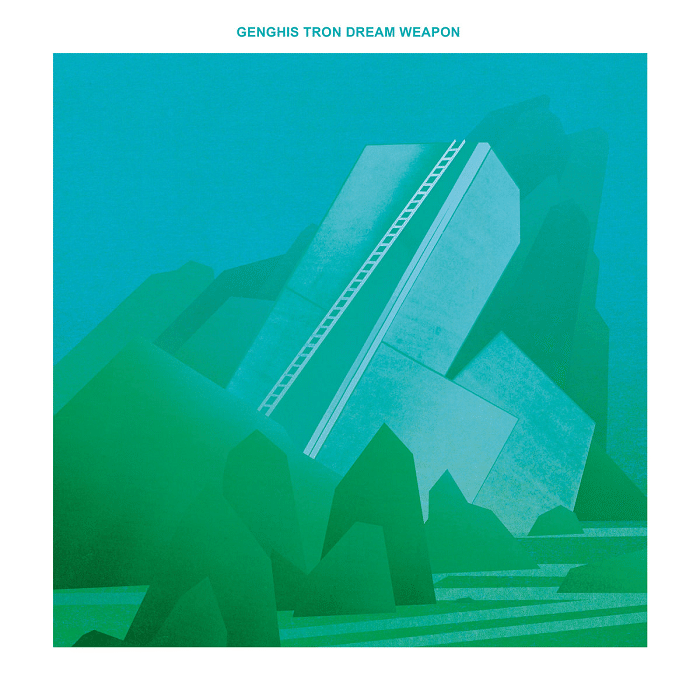
アメリカ・ニューヨーク出身のメタルバンド。10年間の活動休止を経て昨年いきなり再始動を発表。しかもボーカルに Tony Wolski (The Armed) 、ドラムに Nick Yacyshyn (SUMAC/Baptists) を迎えての新体制。さらにこの新譜ではプロデューサーに Kurt Ballou (Converge) 御大、サウンドプロダクション担当に Ben Chisholm (Chelsea Wolfe) を起用という、まあドリームチームかという盤石の布陣なわけだが、かつてサイバーグラインドと形容された苛烈な攻撃性は鳴りを潜め、代わりに空間的なシンセがアンビエント風の浮遊感を醸し出し、淡い色彩が豊かに広がるサイケ/スペースロック的な方向へと大胆にシフトしている。ただそれでもテクニカルなドラムプレイを筆頭にメタル由来の骨太さは十分引き継がれているし、今年の The Armed の新譜がメタル/ハードコアの枠組みを破壊する野心に満ち満ちていたのと同様に、彼らもまた形式的な激しさよりもアティテュードの激しさを追い求め、最終的に他にはないユニークなメタル像をここに完成させている。彼らの再始動は懐古ではなく前進のためだった。
46. Skullcrusher "Storm in Summer"

アメリカ・カリフォルニア出身のシンガーソングライター。基本のスタイルはアコースティックギター弾き語りによるフォーク/カントリーだが、マルチプレイヤー Noah Weinman の助力もあってか、アレンジ面ではシューゲイザーに通じる幻想的な浮遊感を随所で重ねてきたり、"Prefer" ではささやかなシンセを交えてのアンビエントポップを披露したりと、わずか5曲の中でも様々な工夫が凝らされている。ところで表題の「嵐」とは、彼女が昨年にデビュー作をリリースしてからの賛否含めた喧噪を差すとのこと。自分の曲が批評に晒され、想定していたよりも多くの他者に歌詞を細かく解釈されることに困惑を隠せず、時には自信を喪失してしまうこともあったという。そういった苦悩、そしてそれらを振り切っていこうとする気概が、優美な歌と演奏でコーティングされることでますます真摯さを増して響いてくる。もちろん Nick Drake へのシンパシーの表明も見逃せない。
45. Lava La Rue "Butter-Fly"

イギリス・ロンドン出身のラッパー。ラップのみならず歌もきっちり聴かせるスキルの卓越っぷりもさることながら、とにかく1曲1曲の質が高い。ともすればドリームポップの領域にもリーチするトラックの陶酔感の強さ、そして「恋」を一番のテーマに据えているが故の、思わず涙を誘われるほどに甘美なメロディセンス。Isom Innis (Foster the People) 、Clairo 、Vegyn も制作に携わっているとのことだが、参加者全員の足並みが綺麗に揃った上で完成したサイケデリック・ラップソングは、わずか5曲ながらその5曲すべてがキラーチューンと呼べるほどの出来栄え。昨年発表のリード曲 "Angel" を筆頭に、ひどくセンチメンタルで、官能的で、溢れ出す多幸感は時に祝祭的な空気すらも醸し出す。もちろんそれは一転して心を傷つける毒と化す危険性も孕んでいるが、「恋に夢中になり、自分の人生におけるすべてのネガティブなものを断ち切ったように感じた」とインタビューで語る通り、恋心を原動力としてクリエイティビティを加速させている真っ最中の彼女は表現者として全能状態だ。恋は最強。
44. (sic)boy "vanitas"

東京出身のラッパー。L'Arc-en-Ciel をきっかけに音楽に目覚め、学生時代には SiM やマキシマム ザ ホルモンをコピーしていたという彼にとって、昨今のヒップホップ界隈を中心に起こっているニューメタルあるいはポップパンクの再評価ブームは、もちろん自身の名を上げるには絶好の機会だが、その他大勢と十把一絡げにされる危険性も裏側には含まれているはず。しかし彼は今作の痛快なクオリティの高さでもって頭一つ抜けることに成功した。主幹は当然ヒップホップだが、パンキッシュな疾走感、鋭いヘヴィネス、開放的なシンガロングメロディ、時に淫靡なダークネスをも貪欲に取り込み、あくまで快楽原則に忠実に、かつ乱雑とも言える自由な手つきでまとめ上げた楽曲群は、ヒップホップ、パンク、メタル、J-POP 、どの枠組みを当てはめてみても必ずどこかがはみ出してしまう。そこで自分はこんな記事を書いていたりもするので、あえてこれを2021年の、最新型のヴィジュアル系と呼んでしまいたい。メイクさえしていれば音楽性は何でも良かったはずのヴィジュアル系というジャンルは、ちょうど彼のためにあるようなものだ。
43. Lande Hekt "Going to Hell"

イギリス・エクセター出身のシンガーソングライター。女性かつ同性愛者である彼女は差別/抑圧の対象となってしまうことがままあり、その事実が今作に収められた瑞々しく愛らしいインディ・フォークロックの数々に深い影を落としている。彼女が属するパンクバンド Muncie Girls の快活さとは対照的に、素朴で感傷的なラブソングにはふとした拍子に何もかも崩れ去ってしまいそうな脆弱さが常にあり、表題曲 "Going to Hell" と "In the Darkness" のラスト2曲では表明張力を超えてコップから水が溢れ出したかのごとく率直な怒りが露わとなる。自分という存在を伏せざるを得ない現実に対する抵抗の表明。繊細な歌声は激しい叫びであり、シンプルで牧歌的なメロディ、柔和な音の響きが真摯さをまとって鋭い棘を胸に刺す。これこそエモーショナルの結晶と呼ぶべきもの。
42. Charlotte Greve "Sediments We Move"

ドイツ出身のサックス奏者。今作は彼女のバックバンド Wood River とベルリンの合唱団 Cantus Domus を招き、全7楽章の組曲として綿密に構成を練り上げて完成したもの。アルバム表題の Sediment とは堆積物を差すわけだが、それこそ水や土が形状を変えながら積み重なってひとつの大きな塊を成すのと同様に、重厚なクワイアによるクラシカルの荘厳さ、ジャズの洒脱なしなやかさ、エレクトロニクスを導入してのアンビエント風の幻惑感、そしてそれらをバッサリ切り裂くように繰り出される Wood River のフリークアウト状態な肉体派アンサンブル、そういった雑多な要素が重なり合って複雑かつ壮大なアマルガムを形成している。柔から剛へ、美しさから畏怖へと質感をグネグネと変容させて長大な循環の流れを生み出していく様は、クラシカルと言うよりも King Crimson の末裔として捉える方がしっくりくる。菅野よう子ファンにも響きそう。
41. New Age Doom & Lee "Scratch" Perry "Lee "Scratch" Perry's Guide to the Universe"

カナダ・バンクーバー出身のメタルバンドとジャマイカ出身のシンガー/プロデューサーのコラボ作。自分がレゲエ/ダブの元締め Lee Perry を生で確認できたのは2016年のフジロックが最初で最後だったが、酩酊感100%の演奏と音響の中で訥々と歌を聴かせる彼は、観客全員を置き去りにしてひとりで宇宙へと解脱しているようにしか見えなかった。惜しくも今年8月に逝去した彼にとって、結果的に今作は(おそらく)生前最後のレコーディング作品となったわけだが、それが新進気鋭の実験的ドローンメタルデュオとのコラボというのは、ある意味いかにも彼らしいトガりっぷりだ。今作はレゲエと言うよりもドローンノイズやインダストリアル由来の重くダークな雰囲気が色濃く、ダブの音響性が持つ緊張感やアグレッションが極端に引き立てられた、Lee Perry 流のハードコアとでも言うべき先鋭的な内容。混沌そのものなダブサウンドの渦の中で歌われる "Life is an experiment" なるメッセージの説得力たるや。
40. Really From "Really From"

アメリカ・ボストン出身のロックバンド。メンバーの多くが日本や中国、プエルトリコといったアメリカ国外の血を引いており、これまで事あるごとに訊かれてきた「本当はどこ出身なんだ (Where are you really from) ?」という質問はバンド名の由来であると同時に、今作の最たるテーマでもある。エモ/ポップパンクにジャズテイストを加味して骨太さと優美さを両立した楽曲はそれ単体でも十分ユニークで味わい深いものだが、ミックスという出自に由来する戸惑いや逡巡、そしてその出自を受け入れて前進せんとする力強さを明確に綴った歌詞も含めて、今作は複雑なニュアンスを含んだ、実に噛み締め甲斐のある傑作となっている。American Football 直系と言える滋味深さはもちろんのこと、個人的には "Try Lingual" の、決してシリアスにばかりなりすぎず、どこか陽気でコミカルにも映る曲調がバンドの懐の深さを明示しているようで、特にお気に入り。
39. Cookiee Kawaii "Vanice"

アメリカ・ニュージャージー出身のシンガー。Kawaii 概念のパイオニアであるところのきゃりーぱみゅぱみゅが、自身の持つ審美眼のみを頼りに「可愛い」と思うもののみを組み合わせてオリジナルの Kawaii スタイルを定義していたことを考えれば、Kawaii の本質とは混淆であり、愛情であり、自分自身をエンパワーするためのポジティブなバイブスであると言える。それならばこの Vanice Palmer が Kawaii を自称することにはいささかの矛盾も存在しない。収録曲すべてに高速4分打ちを基調としたジャージークラブのリズムパターンを採用し、R&B やヒップホップの要素も盛り盛り。また歌詞もシンプルなラブソングから、朝まで踊り明かすダンスフロアの熱狂、ゲーム/アニメ、ボディポジティブやフェミニズムなど、要するに彼女の中の愛情、信条のみが詰め込まれている。一時は「Kawaii は差別用語だ (Kawaii is a slur)」などという言説がネット上にはびこっていたが、"H@ters Anonymous" において彼女は「ヘイターはすっこんでろ」と前もって宣告済みだ。この作品こそ彼女にとっての Kawaii そのものであり、その正義は決して揺るがない。
38. Full of Hell "Garden of Burning Apparitions"

アメリカ・ペンシルベニア出身のメタルバンド。単独名義のフルレンスはこれでもう5作目だが、勢いは衰えるどころかなお加速しており、相変わらずの頼もしいろくでなしっぷりだ。爆速で放たれるグラインドコアサウンドは音割れも何のその、むしろノイズ処理も施して一層ひしゃげた音像に仕立て上げ、全パートが渾然一体となった上にブラストビートで細切れになって襲い掛かってくる様は、まるで執拗なストロボフラッシュで神経を逆撫でられているようで、バンドが本来備えるネチっこい悪意、キモさを頼んでもいないほど的確に反映している。また "Murmuring Foul Spring" の冒頭をドス黒く飾るバスクラリネット、"Derelict Satellite" のピュアなインダストリアルノイズ、"All Bells Ringing" のワウペダル、"Reeking Tunnels" でブラストを止めて真っ当になるリズムなど、随所の仕掛けがいちいちキモさを倍増させる方向にしか作用していない。今までアルバムに一曲はあった長尺曲が今回はなく、12曲21分とランニングタイム最短記録を更新しているのも含め、より濃縮されたグラインド魂の真髄を体感できる。一生やってろ!
37. Azu Tiwaline "Draw Me a Silence (Extended Version)"

チュニジア出身のプロデューサー。彼女のルーツであるベルベル人(北アフリカの先住民族)の伝統音楽、そしてサハラ砂漠の広大な景色に着想を得た今作は、極めてヘヴィで冷徹なベースミュージックによってアフロビートの躍動を雁字搦めにした、彼女ならではのバランス感覚が光るインダストリアル風ダンストラックの応酬。ルーツ回帰と言うよりも独自の解釈によって新次元へと歩を踏み出す意欲作となっている。ところで今作に収録されている楽曲のほとんどは昨年の EP 作 "Draw Me a Silence Part. I" "Part. II" ですでに発表済みなのだが、あえて2021年作品とした。何故ならこのデジタル配信限定の Extended Version のみに収められた新曲 "Eyes of the Wind" が、ビートを後退させてアンビエントの浮遊感を前面に出した異色の作風で、シリーズ最終章と位置付けられていると同時に、彼女の今後の方向性を示唆しているであろう重要曲だからだ。この最後のピースが加わることでようやく彼女の初フルレンスは完成に至った。
36. YUNGMORPHEUS & Eyedress "Affable With Pointed Teeth"

アメリカ・カリフォルニア出身のラッパーとフィリピン・マニラ出身のプロデューサーによるコラボ作。YUNGMORPHEUS は単独/コラボ含めて今年だけで3作、この3年間では10作ほどのフルレンスを上梓している多作派なのだが、基本的なスタイルは一貫している。ソウル、ファンク、ジャズをサンプリングしたローファイなトラックに、フックらしいフックを設けず、思いきり力の抜けたテンションで飄々とラップを乗せていく、まるで酔拳のようなクールネス。そんな作風がこの最新作ではさらにブラッシュアップされている。全18曲のまさしくすべてにおいて、意地でも力を入れてやるかとばかりにレイドバックしっぱなし。残念ながら歌詞は確認できていない…どうやら政治的に辛辣な内容も多く含んでいるらしいが、それでも淡々と緩やかに流れるばかりの楽曲の酩酊感は、聴き手を発奮ではなく微睡み、瞑想へのみ向かわせる。ここまでズブズブに特化した味わいは彼独自のものだろう。
35. Nubiyan Twist "Freedom Fables"

イギリス・リーズ出身のジャズバンド。10人編成の大所帯に加え、人種/国籍を問わずすべての曲にゲストボーカルを配しての賑やかさが際立つ。また曲調もジャズを起点としつつ、しとやかな R&B ポップからオーディエンスを扇動する高速ダンスチューン、牧歌的なアフロポップなど実に多彩。バンドメンバー間のみならず客演含めての化学反応を楽曲ごとに発生させ、細かなジャンルの区分に囚われない雑食のエンターテインメント性を存分に発揮している。そしてそれは現代のジャズシーンがいかに多様性に満ち、伝統も先鋭も、前衛もポップも柔軟に取り入れられる層の厚いジャンルであるかを雄弁に提示するものでもある。その意味で2021年時点のジャズシーンの写し鏡、ある種の上質なコンピレーションとも捉えられる作品。
34. Charlotte Day Wilson "ALPHA"

カナダ・トロント出身のシンガーソングライター。ソウル/ R&B を軸としつつ、BADBADNOTGOOD の面々を迎えてのトラディショナルなジャズテイストや、Syd (The Internet) のゲスト参加とともにトラップ風の洗練されたグルーヴを取り入れたり、その他にも生演奏のしなやかさとエレクトロニクスの先鋭性を同居させたアレンジなど、それぞれの曲を注意深く聴けば多彩な試みが盛り込まれているのが分かる。ただそれらすべては Charlotte 自身の声によって完全に統率されており、各サウンド、各ジャンルの境目はすっかり融和して溶け合い、歌声が醸し出すビタースウィートな憂鬱の色合いにすっかり染め上げられている。シックに落ち着いたようでいて、場の空気全体を支配するパワーを実は持ち合わせた、初フルレンスにしてすでに貫禄を感じさせる歌声なのだ。繰り返し聴くほどに体に深く染み渡る。
33. Black Dresses "Forever in Your Heart"

カナダ・トロント出身のエレクトロデュオ。ネットの片隅で出会って意気投合した二人は、音楽を作ってネットでバズを起こすことに成功するが、やがてネットの有象無象から理不尽な迫害を受けて活動休止を余儀なくされた。今作はその活動休止宣言後に、グループが存続しているのか不明瞭な状態のままでリリースされている。乱暴に言えばこれは神聖かまってちゃんと同じ音楽だろう。もちろん音楽的な差異はある。彼らの曲はチップチューンにも近い奇矯なエレクトロビートが縦横無尽に暴れまわり、そこに鋭くヘヴィなギターを噛ませ、陰鬱で病的なムードをとことんグロテスクに、直接的なインパクトの強いものに仕上げたものだ。ただいずれにせよ、この作品は居場所をなくして傷だらけの心を抱えた人間による、極めて生理的、反射的な危機感から発せられた防衛本能であり、「やるべきか否か」ではなく「やらざるを得なかった」類の音楽だと思う。このような作品は本来ならばこの世から一切なくなるべきなのかもしれない。
32. 食品まつり a.k.a foodman "Yasuragi Land"

名古屋出身のプロデューサー。ジューク、フットワーク、ダブステップなど先鋭的なクラブミュージックを基盤としながらも、やたらとシュールでファニー、ストレンジだけど妙にポップというオリジナリティ溢れる作風を確立している彼が、そのシュールさ、ファニーさにますます磨きをかけてきたのが今作。リズムパートのみならずギターや管楽器など上モノのサンプル音も断片的に切り刻まれてパーカッシブな打楽器状態と化し、それらを空間的に散りばめることでグルーヴを多角的に形成。小気味良さと居心地の悪さが同居した異形のダンストラックは、道の駅やフードコート、民宿といった「日常の中のちょっとした非日常」を探索する時のサウンドトラックとして絶妙に機能している。懐かしいようで新しく、無機的なようで有機的。ここではないどこかへの憧憬をいたずらにかき立てるニクい一枚。あと Hyperdub 初のベースレス作品だってさ!
31. 中島愛 "green diary"

茨城出身の声優/シンガー。途中に活動休止の期間を挟みながらも、何だかんだで10年以上の長い月日をサバイブし続けてきた彼女。その間に培ってきた経験や表現力、プロップスはすべてこの作品に結実していると言っていいだろう。三浦康嗣、尾崎雄貴、吉澤嘉代子、清竜人、tofubeats 等々の確かな腕の作家陣による楽曲は、各々が各々の手法で中島愛という歌い手の一側面にスポットライトを当てて輝かせ、彼女のイメージカラーである "緑" をモチーフとしながら、デビューから現在に至るまでの彼女の軌跡を鮮やかに彩っている。もしあなたが旧来からのまめぐファンなら、ここにある十通りの彼女の表情すべてに親しみや愛おしさを覚えるはずだし、ご新規様にとっては彼女がどれほど多面的な魅力を備えているかを理解するのに今作ほど打ってつけなものはない。そして軌跡はこれからも続く。
30. black midi "Cavalcade"

イギリス・ロンドン出身のロックバンド。実を言うと未だに全貌を消化しきれていない。メンバー各自の入念な作曲を基に、持ち得る演奏技術を最大限に注ぎ込み、さらに管弦楽器を大々的に導入してクラシカルへの接近も見せた今作は、即興演奏から楽曲を組み立てていた前作 "Schlagenheim" よりも一層自由かつ難解で、全く見当もつかない方向へばかり展開するキテレツな代物だからだ。なかなか消化できないし、それ以前にどうにも笑いがこみ上げてくる。だいたい何かしらの方向に極端に振り切れている表現というものは、得てして受け手がその表現の強度に耐え切れず、反射的に笑いを引き起こす作用があるものだ。このアルバムは完全にその類だ。前作も大概だったが、今作はそのハードルをいとも簡単に飛び越えている。どの場所にも属さない異物であるべしという信念をとことん先鋭化させたその姿は、ある意味ロックバンドとしては至って真っ当なものであるとも思う。
29. 人間椅子 "苦楽"

日本のメタルバンド。ごめんけどやっぱ好きやねん。久々のランニングタイム70分オーバー。だがプログレッシブな構築性よりもアグレッションの方が比較的強調されている気がする。なにせオープナー "杜子春" から年甲斐もなくスラッシーな疾走感に乗せてギターソロ大炸裂。長い曲が多いがタイトに絞られている印象もあり、冗長さは感じない。歌詞はもちろん昭和文学へのオマージュてんこ盛りだが、中には "悩みを突き抜けて歓喜へ到れ" や "夜明け前" のように、苦境を強いられている現代だからこそあえて捻り出されたポジティブなメッセージもある。そう、人間椅子は音楽的/コンセプト的にデビューの時点で完成されていたバンドであり、やることの大方は良くも悪くも変わらないが、それでも当代的な視点を忘れることは決してなかった。常にブラッシュアップ、研鑽を続けてきたからこそ、彼らの持つマンネリズムが退屈な反復ではない、一種の「イズム」であり得たのだと思う。
28. Moor Mother "Black Encyclopedia of the Air"

アメリカ・ペンシルベニア出身の詩人。これまではフリージャズやエレクトロノイズの領域に身を置くことが多かった彼女だが、今作はコズミックな浮遊感の中にトラップあるいはジューク/フットワークを基とした不定形のリズムを散りばめ、そこに Elucid や Pink Siifu などラッパーを多数ゲストに迎えたり、自身のポエトリーリーディングも軽妙なフロウを感じさせるものだったりと、彼女流のアブストラクト・ヒップホップと呼べる内容に仕上がっている。それと同時にジャズ由来のシックな艶やかさも増しているため、彼女は今作を自ら「これまでで一番聴きやすい」「セルアウトした」レコードだと冗談まじりに語っている。確かにそうかもしれない。だが、目つきの鋭さは全く変わっていない。世にはびこる痛みや疑念、不安を直視しながら言葉を紡ぐ、そのアティテュードの厳格さは今作でも健在で、それが直接的な攻撃性ではなく、聴き手に内省を迫るスピリチュアルな音響空間へ変貌を遂げたということだろう。セルアウトだなんてとんでもない。むしろ重みは増している。
27. Erika Dohi "I, Castorpollux"

大阪出身のピアニスト。このアルバムは "Two Moons (Osaka 1995)" というタイトルの楽曲で始まる。1995年の大阪で何があったか。阪神・淡路大震災である。当時の記憶を振り返る独白に始まり、その後は言葉を発するのは数曲のみで、主にはピアノ、シンセ、そしてゲスト陣を交えてのセッション(気鋭のサックス奏者 Ambrose Akinmusire 、インディバンド Poliça のボーカリスト Channy Leaneagh などが参加)によって、およそ四半世紀に渡る時の流れを自由なフォームで表現している。当時まだ10代だった彼女は、震災によって故郷の景色が変貌していくことに困惑を隠せず、またその後には音楽の道に進むために海外への移住を決めたりと、自分を取り巻く状況が次々と激変していく中で、そのスピードに対応できない自身の内面との大きなギャップに苦しんでいたという。そんな彼女の出自と万博公園、太陽の塔といった象徴的なモチーフを交えながら、ジャズ、クラシカル、エレクトロニカの境目で思索の放浪は続いていく。
26. Puma Blue "In Praise of Shadows"

イギリス・ロンドン出身のシンガーソングライター。アンビエント/オルタナティブ R&B にトラディショナルなフォーク要素を加味した音楽性だが、基本的にどの楽曲も十分に注意を払っていないと聴き逃してしまうくらいの脆弱な音ばかりで成り立っている。リズムの一打一打は心音のごとく穏やかに響き、歌声は溜め息にも似たか細さ。彼はどうしても拭いきれない憂鬱を必要以上にドラマチックに飾り立てはしないし、エレクトロニックなサウンドデザインだからと言って洒脱の方向ばかりにも向かわない。アルバムタイトルは谷崎潤一郎の随筆 "陰翳礼賛" からとのことだが、その名の通りここに収められている楽曲のすべてが、影のみが持ち得る繊細さ、物悲しさ、そして官能的な美しさを持ち合わせていると言える。倦怠を帯びた生身の律動を写実的に表したかのような音像だからこそ、どの曲にも陰翳の深み、痛々しいほどのリアリティが宿されているわけだ。
25. Crumb "Ice Melt"
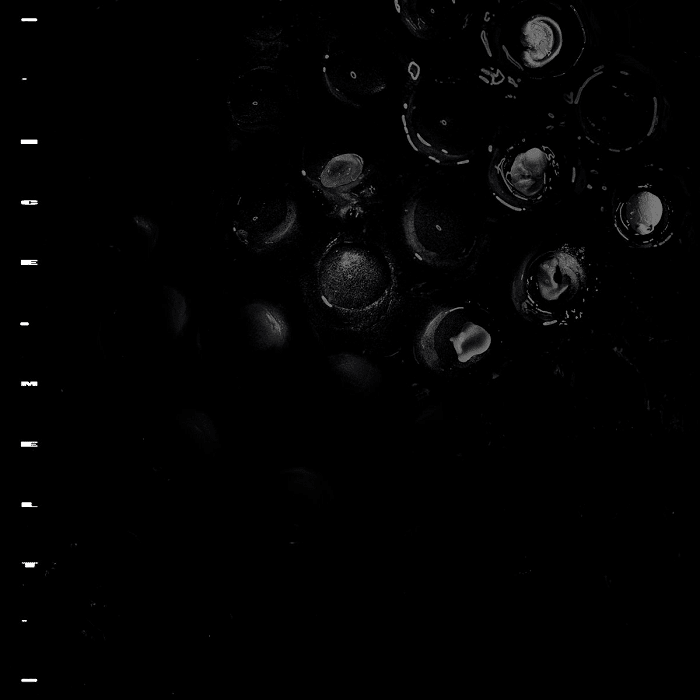
アメリカ・ニューヨーク出身のロックバンド。今作を聴いて自分が真っ先に連想したのは Portishead だった。それは陰鬱さと甘美さがマーブル模様を描いた、全体に蔓延する悪夢のような雰囲気ももちろんそうなのだが、それと同時に音の構築の巧みさ、無音の間を意識した理知的なサウンドデザインによるところが大きい。どの楽曲でも音の裏側に何か得体の知れないものが蠢いているような、嫌な汗をかいてしまう不穏さが通底しているのだ。演奏はしなやかなようで冷たく無機質な印象も同時にあり、歌声は一見優しいが目は虚ろ。そしてどの曲も短く、盛り上がりきる手前のところでバッサリ終わってしまうため、空虚さや薄ら寒さを余計に聴き手に植え付ける。ここに自分はどうしてもゴスの系譜を見出してしまう。彼女らがゴスに対してどれだけ意識的かは定かではないが、それこそ Portishead がそうであったように、何かと絢爛になりがちなゴスの様式ばかりをなぞるのではなく、その内側にある空気感のみを捉えた、言わばノンゴス・ゴスミュージックの最新型がここにある。
24. CFCF "memoryland"

カナダ・モントリオール出身のプロデューサー。2021年も概ねクソみたいな世の中だったが、記憶の中では人はいくらでも自由になれる。ハウス、トランス、ジャングル、ドラムンベース、IDM 、2ステップ…要するに90年代を彩ったクラブミュージック(時にオルタナティブ、シューゲイザーといった同じく90年代のロックミュージックも)の数々を片っ端から網羅し、そのすべてを夢見心地なカラフルさに仕立てたエレクトロ時空旅行。1989年生まれの彼は今作が含む音楽性、その元ネタに当たるミュージシャンはおそらくほとんどが後追いのはずだが、だからこそ90年代という過ぎ去った時代への憧憬が加速され、野暮ったさを削いだ上で美化し、新鮮な刺激に満ちたものとして提示することが出来るのだと思う。当代的な感性というフィルターを通した上での再構築。これこそリバイバルの醍醐味だろう。そしてアルバムの実質的なクローザー "Heaven" では「また会えるよ/さようなら/翼を広げて飛び立とう」と我々を夢から引き戻すメッセージ。落語のような綺麗なオチだ。
23. Sam Gendel "Fresh Bread"
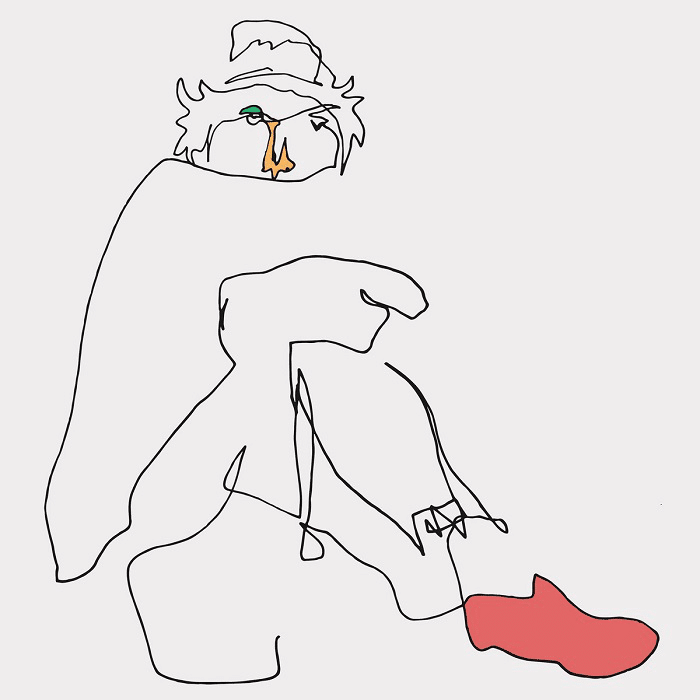
アメリカ・ロサンゼルス出身のサックス奏者。矢継ぎ早のリリースペース、ジャンル問わず多方面へのゲスト参加と、近年活動の場を一気に拡大している彼のクリエイティビティ、その漲りっぷりを確認するにはこの単独作が最適だろう。ここ10年ほどの間にホームレコーディングした未発表曲(一部はライブ音源)をかき集めた、全52曲、トータルタイム3時間40分の超特大ボリューム。彼ならではの独特の丸みを帯びたサックスの音色を軸に、ノスタルジックなメロディで朗らかな表情を見せたり、エレクトロニクスを交えてヴェイパーウェーブにも通じるシュールな浮遊感を醸し出したり…と、奔放なアイディアがひとつの楽曲として結実する直前の、言わばラフスケッチの数々。独自の理論でジャズの可能性を延々と模索し続ける内容は、ある意味で彼の個性が最も濃厚な状態で味わえるもの。"Nara Deer" "干し芋" といった日本にインスパイアされたと思しき楽曲もちらほら。
22. 小袋成彬 "Strides"

日本のシンガーソングライター。そもそも彼はデビュー作 "分離派の夏" の頃から、歌の人、言葉の人という印象があったのだが、それはこの新作でさらに強まった。もちろんサウンド面でも趣向は凝らしており、今作においては粘っこいグルーヴや流麗なムード、リズムの一打一打の痛快さなど、鳴らされている音すべてにおいて肉感的な心地良さがとことん追求されている。革新的かと言われると違うかもしれないが、ここまでピントの定まった高いクオリティを提示されるとさすがにぐうの音も出ない。ただそれらはあくまでも小袋成彬本人の歌声を引き立たせるためにある。綴られる言葉が否応なしに耳を引き、"Work" ではリアルな現実を直視させられて嫌な汗をかかされたり、"Formula" では恋人だった者同士の心のすれ違い…改めて文字に起こすと陳腐になりそうだが、そのあまりに儚くリリカルな描写に思わず遠い目になってしまう。これまでとはまた一味違ったエスプレッソの人間味。
21. McKinley Dixon "For My Mama and Anyone Who Look Like Her"

アメリカ・ヴァージニア出身のラッパー。トラックはロック、ジャズ、ソウル、ファンクをごった煮にした生演奏が主。洒脱かつダイナミックにうねるグルーヴ感満載なプレイの上で、McKinley のラップは性急なスピード感の中に滾る熱気と鋭い目つきのクールさを織り交ぜる。何なら Anderson .Paak ばりの流暢なスキルを惜しみなく披露しているが、そこで綴られているのは極めて泥臭くナイーブな、彼自身に宿る喜怒哀楽のすべて。幼馴染みを亡くしたトラウマに端を発し、「母親と母親に似た人たち」、つまり黒人の持つ歴史やアイデンティティにも触れながら、音楽はまるで一篇の映画のように彼の人生をドラマチックに演出する。ふくよかな暖かみを感じさせる生の躍動から、不穏さが充満したダークネス、または仄かな悲しみを滲ませた穏やかさへ。渦巻く思いが何層にも重ねられた末に、やがて Chance the Rapper にも通じる柔らかなバイブスへと行き着く様はあまりにも感動的。
20. Rodrigo Amarante "Drama"

ブラジル・リオデジャネイロ出身のシンガーソングライター。そもそも彼はオルタナティブロックバンド Los Hermanos のメンバーとして成功を収めた人で、前作にあたる "Cavalo" にもその片鱗は残されていた。だがここでの彼は個人的な趣味性をさらに思い切り良く推し進めており、端々にブルースやサイケデリックロックの感触を見せつつ、フォーク、ジャズ、ボサノバ、アフロビートといった要素を融合して丁寧に熟成させた、内省的かつノーブルな佇まいのインディポップを披露している。アルバム表題やイントロダクションの歓談の声が指し示す通り、往年の名作映画を見る時と同じようにセピア色の世界観の中へとスムーズに引き込まれ、そこに待つノスタルジックな楽曲群は情熱と退廃、アンニュイと躍動が多層的に入り混じった、何とも味わい深いもの。例えば Vampire Weekend や cero が民族音楽的な要素を取り入れるのとはまた違ったテイストによる、懐かしいようで見たことがない、馴染みやすいようでストレンジな、ジャンルや国境の壁をさらさらと融解した高品質ポップソング集。
19. Nao "And Then Life Was Beautiful"

イギリス・ロンドン出身のシンガーソングライター。オープナーを飾るアルバム表題曲、その冒頭で "2020 hit us differently" と綴る彼女。それはもちろんパンデミックもそうだし、その直前まで過酷なツアーを続けてきた末の燃え尽き症候群、そして昨年に第一子を出産したという彼女にとって、2020年は色々な意味で決して忘れられない1年になったはずだ。必然的に自分自身を振り返ることが多くなった彼女は、恋人との関係を清算したり、疎遠になっていた友人たちへの愛情を再確認したりと心の整理を続け、その果てに生まれてきた言葉が「人生は美しかった」。世の中は概ねクソみたいだが、こんな時代に対してもいつかそう言えるようになる日が来るのだろうか。あどけなさと艶やかさが同居した歌声と豊潤なアレンジで、これまで、そしてこれからをまるごと讃美しようと試みるスムース・ジャズ・R&B の最も幸福な形。Lianne La Havas や serpentwithfeet など脇を固めるゲストの人選も抜かりなし。
18. King Woman "Celestial Blues"

アメリカ・カリフォルニア出身のメタルバンド。素晴らしい音楽には素晴らしいカバーアートが必須である。翼をもがれた後の傷跡をそのままに、これが自分だ、このまま痛みを抱えて生きてみせると言わんばかりの勇壮な後ろ姿。ボーカルを務める中心人物 Kristina Esfandiari はバンド/ソロ含めて数多くの名義を音楽性に合わせて使い分けているが、この King Woman ではスラッジメタルの禍々しい重低音、静と動を美しく交差させるポストロックの構築性、思わず息が詰まるようなゴシックの緊張感、そしてアルバム表題が差し示すようにブルースの泥臭い渋味までもを混ぜこぜにした、彼女の中でも最も直接的にブルータルな側面が際立った内容。一貫して圧迫感のあるヘヴィネスとグルーヴが全体の空気を支配する中、絞り出すようにして悲痛、葛藤、抑圧を吐き出す彼女の姿は、それこそジャケットに映し出された彼女の背中と同様に、創痍から転じての気高い煌めきを放っている。
17. Pino Palladino & Blake Mills "Notes With Attachments"

ウェールズ出身のベーシストとアメリカ・カリフォルニア出身のギタリストによるコラボ作。名義的にはこのふたりによる作品であり、作曲の主導権を取っていたのも同じで間違いないだろうが、実際の楽曲は誰かが確固たる中心を担うというわけでもなく、ベースを Pino Palladino 、ギターや民族楽器など諸々の装飾を Blake Mills 、そしてドラムには辣腕 Chris Dave 、サックス(とアートワーク)に Sam Gendel 、その他多くのゲストプレイヤー含めた全員が同一線上に並び、対等な立場で互いの音を鍔迫り合いさせるセッション集となっている。随所にラテン/アフロテイストを塗しつつ、定型のフレーズ、定型のグルーヴを繰り返すことはほとんどなく、協和と不協和の境目をグルグルと行き来しながら、演奏者それぞれの個性、思いつく限りのアイディアが1曲の中に積極的に詰め込まれている。特にリード曲 "Ekuté" のスリリングな奔放さは言葉本来の意味でプログレッシブ極まりない。
16. 박혜진 Park Hye Jin "Before I Die"

韓国出身のプロデューサー。テクノは決してダンスフロアで熱狂を生成するための機能性のみに特化しているわけではない。特に現場そのものを失ってしまったコロナ禍においては、テクノの持つ役割や表情はこれまでよりもさらに多様化せざるを得なかっただろう。今作は太めの粘っこい質感を持ったビートによるストレートなダンスナンバーが揃っているが、そのビートが行き着く先はスポーティに熱量を発散するリスナーではなく、むしろ彼女自身の内面奥深くだ。"Let's Sing Let's Dance" 。"Can I Get Your Number" 。そして "I jus wanna be happy" 。これらはすべて彼女の脳内をそのまま外部にトレースした端的かつリアルな言葉ばかりであり、他者への直接的な呼びかけであると同時に自分自身のアイデンティティの再確認でもある。サウンドデザインはスタイリッシュで軽やか、しかしそのベールを一枚めくってみれば痛々しい瘡蓋があちこちに。我を忘れるのではなく我に返るために踊る、言わば音の私小説。
15. Black Country, New Road "For the first time"

イギリス・ロンドン出身のロックバンド。彼らをポストパンク・リバイバルの枠で括るのは最初から無理があった。そもそもメンバーの出自からしてクラシカルやジャズを素養に持つ者、パンク/ハードコア畑出身、Jockstrap メンバー、Karl Hyde (Underworld) の娘…とまるでバラバラ。なので曲調も、トランシーなうねりを生み出す人力ダンスナンバー "Instrumental" "Opus" が頭とケツを担当しつつ、その間には雑多な音楽性が少しずつ顔を出し、なおかつやたらと不穏、不可解なムードばかりが全体を支配している。破裂しそうで破裂しない、目的があるようでどこにも行き着かない、やり場のないエナジーの漂流。シュールな不協和音も惜しみないあたりから自分が最初に想起したのは Sonic Youth だったが、彼らは他にも多くの先人を参照しているはずで、しかし具体的に何かしらのひとつの像を結ぶことは徹底して拒絶しているように見える。ポストパンク・リバイバルの枠では彼らは括れないが、その実験精神、表現衝動の発露はオリジナル・ポストパンク勢が持っていたアティテュードとまったく同種のものだろう。
14. Tyler, the Creator "CALL ME IF YOU GET LOST"

アメリカ・カリフォルニア出身のラッパー。ことヒップホップに関しては歌詞の内容をきちんと解きほぐしていかないと、サウンドのみで作品の良し悪しを判断するのは危険だということは重々承知している。だが正直、自分にはアルバム1枚分に詰め込まれたラップの情報量を受け止められるだけの英語力がない(今では Genius などの便利なツールも存在するが)。なので身も蓋もないが、今作に含まれている引用や文脈に関しては、自分なんかよりもその筋のプロがきちんと解説してくれているので、そちらの方がよっぽど参考になる。ただそれでも、今作がいかにエンターテイニングで、聴き手をついてこれるかどうか試す挑戦心に満ち、頂点に立ったスターとして更なる高みを目指した充実作であるかは、ざっくり1回聴き通しただけでもすぐに勘づける。ミックステープの体を借り、威嚇的なダークネスからシティポップに通じる軽やかさへの目まぐるしい転身、また性急なビートスイッチも実験性と言うよりフィジカルへの即効性として機能する、傑作 "IGOR" からさらに発展した全方位的な才能のブースト。あえて「ポップス」の最新型と呼んでしまいたい。
13. 上田麗奈 "Nebula"

富山出身の声優/シンガー。彼女が過去に経験した大きな挫折をあえて振り返り、その時の思いを軸にしてアルバム全体のストーリーを組み立てていったとのことで、ひとつの短編小説、あるいはミュージカルを見ているかのごとく、起承転結の流れがこの上なく綺麗に完成されている。曲調はピアノバラードやエレクトロポップなど多岐に渡っており、それに合わせて彼女の歌唱法も器用にスイッチしていくのだが、そのすべてが闇の底~開放的な光に至るストーリーに沿って有機的に連結されており、強固なアルバムコンセプトを確立するに至っているのだ。そして彼女の歌は声優らしい演劇的な立ち振る舞いではあるが、その歌には思わずこちらがのけぞるほど生々しさを表出させる場面が随所にあり、演劇と自然体の境目が融和した、極めて説得力のある表現を成し得ている。初めは人前で歌うことが苦手で、アーティスト活動の話をもらっても1年ほど保留していたというのが今となっては嘘のようだ。大きな飛躍を遂げた充実作。
12. 折坂悠太 "心理"

鳥取出身のシンガーソングライター。今作を聴いていると音楽における "訛り" がいかに重要かを痛感させられる。ジャズやフォーク/カントリーに軸足を置きつつ、ミックス面では立体的でエレクトロニックな感触を重視したサウンドは、昨今の海外インディロック、その最も尖端の部分をいち早く察知したと思しきもので、彼の持つアンテナがいかに鋭敏かはすぐに窺い知れる。ただそれと同時に、すべての楽曲に日本ならではの民謡、浪曲、歌謡的な質感、ある種の訛りがはっきりと滲み出ていて、それが日本人の自分にとってもひどく異様なオリジナリティとして映るのだ。この訛り感は彼の中にはバックボーンとして元来から備わっていたものかもしれないが、それにしてもここまでドメスティックな訛りを含んだ歌のセンスは明確な意識がなければ出てこないはず。ローカルに深く根差しながらワールドワイドを見据えたと言うべきか、この普遍的かつ先鋭的、牧歌的かつ理知的というバランスの妙技には脱帽せざるを得ない。そしてここでも Sam Gendel 参加。
11. Hiatus Kaiyote "Mood Valiant"
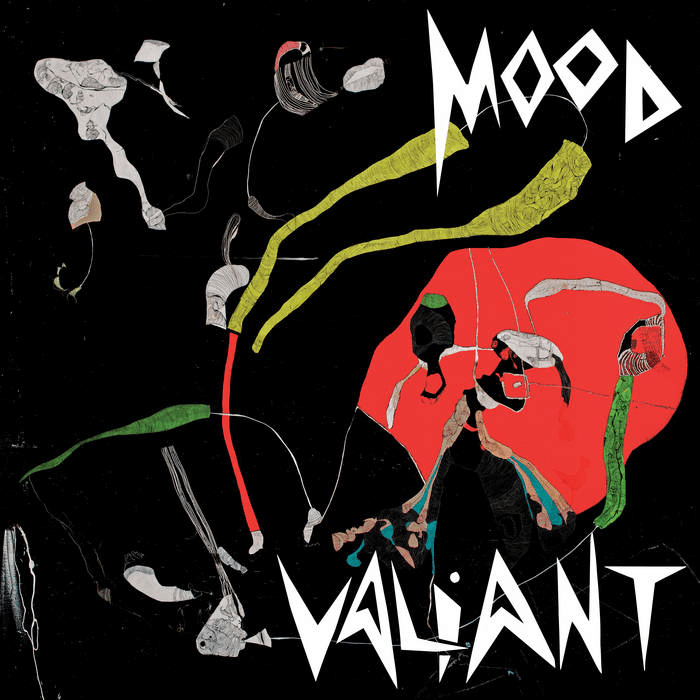
オーストラリア・メルボルン出身のジャズバンド。彼女らにジャンル名をあてがうとすればジャズやソウル、R&B といったあたりになるだろうが、実際の演奏を聴けばこの音に何かしらの物差し、枠組みがまるで無用の長物であることは即座に理解できると思う。アルバム表題は陰と陽、ポジティブとネガティブといった二面性を意味しているとのことだが、例えばリードトラック "Chivalry Is Not Dead" や "All the Words We Don't Say" などに顕著なように、演奏者それぞれが気ままにメロディ、打点、グルーヴを突っ込みまくった結果ひとつの流れがたまたま生まれ出たようにしか思えない、それくらい多層的で自由度の高いアンサンブルは二面性どころかいったい何面まであるんだという勢い。音数もアイディアも満載、艶やかでいてユーモラス、そしてある意味いかにも Brainfeeder らしい宇宙的でスピリチュアルな浮遊感も充満。圧倒的な技量で繰り出される12曲43分の流れがずっとダイナミックすぎて笑いしか出てこない、澄み切った過剰さが堪能できる流石の一発。
10. For Those I Love "For Those I Love"
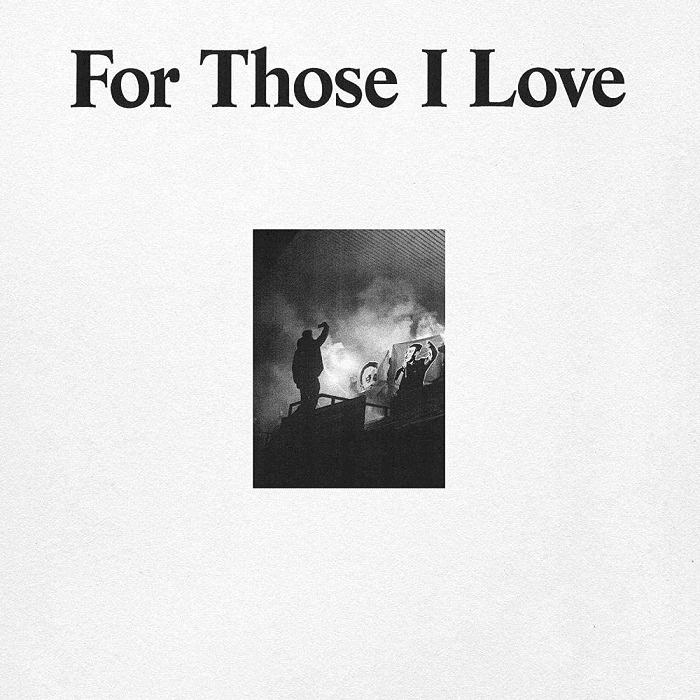
アイルランド・ダブリン出身のプロデューサー。肉体が機能しなくなるだけでなく、年月が経って誰からも忘れ去られてしまった時に、人は本当の意味で「死を迎えた」ということになるのかもしれない。逆に言えば、確かな記録を残して多くの他者の脳内に居座ることさえできれば、それは不死の魂となるのではないか。For Those I Love こと David Balfe は今作まるごとを、彼の学生時代からの親友であり、かつて一緒に組んでいたパンクバンドのメンバーでもあり、3年前に自ら命を絶ってしまった詩人 Paul Curran に捧げている。David の幼少期にまで記憶を辿り、Paul 含め現在に至るまでに直面してきた死にまつわる数々の出来事、それらを叙事詩のように綴りながら、やるせない怒りや悲嘆、前に進むためのストラグルを明確に言葉に刻む。そうして Paul の存在を曲の中に刻み込み、魂を曲の中で生き続けさせようとする彼は、その決意を「愛」と呼ぶ。決してエフェクトでぼやけさせることなく、メロディやシャウトで過剰に修飾するでもなく、ラップと語りの中間のような、聴き手に最も言葉が刺さりやすい手法を選んで、愛を決して絶やさないと決意を露わにする。この重みは確実に聴く人を選ぶだろう。
9. Alice Phoebe Lou "Glow"

南アフリカ・ケープタウン出身のシンガーソングライター。録音はアナログテープ、使用機材はいずれも用意できる中で最も古いものを…と、あえて旧来的な手法のみにこだわって制作に臨んだという今作は、ピッキングや弦の軋みのひとつひとつが生々しくダイレクトに伝わる音作りで、演奏者の息遣い、体温がすぐそばに迫っているような錯覚にも陥る。だがそれと同時にノスタルジックで煤けた色彩がずっと通底しているためか、音自体はリアルなのに総体としてはミステリアスで現実味がなく、まるで亡霊が目の前に具現化したような奇妙な聴き心地。曲調はトラディショナルなロック、フォークを主とした素朴な歌モノなのだが、この絶妙な音の質感が素朴さを素朴なままにせず、背筋に冷気が走るような緊張感、何処か幻想的、退廃的な雰囲気すらも纏わせている。その上で今作での大きなテーマは「愛」。愛情にまつわる安息、官能、時には死に繋がる恐れのある衝動までもを内包した繊細な歌の数々、その静かな気迫には自然と耽溺してしまうのであった。
8. Yu Su "Yellow River Blue"

中国出身のプロデューサー。全体にはダブやアンビエント由来の空間的な奥行きのあるレイヤーが用いられているが、その中に挿入されるリズムは多岐に渡っている。少し YMO を彷彿とさせるアジアン・エキゾチックなテクノポップがあり、ヘヴィな低音を効かせたレゲエがあり、ノイジーで不穏なトリップホップがあり、催眠効果の高いダウンテンポがある。アルバム表題にある通り今作は黄河をイメージして制作されたとのことだが、なるほどこのバラエティ豊かな作風は遥かなる大河を辿って行く時の山あり谷ありな道程を分かりやすく連想させる。実際に彼女は黄河の西端から東端までを横断する大規模なツアーに出ていたことがあり、その行く先々で訪れたクラブの熱狂、演者/オーディエンス含めた中国のローカルなエレクトロニックシーンに強く触発され、今作の制作に至ったのだと。自分は実際に中国に行ったことはないが、きっと個性豊かで多様性に満ち、独創的なサウンドが日進月歩で生み出されている刺激に満ちた場所であろうことは、ここにある楽曲群から容易に察せられる。今作はそんな風に、未だ見ぬ場所へのイマジネーションをいたずらに掻き立てる愉快な作用があるということだ。たまには夢見たっていいじゃない。
7. SPELLLING "The Turning Wheel"

アメリカ・カリフォルニア出身のシンガーソングライター。オーバーグラウンドでは Prince や Madonna などを参照したエレクトロポップがチャートを席巻したり、インディ界隈では Joy Division や The Fall を参照した無機質なニューウェーブサウンドが注目を集めたりと、80年代に生まれた音楽が今では一過性のリバイバルブームを超え、大きな指標、基本として定着した感がある。ただ80年代とはひどく複雑な時代で、例えば一口にロックと言ってもパンクブームの消失以降にドリームポップ、ニューロマンティック、ポストパンク、ゴス、エクスペリメンタルと細分化が進行し続けていたわけで、とにかく一言では収まりきらない雑多さこそが80年代という時代の最たる魅力だったと思う。そしてその雑多さのほぼ丸ごとを一身に引き受けていた存在と言えば Kate Bush なわけだが、この SPELLLING の新譜には彼女の遺伝子が深く根付いており、その意味で今作こそが当代的なポップセンスの最良の部分を体現した作品と言えるだろう。総勢30名以上のオーケストラを従え、アルバム前半を "Above" 、後半を "Below" と位置付けて輪廻転生をコンセプトに据えた今作は、シンセポップ、サイケ、クラシカル、プログレに至るまでを同列で結合した一大アートポップ作で、それはちょうど Kate Bush が志向していた煌びやかな多様性、先進性を新たに更新するものだ。こうして時代は前に進んでいく。
6. Sam Gendel & Sam Wilkes "Music for Saxofone & Bass Guitar More Songs"
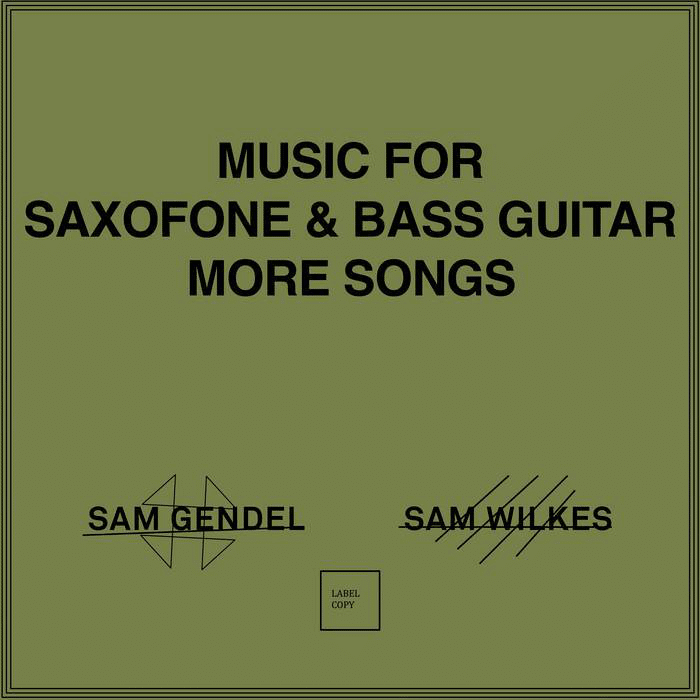
アメリカ・カリフォルニア出身のサックス奏者と同出身のベーシストによるコラボ作。Sam Gendel は単独/コラボ/ゲスト参加/リミックス仕事を含めれば、今年だけでもいったいどれだけの作品に名前を残したのかもはや把握しきれない。ただこのアルバムは確実に、彼が手掛けた数多の仕事の中でも最上の部類に入るだろう。今作は表題そのまま、同タッグによる2018年リリース作 "Music for Saxofone & Bass Guitar" の続編ということで、その前作のアウトテイクとそれ以降に作った楽曲をひとまとめにした内容。なので制作時期はまちまちのはずだがチグハグな感はなく、バラエティに富んだ一枚のアルバム作品として違和感なく聴ける。ミックスがいびつだったり周囲の環境音も混入していたりとデモ音源のようなローファイな仕上がりで、それが Sam Gendel ならではの効果的にエフェクトを施したサックスの音色、またささやかに挿入されるシンセ類とも相まって、ストレンジでいて妙に耳馴染みの良い独特の音響空間が完成されている。なおかつノスタルジックでメロウな感触が全体に通底していて取っつきやすく、中でも "I Sing High" の美しさは何度聴いても陶然としてしまう。The Beach Boys "Caroline, No" のインストカバーも綺麗なハマり具合。
5. Indigo De Souza "Any Shape You Take"

アメリカ・ノースカロライナ出身のシンガーソングライター。例えば最近の宇多田ヒカルの楽曲を聴いていると、内容自体は純粋なラブソングではあるものの、表現が異様なほど真に迫っていると言うか、限りある人生の中で他者を愛するということに対する覚悟が決まりすぎていて、この人は愛する人がいなくなったら簡単に死を選んでしまうのではないか?と薄ら寒さを覚えることがしばしばあるのだが、この Indigo De Souza にもそれにかなり近い印象を受ける。「あなたが血を流していたら私が赤に染まる」「あなたが泣くのを見るくらいなら死んだ方がマシ」、さらには「脳ミソが蕩けるまでファックして」とまで。それらは恋人に耽溺する時の幸福感だけではなく、エレクトロポップ調の曲でもグランジ調の歪んだギターをかき鳴らしている曲でも、死と連結する不吉なムードが常に背後に付きまとっている。ただ、彼女が醸し出す死はやけに軽いのである。それは説得力がないというわけではなく、愛する人に身を捧ぎ、己の生を全うすることの重みに比べれば、死などは恐れに値しないという意味で、死の存在が軽いものになっているのだ。深い愛情、強固な信念、そして命の脆弱さを端的かつ鋭利な言葉で聴き手にこれでもかと突き付けてくる劇薬盤。
4. Nala Sinephro "Space 1.8"
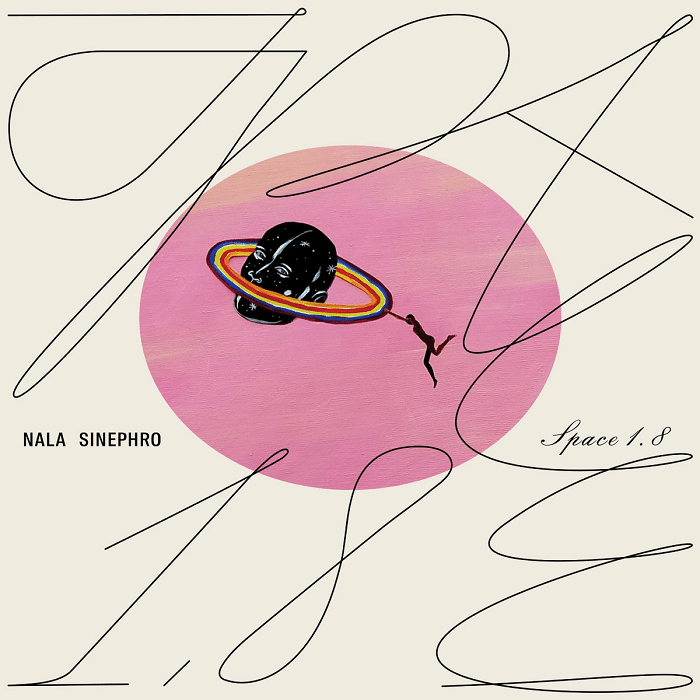
イギリス・ロンドン出身のハープ奏者。今作は2018年に行ったセッションを基に制作されたとのこと。Nubya Garcia や Eddie Hick (Sons of Kemet) など現代 UK ジャズシーンの重要人物たちを招聘し、Nala Sinephro はハープの他にシンセ類も多く用いて、即興セッションあるいは共同での作曲を進め、さらにそこへフィールドレコーディングの素材も追加するなど彼女自らの編集を施した末に完成したのだと。実際の内容はこの世ならざる美しさを湛えたスピリチュアル・ジャズ・アンビエント。参加プレイヤーは楽曲によって流動的に入れ替わるが、いずれも我を発揮して音の鍔迫り合いを見せるのではなく、各々が楽曲を構成するひとつのレイヤーと化し、それらがしなやかに融和することで総体を成している。"Space 1" "Space 2" では陽の光に包まれて溶けていくかのような心地良さが空間一杯に広がり、"Space 4" で顔を出す情感豊かなサックスの美しさは奇跡的ですらある。ただ優しいばかりでは終わらず、"Space 6" では荒波のようにうねるリズムとシンセが不穏な緊張感を醸し出し、17分超の長尺クローザー "Space 8" で全身をデトックスするまでの道程をドラマチックに仕立てている。深遠、かつ親密な世界観を確立した傑作。
3. Japanese Breakfast "Jubilee"

アメリカ・ペンシルベニア出身のシンガーソングライター。「収録曲すべてがシングルカット可能なアルバム」という表現をたまに目にするが、この作品はちょうどそれに当たる。あまりにも目映い煌めきを放つオーケストラルポップ "Paprika" の時点ですでに勝利が確定済みのようなものだが、80年代風味の音処理がキュートなシンセファンクポップ "Be Sweet" 、4分打ちの軽快なリズムにホーンセクションの華やかさがよく映える "Slide Tackle" 、深い悲嘆を歌いながらもメロディは優しく涼やかな "In Hell" 、アコースティックギターの素朴な弾き語りからサイケデリックロック/シューゲイザー風に音が果てしなく膨張していく "Posing In Cars" など、収録されている10曲すべてに異なる個性と役割があり、なおかついずれもがリードトラック級の明確な存在感を示しているのだ。そういった煌びやかさが、母親の死を乗り越えて他者との繋がりに希望を見出そうとする歌詞のテーマとも密接にリンクしており、最終的にはアルバム表題が指し示す通りに生きることの「歓喜」へと至る。全く畑違いの例えでなんだが、L'Arc-en-Ciel が "True" を、椎名林檎が "勝訴ストリップ" を完成させた頃と同じように、今の彼女は明らかにクリエイティビティがゾーンに突入している。そういうミュージシャンが発表するアルバムは得てして「全曲シングルカット可能」なものだ。その瞬間に立ち会えたことを幸福に思う。
2. NOT WONK "dimen"

北海道出身のロックバンド。昨年から続くコロナ禍の最も腹立たしかったことのひとつは、NOT WONK がこの新譜を引っ提げての全国ツアーを敢行できていないことだ。辛うじて北海道内ではライブを行えているが、その現場を目撃した人によれば、この音源テイクからさらに一歩二歩進化したライブアレンジでオーディエンスの度肝を抜いていたという。現時点では自分にはどんな状態なのか予測もつかない。と言うのも、今作ではレコーディング作業だからこそ成し得たであろう実験要素が満載だからだ。立体的な音響の細部にまで気を配り、それでいてバンド本来の気迫を損なわないダイナミックなサウンドデザイン。またキーボード、サックス、パーカッション、ゴスペルコーラスといったバンド外の装飾も随所に施し、エモ/パンクロックの枠組みを自分たちの手で拡大してやろうという野心がありありと浮かんで見える。とにかくこのアルバムは欲望まみれなのだ。バンマス加藤修平のインタビューや、今作を作る上での参照元をまとめたプレイリストを見ても、パンクやエモに留まらずソウル、ファンク、テクノ、ヒップホップ…と、挙げられている例は雑多極まりない。そのすべてを無理矢理にでも飲み下して自分の表現に取り込んでやろうという欲望があからさまに曲にも表れている。この肥大した欲まみれな音像が、シンプルなスリーピースのアンサンブルによる生の現場ではどれほど変貌しているのか、できれば今年中に確認しておきたかった。
1. Floating Points, Pharoah Sanders & The London Symphony Orchestra "Promises"

イギリス・マンチェスター出身のプロデューサー、アメリカ・アーカンソー出身のサックス奏者、ロンドン交響楽団のコラボ作。1位に選出したは良いものの、今作についてどのように言葉を尽くせば良いか分からないままでいる。聴くたびに圧倒されてしまって頭の中が真っ白になるからだ。それでも手探りで書いてみる。きっと怪文書と化すだろう。まあ別にいいか。
自分がせっかちなだけかもしれないが、最初聴いてピンとこなかったものを何度も繰り返し聴いて良いところをなんとか発掘する、という作業は基本的に好きではない。そこまで時間を持て余してはない。名盤であるならば最初の一音目を出した時点で名盤だと分からせてほしいのだ。この作品はそれをやってくれた。おそらくビブラフォンとチェンバロの音だと思うが、最初に鳴らす7つの音で構成されたフレーズ、それが鳴り響いた瞬間に自分の周りの空気が冷たく引き締まるのを感じる。楽曲の世界観に少しずつ手繰り寄せられるのではなく、曲の始まりの時点ですでに自分がその世界観の中にいることを実感させられるのだ。このフレーズは音色を微妙に変化させながらアルバムの終盤までずっと繰り返されるが、その周囲にはアブストラクトなエレクトロニクス、穏やかに情感を滲ませるサックス、時に嵐が吹きすさぶような広がりを見せるオーケストラなどが、各楽章ごとに交代で現れては消えていく。変わっていくものと変わらないものが対照的に同居し、それらが慎重に、柔和に重なって、微かに暖かみを感じさせる総体を成している。一貫して幽玄の美しさをまとっているが、第4楽章で現れる Pharoah Sanders の声はまるで子供をあやす時のおどけ方のようで、曲の中ではいささか異物のようだが、親密で、何だか微笑ましくもある。この声はわずかな瞬間ではあるが重要なもので、今作の世界観がすっかり浮世離れした無機質の空間ではなく、人間の体温がはっきりと宿った、このリアルな世界そのものであることを実感させるファクターとして機能している。
そう、「子供をあやす時のおどけ方のよう」な声の印象に引きずられているせいか、今作を聴いて自分が想起したのは我が子のことだった。「変わっていくものと変わらないもの」、変わらないものはきっと命の尊さだろう。終始リフレインする7つの音は新しく生まれた子供の心音を模している、そんな風に自分には聴こえる。あまねくこの世のすべては変わってしまう運命にあるが、そんな世界の中で苦難に晒されたとしても、美しい心音の響きだけはいつまでも途絶えることがないようにと、願いを込めながら静かに延々とループされる。子供の心音を様々な音、様々な事象が取り囲む形で構成される今作の「世界観」とは、宇宙でも幻想でもない、まさしく自分の生活そのものだった。生活がこんなに美しいものだったということに、自分は今まで気付けていなかった。
だが、第8楽章からは様相が一気に急変する。メインフレーズは途切れ、ハモンドオルガンの音が大きく鳴り響いたあと、突然およそ1分間の無音状態に入る。ここでは無音もまた音と同様に雄弁だ。強い緊張が走り、あまりにも重い。そして最後の第9楽章で鳴り響くストリングスは、直前の無音の緊張をそのまま増幅させるかのような厳かな響きで、優美でありつつ何処か不穏さを残し、決して綺麗な着地をすることなく消失していく。それは解釈によっては残酷にも映るが、仕方ないかもしれない。生活は予測可能な風に綺麗な着地などするはずはないし、未来がどうなるかは誰にも分からないからである。この世が決して美しさばかりでは済まないことを改めて突き付けられているかのようだ。今作はアンビエント的な感触が強いが、イージーリスニングには絶対に成り得ない。それはもちろんサウンドデザインの精緻さにもよるが、聴き手の注意を途切れさせることなく引き付けるダイナミックな曲展開があり、イマジネーションを強烈にかき立てる余白、余韻があるからだ。優しさ、厳しさ、慈しみ、畏れ…多様な感情の機微が詰まったこの作品は、自分の意識をはっきりと覚醒させ、生活へ、現実へ、これからの未来へと目線を向けさせてくれる。この音楽に出会えて本当に良かった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
