
リディラバは地域を救う鬼殺隊になりたい
休眠預金の資金分配団体として2020年、SIIFが採択した「地域活性化ソーシャルビジネス成長支援事業」分野の6団体。今回はRidilover(リディラバ)代表の安部敏樹さんと対談。
新潟県越後妻有で20年続く「大地の芸術祭」や、地域資源を活用した関係人口の創出・拡大と、それを通じた地域エコシステム構築を目指す安部さんに、事業構想の話を聞きました。
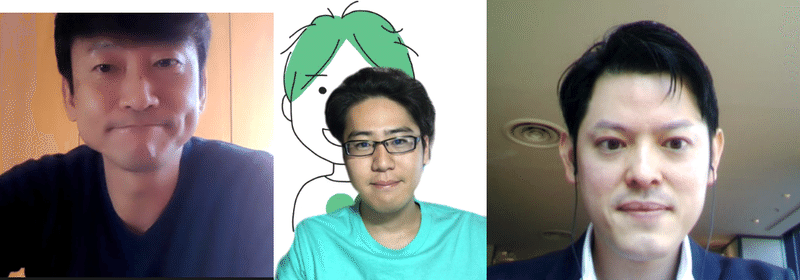
左)社会変革推進財団専務理事 青柳 光昌
中央)リディラバ代表 安部敏樹
右)社会変革推進財団 インパクト・オフィサー 山本泰毅
青柳 今回、申請があった75団体の中から6団体を採択しました。倍率は10倍以上ですね。その中でリディラバさんを選んだのは、これまでの実績や取り組み方が、いい意味でユニークだからなんです。「もしかしたら新しいことができるんじゃないか」という直観。ほかの団体の事業は目的や実現方法を絞った申請でしたが、リディラバさんは十日町市(新潟県)を舞台にして、何が起きるのか、何を起こしたいのか、まだこれからイメージをクリアにしていくことも多い。それをSIIFの担当者と一緒に考えていくことも含めて、面白い事業になりそうだなと期待しています。
安部 うれしいですね。僕らはこれまで、いろいろな地域で社会課題の現場を訪ねるツアーをつくってきました。その中で地方の集落のためにできることはないかと模索して考えたのが、移住定住促進に向けたツアー事業だったんですよね。今は20人ぐらいのツアーを組むと、そのうち1人くらいは1年以内にツアー先へ移住するというデータがあります。このエビデンスをもとに事業化し、地方自治体から予算をいただいて事業を組み立てました。
地域向けの事業を始めたきっかけは、僕自身が2010年ごろから福島県の二本松市や三宅島に通うようになったことなんです。二本松市はほかの地域と同じように平成の大合併で1市3町が合併した地域で、ざっくり言うと市街地と山奥の過疎地があります。どちらにも行って、祭りに参加したり地元の方に泊めてもらったりしましたが、市街地よりも、吸収合併された山奥の集落のほうが面白い。市街地も歴史があっていい街ですが、少し目を移せば国道にチェーン店が並び、多くの人はただのベッドタウンとして住んでいる。一方で、山奥の集落には論理的な理由ではなく「そこじゃなくては生きていけない人」がたくさん住んでいて、地域のためになんとかしたいという熱量を感じたんですね。ただその集落は高齢化がすさまじい速度で進んでいて、たいした産業もない。でも、その地域に住んでいる農業高校の生徒が頑張って昔作っていた野菜を復活させようとしていたりした。地域への熱量は時々こういう事例も産みますし、仮にそうじゃなかったとしても資産だと思ったんです。その資産をわかりやすく可視化できる仕組みをつくりたいと思ったんですよね。それで始めたのが移住定住ツアーです。地域の熱量を感じると、訪れた人は移住したくなる。移住という結果に落として可視化する。そうなると獲得コストを自治体から出してもらえるんじゃないかと。移住定住はその人の人生にとっても大きな変化だし、地域への影響力も大きい。1人くらい移住すると10年20年かければ経済効果はざっくり1億円くらいになります。その移住定住ツアーが、ほかの自治体さんからも依頼をもらえた。
移住しなかった人でどう関係人口をつくるか
安部 でも問題は、ツアーに参加した20人のうち、移住しない19人がいること。これをどうしようかと考えたんです。たとえば三宅島は20年に1度くらい噴火する。自然環境は豊かですけど、必ず噴火が起きる。その事実を知っているのに、実際に住民のみなさんは噴火があって全島避難しても、7割ぐらいは島に戻るんですよ。すごくないですか?また噴火するのに(笑)その奇天烈な島への愛はすごい。例えば高校生とかに聞くと、彼らは東京のあきるの市に避難していたわけではあるんですがほぼ全員、島に戻るって言うんですよね。楽しい東京で青春時代を過ごして東京に友達も多いのに。それぐらい地域にモチベーションを持っている。そういう人と会ううちに、私自身が三宅島が好きになりまして、こういう感じであれば残りの19人を長期的な関係人口にすることができるんじゃないかと思える様になりました。今回は、移住の一歩手前の関係人口を、段階的に作っていけるんじゃないかと思って事業申請したわけです。
青柳 僕の田舎も吸収された方なので共感できますね。合併されても何もいいことはない。合併されないほうが、いい緊張感があって熱量は残りますよね。
安部 そうなんですよ。合併されると元の自治体の役所も分所支所みたいになる。そうなると、オーナーシップを失って、現場のやる気もなくなっていく。
青柳 震災で沿岸部の被災者を受け入れたり、移り住んだ方々も多いから二本松などには熱量を持ってる高校生やそれを支える大人がいるのも分かります。「ここでしか生きたくない」という地元の人のシビックプライドのようなものを感じると応援したくなりますよね。
安部 なりますね。そういうのに僕、弱いんですよね。論理的じゃないなと思っちゃうけど、その感じがすごくいい。合理性を考えたらむしろ人類なんていないほうがいいんだから(笑)。
青柳 気持ちで動く人を応援したくなりますよね。
安部 そんなにやる気がある人がいることにポテンシャルを感じます。東京はやる気のない人も多い。人の往来をデザインするとき、やる気のある人の比率が大事なんですよね。十日町に行けば9割くらいの人からは親切にしてもらえる。旅行に行った人はその1回の経験がすべてだから、「この人たちいいな」と思える人が一定の割合いる地域は、その経験を旅行のコンテンツとして活かしたほうがいい。
青柳 移住定住の手前にいる関係人口のグラデーションの中で、その熱量が可視化できたり、十日町にとってどんないいことがあるかを、明確に出せると非常に面白いですね。
安部 地域に外との往来があって、摩擦が生まれないと地域の中の人も変わらないんですよね。その変わっていくプロセスが、ある種の商品価値になる。そのための「良い摩擦」をどう産むかが、往来をデザインする側として大事。いかに外からきた人に勘違いさせるか。
先日、僕が生まれた横浜の街でお世話になったソフトボールチームの監督が亡くなって、そのお葬式に行ってきたんです。その監督はチャーミングな人で、地域の中で関係性をつくるのが上手な人だったんですよ。お葬式の翌週、参列したソフトボールチームのOBからチームにいっぱい連絡がきた。たぶん「地元のために何かしなくちゃ」って感覚が生まれたんですよ。みんな後輩の指導しようなんて考えたこともない奴らですけど、そのお葬式が何かのメッセージになった。実際チームの運営はいかに継続的に関わってくれるコーチがいるかが重要なので、スポットでの関わりはそこまで重要ではないんです。だからそれはある種の彼らの勘違いなんですけど、「自分のチームだ」っていうオーナーシップが生まれたから動く。ありがたいですよね。地域にも似たような要素があると思うんです。外から来た人のある種の勘違いからオーナーシップが生まれ、地域に新しい産業や文化が生まれれば、もっとインパクトが出せる。地域に消費を生み出すだけでなく、地域に新しい変化が生まれ、産業とか文化をつくるきっかけになったらいいですよね。
青柳 外の人にいい勘違いさせてオーナーシップを持ってもらうと地元の人もまたオーナーシップを持ち直すっていうこともある。それがあるとGDPだけで測れないものができる。
安部 心地いい責任感って、人が生きていくために必要なエネルギーじゃないですか。そういうのは東京にいると持ちにくいですよね。
青柳 人も多いからね。都会って、そういうプレッシャーやオーナーシップが生まれづらいよね。
映画「鬼滅の刃」は社会課題を解決するストーリー
安部 映画「鬼滅の刃」見にいきました?映画館行って面白いなって思ったのは煉獄杏寿郎のシーンで大人がみんな泣くんですよ。子供は結構残酷なシーンとか見つつ笑っているのに。僕は世の中の大人のニーズがそこにあるような気がするんですよね。みんな煉獄杏寿郎の責任感に憧れている。あの現象には何かしらポテンシャルがありますよね。
青柳 自分たちはここまでできないけどやっている人物がいる。ポテンシャルにも感じるね。
安部 映画ではそこまで描かれないんですが、煉獄杏寿郎は20歳前後で今の大学生くらい。ただ、その父親はクソ野郎なんですよね。すごい無責任な人で。その父親のほうが実際の自分たちに被るんじゃないかな。特攻隊に涙するのに似てる。若い人が責任を持って命を張って死んでいく。そこに感動してしまう。僕が似たような感覚を持ったのが、先ほど話に出た二本松の高校生たちです。こいつら16歳、17歳でこんなに地域のことを考えている。すごいなと思った。そういうとき、こちらも生きる意味を問い直さなくてはならない気持ちになりますよね。煉獄杏寿郎みたいな奴は実は日本にいっぱいいるはずだと思っています。
「鬼滅の刃」は実は社会問題を扱っているストーリーなんですよ。鬼は社会問題であり、加害者側。そして他のアニメに無い大きな特徴は、鬼が滅ぶシーンを背景も含めて美しく描くことなんです。炭治郎は鬼の首を切って罰するけど、滅びゆく最後には抱きしめる。リディラバは人の内面には被害者性も加害者性も存在すると考えているので、加害者性を象徴する鬼の人間のときのストーリーまで丁寧に描く「鬼滅の刃」の考え方とは、とても近いものがあります。そういう意味で、リディラバは現在の鬼殺隊になりたいし、なんとか煉獄杏寿郎を十日町に見出したい。SIIFや休眠預金には藤の家的存在としてサポートいただきながら(笑)。
青柳 地元のNPOに煉獄杏寿郎みたいな人はいそうですか?
安部 鬼殺隊みたいものはありますが、組織としてはまだ弱い。強い柱がもっと必要ですね。まぁ創業者が圧倒的だとどこでも起きる問題ですが。
青柳 これから十日町のファンクラブをつくっていくんでしょ。そういう仕掛けはイメージできますか?
安部 大地の芸術祭に関して、頑張って柱を創ろうとした取り組みがオフィシャルサポータ―制度です。柱を外から注入しようとした。その最初の柱がオイシックス・ラ大地の高島宏平さんであり、私もその一人です。今、10人くらいオフィシャルサポーターがいます。この人たちをどう巻き込めるかが最初のトライですね。地域の人が、外から来て良い体験をした人に、ファンクラブに入ることを勧めてくれる。その導線さえ作れたら、うまく回っていくと思います。地域の体験のタッチポイントに、関係者がうしろめたくなくファンクラブを勧める流れができるかが一番のカギですね。その流れが出来てないと、ただおもてなしだけで終わってしまう。地元の人に好きにおもてなしをしてもらって、それが自然とファンクラブに繋がる仕組みをうまく作りたい。
地元の人の「愛情の押し売り」が一番心の奥に届く
青柳 どんなことが訪れた人にとって「いい体験」かは、だいたい可視化できているんですか。
安部 やっぱ魅力の源泉は論理的な合理性を越えたところですね。地域への愛も、アートも、論理だけでは説明しきれない。だから地域の溢れる愛情を体験してもらえばいいんじゃないかと思っています。地元の「おかあさん」は、ダイエットしてる人にもお構いなしで、美味しいからって米を食わせようとする。でも、「おかあさん」に押されるとつい食ってしまう。それが意外に嬉しいし、当然美味しい。合理的にみたら間違ってますけど、僕の個人的な感覚としては、そういう方向で「いい体験」を設計したほうがいい。普通にマーケティングをするより、地元の人の気持ち良さでエンパワーしたほうが結果、数字も伸びる気がします。ちなみに意外に野菜が多いので、むしろ体の調子良くなるんですけどね。
青柳 外の人のニーズに合わせるのはマーケ的には正しいかもしれないけど、続かないかもしれないし、地元も嬉しくないかもしれないね。やっぱり誰に米を食わせてもらったかが大事。
安部 その地元の「おかあさん」たちの成長欲求をどう刺激するかですよね。皆さん、おもてなしが好きなんですよ。来た人が喜ぶとサービスレベルも上がっていく。外から来た人に評価されるのがとっても大事なモチベーションです。現実的にはオンラインで広告を打っていくことと、現地体験をしてもらうことの2本線を走らせながら、会員を獲得していく。もともと大地の芸術祭のおかげで、ある程度、現地に人が訪れる仕組みはあるので。そのスピードを上げるために広告を打っていくことになると思いますね。片方でオンラインだけで会員獲得できる仕組みがあれば、それはそれでやった方がいい。どちらがどれくらいの会員獲得数があるかを見てチューニングしながらやっていくことになると思います。
青柳 面白いですね。
安部 僕も楽しみです。公的機関からの予算って、年度予算使い切り型なんですよ。団体の活動が大きくなるとランニングコストも上がるので、不安定性が高まる。独自財源がないと、次の年予算がつかなければ潰れてしまう。政治的チキンレースです。これはいろいろなところで起きています。大きな予算が毎年取れる保証はない。予算を使って立ち上げた持続可能な事業で独自財源を確保する、つまり予算を独自財源に付け替えることができると、活動が存続しやすくなる。このスキームができれば、ほかの地域でもトライする価値はあるのかなと思います。
青柳 制約が多い地方の予算のフローを、芸術祭というモデルで地元にストック化させていくという取り組みだったわけですね。それを戦略的にやっていく。
安部 大地の芸術祭は芸術資産が地域に残っていく良いストック型の事業なんですけど、芸術作品の維持にも費用がかかる。そのコストをファンクラブの資金という独自財源でできると、継続の可能性が高まりますよね。地元の人にとっては、1集落に1つ作品をつくるという方針で20年やっているので、それが集落の誇りになっている。かかしをモチーフにした作品に対して「うちのかかし」みたいな愛着がある。芸術祭が終わると、地元に愛されている作品が残されていく。それが設計として秀逸ですよね。地域の人が続けたいと思わないと、イベントは続かない。それが地元の熱量です。何を成長のエンジンとしていくかといえば、地域のモチベーションですよね。地域も一枚岩ではないけど、今関わっている人がモチベーションを維持し、関わってこなかった人も僕らが新しく入ることで新たに関わってもらえるといいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
