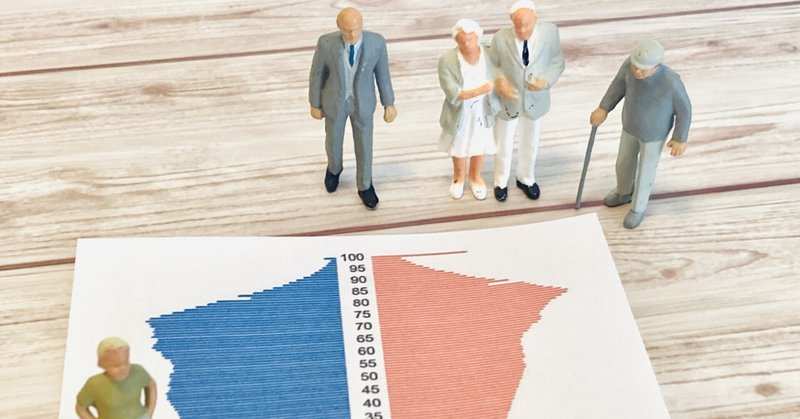
通貨価値と経済力① 人口動態
国際通貨の機能について、その背景にある要因に言及されるのは決済通貨や為替媒介通貨が主であった。資本移動が増大した現在では資産通貨の機能が重要性を増している。だが、通貨価値を支える資産としての優位性にまで踏み込むことは稀である。
国際通貨としてのドル、ユーロ、人民元について、民間部門における資産通貨の側面を比較したい。従来は資産の安全性が評価の主眼となるのだが、成長性まで視野を拡大して比較する。
経済成長の分解
資産の成長性は企業価値の増大によって裏付けられる。さらにマクロ経済にまで拡張すると経済の成長性を確認する話になる。
経済成長を観測する枠組みはソロー・モデルを土台とする成長会計を利用するのが一般的である。成長会計では経済成長を3つの要因に分解する。それらは労働人口、資本ストック、生産性に係る伸びである。
今回は米国、中国、欧州の人口動態について展望する。
2100年までの人口推計
国連が作成した人口推計を米国、中国、欧州について作図した。目を引くのは中国での急激な人口減少である。ただし、2100年という遠い未来の数字はどうも刺激的すぎる。そこで一世代だけ経過する30年後の数字を見る。

データ出所: World Population Prospects 2022、国連
2024年に比べて人口はどうなっているか。中国は10%の減少である。図では欧州の人口減少は緩やかに見えるが30年後には7%も減る。対称的なのは米国で増加率は12%にもなる。
経済成長にとって重要なのは人口規模そのものではなく国全体として若さである。高齢者が多ければ消費の伸びが期待できない。2024年と2054年の平均年齢(中央値)を見よう。中国は39.5歳から51.5歳へと急速に高齢化が進む。欧州は42.5歳から47.4歳に平均年齢が上がる。米国は人口増加するものの38.3歳から43.9歳へと欧州と同程度の年齢上昇になる。
ここで詳しく紹介しないが、平均年齢の大きな上昇から推察できるように中国は生産年齢人口の減少と老年人口の増加が大幅なものとなる。こうした人口動態は経済の活力を削ぐ方向に作用する。
鍵を握る移民
欧米については人口動態の鍵を握るのは移民である。米国には年間100万人程度の移民が流入する。合法的に永住資格を取得した人だけでこの数字である。移民流入が米国の経済成長を押し上げると分析されている。
移民が既存の労働を奪うという見方があるが近視眼的である。むしろ移民は労働市場において補完的な役割を果たし、全体としては労働生産性を上昇させる。
巷で言われるように「もしトラ」が現実となれば移民流入に厳しく対処することは容易に予想できる。しかし、移民は米国経済にとって労働力として不可欠であり、中期的に見て移民が労働市場を下支えする傾向に大きな変化はない。
一方、欧州では移民・難民対策の新制度案が2024年に施行される見通しである。移民・難民の審査を厳格化するだけでなく、強制送還の迅速化まで新制度に盛り込まれる。
2015年の欧州難民危機から流入は続いており2023年の1月から11月までに域内に不正に入った人は約35万人に上る。移民・難民の受け入れにはコストがかかり、入り口となる南欧諸国の負担が大きい。反移民感情が高まったことにより極右政党が躍進する国も出ている。これらが移民・難民流入に厳格に対処することとなった背景である。
しかし、労働人口が減少する欧州において移民・難民の受け入れに厳しく出れば、潜在成長率の下押し圧力として作用する。ひいてはユーロの価値を損ねることにもつながりかねない。
一人っ子政策を廃止した中国
中国に急激な人口減少をもたらすことになった一人っ子政策は2015年に撤廃された。2015年から2021年までは一組の夫婦につき子供二人までもうけてよいことになり、2021年7月には子どもは3人まで認められた。
しかし、国連(2022)による推計では中国の合計特殊出生率は2050年まで1.4を下回る状態が続くという。産児数の制限が緩和されても、中国では結婚する人が10年前の半分になったため少子化に歯止めがかからないのだ。
中国と欧州においては人口減少が経済成長の桎梏となる。国内需要が減少すれば企業業績が下押しされる。また、政府債務の返済原資となる税収も先細りとなる。これは民間企業や政府が発行する債券や株式に関わる話である。人口減少は投資通貨としての魅力を削ぐよう作用するのだ。
経済成長に対する人口減少のインパクトをどうやって埋め合わせるか。資本ストック、生産性、技術革新が候補となるのだが、別記事にて改めて取り上げたい。
終
参考文献
産経新聞、「欧州で移民受け入れ厳格化へ 反移民勢力台頭、右傾化鮮明」、2023年12月22日
IMF(2022)World Economic Outlook, April 2022
国連(2023)World Population Prospects 2022
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
