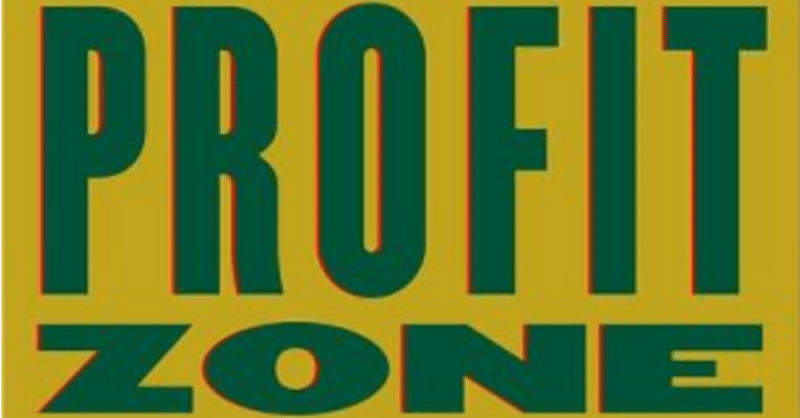
プロフィット・ゾーンでビジネスモデルを捉えてみる練習
はじめに
こんにちはSkyland Venturesの坂井です。
Skyland Venturesはシード期と言われる若いスタートアップ、特に若い起業家への投資に注力をしているベンチャーキャピタルです。さらにいうと、起業して初めての資金調達、プロダクト開発前の起業家さんへの投資も行なっています。
簡単にいうと、スタートアップに初期から投資という形で支援し、将来その会社がエグジット(IPOやM & A)した時に株式を売却しリターンを得るビジネスです。要は、個人が企業の株に投資しているように、我々も投資家ですので、キャピタルゲインで生計を立てる商売です。
詳しくはベンチャーキャピタルのビジネスモデルについて体系的にまとまっている書籍やアニマルスピリッツ/朝倉祐介さんのPodcastなどがおすすめです。
僕はベンチャーキャピタルで働くキャピタリストとして、日々投資したいスタートアップ(起業家)を探して、投資をするか検討するということを日々行なっています。一般的に検討するポイントは、やはりそのスタートアップが成長し、将来リターンを得られるか?という点です。
では、その会社が成長し、将来リターンを得られるかどうか?をもっと細かく分解すると様々な要素が上がると思います。
将来リターンを得られるかどうかという点に関しては、投資判断の際にバリュエーションという概念があり、どんな価格でそのスタートアップを評価するかという検討ポイントが大切になってくるのですが、(その会社がイケイケえもバリュエーションが高かったら、そんなにキャピタルゲインが期待できない、だから投資を見送るということが普通にあります。)
今回は、その会社が成長しそうかどうかを考えるに際して、ビジネスモデルの作り方そのものについて、エイドリアン・J・スライウォツキーとデイビッド・J・モリソンによる”THE PROFIT”の邦訳「プロフィット・ゾーン経営戦略」を参考に考えてみます。
”THE PROFIT”が書かれたのは1997年。それ以前は市場シェアを伸ばし、量的成長を追求すべきだという市場シェア偏重の経営思考がありました。
本書では企業が高い利益を獲得できる経済活動領域であるプロフィットゾーンを中心として、ビジネス・デザインを設計すべきと提唱しています。
2023年とこの本が書かれた時代を比べると、相当にビジネスの環境は変わっていますが、ビジネスモデル環境の変化を捉えプロフィットゾーンを常に捉えるという本書の主張している考えは普遍的でいつの時代に通じるものがありそうです。
前置きが長くなりましたが、今回の文章はビジネスモデルの作り方についてなるべくスタートアップの立場から書いていきます。
*補足しておくと、ベンチャーキャピタル側の視点に立った時に、バリュエーションを評価しなければいけないという観点からそのスタートアップの「市場シェア」と「成長」は大事になってきます。
一方で、スタートアップに限らず経営者の立場に立った時、「市場シェア」と「成長」にだけに注力してビジネスをすれば良いという考えが間違っていそうというのはなんとなく直感的にわかる気がします。
例えば、スタートアップでいえば市場シェアなど言う前に、目の前の1人のお客さんと向き合う必要がありますし、ある程度成長している会社でも複数の事業をマネージしていく必要があり、より会社側に意識が置かれるはずです。
プロフィット・ゾーン経営とは何か?
いうまでもないかもしれないですが、なぜ、市場シェアをとることに注力するとダメなのか?ということを簡単に触れておきます。
例えば、10社の競合相手が存在する市場を考えてみましょう。市場シェアの合計は理論上100パーセントになります。しかし、各社の戦略計画を見てみると、全てが数年後の市場シェアの増加を謳っています。
しかも、微増ではなく大幅な増加です。すべて足すと、5年後の市場のシェアの合計を足してみると、150%みたいなことになっています。これはおかしいですよね。
もちろん、市場でシェアを獲得することも大事ですが、プロフィット・ゾーン経営では、「顧客にとって最も重要なのは何か」という問いから始めます。そして、「どこで利益を得ることができるのか」その後に「どうすれば、そこで市場シェアを取ることができるのか」という順番で考えていくことになります。
ビジネス・デザインの4つの次元とプロフィット・ゾーンに達する方法
さて、本書ではビジネス・デザインとは何かについて、4つの次元で捉えています。
①顧客の選択
利益をもたらしてくれるのはどの顧客か?対象としたくないのはどの顧客か?については重要な問いです。
②価値の獲得
製品そのものの販売以外でもファイナンシング、付属製品の販売、など顧客に向けた価値によって、企業がどのように報酬を得るのか?というのも重要な問いです。
③戦略的コントロール
「なぜ顧客は当社から購入すべきなのか。なぜ当社から購入しなければならないのか」「自社の価値提案を争う競争相手のものと差別化し、ユニークにしているのは何か」について考えていきます。
④事業領域
企業がどのような活動を行うのかについての問いです。当たり前かと思いますが、事業領域は常に広げられたり、狭められたりするので他の3つと同様並行して考える必要があります。
これらを全体として整合性と相互補完性をもって機能するよう4つの次元の整合性を捉える必要があるとしています。どの顧客を選ぶかは、どの顧客が利益を与えてくれるかに依存するし、どのように利益を上げるかは、事業領域に依存性ています。
本書では、この4つの次元を押さえながら、本書でいうプロフィット・ゾーンを中心に達する方法を22個紹介しています。そのうち、最初に挙げられているのが、顧客開発/顧客ソリューション利益です。
顧客開発サイクルの最初の部分で膨大な支出をし、顧客のビジネスを理解する。次に自社サービスをできるだけ顧客の環境に合わせ、それを顧客の事業活動内容に組み込むのである。初期のキャッシュ・フローはマイナスでも、数ヶ月以内に黒字に転ずる。顧客リレーションの維持コストは低く、継続率は極めて低い。
なんだかこの文章、SaaSビジネスを想起させますよね、もちろん、この文章が書かれた当時はには、SaaSという言葉はありませんでした。
他にも22個の切り口から利益の作りかたを捉えているのですが、本の中盤からはコカコーラ、スウォッチなど実際の企業の成功例をもとにプロフィット・ゾーン経営の実戦について書かれています。
プロフィット・ゾーン経営戦略を読む時に参考にしたい企業の例
例に挙げた文章からSaaSっぽさを感じられるように、本書は現代にも通じる普遍的な内容だと思っており、自社の事業や身近な成功している企業についてこの本の内容に照らして問い直しながら読むのが良いかなと思います。
例えば、SaaSで言えば、ラクスやSansan、フリー、マネーフォワードなどはARRが100億円を超える企業になっています。それぞれ複数のサービスを提供しており、どのようにプロフィットゾーンを捉えているのかを考えてみるのが勉強になると思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
