
スナック小谷オンラインVol.1 〜官僚から起業・転職した夫婦が霞ヶ関を離れてわかったこと〜
今年の7月2日、「編集者とまだ見ぬ著者とのおしゃべり空間」をコンセプトに始まったFacebookライブ「スナック小谷オンライン」。
現役書籍編集者の僕と、ユニークなキャリアを持つ著者候補が紹介形式で「ウィズコロナの働き方」をメインに対談していく番組です。
週一ペースの対談が、はや20人を超えました。
自分自身あまりにためになりすぎて二時間以内に収めることがどうしても難しく(汗)、アーカイブとして、また知らない方にも短時間で内容を知って頂けるように、文字化して残していきたいと思います。
第一回目は、元官僚の小林味愛(現起業家)・中西信介(現コミュニティコーディネーター)夫妻との対談です。日経新聞などメディアにも取材されているので、ご存じの方もいらっしゃるかもしれません。では、どうぞ!
-----------------------------------------------------------------------
小谷俊介(ホスト):あらためてよろしくお願いします。こういうの初めてですか?夫婦でオンライン対談っていうのは。
中西信介(ゲスト夫):なんかイベントとかに夫婦で参加したりとかはあったりするんですけど。なんか大体ね。総合構成のあるzoomとかはあるけど、このなんかライブ形式の二人揃っては初めてかもしれないですね。
小谷:今、お仕事お二人とも大変じゃないですか?最初にまず簡単にちょっと自己紹介みたいな感じでお願いしても良いですか?どちらからでも。

中西:じゃあ私から。中西信行と申します。今日はお声がけ頂き、ありがとうございます。現在は都内の保育園で勤務しています。保育士の資格も持っているんですけど、どちらかと言うと園全体の運営だったりとかをやらせてもらっていて。保育園で働いてから約5年くらいたっています。
今日のプロフィールというか、お声がけ頂いた経緯にも関係するんですけども、その前までは国家公務員を。色々転職しながら4、5年くらいやっていまして。それ以外では、豆腐の引き売りっていうリアカーに乗せて引き売りする仕事を。
小谷:豆腐!あんまり豆腐のリヤカーって見ないですけどね。焼き芋くらいしか。
中西:あのラッパで「パープー」ってやつなんですけど。
小谷:リアルには見たことないかもしれないですね。
中西:なかなかね。多分この現代では珍しいですけど。まあそういう事をやったりとかして、5年くらい前に保育園で働き始めて今に至るんですが。
一年半くらい前に娘が生まれて、娘が生まれたのをきっかけに昨年一年間は育児休業を頂いていました。この4月にまた保育の現場に戻ってきたという形になっています。
小谷:じゃあ、復帰ホヤホヤですね。
中西:そうですね。復職と同時に、やっぱりこのコロナの影響などもあって保育園を一時的に閉めたりとか、また開けたりとかっていう形でようやく。まだ落ち着いてないですけど。少しづつ仕事にも慣れつつ、育児と仕事の両立の仕方にもちょっとずつ慣れてきている感じですね。
小谷:今回のテーマというか、Facebookのタグに付けたんですけど、やっぱりテーマは働き方、キャリア(チェンジ)にしたくて。僕も実は結構キャリアチェンジをしているので。
編集者になったのが30歳になる1か月前で。それまでに業界を3つ変わってまして。同世代の中ではジョブホッパーだった認識があるんですけども、今振り返って見ると、それで良かったなっていうのがすごくあるんですね。
世間的には終身雇用は崩れたとか言ってますけど、いまだに転職は良くないっていうのがあったりする中で、新型コロナとか3.11(東日本大震災)とかっていう、いわゆる黒船的なものが来て生き方についての価値観が多様化してきているなっていうのがあって。
新型コロナ騒ぎで、ようやく働き方自体もリモートになって変わらざるを得ないっていうのが出てきてるのかなっていうのがあって。
そういった意味で中西さんもコロナ下の保育園運営っていうのも、コロナ前と物理的に空間的にも違う働き方をされていらっしゃると思うんですけども。またそこはちょっと後ほど伺わせて頂きたいなと思います。
ではあらためて、小林味愛さん。簡単に自己紹介をお願いします。
小林味愛(ゲスト妻):はい。「株式会社陽と人(ひとびと)」という福島県の地方創生に関わる会社の代表をやっております。
私ももともと公務員で、役所は違うんですけど夫(中西さん)とは同期で、公務員を5年やった後に民間の会社に転職して、2017年から福島県の国見町っていう、福島の中でも小さな町に会社を立ち上げて、今は東京に暮らしながら福島で会社を経営している感じです。
小谷:いわゆる二拠点生活っていうやつですよね。
同期ってその、公務員時代に出会われたわけじゃないんですよね?
中西:公務員の内定時代からの知り合いですね。役所は何々省とかそういう形の採用ではあるんですけど、幅広く言うと国家公務員っていう、今でいうと総合職ですけど、当時は国家公務員一種っていう肩書きの横のつながりで、何百人っていう知り合いがいる中でのメンバーっていう感じで。
小谷:今って「一種」って言わないんですか?もう。
中西:そうですね。今は「総合職」っていう言い方ですね。
小谷:そのみんなが集まる場があるんですね。パーティーじゃないですけど何か。オリエンテーリングみたいな。があり、これで知り合い、お付き合いされ。その時は何処の省庁とかに行くのって分からない状態なんですか?
小林:いや、分かってたよね?
中西:そうですね。正確に言うといわゆる何々省とかに内々定が出る直前くらいに出会ってはいるんですけど、実際みんなでグループで遊ぶようになったのは内定が出てからって感じですね。
小谷:ああいうのって、第三希望みたいなのもあるんですか?普通の会社で部署希望を出すときみたいに。
中西:そうですね。官庁訪問の仕組みみたいな感じのことは今ちょっと正確に、現行がどうなってるか分からないですけど、基本的には1次試験と2次試験を通ったら、その中からそこまで合格した人が3つくらいまで希望の省庁を面接受けて回れてるので、その中で相性というか、もちろんこちら側からもそこに行きたいっていう意思と、あちら側からも是非来てほしいっていう意思を大体3回くらいやりとりして、お互いがマッチングすれば内々定がもらえるっていう感じですね。
小谷:なるほど。で農林水産省に入られたということですけど、希望はある程度通ったんですか?
中西:そうですね。官庁訪問っていうので面接に行ってる過程の中でどこがいいかっていうのを考えて、入らせてもらったって感じですね。
小谷:普通に見ると「農林」って泥臭そうなイメージがあるんですけど、現場に行くことはそんなにないにしても、日本って農林関係ってイメージ的にちょっと遅れてそうみたいなのがあるんですけど、どういう理由で農林水産省に行こうと思ったんですか?
中西:そうですね。僕自身、そこまで国家公務員になろうと思ったきっかけ自体にそこまで深い理由はなくて。
小谷:深い理由なくて受かっちゃうなんて凄いですね(笑)。
中西:いやいや(笑)。大学時代にスキーをやってたんですけど、それでいわゆる引退した後に民間の就活に時期的に間に合わなかったっていうのもあって、大学4年の春にみんな内々定とかもらうと思うんですけど、そのタイミングではもう就活も間に合わないので、一年間就職浪人というか、就職のタイミングを後にしてその分何か自分で大学の中に、「今まであまり勉強してこなかった分、ちゃんと勉強できるものを見つけよう」っていうので公務員試験を目指したっていう経緯があって。
で、その中で役所で働いてる方達に出会ったりとかして、国のために働いてる人たちってすごくかっこいいと思って行くようになったんですけど。あとは何々省とかに関しては、正直インスピレーションでいくつか選んだ中で農水がいいなと思ったのは、もともとうちの実家が祖父の代まで農家だったっていうことと、やっぱり面接を通して出会う人たちが魅力的だったっていう、まあ本当にいわゆる「こういう人たちと働けたらいいのかな」って面接してて思ったのがきっかけですね。
小谷:そういうかっこいい先輩たちがいたんですね。
中西:そうですね。結構役所によってカラーとかもあるんで、働いてる人の性格というか気質とかも結構違ったりとか。
小谷:イケてる人いるんですね、やっぱりね。それで入られて、実際リアルな農水に関わるお仕事ってされたんですか? 新聞記事を見ると、国会の審議のペーパーを作るのに殺されそうになったみたいな。
中西:いや、まあ。なんか、そうですね。僕もすごい短い期間で辞めてしまったのでそこについてあんまり深く語れはしないですけれども。
まあ多分皆さん国家公務員で働いているとか官僚で働いている皆さん、大体国会の審議対応とかっていうのは必ず皆さんと通る道だと思うんですけど、最初に赴任したポストが特にいわゆる激務と言われる場所で国会対応で、それこそ徹夜の連続っていう。
小谷:「国会対応は忙しい」っていうのは、やっぱりそこは最初の入省者たちがそこでライオンの子供じゃないですけど谷に落とされて這い上がってくるみたいな意図もあるんですかね。
中西:そこまで深い意図はないと思いますけど(笑)、自然に働いてたら絶対いつかのタイミングでそこにぶつかるっていうだけで、それが最初にくるか二番目にくるか三番目にくるかくらいの話だと思います。
小谷:意外とまだ知られてないですもんね。そんな徹夜の連続みたいな人達がいるっていうのは。
中西:そうですね。
小谷:本当にじゃあ寝袋とかでやってたんですか?
中西:そうですね。でも、今と当時で時代背景が変わって来てるから。今が私が体験したものとイコールではないと思うんですけど。やっぱり、国会対応とかっていうと大臣が読む答弁が出揃うまで朝まで待機してたりとかして、朝5、6時くらいにセットが完了したら一回帰って、また翌朝というか数時間後くらいにまた出勤するみたいな形なんで、帰るけど帰ってすぐまた出てくるみたいな感じですね。
小谷:書類をチェックしてその場でリアルに修正を入れてくれみたいなあれがくるとかってあるんですか?
中西:そうそう。だから私が経験した業務っていうのは国会対応の全般の話の中で言うと、ものすごい人数の人たちがそこの作業に関わっていて。本当に中の文章を考えるところから、出揃って来た資料を全部一つにまとめて綴じるっまでていう。
小林:コピーもね。
中西:そう。なんか色々な部分があって。正直若手の仕事っていうのは一番最後の取りまとめだったりとか関係部署との調整とか。ほんとだからそれですね。
小谷:なるほど。ほんとスーツ着なくてもいいんじゃないかみたいな。走り回れる格好の方がみたいな。
中西:はい。
小林:あれはあれで面白かったね。要は答弁って言っても、紙がバーってなってると読みにくいから一個一個「耳貼り」っていって。付箋みたいなの。1とか2とか3とか。あれがずれちゃいけないっていうんですね。
中西:蛍光ペンとかね。ちょっとその耳につけたりとか。
小林:あれ面白かったね。
小谷:むちゃくちゃ完璧が要求されるんですか?ずれてちゃいけない。
中西:すごいもう皆さんの血の滲むような努力の元に大臣の一言が詰まってると思うと、国会答弁とかもう泣けてきます(笑)。
小谷:ああ、そういうことか。
小谷:勉強のコツ。やっぱりお二人共受験勉強とかが好きだったんですか?公務員目指す人ってそういうのが。
小林:私は高校、大学も受験も受験してるけど彼はあれですよ。大学まで一回も受験した事ないから。
中西:附属高校から早稲田にいって。高校は、たまたまその附属高校がある地元の中学校に通ってたので。よく分からないけど地元枠っていう謎の枠があって、中学校から3人くらい勝手に推薦でいけるってシステムがあって。たまたまその下の高校が、そこに誘致する経緯の中で地域の学生も集めようって事で枠を作ってくれたんだと思うんですけど。
小谷:でもやっぱり全受験科目基本満遍なく出来た方がいいんですか?
小林:もうだって10年以上前の話でしょ?覚えてる?
中西:そうですね。試験のあり方も色々変わってるのかなと思うんですけど。
小谷:数学苦手でもいけるんですか?お二人でも学部といえば文系ですよね。
中西:でも本当色々なパターンがあって。いわゆる今僕らが話してるのって技術職とか農水省で言ったら”農業土木”とか、そういうのやってた人のいわゆる専門コースみたいなやつですね。
多くの人がイメージするのは、多分事務職とか事務官っていうコースだと思うので。それを前提に話をすると、やっぱり教科とかで言ったらすごい満遍ない感じで出題されて。例えば僕は経済職っていうので当時受けたんですけど、経済理論とか財政学とか、経済事情とか。諸々経済系の知識が求められはするんですけど。
そういう意味で言ったら大学で別に、僕経済学先行した訳じゃないんですけど、当然最低限の数学の知識とかは必要かもしれないですけど。でもあれは試験勉強のための試験勉強というか、別の次元の勉強なんで。
小谷:結局だからそれが公務員に向いてるとか、それこそその配属された省の仕事に向いてるとかっていうのは全然関係ないっていうか、いわゆる普通の入試と同じみたいな。
中西:はい。法律職とか経済職とかあるので、正直それがないとその仕事の現場で活躍できないかっていうと多分そんなことはない。ですけど、いわゆる幅広い分野の問題を。要は効率良くインプットして、ある程度試験の形式って決まってるので、そのパターンを自分の頭の中で理解して効率良く学んでいくっていうスタイルはインプットとアウトプットのやり方みたいなものは、処理速度みたいな感じですかね。ある程度頭の中に入れられるストックと処理速度は最低限ないと、やっぱり試験がクリアできないから。
その意味で言うとそういう足切りみたいな意味では意味があるのかなとは思うんですけど。ただ本当に適性があるかどうかっていうのはまたちょっと別の話かなとは思いますね。
小谷:それはそうですよね。徹夜できる体力があるかどうかなんて分からないですもんね(笑)。それって結構重要かなって、僕も経験上思うんですけど。いつかどこかで徹夜に近い事をしないといけない場面ってやっぱりあると思うんですよね。特に二十代の人なんて。どこかで自分の体力がどこまで通用するのかとかっていう試験があってもいいのかなみたいな。会社じゃなくてもなんかこう。僕は全然出来なかったんですけど。
中西:それって、鍛えてなんとかなるものとそうじゃないものがあるじゃないですか。だからその人の特性もあるなと思ってて。僕は寝ないとダメな人なんですけど。例えば3時間睡眠を一週間続けていける人といけない人っているじゃないですか。それは僕は全然いけないタイプで。やっぱり睡眠時間が削られてくる事で頭が働かなくなってくるけど、その中でも働く人とかもいると思うんですけど。
小谷:じゃあ、小林さんも3時間睡眠とかだったんですか?
小林:3時間どころじゃ(笑)。
中西:3時間寝るとしたら職場の段ボールでっていう感じじゃない?
小谷:段ボール?
小林:床にダンボール。
小谷:えー⁉︎ 仮眠室とかないんですか?それは衆議委員時代ですか?
小林:いや、経産省時代。
小谷:経産省で床にダンボール敷いて寝る(笑)。
小林:仮眠室、当時は男性用しかなかったんだよね?
小谷:え⁉︎ めっちゃ差別じゃないですか。そんなの。
小林:当時はね。今は分からないけど。男性用はやっぱり臭かったから嫌だった。
小谷:臭そうですね。確かに(笑)。女性だけ床に寝てたって事ですか?
小林:あ、でも後輩の男子達も床で倒れて。可愛かった(笑)。
小谷:女性って何人くらい居たんですか?
小林:その時の忙しい法律の部屋は私しか居なかったから。
小谷:他は全員男性で。
小林:うん。
小谷:何人くらいの部署だったんですか?
小林:8人くらいかな?
小谷:紅一点でも床の上の段ボールでっていう。
今の前の職業が内装の仕事だったんですけど、内装の時もそんな感じでやってましたけどね。ネズミの出る床の上で、厨房の床の上でとかっていうのはありましたけど。もう思い出したくないですね。
それで30分寝て着替えとか持っていってみたいな。合宿形式って感じですね。(笑)
小林:着替え持っていったかも危ういよね(笑)。
小谷:危ういくらいの。やっぱりもう仕事量がめちゃくちゃ多いって事なんですよね。実際5年やって企業に入ったと思うんですけど、何か一番驚いた事ありますか?霞ヶ関の公務員と民間の働き方ってみたいな。あるいは風土でもいいんですけど。

小林:一番驚いたのは「あ、なんかこんなに適当でいいんだ」っていう。公務員だと一文字も間違えない様にとか句読点の位置どうしようとか、どうやったらわかりやすい表現になるか一言一言こだわって。
小谷:文書作成がやっぱり多かったっていうのもあって、っていう事ですか?
小林:資料作成とか分かりやすい図はどうかとかね。細かいチェックがあって、何段階ものチェックがあって、ようやく資料一個が出来るのに、民間に行ったらなんかちょっと微妙だなと思って出した資料がそのままポンっていっちゃうから「えー!」と思って。
小谷:小林さんは日本総合研究所ですね。
小林:そうですね。三井住友系ですね。
小谷:まあまあ、その適当さというかそのスピードの問題もあるんでしょうけど、その分スピーディーに仕事が進んでたとかじゃないんですか?
小林:いや、なんか適当なのがいっぱいあるみたいな感じ。
小谷:中西さんは農林水産省の後、豆腐の引き売りに。
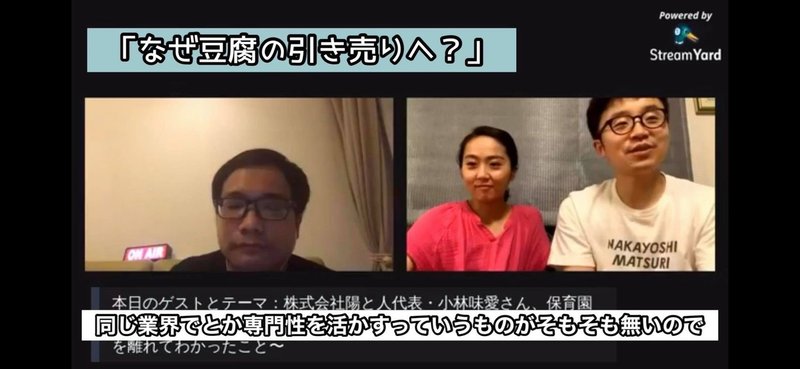
中西:そうですね。なので豆腐の引き売りは、もちろん変わってることしかないので。霞ヶ関で働いてるものと豆腐の引き売りはあらゆるものが真逆なので、違う事しかないんですけど。
小谷:それはネタを狙ってたっていうのもあったんですか?のちのちこのネタ美味しいな、みたいな。
中西:そこまで当時精神的に余裕があったかは分からないですけど。でもなんか今までやった事ないまったく逆の方向で行ってみようみたいな気持ちは当時あったと思います。
小林:なんかバイトのさ、チラシだか雑誌みたいなの見てさ、豆腐のやつ丸してなかったっけ?
中西:そうそうそう。だから本当にそんなテンションですね。
小谷:タウンページとかで見て。
中西:そんな感じ。タウンページとかanとかいわゆるバイト雑誌みたいな。その中で一番奇抜なやつがいいなと思って。
小谷:結構そういうのって昔からあったんですか?性格的に。普通だったらね、やっぱりちょっと年収落とせないなとか、もう少し俺この辺ならいけんじゃねえか、みたいなので。9時-5時で帰る第一とか。まあ農林系だったらどういう選択肢があるのか分からないですけど。なるべく横にスライドさせてステータス落とさずに、みたいなのあるじゃないですか。
中西:まあ正直、培ってきたキャリアって言える程のものじゃなかったから、同じ業界でとか専門性を活かすっていうものがそもそもないので。それであれば、なんて言うんですかね。業種とかいわゆるそういうものとかは一回外れて。そもそも仕事ってなんだろうってことを考えた時に、いわゆる公務員的に会社に行ってすごい大きな組織の中の一つの歯車として、きちんと与えられてる仕事をこなしていくっていう所とは真逆の働き方をやってみたいなっていうのもあって。
自分で会社をつくるとかいろんな選択肢があると思うんですけど、当時そこまで力量とかスキルもあるわけでもないので、自分で働ける選択肢の中で考えた結果、自分の足ひとつで自分一人である程度完結できる仕事で、自分の裁量が自由に生かせて直接人に喜んでもらえる仕事って考えたら豆腐の引き売りだったっていうところですね。
やっぱりこう、なかなか目の前の人に喜んでもらえる仕事って、もちろん例えば職人やってるとか街にあるような仕事の多くはそういう仕事だと思うんですけど。いわゆるデスクワークって目の前にいる人達に価値を提供するっていうよりは、最終的にそれが回り回ってクライアントに届くっていうことだなと思うんですけど。
小谷:B to B的な感じですね。
中西:はい。やってる仕事がいろんな人の手に渡っていって、最終的に消費者とかお客にたどり着くって感じだと思うんですけど。やっぱり目の前にそれを喜んでくれるお客さんがいたりとか、豆腐の引き売りならその豆腐を欲しい人に売るんですけど、買ってくれるお婆ちゃんとかお爺ちゃんとか80代とか90代とか、すごい高齢の方たちで。
それを買って頂くのって、単に豆腐が食べたいって事だけじゃなくて、やっぱりその豆腐を引き売りしてくる若者を応援したいとか、もしくは自分が足がちょっと悪くなっちゃったから、なかなか買い物とか出れない中で。
あとはそのお婆ちゃんとかが郵便局まではがきを出しに行くのも、ちょっと自分の足が悪くて行けないんだけど、それを来てくれた若者に「ちょっとこれ届けといて」って託したりとか。なんかそういう物を介したやり取りだけじゃない色々な形みたいなものをそこで感じて。
仕事ってお金になるとかそういうだけじゃなくて、それ以上の価値とか喜びを提供できる可能性があるんだっていうのをその時感じて。もちろん公務員とか大きな組織で働くっていう事も引いてはそういう所に通じてくるんですけど、やっぱりその「手触り感」がなかなか得がたかったっていうのはすごくあったかなと思いますね。
小谷:お役所の仕事ってほんと、B to Bなのかな?
中西:まあ、ものすごい回ってのB to Cだと思うんですけど。
小谷:でもやっぱり対極ですよね。焼き芋屋とか。結構焼き芋屋さんで有名なテレビで出てる人っていますけど。いも子さんとかね。芋の色の帽子被って。
小林:やばいわ。見たいわ。めっちゃ興味ある。
小谷:いも子さんって入れるともう出てくるんですけど。
小林:東京ですか?
小谷:東京だったと思いますね。結構変態ですね(笑)。あ、戸田公園とか埼玉の方ですね。
小林:えー!?会ったことないね。
小谷:結構やっぱりファンが付いてて。老若男女ですよね。やっぱり焼き芋って女性でも好きだったりとかっていうのがあって。それだけじゃなくて、焼き芋開業講座みたいなのもやってて。やっぱり脱サラした人達が、OLさんとかが「やりたい!」みたいなので。僕もそれ見てすごいやりたくなったんですけど。
「豆腐屋あこ」って人もいるんですよね。知り合いの西澤さんって人がやってるDAFっていうトークライブイベントがあって、そこに出てたんですけど。やっぱりその人も似たようなこと言ってましたね。お年寄りと交流することで、コミュニティを実感するというか。
中西:まさにそうだと思います。
小林:めちゃめちゃ仲良くなってたよね。なんか文通してなかったっけ?お婆ちゃんから来たよとか言って。
中西:そうそう。しばらくずっとやってた。
小谷:それは絶対に前の仕事では得られない所ではあるでしょうね。豆腐の引き売りはどのくらいやってたんですか?
中西:一年くらいですね。
小谷:一年。週5とかで?
中西:そうですね。基本的に毎日豆腐売ってて。日によって行くエリアが若干変わるくらいな感じですね。
小谷:それって、フランチャイズ形式になってるんですか?
中西:まあそうですね。豆腐は自分で作るわけじゃないので、豆腐の引き売り師として登録をしておいて、そのエリアに倉庫を持っていて、会社で。で、豆腐が朝大量に届くんですけど、それをリヤカーに朝積む所から始めて。
小林:豆腐積んでたね!
中西:積んでましたね。本当、今考えたら。
小林:豆腐と納豆と油揚げ。
中西:あと湯葉ね。シソ巻きとか。お爺ちゃんお婆ちゃんが食べてくれそうな物。
小谷:そういうのも作ってそういう登録してる人達の所に配る会社さんに登録されてたっていう。
中西:そうです。
小林:アルバイトだったよね?
中西:そうですね。アルバイトっていうか個人事業に近いかな。だからきちんと売り上げ残せば稼げるし。
小林:売り上げ、めっちゃ低くなかった?
中西:だから売れ残ると買取になるんですよ。
小林:そう。当時うちの冷蔵庫、豆腐と油揚げと納豆しかなかったですから。
小谷:ヘルシーですけど飽きますよね(笑)。さすがに。
中西:一年分、一生分くらいは食べましたね。あの一年間で。
小林:美味しかったね。
小谷:買取。結構ブラックなのかな?分からないけど。
中西:まあ結構ブラックではあったと思います。基本的にあんまり売れないですから。
小谷:一日に何丁くらい売れるんですか?
中西:一日、とりあえず3万円は売らないと赤字になるとか、そういうラインはありましたね。
小谷:豆腐で3万って、結構ですよね。一丁三百円とかそんなものですか?
中西:多分それくらいだと思います。もちろん良い豆腐なので普通にスーパーで買うやつより高いんだけど。でも豆腐三百円だったら百丁売ってようやくトントンみたいな感じでした。
小林:トントンになってたんだ(笑)。
中西:まあ、やっぱりある程度続けるとお客さんもついてくれるから、そうするといくんですけど。そこまで持っていくまでが結構大変で。
小林:なんか新聞とか作ってたんですよ。「中西新聞」っていう新聞を。自分で手書きで書いて、自分の顔のアップをどーんって、なんか写真貼って。
小谷:素敵ですね。
中西:結局やっぱりね、ファンになってくれるかどうか。やっぱり自分のことをちゃんと知ってもらうとか、お客さんのことをちゃんとこっちも理解するっていう意味で言うと。
だから本当あれですよね。今いろいろオンラインサロンとかありますけど、それの超オフライン版みたいな感じですよね。ファンコミュニティをどう作るかみたいなところ。
小谷:そうですよね。ファンビジネスですよね。
小林:それこそ今でもつながってるもんね。
中西:そうですね。本当だからそのエリアに行けばそこの人たちに会いたくなるって感じですね。
小谷:それは埼玉の方で?
中西:そう。川口とか蕨とかあの辺りのエリアですね。僕がやっていたのは。
小林:なんかママ達にサザエさんのカツオに似てるとか言われて、「カツオちゃん」って言われて(笑)。
中西:そうですね(笑)。坊主で豆腐売っていたので。
小谷:坊主でメガネで豆腐売ってたら、気に入られるしかないですよね(笑)。ちょっとわかる気がするなっていうのは、僕も昔出版社を辞めた時に次を決めずに辞めちゃったんで、どうしようかなってなった時に食い繋ごうと思うってチラシ配り、ポスティングやったんですよね。
中西:ポスティング?
小谷:ポスティングなんですけど真夏だったんで本当にクソ暑い時期に。結構ちゃんとしたところで、どこかのゴミ箱とかに捨てるの分かったら罰金みたいな。それでもみんなコンビニとかに捨てたりするんですけど、バレたらバレたやつを毎回毎回発表してくるんですよ。で、毎回日に日に減っていくんですけど。
中西:一枚いくらとかなんですか?やっぱり。
小谷:いや、もう日当制ですね。十何年前なんで、多分時給千円もいってないと思うんですけど。でもなんか楽しめたんですよね。編集者とは全然違う仕事だったんですけど。お婆ちゃんが縦長の買い物バックを入れて引くカートみたいなのあるじゃないですか。
中西:あります、あります。カラカラしてるやつ。
小谷:分かりますかね。あれを買わされて。
中西:あ!チラシ配ってる人あれ。
小谷:そうなんですよ。何が面白かったかっていうと、結構色々な苗字がポストで見れるんでその苗字に興味を持って。この人すごい変わった苗字とか楽しみになって。なんか楽しみって見つけられるものだなって人間って。「一言」って苗字があったりして。どういう流れでその一言っていう苗字になったのかなとかいうのを家に帰って調べるとか。そういう本当に細かい所に楽しみを見出すみたいな。というので、結構仕事って、どんな仕事でも楽しめるものはあるんだなっていうのをあの時思ったんですけど。
でも一年やって、それで何か次へ移ろうと思ったんですか?
中西:そうですね。結局豆腐買い取りまくってるので収入の柱としてはとてもならないし。さっきのポスティングもそうかもしれないですけど、夏は暑い中リヤカー引いて、でも冬の方がきつくて。冬でも豆腐は氷水に入れてるから。
小谷:それはきつい。
中西:雪道の中も歩かなきゃいけないとか。歩道橋とかがすごい危険なんですけど。まあ大変だから長くやれるものではないなと思って。
小谷:そうですよね。
中西:当時結婚はしていなかったので、もう少し長い先のこと考えたら収入の土台がないと結婚できないなと思って。
小谷:そこで結婚したらめちゃくちゃロックですけどね(笑)。
中西:まあ新郎のお仕事は豆腐の引き売りですみたいなのも。ある意味面白いですけど。
小谷:ケーキが豆腐ケーキみたいな(笑)。
中西:そうそう豆腐で作って欲しいですね。お色直しリアカーで入場して。
小谷:ぶっちゃけでも引き売りの収入ってどのくらいだったんですか?
中西:たぶんですけど、アルバイトとかでも1日働いたら1万円とか。でも買取があったから、きっと多分半分くらいしか稼いでなかったんじゃないかな。1ヶ月で10万とか15万とか。まあワーキングプアみたいな感じですよね。
小谷:さすがに二桁はね。
小林:でも貯金はマイナスだったよね?
中西:やっぱりね。なかなか。
小谷:いや、20代で貯金できる方がもうおかしいと思ってますけどね。
中西:そうですね。投資をした方がいい。
小谷:投資をね。豆腐に投資をされたわけですね。あとそうだ。保育園のコミュニティマネージャーって。僕もその子供預けてる立場からみて思うんですけど、どういうお仕事なんですか?

中西:僕がやっているのは保育園の、正式には「コミュニティマネージャー」っていう仕事で。なかなか聞かない仕事ですよね。今は結構コミュニティマネージャーとか増えてきてると思うんですけど。僕が働き始めたのは6年前とかで、まだそこまでそういう仕事って増えてなかったんですけど。
小谷:ですよね。
中西:なんか時代背景としては2011年に東日本大震災があって、やっぱりその後に結構NPOとか、ソーシャルベンチャーとかソーシャルビジネスとかっていうのがすごい勢いで、時代的にも来てた時あったじゃないですか。
小谷:はい。
中西:当時僕も、豆腐の引き売りの後に公務員の仕事をしていたんですけど、その中で働く中でやっぱり震災復興とかそういうテーマにも関わったりとかする中で、この公務員の仕事をこの先ずっと10年20年かけて続けて行くのか、どこが一番自分に向いているんだろうなっていうのを3年くらい働いた時にすごい考えていて。
やっぱり公務員とか大きい組織の中で身を置いて働いていくってことは安定するし、見通しも立つんだけど。なんかその中で何十年もいるっていうイメージが自分の中で湧かなくて。
やっぱり当時ビジネスで社会課題を解決することににすごく興味を持って、いろんなところの人たちを訪ねてお話を聞いてたんですけど。その中で一番ピンと来たというか、いいなと思ったのが今勤めてる保育園で。当時まだうちの代表が会社を作って3年くらいの時だったんですけれども。
新しく今度保育園を開園するんで、そこの保育園に「コミュニティマネージャー」という専門職をそこに置きます、という話をメディアとかでも語っていて。で、僕もすごいその仕事に興味があったので入らせてもらったんですけど。当時どんな仕事やるかとか一切決まってなくて、自分で考えてちょっとやっていきましょうみたいな感じだったんですよ。
今お子さんを保育園に預けられてるからイメージ湧くかもしれないですけど、保育園って地域の中の核になるような施設で、まあ要は地域で生まれた子供達が同じ場所に集って、かつその地域で働く大人たちもそこに毎日送り迎えとかで通ったりとか。今コロナで改めて保育園の機能とかそういう価値とかって皆さん実感されてるし。僕自身もすごい感じてるんですけど。
やっぱり社会的に大きなインフラになるなと思っているんですけれども。そう考えると、そこに通ってる子供達の育ちを支える事はもちろん保育所として大切な機能なんだけれども、そこにコミュニティを作っていくってことで子供を中心にその街がどう育っていくかっていう事とか、地域の人とその子供達の関係性が作れるかとか。
逆にそこに集まってくる親御さんっていうのは、同じ時期に子供をそこで育てていく「同士」でもある訳だから、家庭同士の交流とかをもうちょっと活発にする事で子育てがより孤独というか孤立したものではなくて、街ぐるみで子供が育っていくっていう事をできる一つの大きな役割を持っているんじゃないかっていうことでコミュニティマネージャーって仕事が意味を持つ。あとはどういう事をやるかは考えながらやっていきましょうみたいな話なんですよ。
なので実際入ってから、保育や子供のことも聞いた事も学んだ事もなかったので、まずはその保育の勉強をしたりとか、色々な親御さんとか地域の人たちとお話をする中でなんかちょっと子供達とこういう地域で、野菜づくりがすごい上手な人たちが出会ったら面白いんじゃないかとか。保育園に通うお父さん同士ってなかなか交流がないから、お父さん同士で保育園のDIYを一緒にやったりとか飲み会をしたりしようとか、そういう形でとにかく接点を増やしていったりとか。それが回り回って子供達の豊かな子育てに繋がっていくんじゃないかっていうことを考えて形にしています。
小谷:なるほど、親同士を引き合わせてる事で化学反応というか、それがうまくいけば繋がるしっていうので。確かに園がコミュニティっていうのはアリですよね。
中西:なんか今ね。例えば会社もコミュニティ化。なんか色々そういう感じでかなり言われるとは思うんですけども。保育園ってね、やっぱり地域の中の大きくね、存在になるし。やっぱりいろいろな今地域との接点って普通に働いてる人にあまりないじゃないですか。子供が生まれて初めてやっぱりそこで地域に根ざしてる人達に関心を寄せるようになる一つのきっかけではあると思うので。
小谷:なるほどね。そういうの幼稚園ではもしかしたらやってるのかな?分からないですけど。小学校とかも分からないですけど。でも学校をそういうコミュニティにするっていうのは、新しいですよね。押し付けがましくないっていうか。
中西:はい。
小谷:いわゆるそういう地域の学校関連のコミュニティっていうのは、やっぱりよくあるPTAっていう言葉しか思い浮かばないんですけど。結局今もう訳分からないことになってるんですよね。小学生のママとかの話を聞くにつれ。ベルマークを無意味に集めさせられたりとか、なんかその仕分けですごい有休取らなきゃいけなかったりとか。なんかもうPTAっていうのはもう悪みたいな感じで。結局コミュニティの機能になってないみたいなのだろうなみたいなのはあるんですけど。そうじゃなくて、やっぱりもう実際の交流を目的としてるところですもんね。
中西:はい。
小谷:そういうのは良いですよね。特に今って本当にマンション暮らしの人とか多いですしね。やっぱりうちも未だに隣の所に挨拶してないとか、やっぱりそういう人達ってもう間違いなく増えてきてると思うので。
コミュニティ、そういうのが保育園だったら。あまり子供が大きくなっちゃうとあれですけどね。確かに小さいうちだったら交流はしやすいっていうのも、子供同士がね、抵抗なくっていうのはあると思うんで。
中西:うん。まあでもある意味、震災以降もそうだしコミュニティの価値みたいなものはすごく言われてはいますよね。まあなんかただ実際どう手を付けていいか分からないっていうのは実態としてはあると思うし。
小谷:そうなんですよね。
中西:あとは多分昔からの幼稚園とか保育園って、お寺が経営するじゃないですか。やっぱりお寺ってたぶん檀家制度を通して昔から一つのコミュニティとしてずっとその地域の方達にとってお寺自体が学び舎として機能してたり。そのお寺のコミュニティ機能っていうのがやっぱり幼稚園や保育園にも生きていたものがすごくあると思うんですけど。
小谷:寺子屋的な。
中西:そうですね。ただやっぱり高度経済成長以降に人口がどんどん増える中で都心の方にできた保育園って、とにかく保育、子供を預かるだけの場所として増えてきた経緯があるので。やっぱり地域との接点ってどちらかというと薄かったりとか。
やっぱりこう色々子供を取り巻く事件とかっていうのも90年代以降増えてきたりしたとか。よりどちらかというと安全とか安心っていうのが謳われたりしていた経緯があるので。やっぱり地域との交流っていうのを積極的にやるというよりは、やらない方向になっている部分もあったんですよ。
ただまあ、震災以降はコミュニティの機能が注目されつつあると思っていて、これから先を考えていくとより働き方も多様化する中で、大人が要はこれまでって都心にみんな通って行ってるような時代だったと思うんですけど。このコロナでみんな在宅ワークとか増えて、改めて自分の住んでる地域で暮らす時間っていうのがどんどん長くなって来てる中でいうと、なんか住む街とか暮らしてる街に対する関心とかアンテナっていうのが高くなってきてるのかなとは思います。
小谷:いま、出会う場ってないですからね。新しい土地で。僕ももともと池袋に住んでたのが結婚を期に横浜に移ることになって。飲み屋街が全然無い地域で結構新しい地域なんですよ。なので飲み友達もできず、家帰って子供と家族とだけしか交流がないっていうのはあったんですけど。職業が職業なんで地元で、横浜で著者と知り合えたらなみたいなのとか。そういう交流が確かに保育園とかでそういうのをやってくれたら非常にありがたいですよ。今なんてお父さんが送り迎えに行くとかっていうのは普通にありますし。うちの保育園でもできないかな。
中西:そういう親主体というかね。どちらかと言うと親は預けに行くっていうスタンスが多いんですけど。これ目指すべき学校の形とかも関わってくると思うんですけど。やっぱり学校とか職員側が園や学校を作っていくのではなくて、子供の方が主役だしそこに預けてる親もがその学校を作ってる構成員の一員だっていう事を、上下関係じゃなくフラットに考えていけるようにしたいなと思いますし。逆に一親としては子供を預けてる園にどう関われるかとか、どうそこでまた楽しんで親同士が付き合ったりとか。他の子供達とも接点を持てるみたいなことは、なんか色々考えたいし、多分提案したらきっと多分喜んでくれる園の方達も多いんじゃないのかなと思います。
小谷:コミュニティデザイナーっていうのは保育には直接携わらない訳じゃないですか。保育士の資格をお持ちだっていうのはありましたけど。そういうのはちゃんと収入が入ってくる事になってる訳ですか?仕組みとして。
中西:そうですね。いわゆる。僕今保育士も持ってて、保育の手伝いとかももちろんしたりはするんですけど。そういう意味でいうと保育園の多分そのお金の流れみたいなやつは詳しくは調べてもらった方が分かるんですけど。基本的に認可の保育所とかは決まった金額を補助金という形、運営費という形で行政からお金を頂くような形なので、その中でどういう風に園の運営費を使っていくかっていうのは基本的に任されているところがあって。
で、コミュニティコーディネーターっていう仕事も園の運営を担う人間ではあるので、園の事務的な仕事をしたりとか保育の補助をしたりとか、本当に子供達と関わる時間をたくさん持ちながら、プラスでさっき言ったような仕事をしていくっていうような事なので。その仕事だけやってる人っていう感じではないですね。なので、園を運営していく上では欠かせないメンバーになることで、園がチームとして機能していく上では職員との連携とかもすごく大事なのでそこをやりながらっていう感じですね。
小谷:なるほど、新しいですね。最先端ですね。ある意味。
中西:だから、別にコミュニティコーディネーターっていう肩書きがなくても今言ったような世界観とか価値観を持って動いていく人が園の中にいたりするといいよね、と。
やっぱり先生とか教職員とかってどちらかというと大卒でみんなそのままそこの仕事に就いてたりすると、他の世界のことを知る機会がなかったりとか。どうしても同質性が求められたりする中にいると、そういうちょっと異質な人が組織の中にいることで何か理屈じゃない「面白そうだな」とか「ワクワクするな」みたいな所を起点にやっぱりこう物事が進んでいくっていう事ももっとあってもいいんじゃないのかなっていう。
小谷:へー。幼稚園でもそういう人材の多様化が進んでるんですね。
中西:そう。だからほんとコミュニティコーディネーターは園に多様性を持たせるような人であるっていうのはありますね。
小谷:それは面白い。そやりがいがありそうですね。じゃあ是非園長目指してガシガシ広めていただいて、本を書いていただいて(笑)。目標としてはあるんですか?もっと広めて行きたいとか。
中西:もちろんそういう面白い取り組みが横展開で色々なところで起こっていったら面白いなとは思いますけど。僕は別に保育の専門家ではないから専門性を掘り下げる人ではなくて、やっぱり保育とか一つの分野があったとしたらその裾野を出来るだけ広げていきたいというか。
今まで保育や教育に関わってない人とか、「なんかそういうのって自分とは違うな」って人たちにも興味を持ってもらったりとか、専門性を掘り下げる方ではなくて専門性を広げるというか、なんかできるだけ別の領域の人達と接点をもっと持てるように価値を広げていくような仕事の方が楽しいなとは思いますし。これからね、また仕事をしていく上で言うとそういうスタンスで常にやりたいなと思ってますね。一つのことを突き詰める職人タイプみたいな人も大事だけど、それだけじゃやっぱり。こういうコロナ時代もそうだしあらゆる変動要因が多い中でいうと、色々な人たちが組織の中にいることは良いなとはすごく思います。
小谷:そういう活動のアウトプットみたいなものは。
中西:仕事の話に関しては、仕事の中で今そういう活動というか、コミュニティーコーディネーターの事に興味を持ってくれてる人達との講座みたいなやつを年間通してやってたりとか。
小谷:コミュニティには興味あって、編集者っていうのも人と人を繋ぐ仕事なので。人と人を繋ぐって、繋いで本という形に。まあHUBってよく言われるんですけども。やっぱり。そういう仕事なので、こういう企画もそうなんですけど。コミュニティを作るっていうのはやっぱりやってみたいなっていうのはすごいありますね。
中西:確かになんかその。今保育園とか子ども園。今系列園がいくつかあって。各園にこういうコミュニティコーディネーターっていう仕事をしてる人がいるんですけど、出版社から転職してくる人って結構いて。だから今5人中2人は元出版社。確かに、いわゆる編集の仕事と多分すごく通ずるところがあるのかなとは思います。
小谷:そうですね。橋渡し。読者と本と読者の、著者と本、まあ読者の橋渡しっていう媒体的な意味合いもあるので。多分その形がね、本ではなくてマッチングというかそういうイベントとかっていうのに変わるだけで、本質は多分同じだと思うので。
なのでやっぱり地方創生っていうのも、話があれするんですけど。興味がありまして。最後に小林さんに伺いたいんですけど、地方創生って僕もある程度その内容、今までのエピソードは記事拝見してるんですけど。例えば今、自分がこのビデオ見てる方の中、あるいはこれから見られる方の中で地方創生やって見たいんだけど、別にそれを仕事にするっていうより身近な、例えば週末にどっか行ってやるみたいな。やり方も出来るんですか?
小林:もちろん関わり方は。
小谷:アルバイト感覚というか副業感覚というか。
小林:関わり方は人それぞれで自由だと思います。色々な関わり方があると思うので、その人にあった関わり方が出来るのが一番良いのかなっていう。
小谷:そういう時、ポータルサイトみたいなのってあるんですか?例えばここの地域が好きだからここで田植えをしてみたいなとかって思うとするじゃないですか。茨城かどっかとかで。気軽になんかそういうポータルサイトみたいなのがあるのかなとか思ったり。あと人手を募集してますとか。
小林:あんまりそんなまとまったのはないかもしれません。
小谷:要は地方移住を将来的にもしかしたらやりたいかなと思って、ちょっとお試しでお手伝いとかやってみたいなとかっていう時にアクセスする方法って何かあるのかなって。個人的に思ってて。
多分小林さんとかだったらお仕事でも関われたわけですよね。その前職の。仕事で直接関わってない人がそういう事に興味を持った時にアクセスする方法ってあるのかなって。
中西:要は移住未満の関わり方って事ですよね。
小谷:そうです。
中西:観光以上、移住未満って事ですよね。
小谷:そうですね。まさに、まさに。
中西:ちょっと前に「関係人口」っていうね、ワードがブームになった時もあったけど、多分その。
小谷:関係人口?
中西:地域のファンになったりとか観光で行くとかっていうレベルよりは、例えばなんかそこの地域のものを買って応援するとか。その地域の何かしらお手伝いとして関わるとかそういう人口の、都市に住みながらそういう地方の事に関わっていくような人たちの事ですけど。
小谷:ふるさと納税のリアル版みたいな。
中西:そうそう。お金的なつながりももちろんあるし、それ以外のもう少しこう実際に足しげく通って色々お祭りに参加するとか。そういう関わり方とかあるけど。なんかでも、そういうのはやっぱり自治体がやっていますね。
小谷:気になる自治体のサイトを見てそこでイベントは分かるっていう感じなんですかね。
中西:あとはだから協力隊とかにみんななってたりとか、地域おこし協力隊とかになるか、その前の地域おこし協力隊になりませんか的なイベントとかは結構そういうの狙ってやってるやつはいっぱいあります。
小谷:青年海外協力隊的な。
中西:その地域版ですね。だいたい皆さんあれですよね。自分の地元とか、もしくは学生時代に所縁があったとか。大体ね、興味を持つ場所はそういう所だと思うんですけど。
小谷:そうですね。自分自身今、横浜に住んでますけど、実際小学校1年から5年まで同じ横浜市には住んでいて。あざみ野って所なんですけど。やっぱりなので、ちょっとしたその縁っていうのは感じていて。過疎ってるわけでもなんでも別になくて、多分これから人口が増えていく地域ではあるんですけど、ちょっと文化があまりにもない地域なので。コミュニティっていうんですかね。本当にマンションとそういうカンファレンスビルみたいな物しかないみたいなっていう所なんで。逆になので創生っていうより、そこに新しいコミュニティを作るっていう事ができればなっていう。自治体をチェックするっていうのは確かにありですよね。本日はありがとうございました。
対談のポイントまとめ-----------------------------------------------------
・二人に共通しているのは「人生なんとかなる」という楽天さ、起きたことをポジティブに解釈する前向きさ、いい意味でのプライドのなさ、そして「本当に自分がやりたいこと、貢献できることは何なのか」を目の前の忙しさに流されずにきちんと考え抜く真摯さ
・自分に言い訳したり社内の同調圧力に屈せず、自分が勝てる場所を探し続けることが転職を成功させる秘訣
・「官僚」から「豆腐の引き売り」のように正反対の選択をすることで、自分に足りない経験を手に入れやすくなる
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
