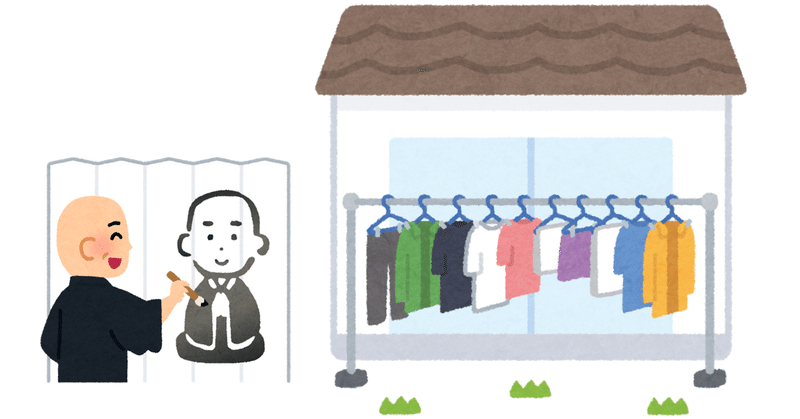
坊主がダベリに来る休日
結婚後2年間を過ごした松戸のアパートは新築の1階で、だだっ広い駐車場に面した猫の額ほどの庭があった。
私の通学も妻の仕事もない日曜は、庭に面した6畳間の掃き出し窓を開け放ち、お茶を飲んだり本を読んだりしながら呑気に過ごした。
ちなみに、その部屋には義兄からのお下がりである古いブラウン管テレビがあったが、引っ越して間も無く画面に何も映らなくなった。音声を発するだけのその『箱』を、私たちは『ラジオ』と呼び、NHKが受信料を徴収に来るのを心待ちにしていたが、ついに現れることはなかった。
今でも時々想う ──
あの『ラジオ』を見せ、
「これでも払わなきゃならないの?」
と尋ねたら、集金人はどう反応しただろうか?
もちろん、置き物と化した『ラジオ』を聴くことはほとんどなく、それは、テレビに半ば支配されている現在の生活とは異なり、我々の休日には無限の自由度があった。
そして、庭に足を出して爪を切るなどしていると、整備などされておらず限りなく空き地に近い駐車場を横切り、境界のまばらな生け垣を乗り越えて、にこやかに庭に侵入してくる男がいた。
「いい天気ですね。ちょっとお話させていただいてもいいですか?」
── 最初はそんな感じだった。
年齢は私たちより5歳ほど上、20代の終わりぐらいだったろうか、
「近くのお寺で僧侶をしています」
と自己紹介した。
髪は短めではあったが、服装は休日のサラリーマン風だった。
彼は住職である父親の助手的な地位にあり、僧職以外の仕事は持ってはいなかった。『御勤め』が無い時にはありあまる時間を持て余しているらしく、散歩コースに建ったアパートに住む若いカップルに興味を持ったようだった。
私が国立大の大学院生で結婚したばかりだとわかると、休日にしばしば現れ、縁側状態の部屋の端に腰を下して尋ねもしない自分語りを始めるのだった。
「いや、基本的にはヒマなんですけどね、いつ檀家の方がお亡くなりになるかわからないですから、長い旅行・遠い旅行には行けないんです」
「お酒お好きですか? ウチにはお供えのお酒、いっぱいありますよ。とても飲みきれません。持ってきましょうか?」
妻はこの人物がやって来るのをあまり好まなかったが、お茶ぐらいは出していた。
私がひとりでいる時、話のトーンは少し異なった。
「お寺って、儲かるんですよ……」
と『坊主丸儲け』を匂わせてから、
「でもねえ、この近くでは遊べませんねえ。檀家さんと出くわすかもしれませんからねえ。西日暮里より向こうには行かないと ── そのう……女のコのいる店で遊びたい時にはね」
辺りを気にしながら、小声で話すのだった。
「おシゴト、何してるの? って女のコに聞かれても、絶対にホントのことは言いません。**だということにしています」
── 残念ながら、その職業『**』の中身は憶えていない。
妻がこの人物を敬遠するのは、庭に干している洗濯物を気にしているからかと思っていたが、この時、理由の一端を見たような気がした。
けれど、まあ……率直で人間的だったともいえる。
一時期は毎週のように現れたこの『ナマグサ坊主』は、最初の1年ほどで姿を見なくなった。
(おそらく、結婚したのだろう……)
たぶん、お見合いで ── そう思った。
なお、彼が『お供えの酒』を持って来ることは ── ちょっぴり期待していたのだが ── ついになかった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

