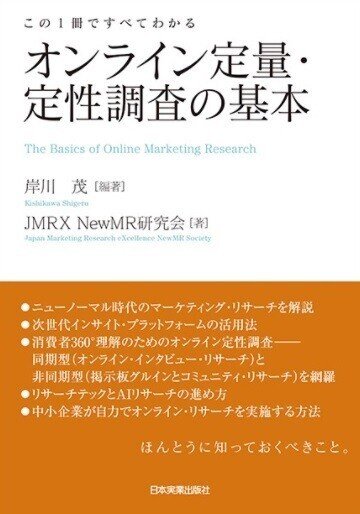『オンライン定量・定性調査の基本』
【2019年以降注目のマーケティング関連書籍】その9
『オンライン定量・定性調査の基本』
編著:岸川茂
著:JMRX NewMR研究会
出版社:日本実業出版社
第1刷:2021年5月1日
*今回は諸事情により、2日間前倒しで水曜日の公開です。
1. 本書を読んだ背景
昨年12月にご紹介した『マーケティング・リサーチの基本』(2016年10月1日第一刷)の第2弾です。
https://note.com/shuji_0212/n/n96acdf18b1de
本書の「編者」岸川氏と「著者」であるJMRX NewMR研究会につきましては、こちらのサイト(↓)もご参照ください。
https://jmrx-newmr.jp/
2. どんな人に向いているのか?
オンラインリサーチのなかでも内容は、ほぼ定性調査中心といってもいいでしょう。
そして、定性調査の理論というよりは、今現在、定性調査をする上で、どういう企業がどういったツールで調査を行っているかという、極めて具体的な“手引き書”というのが本書の最大の特徴です。
リサーチャーにとって必読とは思いますが、マーケティング調査を自ら行われたり、調査会社に発注される側の人たちに読んでいただきたいと思いました。
3. 本書のポイント
上述の通り、オンライン定性調査を企画する上で"座右の書"なのですが、定性調査理論についてボリューム小ながら貴重な知見も記されています。
私が注目した方がいいと思った章の執筆者は、クロス・マーケティングの井上さん(私の研究仲間ですがこの記事はヤラセではありません)と、デコムの大松さんのお二人。
まず、井上さん。
この1年間、定性調査専門外の私の眼と耳に入ってきたのは、「オンラインのグループインタビューでは6人は多すぎで人数を減らした方がいい? よねぇ?」。
このままならそういう(微かに)同調圧力的な「空気感」に定性調査業界が覆われちゃうんかな? と思っていたら、
「いやぁ、そうじゃないでしょ? あのなぁ、本質つーのはな・・・」
と井上さんの実践に裏打ちされた理論がドカンと炸裂しています。
本書に掲載されたのは井上さんの理論の数十分の一のボリュームなので、本書をイントロダクションとして単著としてのご著作出版が待たれるところです。
大松さんの理論につきましては、第1弾の『マーケティング・リサーチの基本』では最も輝かれていたというのが私の所感でした。
今回も短いながらインサイト探求のケーススタディは興味深いものでした。
大松さん(とデコムさま)の基本思想には私も共感しております。
「商品やサービスもいいんだけどよ、まずはな、人間を見ようや、オイ!」
言葉遣いは失礼かと思いましたが、私の我田引水による解釈です。
テキストマイニングによるインサイト解析も勉強になりました。
テキストマイニングでは私はKH Coder使ってますが(こちらもご発注くださいよ! 奥さん、じゃなくって皆さん、、マキタスポーツかよ?)。
4. 感想
コロナ禍から1年以上経過したこの5月、本書が刊行された意義は大きいと思いますし、岸川さんのご尽力には頭が下がるばかりです。
以下は2点、私が本書を読んでインスパイアされたことです。
定性調査の専門家ではないこともあり、実務的な興味よりも研究的な興味です。
1) MROCリクルーティングについて(215ページ)
MROCの事業者なら、ブラックボックスにしておきそうなのが、良心的に内実を明らかにしていることも、本書の大きな特徴でしょう!
たとえば50%が不適合者であって、そのまた半分が受動的。
有益な参加者は25%という経験に基づく知見があり、調査品質向上のためオーバーリクルーティングをされているとのことですが、どの程度まで品質向上が図られるのか? という検証結果が出てくるのかな? と思いました。
これはオンライン定性にとどまらず、パネルの劣化が問題となっている定量調査でもそうかな? とか。
つまり、「パレート(80対20)の法則」のような法則も検証できるのかな? と思ったからです。
「有益」な参加者が100%というのはあり得ない話だと思うからです。
働かないアリを排除しても、残りの働いていたアリの中から同じ比率で働かないアリが出てくるわけでして。
で、「有益」な参加者が、今現在の経験則で25%だとしたらそれが何パーセントまで向上するのか? という興味です。
2) 「文学社会学」的なモデリング(仮説)の構築
「人の明暗両面を見なきゃダメダメ」というデコムの大松さんの知見(エンジェル&デビル)に刺激されたんですが、私の得意分野で「文学社会学」でフレームとか作ってみたいな、というアイデア以前の思い付きです。
これはまだ研究以前、趣味ですかね?
故 油谷遵氏の『マーケティング・サイコロジィ』の参考文献リストにも、「人間を心的存在として把握する方法のトレーニングのため」に、夏目漱石『道草』が挙がられてました。
KH Coderのマニュアル『社会調査のための計量テキスト分析』も、夏目漱石『こころ』が題材でしたしね。
最後ですが、JMRX NewMR研究会のサイトには私も寄稿させていただいております。
(岸川さん、どうもありがとうございます!)
書籍のテーマである「オンライン」とは直接関係してませんし、「デスクリサーチ」についての原稿です。(↓:表紙をクリックください)
・この2年ほどの間、配布させていただきました資料の解説版でもあります。
・執筆内容につきましては、クロス・マーケティング様に感謝しております。
以上です。
*見出し写真:高遠湖ー高遠さくらホテル客室より(2017年5月)
ここに写っていない左側に、お花見で有名な高遠城址があります。
戦国・江戸期の高遠城の雄大な姿は、現在、ダム湖の中に沈んで見えません。よく言われる「潜在意識」のアナロジーということで掲載しました。
◆ホームページはこちらです(↓)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?