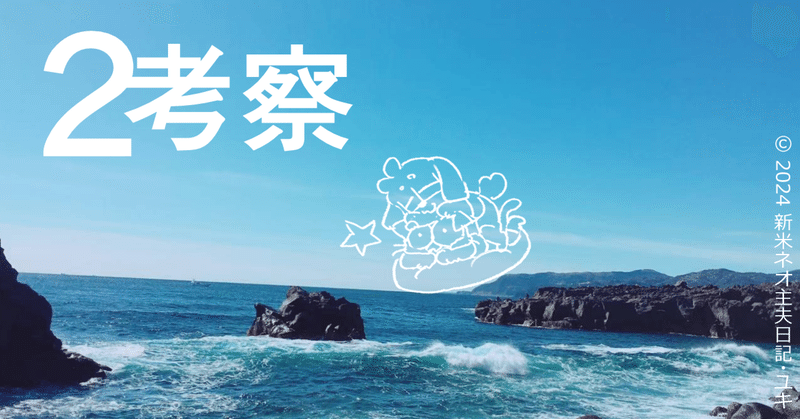
あっちじゃない裁判を考えたゲイ主夫(2/2考察パート)
<修正履歴>
2024.05.20
「補足考察※2」の文章を一部修正。
理由は、筆者による片寄った表現であったため、実際の政府の言葉を引用し、訂正しました。ご指摘ありがとうございました。(コメント参照)
訂正後)
現政府の言う「現行憲法では、同性カップルに婚姻の成立を認めることは想定されていない」という主張。
訂正前)
現政府の言う「憲法を改正しない限り同性婚を認められない」という主張。
――つづき
今回は「同性パートナーにも犯罪被害の遺族給付金を」訴訟の考察パートです。
判決文からの疑問点と考察
判決文を読み解いたが、3点の疑問が生まれた。
以下の通り。
婚姻できない同性カップルをなぜ「事実上婚姻関係」と認める?
これで同性カップルも「事実婚」ができるようになる?
最高裁はなぜ自ら判決を確定せずに差し戻した?
1つ1つ調べたり、考えてみた。
疑問1.婚姻できない同性カップルをなぜ「事実上婚姻関係」と認める?
なぜ同性でも「事実状婚姻関係」と認めるか。
実は、判決文から明確な理由は見つけられなかった。
こんな感じ。
~(略)~事実上婚姻関係と同様の事情にあったといえる場合には、犯罪被害者 の死亡により、民法上の配偶者と同様に精神的、経済的打撃を受けることが想定さ れ、その早期の軽減等を図る必要性が高いと考えられるからであると解される。し かるところ、そうした打撃を受け、その軽減等を図る必要性が高いと考えられる場 合があることは、犯罪被害者と共同生活を営んでいた者が、犯罪被害者と異性であるか同性であるかによって直ちに異なるものとはいえない。
一部抜粋
言ってることは、かなりシンプルだ。
シンプルすぎるので、最高裁が言いたかったことを考察してみた。
キーワードは、やはり「事実状婚姻関係」。
「事実上婚姻関係」とは婚姻制度ありきで成立するイメージだろう。婚姻関係になれない同性カップルは、必然的に「事実上婚姻関係」にもなれない、と。
逆に、社会で想定されていない関係に、先に「事実上婚姻関係」が顕在化したとしたら、どうだろう。
次に、社会で「事実上婚姻関係」を守ろうとして法律が制定され、「婚姻関係」ができあがる。男女の婚姻制度も、きっと流れは同じだったろう。
そうなると、過渡期(法律制定前)は、「事実上婚姻関係」だけが存在する状態があり得る。
今が、その過渡期だとしたら。
同性同士で、「事実上婚姻関係」だと表現してもおかしくない。
事実、2審の名古屋高裁は、棄却しながらも、原告の内縁関係は認めている。最高裁はそこに、”なぜ同性というだけで「事実上婚姻関係」と言えないのか”、と言いたかったわけで。
明文されていないが、似た理論で最高裁は判決をしたのではないか、というのが私なりの解説&考察である。
疑問2.これで同性カップルも「事実婚」ができるようになる?
これは、明確に「否」と言える。
誤解しやすいが、「事実婚」は「事実上婚姻関係」の略ではない。
判決文を読み解くに、以下の式ができあがる。
「事実上婚姻関係」=(男女の)事実婚+(男女の)重婚的内縁+(男女の)近親婚的内縁
つまり、「事実上婚姻関係」の一部が「事実婚」だ。
今回の件で、同性が「事実上婚姻関係」の一部になれるといっても、「事実婚」になれる、という話ではない。
(直接的には「否」だが、間接的には、今後、事実婚につながる可能性はある。(補足考察>文末※1))
疑問3.最高裁はなぜ自ら判決を確定せずに差し戻した?
Wikipedia曰く、上告審が判決を覆す時は、「差し戻し」が一般的とのこと。
(へぇ~)
逃げ腰な判決かと勘ぐってしまったが、そうではないようだ。
最高裁を責めないようにしよう。
総括/裁判を経てもう1つの考え
現在は、
「事実上婚姻関係」=(男女の)事実婚+(男女の)重婚的内縁+(男女)近親婚的内縁
である。
ここに、一連の結末を経て、「同性カップルの内縁」がプラスする。
キーワードとなる、「事実上婚姻関係」という言葉。
同じ言葉が、民法や条例に多く使われている。
今回の結果が、他にも波及してゆく可能性がある。
この可能性は、判決文でも、1人の裁判官が危惧を表している。
犯給法5条1項1号の「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事 情にあつた者」と同一又は同趣旨の文言が置かれている例は少なくないが、そうし た規定について、多数意見がいかなる解釈を想定しているかも明らかでない。個別 法の解釈であり、犯給法と異なる解釈を採ることも可能と考えられるとはいえ、犯給法の解釈が他法令に波及することは当然想定され、その帰趨次第では社会に大き な影響を及ぼす可能性がある。現時点で、広がりの大きさは予測の限りではなく、 その意味からも多数意見には懸念を抱かざるを得ない。
一部抜粋
あくまで、最高裁は「(今回争点の)犯給法」だけの判決だと言っているが、同性カップルを除外する明確な理由がなければ、波及は止められないだろう。
もし、多くの法律で、同性カップルの内縁がプラスされるとしよう。
「事実上婚姻関係」にプラスされまくった結果、同性カップルで「婚姻関係」が無いのはおかしい、という理論は、結果、成立する。
(補足考察>文末※2)
この未来を、本裁判で最高裁は見越したか。
最高裁が、ひそかに「同性婚」へつながる道筋を作り上げたのだとしたら、凄い。
最後に
今回の判決は、最高裁から「同じ人間として、マイノリティよ、頑張れ」とメッセージが発信されたような気がした。
最高裁なのに、めずらしく弁論の場を設けたこと(こちら参照)にも、メッセージ性を感じる。
最後にこの憲法を貼り付けておく。
〔個人の尊重と公共の福祉〕
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
この判決は、ひそかに、そしてあっとゆう間に未来を変える可能性を秘めている。
そう確信している。
P.S.
当考察をボコさんに熱く語ったら「よかったね」って言ってました。
長文、失礼しました。
ということで、大いに興奮すべき状況だ。
法律よ、早く追いついてくれ~!
おしまい。
補足考察
ご興味ありましたらどうぞ。
素人の考察です。
補足考察※1(「疑問2.」より)
「事実婚」や「内縁」だが、実は、条件は法律に定義されていない。
法律で認める関係性ではないからだろう。
みんなが思っているより、ずっと自由なものなのだ。
言葉すら認定されたものでなく、内閣のページでは「いわゆる事実婚」と枕詞までついている。(検索いただければ、わかる)
簡単に言うと「この人とは事実婚です」と叫べば、事実婚である。
事実婚のために住民票を1つにする人もいるが、対外に認めてもらう場合に限るもので、事実婚の条件ではない。
今回の結果「事実上婚姻関係」が波及してゆけば、同性婚より先に事実婚が対外に、しいては国に、認められる可能性はある。
事実婚は、いい意味でとても曖昧なのだ。
P.S.
ちなみに、ボコさんの会社から同性カップルとして扶養補助を頂いているのだが、頂く条件は「住民票を1つにすること」でした。ぼくら既に、内外ともに「事実婚」!? U〼ﻌ〼U
あくまで独自考察です。
補足考察※2(「総括」より)
同性婚ができる道筋は本当か、をあえて疑ってみる。
一つ。いやらしい可能性を考えようと思う。
政府が、同性婚を成立したくない前提で。
現状、同性婚は法律で禁止されていない。
想定すらしていないので、認めるも禁止もしていない。
(「対象外」と表現する人もいる)
逆に、重婚や近親婚は、法律で明確に禁止されている。
「事実上婚姻関係」で認める同じ内縁でも、こういった違いはある。
話を戻そう。
「同性婚」への道筋の話。
政府が今後、同性婚を法律で禁止にして、重婚、近親婚と同じように並べる、という未来もゼロではない。(内縁関係だけ認めるパターンね)
そうすれば、「同性婚」への道筋は断たれる。
しかし、この未来は無い。
具体的にどう法律で禁止するか考えてみよう。
今回の裁判中、被告は(愛知県、愛知県公安部(※上に警察庁))「現在ある、男女の婚姻の枠組みの中に、禁止制度として男女の重婚、近親婚がある」的なことを言っていた。
重婚や近親婚は,婚姻に該当することを前提とした上で,これを認める弊害に鑑み,政策的 に法律婚としては一律に禁じられているものである。それゆえ,個別具体的な事情の下で婚姻を禁ずる理由となっている弊害が顕在化することがないと認められる場合には,法律婚に準ずる内縁関係としての要保護性まで否定する理由はないとの判断が働き,そのような場合の内縁関係 は法律婚に準ずるものとして保護されるものと解される。
これに対し, 同性間の共同生活関係については,政策的に婚姻が禁じられているというのではなく,そもそも民法における婚姻の定義上,婚姻に該当する余 地がないのであるから(なお,この解釈自体については,原告も争うところではない。),重婚や近親婚の場合とは自ずから局面を異にしてい るといわざるを得ない。
名古屋地裁(1審)の判決文より抜粋
では、この説明を利用し、禁止制度に「同性婚」を加えるとしよう。
なんと、男女の婚姻の枠組みの中に同性の話が出てきて、話は矛盾してしまった。男女も同性もどっちも婚姻に想定しないと話が進まない。では、政府は同性の婚姻を認めて、同性の婚姻の枠組みの中で、禁止制度として同性婚を加えてみよう。なんじゃ~こりゃ。婚姻を認めた上で禁止するとなってしまった。また、話は矛盾した。(同性の婚姻の枠組みの中で、重婚、近親婚の禁止、はあり得るが)
つまり、同性婚の禁止は、できないのである。
さらに、もう一つ、いやらしい可能性を考えよう。
現政府の言う「現行憲法では、同性カップルに婚姻の成立を認めることは想定されていない」という主張。
つまり、同性婚の法律を永遠に作らない未来だってありえる。
しかし、日本の三権分立が崩壊しない限り、この未来はない。
当裁判で最高裁の結論が出てしまった以上、この未来になったら立法府が機能していないことになってしまう。
〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕
第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
事前知識として。
憲法は上記のとおり、「夫婦」と表現しているが、夫夫、婦婦を禁止するなどの明記はない。
同性婚を作っても違憲にならない(同性婚を明確に禁止にしていないので)、という事実が重要だ。
その上で。
確かに、今までは「違憲状態」として政府の放置は許された。
しかし、今回の判決が出てからは、「事実上婚姻関係」として同性カップルが想定されてしまった以上、放置すること自体が24条2項「個人の尊重」違反となってしまう。
むしろ、放置できない状態になってしまった。
政府が「同性カップル向けの婚姻関係に似た何かしらの制度」を作る未来も考えられるが、同性が「事実上婚姻関係」に含まれまくった未来では、婚姻関係以外の道筋をつくるのは相当な理由が必要だろう。
つまりは、「同性婚」を禁止する、作らず放置する事は、今回の裁判の背景をなぞると、不可能になってしまう、ということだ。
逆説的に言うと、「事実上婚姻関係」の同性が他の法律に波及すれば(するだろうが)、「いわゆる同性婚訴訟」を待たなくても同性婚ができる、と言えてしまう。
P.S.
もし、こういった未来まで見越した判決だとすると。
ううむ、最高裁すげぇ~。
U〼ﻌ〼U
あくまで独自考察です。
自分メモ
※参考文献
6.pdf (gender.go.jp) …内閣府HPに唯一ある「事実婚」の表現
※犯給法
※判決文(&補足)
裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan …1審/名古屋地裁
裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan …2審/名古屋高裁
※参考記事
同性のパートナーを殺害された遺族の方が、犯罪被害遺族給付金の支給が認められず、裁判を起こしました | ゲイのための総合情報サイト g-lad xx(グラァド) (gladxx.jp)
名古屋地裁、同性パートナーは犯罪被害遺族給付金支給の資格なしと判決 | ゲイのための総合情報サイト g-lad xx(グラァド) (gladxx.jp)
犯罪被害者給付金訴訟最高裁判決を受けて新聞社説「法整備を急げ」 | ゲイのための総合情報サイト g-lad xx(グラァド) (gladxx.jp)
※その他参考
5100021.pdf (sn-hoki.co.jp) …近親婚的内縁への支給を認めた事例
重婚的内縁関係者は遺族年金を受給できるか | 弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所(東京都港区) (t-leo.com)
事実婚の手続きは法律婚と違う?必要な届け出は?ポイントを解説|離婚コラム|離婚弁護士に無料相談!離婚に強い弁護士なら弁護士法人あおい法律事務所【離婚問題専門サイト】 (aoilaw.or.jp)
事実婚の定義とは?法律婚との違いやメリット・デメリットを解説|ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ) (ricon-pro.com)
【内縁】どこからが内縁か。何があると内縁になるのか。 - 横浜の離婚弁護士に無料相談|弁護士法人なかま法律事務所 (nakama-rikon.jp)
【保存版】裁判でかかる費用のすべて|負担を減らす工夫も紹介 | 弁護士保険のエール少額短期保険 (yell-lpi.co.jp)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
