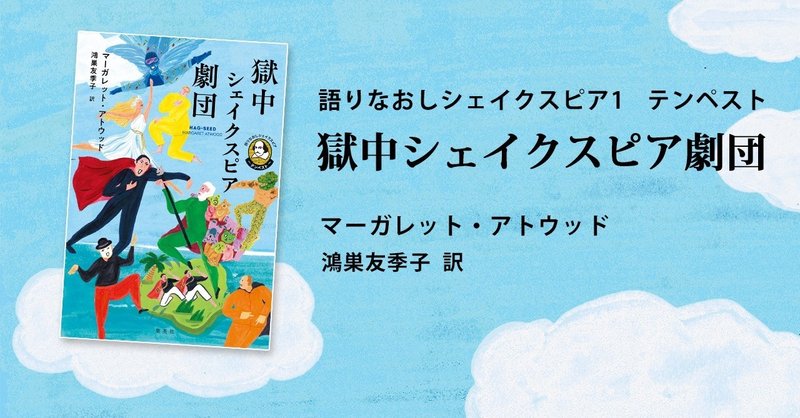
【インタビュー後半】マーガレット・ アトウッド 聞き手・翻訳/鴻巣友季子 「シェイクスピアの物語は、無限に解釈が可能なのです」

ⓒLiam Sharp
『獄中シェイクスピア劇団』の著者、マーガレット・アトウッド
さんと、zoomによるインタビューが実現! 聞き手・翻訳は鴻
巣友季子さん。コロナ禍のために、カナダのご自宅で過ごして
いるというアトウッドさんは、時折見せる笑顔が猛烈チャーミン
グ。穏やかな口調に熱を秘め、1時間以上にわたり語ってくださ
いました。小冊子では紙面の都合でカットした部分も含めて、
たっぷりとお届けします。インタビュー後半です。
ミランダは力持ち
(→前半より続き)鴻巣(以下K) 本作の複雑で重層的な語りのスタイルについてお伺いします。一つ目に「テンペスト」と小説のストーリーが見事にパラレルな関係になっています。二つ目に、劇中劇の形をとっていて、小説が「テンペスト」の獄中版を内包しています。三つ目に、獄中劇団による「テンペスト」公演の「メイキングもの」にもなっています。どのようにこの劇が作られていくかが細かく語られる。四つ目に、ここがとてもユニークだと思いますが、本作は「テンペスト」を読み解き、分析する研究書にもなっています。劇の発表会の後、それぞれの役者が自分の考える「テンペスト その後」のレポートを発表しますね。受刑者たちの精神的な成長を感じる場面です。この重層的な造りをどのように構想しましたか?
アトウッド(以下A) 刑務所でシェイクスピア劇を教えている人たちの本をたくさん読みました。教えるだけでなく実践的な上演をおこなったりしている人たちです。こういうプログラムでは、初回のクラスでなにをするのか? 演劇に参加したい人たちはもちろんその台本を読みますね。つぎに、登場人物たちの人となりを掘り下げるためにディスカッションを行う。どんな劇でもそうです。キャストはその劇のなかでなにが起きているのか理解する必要がある。自分がどんなキャラクターを演じているのか、その人物にはどんな解釈が可能なのか。フェリックスは教師でもあるので、劇団のメンバーにいくつか課題を出します。その課題の一つが、「劇の終わった後、自分の演じたキャラクターがどうなるか考える」というものなんですね。
「テンペスト」には答えの出ていない問いがたくさんあります。たとえば、キャリバンはあの後、どうなったでしょう? これまでにもいろいろな解釈の舞台があって、島に残ったキャリバンが幸せそうに暮らしている、というものもあります。とうとう自分の島をとりもどしたわけです。でも、これは本当に幸せなことでしょうか? 島にはほかに誰もおらず、彼は独りぼっちになるのです。どうしてハッピーエンドなのでしょう? もう一つの解釈は、彼がプロスペローたちと一緒にミラノ行きの船に乗るというものですが、ミラノに行ったキャリバンはどうなるでしょう?
要するに、みんなよくわからないわけです。誰が演出をしても、その疑問は残ります。シェイクスピアにもわからなかったんじゃないかという気がするときがあります。ですから、わたしたちが決めなければなりません。シェイクスピアの劇には、こういう「空白」がたくさんあるんです。
K そのレポート発表のなかで、キャリバンは実はプロスペローの息子なのではないか、という問いかけが提示されますね? これは研究者の間で囁かれてきた仮説ですか?
A あれは、(本の中の)劇団のひとりがでっちあげた説ですので、これまで提言されてきたかどうかはわかりません。でも、この解釈の裏付けとなるものが作中にあるんですよ。「闇から生まれた此奴」をプロスペローが「自分のものだと認める」場面がありますね。これは、なにを言わんとしているのでしょう? 観客には語られません。「よし、こいつはわたしが引きうけた」ということでしょうね。つまり、何らかの関係があるということ? キャリバンをプロスペローの陰の部分とするということ? それはどういう意味か? 発表者のレッグズは、こういう推測をする。プロスペローと鬼婆(魔女)のシコラクスは同じ類の魔術を使える。同じようなことをしてきた。わたしたち読者は彼らが言外にほのめかしていることを、信じればいいではないか? この「ダークサイド」を「認める」というのは、つまりキャリバンはシコラクスとプロスペローの息子だということではないか。レッグズはそう主張しているわけです。考えてみると、一理あるでしょう。興味深くないですか? あの島に一種の家族ができあがるのです。プロスペローがお父さん、キャリバンは悪い子、ミランダは良い子……エアリエルも良い子ですが、そのことに不満がある。でも、少なくとも言われたことはやる。小さなプロト・ファミリー(家族の原型)ですね……プロスペローを父と考えると、(島の)ほかの登場人物はみんなある意味、彼の子ですが。そう考えると筋が通りませんか?
K 今回、男性ばかりの男性のなかに、すばらしく無敵の女性キャラ、アン=マリー・グリーンランドという元体操選手で、現在女優/ダンサーを登場させましたね。
A 「テンペスト」のミランダという役を考えてみると、彼女はおてんば娘です。かしずかれて育った貴族のお嬢さんではない。潤沢な衣装もなければ……たいてい裸足で登場し、島じゅうを駆けまわって、宮廷の令嬢なら決して許されないようなことをしています。自由な精神の持ち主で、きっと肉体的にもかなり頑強な人でしょう。毎日、そうとう体を動かしていますからね。宮廷画に出てくるような女性ではありません。きっとああいうドレスを着たお姫さまたちはとても脆弱だったでしょうね。まったく運動もしないし……ほら、ミランダが薪を運ぶファーディナンドを手伝う場面があるでしょう? ファーディナンドは出来ないのに、ミランダは薪をひょいっと持ちあげる。ものすごく力持ちなんですよ。
フェリックスはこのミランダ役に、精力ばりばりのダンサーであるアン・マリーを採用します。彼女が参加していた〈キッド・ピボット〉というダンスグループは実在のものです。アン=マリーはとてつもなく激しい、身体的なダンスを踊る。この手のダンスは、ずば抜けた運動神経と体幹の強靭さがなければ踊れません。
歴史が教えてくれるもの
K フェリックスは娘の死で抱えた深い喪失感ゆえに、不思議な症状を経験します。「サードマン 奇跡の生還へ導く人」という書籍を、謝辞の参考文献で挙げておられましたが。
A ええ。よく知られた症候群で、ジョン・ガイガーという著者の本です。山で遭難するとか、たいへんな窮地に陥った際、だれかが現れて助けてくれるんです。非常に近しい人を失った場合にも起こり得る現象です。なにかあるごとにその人が現れる。実際にしばしば起きる現象です。フェリックスはほかの人たちに聞こえないことが聞こえる。いるはずのない人に話しかける。はたから見たら、独り言をいっているようにしか見えない。
しかしここで問題が持ち上がります。「現実」とはなんなのでしょう? 「サードマン症候群」を経験する人、(短編の一つ「老いぼれを燃やせ」に出てくる)脳神経に関わる「シャルル・ボネ症候群」(鮮明な幻が見える)を抱える人にとって、目の前に現れる幻覚は「本物」以外の何物でもないでしょう。本物ではないと頭でわかっていても、実物の質感をもっている。蜃気楼を見たことがありますか? 砂漠や北極などで見られるものですね。わたしは見たことがあるのですが、実物そっくりに見えますよ。そこに存在しなくても、実在するように見える。人間の脳というのはおもしろいものですね。もちろん、プロスペローは魔術師で、幻覚を見せるわけですから「幻覚(イリュージョン)の科学」を勉強していました。魔術師というのは、どうやってそこに存在しないものを見たと錯覚させるんだろう? じつに興味深いですね。
K あなたはこれまで多くの社会問題を、それが表面化するはるか前に「予言」してきました。最近では、コロナ禍が引き起こした「ブーマーリムーバー現象」とか。これとよく似た運動を「老いぼれを燃やせ」という短編(2016年刊)に書いていますよね。また、摂食障害、解離性人格障害、虐待による心的外傷(トラウマ)など、多くの精神障害や症候群も「予見」してきました。それから学校におけるいじめ、ディストピア的な政権まで。『獄中~』では、”ソーシャルディスタンシング・ヴァーチャル演劇”と呼ぶべきものを早くも取り入れていました。あなたは「わたしは歴史上、あるいは現在に起きたことのないことは、一つも書いたことがない」と言いました。すべて実在すること、現実に起きていることだと。社会問題に対して、どうしたらそのような鋭敏で深い洞察力がもてるのでしょうか?
A「予言」ではないですよ。わたしに予知能力はありません。もしできたら、株をやって大儲けしています。そうでしょ?(笑)でも、本を読めば、人類の歴史のパターンは見えてくるものです。人間が行ってきたことは、繰り返される。だから、歴史を眺めてみれば、人間に可能なこと、やりそうなことは大抵わかるんです。良いことも、悪いことも。天候がつねにどのように歴史に作用してきたかもわかる。不作の年は、人びとは飢えて物価が上がりますから、社会不安が起きるだろうと予想がつく。そうならないはずがない。
演劇の公演に関しては、あの状況で何ができるのか、そしてそれをどう実現するか考えたのです。実際、劇場は今、新しい公演方法を試行錯誤していますが、それはその必要があるからです。必要は発明の母で、いつもそこに危機があると、刺激されて発明が生まれる。それは人々が、それならこうしたらどう? と他の道を考えるからです。人間の良いところは、発明家であるということですね。人間は創造的で、発明家で、問題を解決する。ただ、その発明がどんな影響を及ぼすか予期できない。これはもっと大きな問題ですね。
シェイクスピア劇は「美しく」はない
K こんにちの読者にとって、シェイクスピアの最大の魅力とはなんだと思いますか? なぜ四百年以上、読み継がれていると思いまか?
A まず、「読者」というのはやめましょう(笑)……シェイクスピアが魅了するのは「聴衆」ですね。シェイクスピアの戯曲は、本で読むと「ひどい」と思う人もいるでしょう。「こんな劇、誰が観るんだ?」と。でも、舞台にのってみると、なるほどと唸る。舞台技術やいろいろなものが合わさって、とてもドラマティックに見えます。たとえば、「タイタス・アンドロニカス」。本で読んだときには、「うええ」と思うでしょう。でも、舞台を観劇すると、すっかり引き込まれてしまう。
シェイクスピアは自分の作品を、座って読むものとして書いていません。自身が役者で、プロデューサーで、演出家でもあり、劇の作者でもある。シェイクスピアは「ぼくはシェイクスピアになるぞ」と思ってなったわけではありません。そんなことは考えていなかった。客を劇場に呼び込むのに、「つぎはどんな劇を上演しようか?」と考えるのに忙しかった。今、英国で史劇のベスト作品というと、かならず「ハムレット」や「マクベス」が思い浮かびますよね。でも、シェイクスピア自身にとってのベストは、いちばん収益の上がった作品ですよ。
シェイクスピア劇というのは、貴族相手のものだったその時代のフランスの古典演劇とは違って、万人に向けて書いていました。だから、悪趣味な喜劇的な人物も出てきて、庶民と同じようにしゃべる。卑猥なジョークを飛ばしたり、ダジャレを言ったり、馬鹿みたいなことをしたりするのです。木戸銭を払ってくれる庶民にもわかるように。木戸銭は箱に入れたので、チケット売り場のことを今でも「ボックス・オフィス」という、という俗説などもありますね。シェイクスピアの描きだす人物たちは、庶民に大ウケしました。コミカルな門番とか、「マクベス」だったらコミカルな墓掘りなんかが出てくるのは、そのためなんですよ。「ハムレット」では、お客はみんな、道化の登場を待ちわびていました。「おーい、お笑い男、出てこいよ!」と。人気の役者を出して、そう、当時の演劇界のお約束をやる。決まって悪趣味と低俗なシーンが出てくる。でも、シェイクスピアは役者のために書いているのではなかった。観にきてくれるお客さんのために書いていた。貴族向けにも書きましたが、ブルジョワジーはブルジョワな面を好み、プレブス(平民)は俗っぽいものを好んだのです。
シェイクスピア劇は「美しく」はありません。人は彼の美しいモノローグばかり諳んじますが、それは特定のキャラクターに限られたセリフなんです。シェイクスピアはスタイルの豊かなメランジェ(混交)で、だからこそ、人々は今でも彼の芝居に足を運ぶし、大いに魅了されるのだと思います。それぞれのキャラクターは多元的で、その物語は無限に解釈が可能です。この人の解釈、あの人の解釈がある。だから、何度も観て展開がわかっていても、このキャストなら、この演出家ならと言ってまた劇場に出向いていくでしょう。ときには呆れた演出もあるでしょうし、うべないがたい舞台もあるでしょう。以前は理解できなかったけれど、その舞台を観たら初めて理解できた、ということもあるはずです。
わたしも二年ほど前、「リア王」の舞台を観たとき、それまで見えていなかったものが見えて膝を打ったことがあります。リア王の演じ方よりも、ほかのキャラクターの演じ方に発見があった。この劇作の意味をより高めるような演出と演技でした。シェイクスピアには、人間の本質に対する無数の解釈と理解がある、だから、今も魅力が褪せないのです。
マーガレット・アトウッド Margaret Atwood
カナダを代表する作家・詩人。その著作は小説、詩集、評論、児童書、ノンフィクションなど多岐にわたって60点以上にのぼり、世界35か国以上で翻訳されている。1939年カナダのオタワ生まれ。トロント大学、ハーバード大学大学院で英文学を学んだ後、カナダ各地の大学で教鞭を執る。1966年に詩集「The Circle Game」でデビューし、カナダ総督文学賞を受賞。1985年に発表した『侍女の物語』は世界的ベストセラーとなり、アーサー・C・クラーク賞と二度目のカナダ総督文学賞を受賞。1996年に『またの名をグレイス』でギラー賞、2000年には『昏き目の暗殺者』でブッカー賞、ハメット賞を受賞。2016年に詩人としてストルガ詩の夕べ金冠賞を受賞。そして2019年、「The Testaments」で2度目のブッカー賞を受賞した。トロント在住。
鴻巣友季子(こうのす・ゆきこ)
翻訳家・文芸評論家。1963年東京生まれ。訳書『恥辱』『イエスの幼子時代』『イエスの学校時代』J・M・クッツェー、『昏き目の暗殺者』『ペネロピアド』M・アトウッド、『嵐が丘』E・ブロンテ、『風と共に去りぬ』M・ミッチェル、「灯台へ」V・ウルフなど多数。編書に『ポケットマスターピース09 E・A・ポー』(共編、集英社文庫ヘリテージシリーズ)など。『全身翻訳家』『翻訳ってなんだろう?』『謎とき「風と共に去りぬ」』ほか、翻訳に関する著作も多数。
作品情報はこちらから
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
