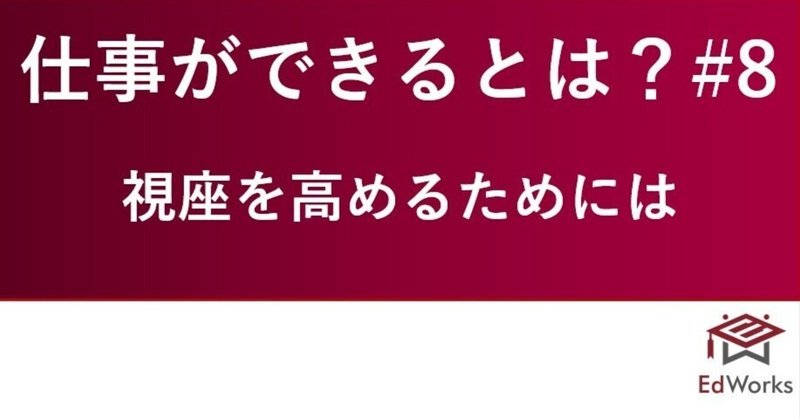
仕事ができるとは?#8 視座が高いとは
視座が高い人材が育たないといった相談を受けるケースが多くあります。
視座が低いため、部門全体・会社全体で仕事を考えることができない、経営計画達成のために各部門・自分がすべきことが判断できないというのです。
これは一般社員に限った話ではなく、管理職以上、時には部長職クラスでも同様の話が出てきます。
皆さんは「視座が高い」人はどういう人だと思いますか?
また、「視座を高める」ためには何ができると思いますか?
視座が高い人とは?
視座が高い人の定義は人によって多少異なりますが、おおむね次の2点は共通項だと思われます。
・部分ではなく全体を見られる
・人とは違う視点や相手の立場から見られる
具体的な話を通して、視座の高さについて考えてみたいと思います。
まずは日常の場面から見てみます。
駅を歩いていると後ろから大急ぎで走ってくる人がいて、とっさに横に避けました。こんな人混みを走っては危ないじゃないかと誰もが思います。普通はここでイライラして終わりですが、視座が高い人であれば「それほどまでに急ぐ理由が何かあったのだろうか」と相手の立場からものを見ることができます。(これはアンガーマネジメントにもつながる話です)
イメージにすると、他者と自分の壁を乗り越えて、相手側の意向を推察する力と言えます。

次はビジネス場面で考えてみます。
会社の方針で経費削減のため、出張をできるだけ控えるようにという指令が出ました。営業部に所属する自分としては、営業に関連する出張は認めるべきだと内心反発をしています。そんな中、営業部長がミーティングの中で出張は極力行わないようにと、会社の意向に即した発言をしました。「部長も結局会社の言いなりか・・・」と思ってしまいます。しかし、視座が高い人は「部長も内心反発をしているだろうに、部長という肩書を持つ以上、部下の面前では会社批判ができないのかな」と思いを馳せることができます。もしかしたら、水面下で経営層と営業部の出張緩和の調整をしている可能性もあります。
これも同じくイメージにすると、文字通り自分の職位より上の立場に立って考えることができる、まさに視座が高い人の特徴です。

では、視座が高いとはどういう能力が高い人のことを言うのでしょうか。
私はこれを二つの言葉で表しています。
一つが「鳥の目、虫の目、魚の目」、もう一つが「メタ認知能力」です。
「鳥の目、虫の目、魚の目」
「鳥の目、虫の目、魚の目」を聞いたことはあるでしょうか。
鳥のように、高い視点からものを見られる。虫のように近づいて様々な角度からものを見られる。魚のようにものごとの流れを見られることです。
魚の目は理解が難しいと言われますので補足します。物事には流れがあります。先ほどの例で言うと、なぜ会社がこのタイミングで出張を控えるように指示を出したのか、それは会社が中期経営計画(中計)達成の最終年度となり、利益率を中計目標に合わせてどうしても達成させたい、そして次に立てる中計につなげたいという考えがあるからかもしれません。目の前の事象を見るだけではなく、大きな流れで見ると、違った見方を獲得することができます。
メタ認知能力
もう一つがメタ認知能力です。鳥の目、虫の目、魚の目を学術用語で言い換えると、それはメタ認知能力の高さです。
メタ認知能力とは「認知に対する認知」です。平たく言えば、客観的に見られるということです。
自分がいま怒っているという感情を客観的に認知する、自分が置かれている立場を認知するなどです。
メタ認知能力が高い人は物事を抽象的に考えたり、全く異なる事象から共通点を見つけたりすることができます。営業の経験しかないのに、バックオフィスの改革プロジェクトを率いて成果を出せたりします。営業での経験からバックオフィスでも活用できる共通項を探し、適用することができます。例え(メタファー)が上手な人も同じことが言えます。
メタ認知能力の高さが及ぼすプラスの影響はこれだけに留まりません。下記の図のように、メタ認知能力が高いと、たくさんのタスクの中での重要度や緊急度を見極めることができ、優先順位付けがうまくなります。その中で、リスク要因に気づくことができるため、リスク管理能力にも長けてきます。

視座を上げるためには
それでは視座を上げるためにはどのようなことができるでしょうか。
ここでは、普段からできることを書いてみます。
一つは「自分と異なる考えに出合った時に、その人の視点からものを考えてみること」です。
世の中には賛否両論のテーマであふれています。「消費税を減税すべきか、増税すべきか」、「電車・バスの優先席はどんな時も座らない方が良いか、空いていたら座っても良いか」。このように相反する意見が存在する中で、あえて自分と異なる意見の根拠を考えてみることも視座を上げる訓練となります。
もう一つは、誰かに言われて気づいた新しい視点を書き留めることです。仕事をする上で、上司や先輩から指摘をされて、ハッとなった経験は多くの人がお持ちと思います。そのような時に、なぜハッとさせられたのか、その上司や先輩は自分と違ってどのような視点を持っていたのかを考えることです。
もしかしたら、自分は目の前の仕事ばかり見ていて、大局を見られていなかった、など気づいたことを書き出してみることです。これは少し精神的にもパワーが必要な作業ですが、後々上司や先輩の視点を自分のものにできる重要なことです。
もし、自分にはハッとさせられた経験がないという場合は要注意です。自分の考えに凝り固まっている可能性があるため、一つ目のあえて別の視点から考えてみる訓練をしてみると、新たな視点、より高次の視点からものを見る目を養うことができるでしょう。
よく言われることですが、SNSはそういう意味で視点を養う場としてはあまり向いていません。なぜなら自分の「スキ」を理解したアルゴリズムに則った投稿ばかりが出てくるため、視点を広げるチャンスがなかなか巡ってきません。
自分と反対の意見に耳を貸すことは精神的に疲れることもありますが、一旦感情は置いてそのような視点に触れて、分析をすることで、視座を高めること可能となります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
