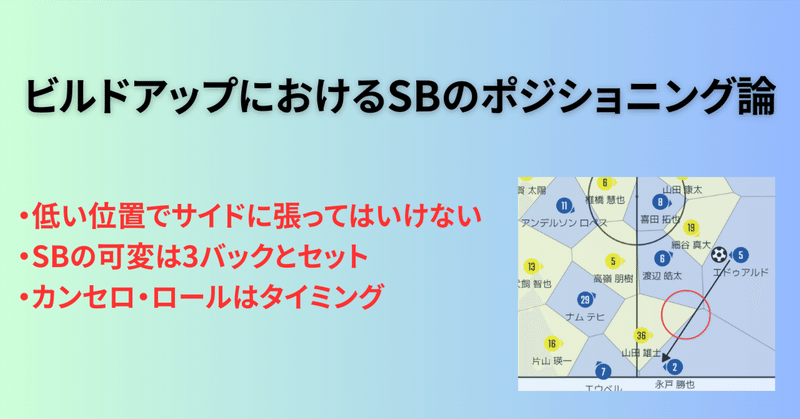
ビルドアップにおけるSBのポジショニング論
近年のサッカーでは一般的にボール被保持、特にミドル・ハイプレスの戦術が発展し、ボール保持に対して有利になっていると感じる。まず中央を閉じることでサイドに誘導し、相手がサイドにボールを移動させたら近くの相手選手やスペースを潰して、サイドでボールを奪う同サイド圧縮の強度や練度の高いチームが多い。それは欧州のみならずPSG戦のセレッソ大阪は素晴らしくJリーグにおいても顕著である。この潮流でポゼッションする際に重要なのはSBのポジショニングだ。本記事では結論として「SBはビルドアップにおいて低い位置でサイドに張ってはいけない」と主張する。ただ、それは相手が同サイド圧縮を行ってる場合で、WGやSHが外切りプレスをしてくる場合は除く。
SBの種類
・外張りSB:ビルドアップにおいて低い位置でサイドに張るSB
・幅取りSB:高い位置に上がり、幅を取る役割のSB
・カンセロ・ロール:ハーフスペースへ移動しIH化するSB
・ルイス・ロール:相手CFの背後へ移動しCH化するSB
・柏レイソル対横浜Fマリノスの実例
まず柏対横浜FMでの横浜FMビルドアップを参考に、低い位置でサイドに張るSBに起こる問題を紹介。マリノスの問題点について述べますが、マリノスを批判したいわけではなく、多くのチームが同じ問題を抱えている中で、問題がわかりやすかったため実例として使わせていただきます。

横浜FMは442ゾーンで守る柏に対して442でビルドアップ。CBがボールを持った時にSBが低い位置でサイドで張っていると、CBからSBへの距離が遠くなる。これによって起こる問題は、①相手SHにパスをインターセプトされるリスク、②SBへボールが届く時点で相手SHは距離を詰めれる。このような二つのリスクがある。

特にCB目線になるとビルドアップにおいてインターセプトされるリスクのパスは出したくない。するとSBへのパスを躊躇い、CB同士のパスが多くなる。するとボールを左右に動かせないため、柏の4+4ブロックを左右に揺さぶることができない。

その結果、柏守備ブロックが広がっていないにも関わらず、中央へのパスを出すしかなくなり、中央を固めている柏のCHやCBにボールを奪われてしまう。

そしてSBは低い位置でサイドに張っているため、CBとSBの間にはスペースがある。中央でボールを奪われるとそのスペースを使ってカウンターを打たれてしまう。この時にSBのプレスバックが間に合えば良いのだが、間に合わずCBが追撃したりCHがプレスバックすると、クロスに対して中央の守りが薄くなってしまう。
このような外張りSBによるビルドアップと被カウンター時での問題が、この試合に多く見られ、ハイライトにも残っている。
このオフサイドで取り消された椎橋のゴールや、その後のM・サヴィオのシュートシーンはまさにだ。CB同士のパスが多く、狭い中央へ配球し、ボールロスト、CBとSBの間をカウンターで使われる。ぜひ動画で見ていただきたい。

また横浜FMはSHが内側に入りSBが高い位置で幅を取る幅取りSBを選手が臨機応変に行う。しかしこの時にCBとSBの距離が遠くなり、外張りSBよりもよりリスクが高くなる。
この79分の武藤の決定機に繋がった柏のカウンターがまさにそうだ。エドゥアルドがボールを持った時に、エウベルが内側に入り吉尾が高い位置で幅を取っている。しかしエドゥアルドから吉尾へのパスコースが繋がっておらず、エドゥアルドは浮き球を選択する。しかし浮き球が成功する確率は低く、ヘディングでクリアされ柏ボールに。そして吉尾の裏を使われてカウンターを打たれてしまった。
ここではハイライトに残っているシーンを実例としたが、フルタイムで見ていただければ、ここで説明した問題が数多く見られるのでぜひ。
・ビルドアップにおけるSBのベストポジション
内側SBのメリット
ではビルドアップにおいてSBのベストなポジショニングはどこであろうか。結論の前に、前述した、外張りSB・幅取りSBそしてルイス・ロールの問題点を可視化する取り組みとして、ボロノイ図を使ってみたい。
ボロノイ図とは、各点(選手)に最も近いスペースを示している。

これは永戸が外張りSBをやっている場面。エドゥアルドから永戸へのパスコースの間に、エドゥアルドや永戸よりも山田の方が近い地点があることがわかる。もちろんこのボロノイ図には時間の概念がないため実際の選手のプレー範囲と一致はしないが、CBがSBにパスを出そうとした時に怖く感じるのがわかるだろう。

そしてこれは永戸が幅取りSBをやっている場面。この場合は山田のゾーンがより広くパスコースと被っており、インターセプトされる確率は特に高いと言えるだろう。

これはSBが内側に入ってボランチ化するルイス・ロールをしている場面。これも幅取りSBと同じ現象なのがわかる。
ではCBがインターセプトされるリスクを感じずにサイドへ配球できるSBのポジショニングはどこであろうか。

それが上の図だ。SBがタッチラインから数m内側に入るだけで、CBからSBへのパスコース上に山田ゾーンが被ることはない。これによってサイドへ配球する際の問題が解決される。一方で永戸からエウベルへのパスコース上に山田ゾーンが被っている。しかし守備の優先順位は中であるからして、ここまで外側のパスカットを狙うことはあまりない。
このようにSBが数メートル内側に入るだけでDFラインでのボール回しはスムーズになる。またSBとSHへの関係性にもメリットがある。
中央への楔のパスは角度をつけて斜めに入れると、受け手はゴールに対して半身を作って前を向けるため、斜めのパスが有効だと言われる。そしてこれはSHへのパスについても同じことが言える。
外張りSBが幅を取っているSHヘパスを出すと、SHはゴールに対して半身を作ることができず、後ろから相手SBに当たられてしまう。しかし内側のSBからSHへ斜めにパスを出すことでSHは前向きで相手SBへ勝負できる。自分が部活でSHをやっていた時は、この後ろ向きでボールを受けるのが嫌でしかたなかった。
この他にもSBがGKへボールを戻してやり直す際にも、GKへの距離が近くバックパスをしやすくなるなどメリットがある。一方でデメリットとしては、相手SHに近いポジショニングとなるため、ボールを素早く扱う高い技術が必要になる。
内側SBの原則
では内側のSBはどのような基準でポジショニングすれば良いのだろうか。

それが上の図だ。SBの原則は二つ。①SBはCBとSHへの距離が同じになる位置。②その中でSHにパスを出せるギリギリの高さ。図の黒い線はCBとSHから等距離にある点の集まりだ。従ってこの線上が①の原則だ。そしてこの線上でも高い位置だとSHへのパスコースがなく、低い位置だとSHへ斜めのパスが出せない。従ってSHへパスを出せるギリギリの高さが②の原則だ。この原則ではSBはCBのポジショニングによって左右される。そのためCBのポジショニングの原則も補足として示しておいた。
ブライトンのSBはこの原則に近いものとなっている。しかし若干の問題がある。特にエストゥピニャン。

ブライトンのSBが外張りSBをすることはほぼない。しかし逆に内側に入りすぎてしまうことがある。それが上の図だ。SBが内側すぎるためSHへのパスを相手SHにインターセプトされるリスクがり、ボールの移動中にSHは相手SBのプレッシャーを受けてしまう。
このように内側SBは非常に繊細で難しいポジショニングだ。しかしこれができているチームや場面では、スムーズにCBからSHへとボールが動く。それはつまり相手守備ブロックを左右に揺さぶることができ、中央のスペースを生むことにもなる。ポゼッションサッカーをやる上で非常に重要な概念だ。
・SBによる可変における原則
ここからは、幅取りSB、ルイス・ロール、カンセロロールを行う時の原則について。このようなSBを行うとCBからSBやSHへの距離が遠くなり問題が生じると述べてきたが、これらを解決する原則を紹介。
まずルイス・ロールのポイント。

SBがCH化するルイス・ロールだが、最終的なチームの陣形は幅取りSBと同じになり、問題点も同じだ。

これは幅取りSBの場合。柏対マリノスの実例ではSBが高い位置に移動するものの、DFラインの残り3枚がポジショニングを修正しないため問題が起きていた。しかし上のように残り3枚が横にスライドして3バックを形成すれば、左CBは右CBとSBへの距離が等距離になる。
これはルイス・ロールについても同じ。SBが定位置を離れCHやSHになる場合、DFラインはスライドして3バックを形成することがセットとなる。川崎の山根がルイス・ロールする時やマリノスの永戸が幅取りSBをする時はそれができていない。
カンセロ・ロールに関しては事情が少し異なる。もちろんカンセロ・ロールもSBがハーフスペースへ移動し終わった後は、DFラインがスライドする必要がある。しかしカンセロ・ロールは移動中にメリットがある。

SBがカンセロ・ロールとしてハーフスペースへ移動際に、相手SHはその動きにつられて一瞬内側に入る。かつ相手SBもハーフスペースへ進入してくるSBを警戒して内側へ。この時CBからSHへの距離は遠いのだが、インターセプトされるリスクは低く、速いパスを送ることでSHは相手SBへ前向きで勝負できる。このSBの移動中にCBがSHへパスを出せるかが鍵となる。逆に言えばCBがSHへパスを出せるタイミングでSBが移動できればベストだ。
もし相手SHもSBもカンセロ・ロールのSBを警戒しなければ、そのSBへパスを出せば良い。
・まとめ
このようにビルドアップにおいてSBは低い位置でサイドに張ってはならず、記事内で紹介した原則に従って内側にポジショニングする方が良い。また定位置を離れて幅取りSBやルイス・ロールをやる場合は、残りのDF3枚のスライドがセットとなる。もちろん内側SBに関してはセンスも必要になるだろうし、難しいことは変わりない。しかしこれをやらなければ、ポゼッションは上手くいかない。
そしてこの記事で紹介した理論の9割以上は、Leo the footballさんのYouTubeや著書『蹴球学』で記されているものです。SBのポジショニング以外にも様々な原則が紹介されており、合計2万部の印刷が決定しておりますのでぜひ。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
