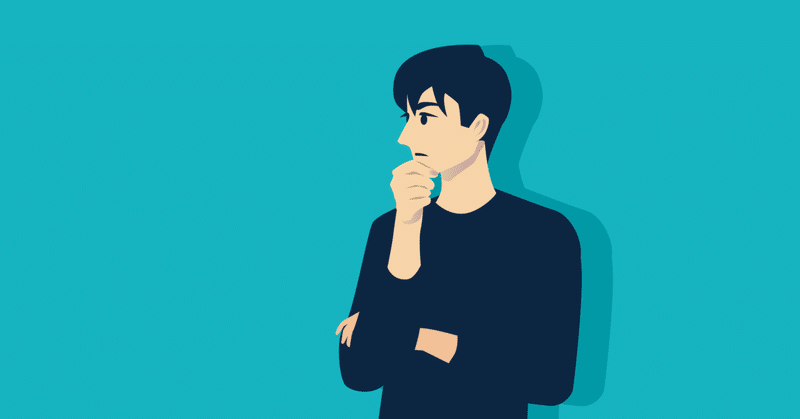
外務省から国際機関に転職した理由
私は日本の大学を卒業後、外務省に入省し、南米とアフリカの日本大使館での勤務も含めて約14年間勤務しました。
その後外務省から国際機関に転職し、現在はとある国際機関で国際公務員として勤務しています。
今回は、両者の違いに言及しつつ、外務省から国際機関に転職した理由について5点記載したいと思います。
外務省や国際機関での勤務にご関心のある方々の参考となると幸いです。
また、以前、外務省での経験や若手職員の勤務の様子等についてのkindle本を執筆しました。
Amazonのkindle unlimitedに加入されていれば無料で読むことができますので、是非お読みいただけるととても嬉しいです♪
Amazon.co.jp: グローバルキャリアの扉を開ける: 若手外交官から国連職員への冒険と挑戦 eBook : Shuto: Kindleストア
1 学生時代からの憧れの職業
私は大学生時代に観光でニューヨークの国連本部を訪問して、日本人職員の案内によるツアーに参加し、世界の現状についての説明を受けたことで、国際機関での勤務に憧れを抱くようになりました。
その後、貧困や開発学関連の書籍の読書や大学の授業を受講していくうちに、国際機関で勤務したいという想いがどんどん強くなっていきました。
一方で、大学生当時、国際機関での勤務のためにほぼ必須と言える修士号の取得や英語+他の国連公用語の習得にハードルを高く感じていておりました。
このため、ODA等を通じて国際協力に携わっている日本政府での勤務を目指すようになり、新卒で外務省に入省しました。
しかし、海外の日本大使館で勤務して、国際経験を積んで語学力の向上や実務経験を積んだことに加えて、様々な国際機関職員と一緒に仕事する機会があったことや、開発協力事業に携わったことで、国際機関で人道・開発協力に携わりたいとの想いが蘇ってきました。
そして、色々と熟考した結果、JPOという形で国際機関で勤務する機会をいただけたこともあり、学生時代の憧れの仕事に就くことを決断しました。
2 開発協力事業の現場により近い立場
私がアフリカにある日本大使館で勤務した際には、開発協力関連業務を担当し、JICAや赴任国の政府機関、他のドナーや国際機関などと一緒に働きました。
国際機関との関係では、ユニセフや世界食糧計画(WFP)などに日本政府の資金協力を行った連携プロジェクトなどにも携わりました。
しかし、大使館で勤務して感じたことは、プロジェクトの現場や裨益者から遠いということです。
また、日本の税金を使用するということもあり、開発協力事業も日本の国益に資する形、例えば(少し費用が高くなる)日本企業を通じたインフラ事業や日本の比較優位が活かせるような分野での事業が多く、必ずしも相手国の優先事項に即した形ではない事業もありました。
日本政府は「ドナー」であり、プロジェクトの実施者ではないため、どうしてもプロジェクトの現場から遠くなってしまいます。
プロジェクトを実際に実施するのは国際機関(IOM等の国際機関は自らプロジェクトを実施)や民間企業(インフラ整備等の事業では民間企業が建設を行う)、NGO(国際機関から委託される形でプロジェクトを実施)などであり、ドナーは赴任国政府との交渉や資金供与、プロジェクトの進捗状況の確認、完成時に式典に参加する等で、現場でのプロジェクトの実施にはほとんど関与しません。
人道支援・開発協力に関心を有していた私としては、ドナーとしてではなく、プロジェクトの計画・立案・実施に携わりたいと考え、現場と政府の両方に近い国際機関での勤務を目指すようになりました。
なお、国際機関転職後の私の仕事の現状としては、フィールドから少し離れた首都のカントリーオフィスで勤務していることもあり、思い描いていたほど現場に近くありませんが、それでも出張などを通じて現場を訪問する機会は時々あり、大使館で勤務していた頃と比べると現場の近さ、ニーズや問題の理解度は増しました。
今後は、現在よりもフィールドに近い立場からプロジェクトの計画立案・実施に参加していきたいと考えています。
3 より多様性のある職場
大使館で勤務していた時に感じたことは、入省以前に想像していたよりもずっとドメスティックな職場ということでした。
大使館の同僚は、現地職員以外は上司も含めて全員日本人で、普段やりとりをすることが多いのは本省の同僚です。仕事を進める際に決裁を仰ぐ上司も日本人ということもあり、普段のメールでのやりとりや報告書等の作成の大半は日本語での勤務となります。
新聞の読み込みや現地政府とのやりとりこそ現地の公用語を使用し、他国の大使館員等の外国人と会うときは英語を使用することになりますが、体感的に日本語と外国語の使用は7:3くらいの割合でした。
このため、どうしても日本的な仕事の進め方が多く、せっかく外国で勤務しているのにもかかわらず、国際的な仕事をしているという実感はあまりありませんでした。
(週末こそ日本人との付き合いを断って外国人とのみ付き合うようにしていましたが・・・。)
一方で、国際機関での勤務は、想像していたとおり大変多様性のある職場です。
私の事務所では日本人は私しかおらず、上司はカナダ人、スイス人、ブラジル人で、ナショナルスタッフの他に15~20か国程の国籍から成り、文化や考え方、バックグラウンドも異なる同僚に囲まれています。
このような多様性に富んだ職場は、国際機関ならではの環境であり、色々と学ぶことも大変多いです。
外務省で同じ国籍と似たような考え方を持つ同僚と共に仕事を行ってきたことで、徐々に視野が狭まってしまうことを懸念していたこともあり、多様性に富んだ環境で仕事をすることができて大変満足しています。
4 新たなスキルの獲得や視野を広げる
外務省で10年以上勤務して外務省での仕事に慣れていたこともあり、コンフォートゾーンから出て、全く異なる環境で、新たなスキルや専門性、視野を広げたいと考えておりました。
外務省で勤務していると、仕事を通じて様々な分野を広く浅く学ぶことができましたが、人事異動などもあり、どうしても特定の分野に関する専門性を深めることが難しいと感じておりました(もちろん、外務省内には特定の分野の専門性に特化した専門官という方もたくさんいらっしゃいます。
また、自分の専門言語こそ使う頻度はそれなりにありましたが、英語力の向上にも限界を感じていたところでした。国際的な仕事をするためには共通言語である英語力の向上が不可欠であり、そのためには毎日英語で仕事をする環境が重要であると考えています。
国際機関に転職した後、未だ特段のスキルや専門性を深められているわけではありませんが、専門性を深めていきたい特定の分野がなんとなく見えてきたのも事実です。
今後は、外務省時代に培ったスキルや経験を活かしつつ、特定の専門性を深めて、ユニークな職員として活躍・貢献していきたいと考えています。
5 日本の仕事のやり方に窮屈に感じた
最後に、日本での仕事のやり方に窮屈さを感じていたことも転職の理由の一つです。
外務省では個々人や大使館にマンデート(裁量権)があまりなく、意思決定は決裁書と作成してボトムアップで相談していくか、本省からの承認を得て行動をする必要があります。
このため、迅速な行動がしづらく、また各職員が自ら判断して意思決定を行いにくい環境にあります。
一方で、国際機関では国事務所に大きなマンデートがあり、また各職員の判断で決められる裁量が多くあります。
日本のようにわざわざ決裁書を作成して意思決定をする必要もなく、必要なことは上司と直接話すかメールでのやりとりのみで十分です。このため、書類作成に割く時間を省くことができ、より効率的に思います。
例えば、JPOというジュニアなポジションである私であっても、事務所を代表して国連機関間の会合に参加し、とある基金からの資金の獲得・割り当てに関する交渉に参加し、自分の判断に基づいて発言し、合意に達しました。
外務省であれば事前に対応ぶりをすり合わせた上で、その対処方針の範囲内でのみ行動・発言できますが、国際機関では合意内容を事後的に上司に報告するのみでした。
若手であっても一人のプロフェッショナルとして扱われ、より多くの裁量を与えられる国際機関の方がやりやすいと感じています。
最後に
以上のように私が外務省という安定した職場から不安定な国際機関に転職した理由について5点記載しました。
転職後、色々と悩みを抱えることもありましたし、本当に転職して良かったのかと自問自答することもありました。
未だ転職して本当に良かったと心底思えるか微妙なところですが、転職という決断を正解にできるかについては今後の自分の努力にかかっているかと思います。
現時点では国際機関でのびのび?と仕事ができていますので、今後は自分の専門性を深めて、今の機関で活躍し、様々な人々の生活により多くのインパクトを与えられるように努めていきたいと思います。
今回の記事が少しでも皆様の参考になると幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。カニマンボ!
ここから先は

アフリカにある某国連機関のカントリーオフィスで勤務する新米国連職員の体験談です。 外務省で14年勤務、南米とアフリカの大使館で勤務した後に…

外交官体験談
私は8年以上の在外勤務を含め約14年間、外務省で勤務しました。 大使館や外務省での勤務を踏まえて、外交官とはどのような職業か、日々どのよ…
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
