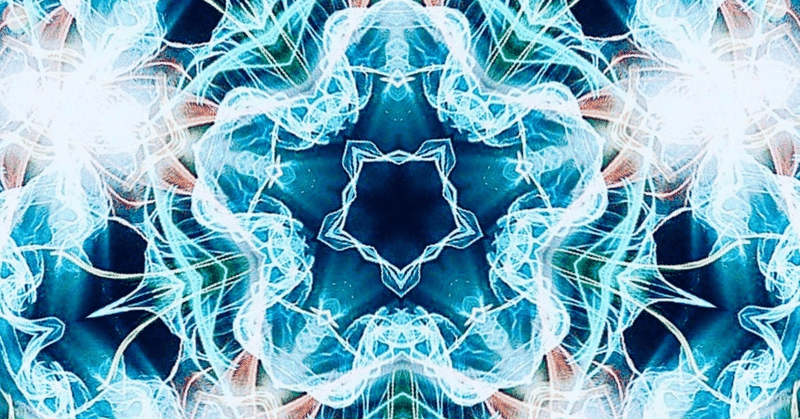
世界=経済の拡大の限界と、今後の世界
この記事は、以下の書物に対する注釈、あるいは読書ノートである。
・柄谷行人『世界史の構造』(岩波書店)
・柄谷行人『帝国の構造』(青土社)
ポール・ヴィリリオは、どこかで、「大航海時代以来の西欧の帝国主義の拡大は、1969年のアメリカの月着陸と、60年代末までのベトナム戦争での敗北で、その極限に達した」というような趣旨のことを述べていたと思う。
この言い方を少し変えてみると、西ヨーロッパに発する16世紀以降の世界=経済(ブローデル)(ウォーラーステイン流に言えば「近代世界システム」)の拡大は、1960年代末までに、その終着点に達したということである。
この、世界=経済の自己拡大する運動が限界に突き当たったという事態は、それまでに世界=経済(近代世界システム)で生じてきた様々な反復的事象にも影響を与える。
例えば、世界=経済が順調に拡大していく過程においては、ヘゲモニー国家の交代(すなわち、世界=経済の中心となる都市の交代)が生じる。それは、ジェノバ、オランダ、イギリス、アメリカと続いてきた。
しかし、世界=経済の拡大が行き詰った現在、このような反復的事象が生じにくい状態となっている。
すなわち、世界=経済が順調に拡大していく過程においては、世界=経済に内在的な運動法則が完全に支配するような事態が生じる。つまり、この場合は、ヘゲモニー国家の(順調な)交代である。
しかし、世界=経済の拡大が外生的要因により行き詰った場合、世界=経済に内在的な運動法則は、(この外生的要因により)貫徹されなくなる。このため、ヘゲモニー国家の順調な(これは、16世紀以来の歴史が示すように戦争という状況も含む)交代が生じない可能性がありうる。
アメリカの次のヘゲモニー国家は、中国かインドではないかと考えられているが、世界=経済に内在的な運動法則が貫徹されないような、現在の状況では、そもそも、ヘゲモニー国家の交代が生じるか、あるいは、より根本的に、ヘゲモニー国家が出現するのか、といったことが疑わしくなる。
現在の中華人民共和国が次の(2050年代以降の)ヘゲモニー国家になるような状況は、今現在(2022年)の状況では、なかなか想像しにくいし、インドにいたっては、もっとそうである。すなわち、今後の世界=経済においては、従来のようなヘゲモニー国家が出現しない可能性がある。
これは、近代世界システムが始まって以来、はじめての出来事であり、例えば、近代世界システムの出現や、産業資本主義経済の成立、世界=経済が19世紀初頭において世界=帝国を超える力を持ったこと、などの事象群と同じような、歴史の変曲点、歴史上の大きな変化の局面であるといえる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
