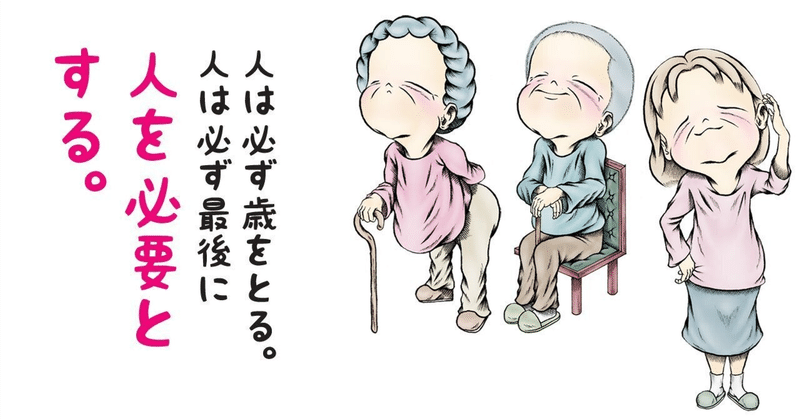
日本の高齢社会に展望はあるのか
織田信長が『敦盛』の「人間五十年 下天の内をくらぶれば 夢幻の如くなり」という幸若舞を好んだという話は有名だ。信長が本能寺で明智光秀に討たれたのは享年49歳だった。多くの部下を従えて強大な権力を持っていた信長ですら、この世は夢幻のようであり、すぐに形を変えて行くものだと感じていたのだろうか。
豊臣秀吉は62歳、徳川家康は75歳まで生きた。戦国武将の中には100歳を超えた人もいたようだが、戦国時代に生きた人たちの平均寿命は40歳に届かなかったようだ。庶民の暮らしは貧しく、乳幼児死亡率も極めて高かったことが想像できる。また、飢饉、疫病の流行、戦乱などが一般的であった当時において、寿命が著しく短かったことは容易に推測できる。
徳川家康の全国統一により、250年もの太平の世が続いた江戸時代は、戦国時代に比べて人々の暮らしははるかに安定的に営まれるようになった。18世紀以降、社会全体の生産力が上がり、医療の恩恵にあずかる層が広がると、長寿の可能性は、身分・階層・地域・性別の格差を超えて拡大し、命の危険に晒されやすい乳幼児期を生き延び、二十歳(はたち)まで生き延びた人たちは60歳以上の余命をもてるようになった。
江戸時代、日本では老いによる身体や認知機能の低下を「老耄(ろうもう)」と表現していた。「耄」とは今ではなかなか見かけない言葉だが、辞書を開いてみるとそこには「耄:おいぼれる」と記されている。「おいぼれる」という言葉は、現在では年齢に伴う様々な変化をネガティブに表現する際に用いられる。いずれにしても、老いと折り合いをつけながら長く生き延びる人々が増えたことは、親や祖父母の老いの年代を長期にわたって支える家族が増えることになった。
横井也有(やゆう)は尾張藩の武士で寺社奉行や用人などの要職を歴任し、藩主側近として重用されたが、病気を理由に50代前半で辞職。その後、別宅「知雨亭」で隠居生活を始めた。天明3(1783)年に天寿をまっとうするまで、俳句や和歌、漢詩など創作活動や琵琶演奏にいそしんだ。江戸時代の根岸鎮衛作の雑談集「耳薬 (みみぶくろ)」(1814年)の中に、横井世有作「老人へ教訓の歌」が収録されている。
皺はよるほくろはできる背はかゞむあたまははげる毛は白うなる
これ人の見ぐるしきを知るべし
手は震ふ足はよろつく齒はぬける耳は聞えず目はうとくなる
これ人の數ならぬを知るべし
よだたらす目しるはたえず鼻たらすとりはずしては小便もする
これ人のむさがる所を恥づべし
又しても同じ噂に孫じまん達者じまんに若きしやれ言
これ人のかたはらいたく聞きにくきを知るべし
くどうなる氣短になる愚痴になる思ひつく事皆古うなる
これ人のあざけるを知るべし
身にそふは頭巾襟巻杖眼鏡たんぽ温石しゆびん孫の手
かゝる身の上をも辨へずして
聞きたがる死にともながる淋しがる出しやばりたがる世話やきたがる
これを常に姿見として、己れが老いたるほどをかへり見たしなみてよ
ろし
しからば何をかくるしからずとしてゆるすぞと いはく、宵寢朝寢昼
寢物ぐさ物わすれそれこそよけれ世にたらぬ身は
簡単に言えば、「老耄」は不可避的現象なので逆らわず自然体でふるまうようにと横井也有は諭している。
私が好きな映画に藤沢周平原作で山田洋次監督による作品『たそがれ清兵衛』がある。原作と違って映画では、老母の介護のシーンが描かれる。主人公の井口清兵衛は妻を長い闘病の上に亡くし、残された2人の幼い娘と耄碌の進んだ老母の世話をするために、夕刻に城勤めを終えると家路へと急ぐ。清兵衛は母の耄碌の進行も老いの自然な姿と受け入れ、虫籠づくりの内職のかたわら、娘たちの手習いの話に聞き入り、母にいたわりの声をかける。映画『たそがれ清兵衛』が公開された2002年は高齢化社会から高齢社会へと転じる時期だった。日本社会には親の老いをいかにして支えるのかが深刻な問題となって迫っていた。仕事を終えると同僚からの誘いを断り、まっすぐ家に帰る清兵衛は同僚たちから「たそがれどん」と揶揄されていたが、それを気にすることもなく、家長として子どもたちの養育の責任と親の老いを看取る責務を実直に日々を暮らす姿は、貧しさはあれど美しくみえた。なぜなら、今の日本は、家族が親の介護をする、家族が親を看取る、そんな社会ではなくなってしまっている。家族に時間的にも精神的にも年老いた親を介護する余裕がなく、高齢者介護施設に頼らざるを得ない状況にあるからだ。
日本の社会は、子ども人口がどんどん減少し、高齢者人口が増加した逆三角形のピラミッド状態になっている。我が国はこれからどうなっていくのだろうか。厚生労働省によると、日本の生産年齢人口は2017年の6,530万人に対し、2025年の時点で6,082万人、さらに、2040年にはわずか5,245万人にまで減少するとみられている。こうした予測のベースにあるのが、日本の長年にわたる出生率低下と、その結果としての人口の高齢化だ。税収と労働人口が減少し、膨張する医療費を高齢者にも負担させる事態に直面することになりそうだ。日本はこの先どうなっていくのだろうか。子どもたちの未来はどうなっていくのだろうか。
私の記事を読んでくださり、心から感謝申し上げます。とても励みになります。いただいたサポートは私の創作活動の一助として大切に使わせていただくつもりです。 これからも応援よろしくお願いいたします。
