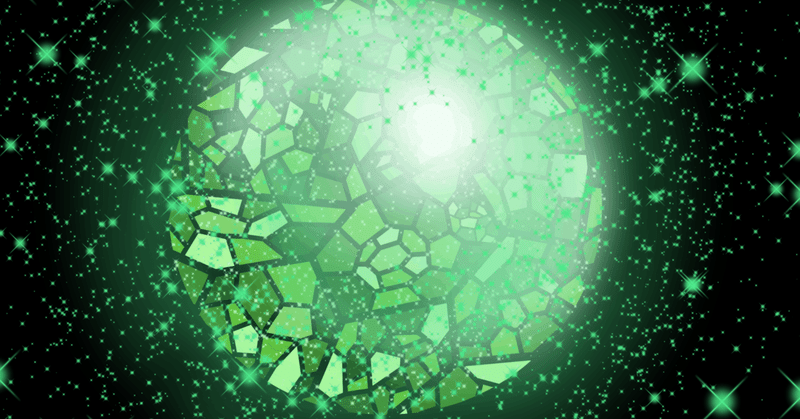
こころを育む衣服~「服育」~
ここ数年、ナゴヤ学生服販売の店長さんにご案内いただき、教育関係者対象の「服育発表会」に参加してきた。「服育」とは、「食育」が食のあり方を再認識させる教育であるのと同様、衣服を通して子どもたちの豊かな心と健やかな体を育む取り組みのことである。
服育の目指すポイントとしては、次の4点に集約され、すでに小中学校や高等学校において、衣服を通した総合学習として実践されている。服育とは私達の暮らしになくてはならない衣服の大切さやその力について理解し、私達の暮らしに活かす力を養う取り組みだ。衣服は生活を支える三要素「衣食住」の一つでありながら、おしゃれの観点から語られることが多く、私達の生活を支える様々な役割を担っているものであると意識されることは少ないのではないだろうか。服育では健康、安全、人とのコミュニケーションはもちろん、環境や海外とのつながりなど衣服の様々な役割や可能性について学び、その力を生活の中にいかすことのできる「生きる力」や「豊かな心」の育みを以下の4点において目指している。
① 健康・安全
「寒さや外敵から身を守る」という衣服が持つ本来の役割から、子どもた
ちがより快適にそして健康に過ごすことができる工夫を衣服から考える。元々私たちは自分を"守る"(防護性)ために衣服を身にまとうようになった。これは現代の衣生活においても大切な基本的目的である。どのようなデザイン、色、素材の服が健康や安全を考える上で有効なのか(もしくはどういったものが危険性を増すのか)、正しい知識を持ち着こなすことは自分自身を守るために大切だ。
② 社会性
社会の中で生きている私たちは、毎日様々な人々とかかわりながら生活しており、衣服の色やデザイン、着こなし方によって、多くの情報を他者に発信している。人と接する上での服装マナー、TPOに応じた着こなしなどから子どもたちの社会性を育む。
成長していくにつれ、子どもたちの社会は広がっていく。社会が広がり人との付き合いが増えていくと重要になってくるのが、他者とどのようなコミュニケーションをとるかだ。ノンバーバルコミュニケーション(非言語コミュニケーション)の一つである衣服は着ているだけで自分を伝える重要な役割を担っている。この衣服のコミュニケーション力について理解し、TPOに応じた表現力を身に付けることは社会生活を送る上で大切な力となる。
③ 国際性
国によって違う衣服の特色から、地域・気候との関わり、文化伝来の様子から国際感覚を涵養する。国や地域による服の特色を知ることは、自国はもちろん他国の文化を理解することにつながり、また、性の多様性などについて考えるきっかけにもなりえる。例えば、着物やふろしき等の日本の布文化から和文化への理解を深めることが大切だ。
④ 環境
地球環境に対する問題がクローズアップされ、国際的にも注目を集める「もったいない/MOTTAINAI」の心を持つ私たちが”衣服と人と環境”のかかわりについてもっと考え、行動していく必要がある。様々な素材で作られ、その多くがいまだ廃棄処分されている衣服は、環境について考えるきっかけとなりえる。誰もが毎日着用する衣服だからこそ、その選び方・着方・処分の仕方についての正しい知識を持つことで、気づきを行動に変えていくことができるのだ。さらに、繊維のリサイクルはもとより、繊維の生産量・消費量の変化、様々な素材、そして衣服の歴史的側面から「衣服と環境」のかかわりを考えることが大切だ。
ナゴヤ学生服さんが所属する愛知服育研究会では、制服のリサイクルをより有効に運用していくために、使用済みとなった制服を回収し、成長補正や修理体制の充実によって制服として再利用できるものは再利用している。再利用できないものは、リサイクル工場にて自動車の断熱材や手袋の材料として利用される。
環境への貢献のあり方として、商品に「カーボンフットプリント」のマークを表示する取り組みがある。カーボンフットプリントとは、直訳すると「炭素の足跡」…商品やサービスの原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクル全体を通して排出される温室効果ガスの排出量をCO₂に換算して、商品やサービスに分かりやすく表示する仕組みだ。子どもたちに身近な商品では、井村屋のあずきバーがカーボンフットプリント制度を導入している。井村屋のあずきバー(6本入り)はそのライフサイクル全体で630gのCO₂を排出しているとのことだ。
私たちは、私たち自身の生活や行動が環境保全のあり方に逆行しているということを、もっと真剣かつ早急に考えなけれなならない。
私の記事を読んでくださり、心から感謝申し上げます。とても励みになります。いただいたサポートは私の創作活動の一助として大切に使わせていただくつもりです。 これからも応援よろしくお願いいたします。
