
今すぐ役に立つ! 課題発見して成長するための10のヒント
ありがたいことに、若い子が作ったゲームを見てレビューさせていただく機会があります。
過去には採用だったり、インターンだったり、最近はイベントだったりするのですが、そんな中でアドバイスをしていく中で「毎回同じことを言っているな」と最近気づきました。
それは、僕がこれまで蓄積してきた「考え方のコツ」なのですが、総合的にまとめると「多様な視点で物事を捉える方法」ということになります。
物事を考える上で、視点を多く持っていることは武器です。
なぜかというと、この視点によって「課題発見」ができるからです。
では具体的に、どういう視点の持ち方があるのでしょうか。
10個ほど洗い出してみたので、この機会にまとめてみたいと思います。
ゲームの事例ではありますが、どんなコンテンツにも、そして「仕事の仕方」や「生き方」にすら応用できるTIPSになっています。
なぜそうなのかは、後述します。
① プロモーション方法と競合について考える
いま作っているものを「どのようにプロモーションするのか」考えるのは、思考を洗練させていく上で、よいヒントを与えてくれる視点です。
ゲームを作るとき「面白いゲームです」と宣伝することはありません。
もう少し具体的な内容に踏み込む必要が出てくるはずです。
たとえば「世界観の魅力」を伝えるべきかもしれないし、「キャラクターの魅力」を伝えるべきかもしれない。
押し出すべきは「アクションの中毒性」かもしれないし「生活におけるゲームとの新しい関わり方」かもしれない。
一度引いた目線で、プロモーション方法を考えてみましょう。
プロモーションについて考えることで、いま作っているものの「ゲーム以外の競合」が見えてきます。
それはYoutubeのミュージックビデオかもしれないし、Twitterやインスタかもしれない。今やっているテレビドラマかもしれないし、今度劇場公開される大作映画かもしれない。
競合との比較によって、足りないものが見えてきます。
そして、相手が単純に想起される分野外であるほうが、学びが得られます。
こうした思考をぐるぐると回すことが、ときにとても大切です。
スターバックスの競合はコーヒーではない、というのは良く耳にする話です。
同じように、あなたのキャリア上の競合は同僚ではないかもしれません。
大切なのは「本当の価値を見定め」「本当のライバルを見つけ」「学びを得る」という3ステップです。
② 提供すべきは「ルール」と「ツール」
ステージ制のゲームを作るとき、プレイヤーの自由度をステージの側に紐付けてしまうというデザインをよく見かけます。
そうすると、プレイヤーにできることが限られてしまい、ゲームプレイが「開発者の脳内当てゲーム」になってしまう。
提供すべきは「攻略順」ではなく「ルール」と「ツール」です。
手に入れた能力を組み合わせて、開発者の想定しない解き方をされてしまってもいい。その自由度がゲームの面白さです。
開発者の裏をかく体験や、チート感は「快楽」です。
創意工夫によって何かを生み出すことができるというのは、人間が持っている素敵な特性です。
ルールとツールだけを手渡し、あとは自由に楽しんでもらう。
盛り上がりは開発者だけが提供するのではなく、ユーザーに助けてもらいながら作っていく方がずっと素敵です。
なぜなら、自分自身だけの力で出せるより、ずっと大きなパワーがそこにはあるからです。
たとえば、部下を育成するときにも「ルール」と「ツール」を提供するという考え方は活かせます。
また、自分自身に与えられた仕事上の環境について考えるときも、「上司は何を求めているんだろう」と考えるより、「与えられてるルールとツールはなんだろう」と考えたほうが、ずっと楽しくなるはずです。
③ すべてを「感情の起伏を生み出す装置」と定義する
ゲームは「感情の起伏を生み出す装置」です。
いったいどんな感情を生み出すために作られているのでしょうか。
実装する細かな仕様のひとつひとつは、必ずなにかの「感情」のためのものであるはずです。
もしそれがはっきりとイメージできないのであれば、その仕様は不要かもしれません。
あるいは、本来あるべき姿から少しだけズレてしまっているかもしれません。
②の「ルール」についても「感情の起伏を生み出す装置」と捉えることができます。たとえば、よりよい組織設計の方法を探し出すヒントとして使えるでしょう。
同じように、プレゼンテーションの1ページずつを「感情を盛り上げる / 抑制するための装置」として捉えることもできます。
What to Say(何を伝えたいか)だけのプレゼンテーション資料に、How to Say(どう伝えるか)の視点を注ぎ込むために役立つ考え方です。
④ 期待感とは組み合わせによって刺激される想像力
長くコンテンツに触れつづけてもらうためには「期待感」という感情に目を向けることがとても大切です。
そして「期待感」は、組み合わせによって発生します。
街人Aの話と、街人Bの話を組み合わせることによって、Cという展開を期待しながらプレイする。
以前戦ったボスが巨大であったことと、あるスキルでザコ敵を倒すのが気持ちいいという情報を組み合わせることで、同じ戦略で挑む巨大ボスとの戦いを期待しながらプレイする。
白熱したオンラインランキングの体験と、新しく実装されたシステムから、未来のイベントが盛り上がることを期待しながらプレイする。
魔物に襲われた一軒家で、夫婦の死体とともに、子どものおもちゃを見つけることで、いつか攫われた子どもと出会う展開を期待する。
このように「期待感」は「組み合わせ」から生まれるのです。
なぜかというと、事象と事象をつなぎ合わせて未来を予測するというのが、太古から人間が育ててきた「生き抜くための能力」だからです。
人は紙芝居のように事象を捉え、未来を想像します。
期待感を作りたいと思った場合「何の組み合わせによって?」という問いを立ててみるとよいでしょう。
たとえば「あなた」と「情報」の組み合わせを考えてみましょう。
よくデートの誘い方として出てくる「水族館と美術館、どっちに行きたい?」という質問は、あなたと水族館、あなたと美術館という、組み合わせによって想像力を働かせる方法です。
あるいは「実は高校時代、部活で30人くらい仕切ってたんですよね」というエピソードトークが、上司の想像力を刺激し、新たなキャリアのチャンスを開いてくれるかもしれません。
⑤ 受け手の「姿勢」をイメージする
コンテンツに触れるとき、ユーザーはどのような姿勢でいるでしょう。
寝る前のベッドに寝転がっているでしょうか。
椅子に座って真剣に向き合っているでしょうか。
あるいは、何かをしながらの「ながら」プレイでしょうか。
人は姿勢を変えることで、心拍数が変わります。
その心拍数と、コンテンツが要求するテンポ感は一致させたいところです。
ユーザーイメージを持つのはとても大切なことです。
それを一歩押し進め、姿勢を、心拍数をイメージしてみましょう。
たとえば、1日かけて作って定時間際にできあがった資料。いつ送るべきでしょうか?
すぐに送る? 少し見直して夜中にする? それとも明日の朝にする?
読む人の「姿勢」を想像しながら考えてみましょう。
たとえば、いま作っているその資料、事前に送るものですか?
それとも会議で初出し、プレゼンするものですか?
見る人の「姿勢」を想像しながら、資料を整えてみましょう。
⑥ 配信を見る人までイメージする
ユーザーはプレイしている人だけではありません。
今の時代、プレイしている人の周りにもたくさんいます。
単純な感情ほど伝播しやすく、その中でも笑い、緊張感、恐怖などは言葉にしやすいため、実況に向いていると言えます。
実際にプレイしながらエア実況してみるというのもいい方法です。
これまで気づけなかった、様々なことに気づけるでしょう。
その資料、相手に伝えて役目が終わりではありません。
その相手が、他の人に説明するときにも使われます。
自分以外の人が説明する側に立ったとしても、伝わりやすい資料になっているでしょうか。
⑦ 指先と向き合う
今はスマートフォンもPCも、OSが非常に優れています。
それらの手触りから、地続きにコンテンツにやってくるため、指先の反応と向き合い、インタラクションを突き詰めないと、コンテンツが安っぽく見えてしまいます。
この視点における競合は、たとえば手元でいつも使っているアプリです。
指先に対してグラフィックがどういった反応、アニメーションをしているのか、事細かに観察し、足りていない点がないかを考えつづけてみましょう。
こういった資料も刺激に溢れています。いまや、インタラクションの動きは無視できない要素になっています。
せっかく中身にこだわったのですから、最後の最後で、触覚にまでこだわってみましょう。
資料はめくりやすくファイリングを。
握って気持ちいい形状の商品を。
デートの前にはハンドクリームを。
⑧ 体験のコアを正しく捉える
ゲームにはゲームサイクルがあります。
大サイクル、中サイクル、小サイクルと分解されたりするのですが、コンテンツにとってまず大切なのは、一番小さいサイクルが成立しているかどうかです。
言い換えると「定期的にやってくる気持ちよさ」があるかどうかです。
コンテンツを作っていると、徐々に複雑化していく中で、この「小さな気持ちよさ」を見失いがちになります。
だからこそ、きっちりと言語化して定義しておくことが重要です。
たとえばアクションゲームであれば、初期に定義した「叩いて」「叩いて」「避けて」「倒す」というノーダメージの気持ちよさが、徐々に難易度が上がっていくことで、いつのまにか消えていたりするなんてことが良く起きます。
自分たちの実現したい気持ちよさはこれだ、と、きっちり自己認識しておけば、そういうことは起こりません。
大切なのは「小さな気持ちよさ」をキープしつづけることです。
これはゲームだけの話ではありません。
たとえばニュースアプリなら、見たい記事を見つけてタップする瞬間。
SNSなら、何らかの通知がきてタップする瞬間。
体験のコアは「定期的にやってくる気持ちよさ」にこそあります。
その書類、ひと段落だけを抜き出しても、全体で伝えたいことの一部がちゃんと詰まっているでしょうか。
あるいは部下に対して、半期に一度のMBOだけでなく、日々の業務の中に成長実感を詰め込んだ成長設計ができているでしょうか。
⑨ 世界観を足し引きしてみる
たとえばパズルゲームは、図形の組み合わせで作ることができます。
でもそこにキャラクターを乗せてみると、一気に魅力的になったりします。
(ぷよぷよが長く愛されつづけているように)
すべての数値、細かなUI要素について、世界観を付加すべきかどうか検討してみるとよいでしょう。
ここで気をつけておきたい基本ルールがあります。
・世界観を付加すると、対象ユーザーが狭まり愛が深まる
・世界観を排除すると、愛が浅くなり対象ユーザーが広がる
どのくらい対象を狭めるか、愛を深めるかは、付加する世界観の濃さにもよります。
これはあくまで基本ルールなので、世の中の「大ヒットコンテンツ」を見ると、ルールから外れているものも多いです。
ただし、上記の基本ルールのもと、濃い世界観を広いユーザーに伝えるためには、それだけ強い「想い」が必要だということは認識しておきたいです。
(世界観を飲み込む努力を支払う「納得性」が必要なのです)
あなたの存在もまた、立派な「世界観」です。
今日チームメンバーにする大事な話は、自分の思い出話からはじめてみてもいいかもしれません(過剰にならないように気をつけながら…)
⑩ 欲求があるから学習が捗る
コンテンツは、その使い方を伝えなければ使ってもらうことができません。
使い方を知るとは「学習」です。
それどころか、存在を知ることですら「学習」です。
人間はとてもめんどくさがりな生き物です。
そんな人間にとって、学習はめんどくさいものです。
まず欲求が存在しなければ、ルールを学ぼうとは思いません。
だからこそ、何かを伝える前に欲求を作ることが大切です。
この先の世界を知りたいという欲求を作ってから、扉の開け方を伝える。
もっと強くなりたいという欲求を作ってから、武器の育て方を伝える。
この欲求づくりは、プロモーションの段階からはじまっています。
たとえばどういうヴィジュアルでコンテンツを伝えるか。
タイトルは何で、それはどういう欲求を掻き立てるためのものなのか。
欲求が学習を上回らないようにするコントロールはとても重要です。
とはいえ、ここを重視するあまり、学習させるスピードが遅くなりすぎてしまう状況も避けなければなりません。
既に高い欲求がある状態で、学習を遅らせるとストレスが溜まります。
このスピード感を個人で判断するのは、とても難しいことです。
客観的な意見を参考にして、チューニングしていく必要があるでしょう。
大好きなあの人に、自分の趣味を熱っぽく語るのは今でしょうか?
ちょっと早すぎるかもしれませんし、あるいは、ちょっと遅すぎるているかもしれません。
まとめ : すべてのスキルは「対人スキル」である
冒頭に書いた「なぜゲーム制作の事例が、仕事の仕方や人生にまで活かせるのか」の答えがこれです。
すべてのスキルは「対人スキル」と言えるのです。
ユーザーに向き合うというのは「対人スキル」です。
製品を作ることも、製品を伝えることも、それらの人々を支えることも等しく「対人スキル」です。
もちろん、組織を作ることも「対人スキル」です。
プログラムの設計も、チームメンバーに対する「対人スキル」です。
自己研鑽する個人競技のスポーツであっても、自分自身との向き合い方という点においては「対人スキル」になります。
すべてが同じ「対人スキル」だからこそ課題発見の方法は共通しています。
大事なのは、自分自身が培った力を汎用化/一般化して、広く共通に用いることのできるスキルとして整理しておくことです。
ゲームから発想し、ゲームのことを書きました。
でも、きっとみなさんにも役立つTIPSだったんじゃないかと思います。
これこそが、今回の記事で、実例をもって伝えたかったことです。
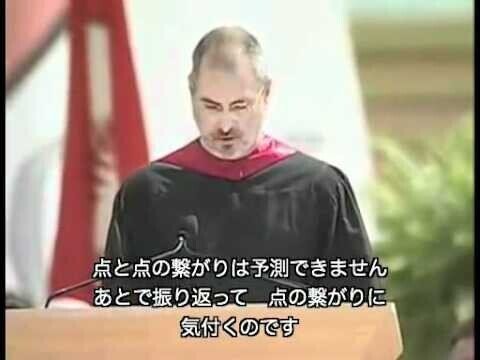
僕はこれこそが、スティーブ・ジョブズの語った「Connecting The Dots」の真実なんじゃないかと思っています。
すべての点は、繋がるようにできている。
なぜなら、それらは全部「対人スキル」だからなのです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
