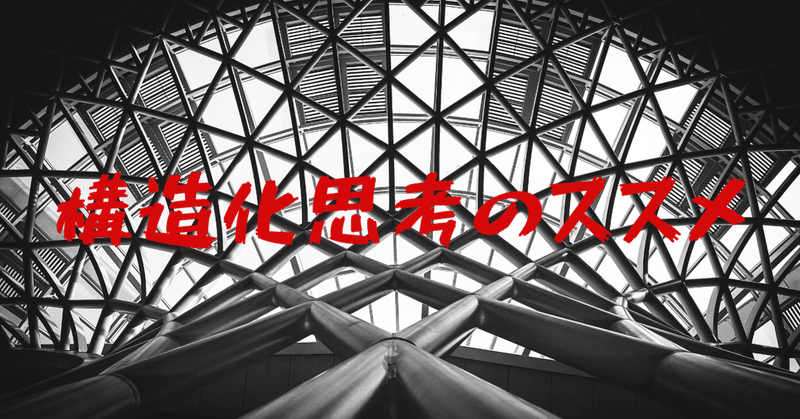
構造とディティール、在り方とやり方
私は元大工の経営者です。最近、自分の一番の特徴は(元大工だけに)構造がわかる事だと気がつきました。同時に、構造が分かってない、もしくはその存在に気がついて無い人が多いなー、と言うことも感じており、問題や課題の相談を受ける度に「それって構造の問題だよねー」と根本的な部分に光を当てることをオススメしています。
パタンランゲージ
元大工だけに構造が分かるって書くと、建築的な分野の能力に聞こえるかも知れませんが、実はそうとも限りません。長年、経験を積み重ねると建物や構造物、工作物の構造が分かる様になるのは当然ですが、構造が分かる→基礎から見直す(=根本的問題に目を向ける)を繰り返していると、パターンが見えてくる様になります。UXデザインの世界ではパタンランゲージという言い方をされますが、繰り返しの問題解決に向き合う事で構造的エラーを全体を見るだけで感じられる様になりました。10年位前から「そもそも」や「根本的に」が口癖になっていると指摘されることがしばしばありますが、それは構造のエラーに気がつくようになった兆候だったのかもしれません。

あらゆるものが構造されている
実は、構造をしっかりと固めると言う考え方は、何にでも当てはまります。建物だけでなく、組織形成やビジネスモデル、文章の書き方など、構築と言う言葉が当てはまるものに対して、すべて構造が関わっています。例えば、事業の組み立て方で例えると、まず基礎の部分に何のために?と言う存在意義の問いかけがあり、その上に一緒に授業を行っていく人材が集まるべきです。メンバーの意図や方向性が共有された上で業務を回す仕組みが機能し、顧客やステークホルダーといったコミュニティーが生まれます。この構造、何度も繰り返し評価することで、倒れにくい強固な事業所になって行き、当初の問いの答えである人間や存在意義の実現が1番上の屋根のように覆い被さるはずです。構造化思考を用いることで、目先のやり方だけにとらわれることなく、着実に事業所の形成が進んでいきます。

同じエラーを繰り返す理由
ビジネスモデルの構築や組織作り、プロジェクトの立ち上げなど、どれをとっても目的を明確にするところから始まる構造がしっかりしていることが重要なのは、誰しも理解されると思います。しかし、それぞれの取り組みを進める中で起こる様々な問題や課題に対して行うのは、圧倒的に対処的な反応が多くなります。緊急性の高いものについては、それも致し方ないのも事実ですが、同時に構造に目を向けて根本的なテコ入れをしなければ同じことが何度も繰り返されてしまいます。この部分に目が向かない人が多い理由は、構造を認知していないからだと感じています。

構造化思考の入り口
根本的な問題解決を推し進め、エラーの発生による対処を減らしていく構造化の思考を多くの人に身に付けてもらいたいと思います。私が実感として持っているのは大工上がりの経営者は、確かにその力を持っていると感じる人が多いことです。とは言え、大工が全員根本的な問題に目を向けるかと言うと、もちろんそんな事はありませんし、構造化思考を身に付けるために、ものづくりの世界に身を投じると言う訳にもいきません。しかし、実は身近な頻繁に使う言葉で構造的な思考に切り替えてもらえるようにアドバイスをされているのをよく耳にします。それは、やり方ではなくあり方を考えろ。との言葉です。建築的な言い回しをすると、やり方はディティールであり、在り方は構造です。まず、何のために?との問いを自分自身に立てて、目的を明確にし、どのようなゴールを目指したいのか、どのような世界にしたいのかをリアルにイメージすることができれば、構造化思考へのシフトができると私は考えています。この軸をしっかり持てば、誰もが構造のエラーに気づくようになると思うのです。
________________
構造化思考のインストーラとしても活動しています。活動一覧リットリンクにまとめてますのでよかったらつながってください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
