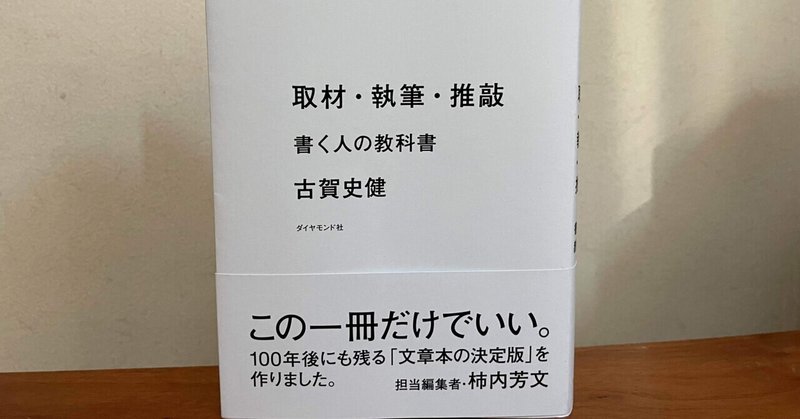
『取材・執筆・推敲 書く人の教科書』を読み始めたら、ライターではなく編集者のあり方が腑に落ちた【読書メモ】
まだ読み始めて数分の一しか進んでいませんが、この時点でメモっておきたいことがある。
この本は、「ライター向けの教科書」というコンセプトで書かれた、いわゆる「ライター」向けの本だ。
ライターは、ただ文章を書いているのではない。書くことを通じて、コンテンツをつくっている。同じ書くでも、現代史や純文学のような形式をとらない、けれども「コンテンツ」としか名づけようのないなにかを、ライターはつくっている。(P8 ガイダンス)
ぼくは「エンターテイン(お客さんをたのしませること)を目的につくられたもの」は、すべてコンテンツだと思っている。
お客さんの存在を前提にしていること。そして、お客さんの「たのしみ」や「よろこび」に主眼が置かれていること。つまりは、自分よりもお客さんを優先していること。この原則を守って作られたものは、すべてコンテンツだ。(P9 ガイダンス)
じゃあ、どうすれば「文章を書く」だけのライターから、「コンテンツをつくる」ライターへのジャンプができるのか。
その鍵になるのが、「編集」という概念であり、プロセスである。
(P11 ガイダンス)
ここで話は「編集者」の話に進んでいく。そして読み進めていると、ここで説明された編集者のあり方は、kintone Caféなどの勉強会や、オンラインイベントの企画のあり方に似ていると思った。
そうか、イベントや勉強会を企画運営するということは、「編集者」の仕事に限りなく近い。
— Shotaro Matsuda(松田正太郎) (@Shokun1108) September 17, 2021
決して司会進行役だけが企画運営ではない。
ライティングの本を読みながら、序章から繋がる繋がる#読書メモhttps://t.co/4wMlIp5o1E
原稿を編集するのは、あくまでもライターだ。そして編集者は、原稿の外側にあるものを、つまりコンテンツの「パッケージ」を編集する人間である。
では、コンテンツのパッケージとはなにか。
簡単に言えば、「人」と「テーマ」と「スタイル」の3つだ。
つまり、「誰が(人)」「なにを(テーマ)」「どう語るか(スタイル)」のパッケージを設計していくのが、編集者のもっとも大切な仕事なのである。(P12 ガイダンス)
この、
1.人・・・誰が語るか
2.テーマ・・・なにを語るか
3.スタイル・・・どう語るか
という3つのパッケージの要素のトライアングルがうまくつながったとき、コンテンツの価値は最大化する。
この考え方も、イベントを企画するときにぼんやりと考えていたことを、見事に言語化してくれている。
そしてこの3つのバランスを取りながらコンテンツを考えていくプロセスは、正直すごくエネルギーを使う。
まぁ、それはkintone Café 東京の開催頻度が、1年に1回程度になっていることのイイワケなのかもしれないけど(^^;)
今、2021年11月に開催予定の、kintone Café JAPAN 2021の企画を、運営メンバーで考えているところだ。10月の頭ぐらいにはみなさんに開催リリースをお知らせできると思うので、楽しみにしてください!!
いただいたサポートは、今後とも有益な情報を提供する活動資金として活用させていただきます! 対価というよりも、応援のキモチでいただけたら嬉しいです。
