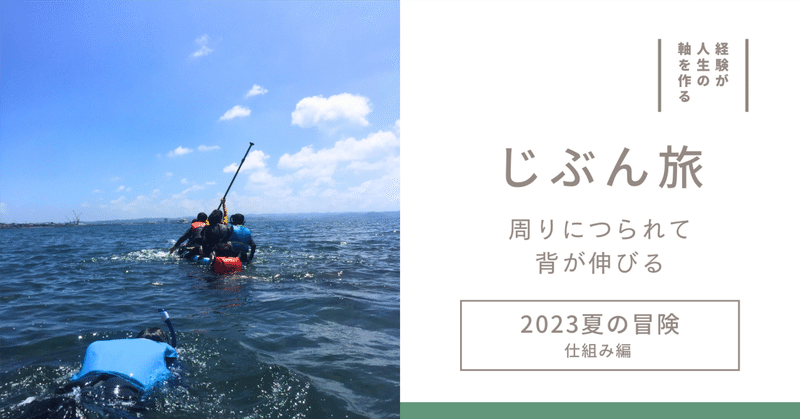
夏キャンプ。「周りにつられて背が伸びる」の仕組み編
「経験が人生の骨格を作る」をモットーに活動する「じぶん旅」。夏の4泊5日の冒険旅行の後編、仕組み編です。
前編はこちら↓
暇の先に生まれる、名もなき遊びたち
キャンプ中、子どもたちみんな、徹底的に遊びました。
時間があるって、素晴らしい。「暇だー」って言っている子が、気づくと引き込まれている。
海では、SUPに何人乗れるかチャレンジをしたり、大きなカニと激闘を繰り広げたり、大きな波に乗ってみたり、鬼ヤドカリから”宿”を奪おうとトライしてみたり、網で魚をたくさん捕まえたり、釣りしてみたり、海水から塩作りにチャレンジしたり、釣った魚を捌いたり、それぞれ自由に何十通りと広がる「名もなき遊び」に没頭していました。
途中から「海行くのめんどくさいー」なんて言葉も出てきましたが、いざ海に入ると、どんどん遊びに夢中になっているのです。ここで何ができるを知り、遊び方のバリエーションが増えた子どもたちは、目線が変わる。自然の中で、自分たちでルールメーカーとなる「名もなき遊びたち」を生み出すことができるのです。

「なんでもいい」の裏側
キャンプ開始すぐ、子ども達に「何をしようか」と聞くと、「釣りがしたい!」「磯遊びしたい!」と具体的にイメージしている子もいる中で、大半の子は「なんでもいい」と返ってきます。
一見、ぶっきらぼうでやる気がないのかなとも見えますが、選択肢を自分で持ってない、そして、心理的安全性がない場のため、よくこの言葉が出てくるのです。
そこで、彼らから「何したい」を引き出すために、じぶん旅では、遊びの引き出しをそれぞれが持つため、そして心理的安全性を確保するため、3つの要素を設計しました。

① 場を知る
「さあ、遊んで」と言っても知らない場所で遊び方も知らないもの。特に自然相手の場所だと、ある程度の慣れも必要。それを補完するために、南房総出身で海遊びのプロフェッショナル"くじらのもり"「ネギ」にサポートを依頼。どこの磯で何ができるのか、どこで飛び込めるのか、釣りは何をつけたらいいのか。遊びの兄貴ネギが最初、場を引っ張ってくれます。
また、外遊びでは無視できない自然環境も、潮回り、天候、気温、これらについても事前に学んだ上でキャンプに臨み、随時「明日は大潮だけど、何時が干潮だっけ?」なんて話しながら進みます。
② 仲間を知る
夏キャンプの良さでもあり、ドキドキでもある「知らない仲間が集う」点。
知らない仲間だからオモシロイ。新しい価値観にも出会えるし、自分自身の新しい面も出てくる。
ここは、互いに理解を深めるために、グループでの「作業」もプログラムに入れます。互いに話す機会を増やし、さらにちょっと上の高校生大学生スタッフが適度な距離でお互いを繋ぐ役割をしていきます。
③ 自分を知る
「じぶん旅」いちばんのポイントは、ココ。
毎度、「人はみんな違う。だから自分がどう思ったか、その時の感情を大事にしよう」ということを伝え続けます。同じ経験をしても、人によって受け取り方も感じ方も違う。だからこそ自分自身がどう思ったのか、そこに価値があると。そして、違った感情や考え方を持つ人がいるからおもしろいんだと。
キャンプ中、毎晩ノートに「疲れ度」と「感情」をメモリに表し、その理由と共に、自分の感情に向き合う時間を作りました。
それは、楽しいのか、ツラいのか、うれしいのかを把握するのはもちろんなのですが、その前にある「どうしてその感情になるのか」を認識してもらうためです。
その「うれしい」「楽しい」「悲しい」「ツラい」感情になるバロメータを知っていると、自分のワクワクに気づきやすくなるし、逆に心がザワザワする理由についても自分自身で気づきやすくなります。
自分の今の感情を言語化し、その理由まで書くのは慣れるまで難しいもの。これはオトナでも難しい。
初めの頃は「疲れた」「楽しかった」という感想のみが書かれたノートでしたが、日を追うごとに、「(仲間に)助けてもらったから優しい気持ちでいっぱいになった」「自分で動けたのがよかった」や、「自分のいい面が出せていると思う」「1人で悩んでても仕方ないから(仲間と)協力する」という一歩踏み込んだコメントも出てくるように。
まとめ
最終日に、今回の旅で印象に残ったことを聞くと、
大鍋から直接スープを飲んだ経験を話してくれたり、キャンプファイヤーの火の上を飛んだ子がいた光景だったり(共に安全は管理しております)、ロープブランコを二人乗りした経験だったり、何気ない「名もなき遊び」が彼らの心に残ったようです。
それらは、オトナが与えたものではなく、自由の中で子どもたち自身で見つけたものでした。
自分の背丈を知り、そして背を伸ばす
この旅の中で、子ども達は、自分の背丈を知りました。と共に、周りの仲間に感化され揉まれながら、グングングンっと背丈を伸ばしていきました。1回りも2回りも、見ているこっちが誇らしくなるくらい。
こういう経験によって「自分はできる」という「自己効力感」が養われていくんだと実感しています。
先の見えない世の中だからこそ、何かの岐路に立った時、「自分はできる」とさえ思えたら、できる方法を探り出す。だからこそ、自己効力感の醸成が何より大事だと考えています。
これからもじぶん旅の冒険はつづく。
さあ、次の冒険にGo!!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
