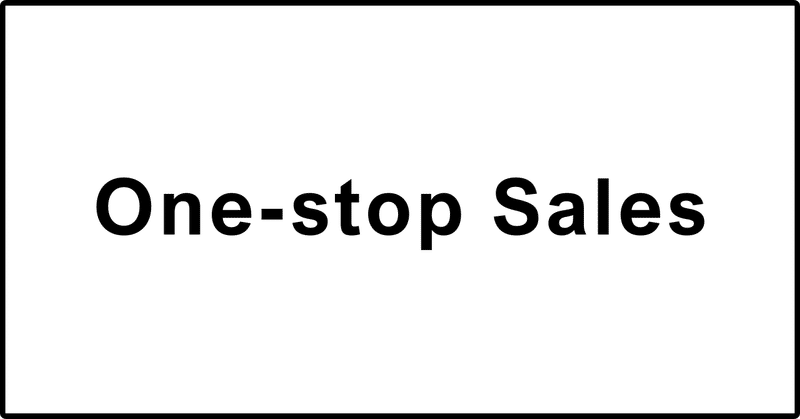
SaaS乱立時代の”ワンストップセールス”
こんにちは、HQ(エイチキュー)代表の坂本です。
このNoteでは、
「ワンストップセールス」という、次なる10年に求められる新しいセールスのありよう
について書いていきたいと思います。
私たちHQは、「福利厚生をコストから投資へ」をビジョンに掲げた福利厚生産業スタートアップで、
創業時から、いわゆる「コンパウンド戦略」を採用しています。
コンパウンド戦略とは、大まかには、
「プロダクト同士を連携させながら、多数の新プロダクトを開発していく戦略」
を意味しています。
コンパウンド(Compound)という概念は、今をときめく急成長スタートアップ/時価総額1兆円超であるRipplingのFounder/CEOのParker Conradが提唱したもので、
日本でも、「freee」「バクラク」「ジョブカン」などが近い戦略を採用しているといえるでしょう。
私たちHQは、3年前の創業時(21年3月)から、まだコンパウンド戦略という言葉が日本になかった時代から、一貫して本戦略を取ってきました。
(創業3年で現在は「リモートHQ」「カフェテリアHQ」の2サービスを出していますが、あと2年間で5-6サービスまで次々と増やしていく予定です。)
自社の成長戦略の核として、
私は、以下のように、自分たちのコンパウンド戦略を定義しています。
①プロダクトの数:
初期から、単一プロダクトではなく、複数プロダクトを提供。その後も、次々とプロダクト数を増やし続けている。
②プロダクト連携による価値創造:
データを中心にサービス同士がなめらかに連携することで、顧客価値を高めている。
③高い開発効率:
共通部品/ミドルウェアを活用することで、凄まじい開発効率、開発スピードを実現している。多数のプロダクト連携を前提としたアーキテクチャ。
④連続的な新事業開発力:
巨大なエコシステムを制御しながら、新製品を次々と開発し続けられる新プロダクト開発体制をもっている。
⑤クロスセル・クロスマーケティング:
マーケティング/セールスのあらゆる施策が全てのプロダクトの販売につながる。顧客ニーズにあわせて最適なソリューションを案内することで、顧客獲得単価を低く抑えることができている。
このなかでも、ビジネス面で非常に重要なのが、
「⑤クロスセル・クロスマーケティング」であると考えています。

クロスセル・クロスマーケティングは、あらゆる集客・営業施策で一石二鳥、三鳥を狙える戦略。
シンプルに、集客効率・営業効率が凄まじく上がるというメリットがあります。
私たちHQも、単一プロダクトで集客、販売していた創業期と比較して、劇的に営業効率があがっており、大きな競争優位性だと感じています。
実際、キーエンス、大塚商会、オービックなど、日本を代表するB2B企業のなかでも特に生産性/利益率が高いと定評のある会社は、ワンストップセールスに近い営業体制を整備していることが多いです。
そして、クロスセル・クロスマーケティングの何よりもの意義は、
「顧客から本当に求められる、非常に素晴らしい営業体験を届けられる」
という点にあると感じています。
特に、1人の営業(アカウントエグゼクティブ)が、多くの製品のなかから最適なものを案内していく「ワンストップセールス」という営業手法は、
これからの日本で強く求められる「B2B営業の未来のアタリマエ」ではないかと感じています。
本noteでは、私が実際にコンパウンド戦略・ワンストップセールス体制を実践していくなかで得られたリアルな気付き・学びをもとに、
ワンストップセールスが求められるようになった時代背景
ワンストップセールスという職能
ワンストップセールスで築けるキャリア、市場価値の向上
ワンストップセールスを支える専門サポート部隊
ワンストップセールスによって実現する理想の営業体験、世界観
などについて説明していきたいと思います。
SaaS乱立時代に求められる営業体験とは?

この10年ほど、SaaSブーム、DXブームのなかで、無数のB2Bサービスが乱立してきました。
例えば、ひとつ労務、会計、経営管理などをとっても、無数のサービスが並んでいます。
サービス提供者側は、日々、商談数や成約数を追っています。
一件でも多くの新規商談を増やしたいと思っています。
ホワイトペーパーやウェブセミナーが量産化され、登録すると、インサイドセールスからすぐに電話がかかってきます。
一方、お客様は、新規商談の設定はもうたくさんだと思っています。
このようなサービス乱立時代において、お客様の多くは、新しいサービスについて話が聞きたい、とは積極的に思っていません。
顧客目線でみると、商談はコストに過ぎません。
決して増やしたいものではなく、むしろ一件でも少なくしたい時間です。
年々、顧客獲得費用は上昇していますが、それは、広告テクノロジーが悪化したからではありません。
サービスの数が増え、需給バランスが供給過多になるなか、
新サービスの話を聞きたい、というニーズそのものが下がっているのです。
そもそも、お客様の視点でみれば、
同カテゴリで、色んな会社に別々に新規営業されるのは、面倒なことです。
日々本業で忙しい日々を送っているにもかかわらず、多数の営業に対して、
自社の経営方針、部門方針、課題
予算の考え方、決裁方法
自社の文化、哲学
などを丁寧に説明するのは非常に手間がかかる面倒なプロセスです。
また、それらを伝えたところで、フィールドセールスから、悪気なく、自社プロダクトを売るためのセールストークが繰り広げられます。
知らず知らずのうちに、顧客本位の営業ではなく、提供者目線の営業が世に溢れている構造になりつつあります。

この10年のB2Bセールスは、分業化、専門化のトレンドでしたが、その弊害が目立ち始めています。
「The Model」というキーワードが流行するなか、多くの会社で、マーケティング、インサイドセールス、フィールドセールスのような分業が増えていきましたが、
KPI至上主義・部分最適主義による「顧客体験の毀損」「生産性の低迷」
がいたるところで起き始めています。
マーケティング部門は、リード数ばかりを見て、セミナーやホワイトペーパーが需要をはるかに超えて世に溢れています。
セールス部門は、成約率をみて、細かなセールストークを磨いていますが、顧客が本当に何を求め商談に臨んでいるのか(どんな切り口で商談は設定されるべきか)への感度が鈍くなっています。
(もちろん、一社一社にとって、本気でKPIや売上を追うことは非常に大切なことです。ここでは、あくまで社会全体のマクロな議論として、新規商談過多になっているという点を指摘しています。)
そんな状況でのお客様の本音は、以下のようなものではないでしょうか。
「新規商談は無駄に増やしたくない」
「自社のことを深く理解してくれている営業とだけ付き合いたい」
「その営業からは、一般的な情報提供だけでなく、自社に合った課題解決まで提案してほしい」
そして、このようなサービス乱立時代のお客様の真のニーズへの答えが、
「ワンストップセールス」という新しいあり様だと私は考えています。
これからの時代に求められる「ワンストップセールス」とは
ワンストップセールスでは、
「顧客にとっての”ワンストップ総合窓口”としてふるまい」
「一人の営業が、数多くのプロダクトの中から、最適なものを提案する」
という形式で営業します。

一方、プロダクト数の増加という点だけでワンストップセールスを捉えると、その本質を見誤ります。
ワンストップセールスでは、顧客にとって本質的にこれまでとは異なる存在としてふるまうことを目指します。
例えば、HQ社としてのワンストップセールスの定義は、以下の様なものです。
①長期的関係
ひとりの営業が、中長期的にお客様と関係値を築く。お客様としても、たらい回し感なく、ストレス低く情報インプットが行える。②深い顧客理解
企業体としても人対人としても、お客様のことを深く立体的に理解したうえで営業する。③個別最適な提案による付加価値創出
決して単一プロダクトを無理に売ろうとしない。戦略や商談相手の課題感に合致した最適なソリューションを案内することで、顧客にとって付加価値を創造する。
つまり、ワンストップセールスは、ありよう/Beingとして、
「長期的関係を築き、深い顧客に基づいて、個別最適な提案を行い続ける」「その顧客にとって価値ある戦略パートナー」
であることを志向します。

顧客からみれば、信頼しているワンストップセールスに相談できれば、多くの新規の商談相手に、一から自社のことを教える必要はないですし、付き合う価値があるかどうかを判断するために営業の実力値を見定める必要もありません。
つまり、お客様にとって、中長期的な付き合いの信頼できるワンストップセールスとの商談は、より付加価値の高い時間の使い方になります。
プロダクト導入という枠を超え、自社にとってより付加価値の高い課題解決をすることに集中して議論検討することに時間を使うことができます。
ワンストップセールス戦略とは、
「お客様にとっての理想の相談相手とはなにか?を突き詰めるプロセス」と言ってもよいかもしれません。
結果として、サービス乱立時代に蔓延しつつある不快な営業体験を減らすことにもつながり、顧客にとって最適な営業体験を届けられるのです。
ワンストップセールス体制がもたらす劇的な経営インパクト
長期的関係/深い顧客理解/個別最適な提案/付加価値の高い時間・・・
などの単語をみる限り、
一見すると、ワンストップセールスは、丁寧すぎる営業であり、商売として非効率的に見えるかもしれません。
しかし、実は、直感に反するかもしれませんが、
ワンストップセールス戦略が成功すれば、劇的にビジネス経営効率、すなわち最終成果が上がります。
ワンストップセールス体制では、「商談数」「成約率」「リードタイム」など、プロセスKPIへの強度がどうしても下がります。
ワンストップセールスを担う営業が実に多くのことを担当するため、細かなKPIの議論はどうしてもおざなりになりがちになるからです。
実際、KPIの一部はあきらかに悪化します。
たとえば、インサイドセールスからの商談をひたすらこなしていくタイプの営業スタイルと比較すると、フィールドセールス一人当たりの新規商談数は間違いなく減ります。

しかし、部分的なKPI悪化は、あくまで中間指標の問題にすぎません。
虫の目ではなく、鳥の目で見る。
ワンストップセールスが機能すれば、
商談獲得費用という最大のコストが劇的に改善することで、全体としての経営効率は大きく上がります。
例えば、全く広告費をかけなくても、マーケティングやインサイドセールスが全く動かなくても、
信頼されている一人の営業からのたった一通のメールや電話で、すぐに超高品質の商談を創出できます。
これは、ワンストップセールス営業からすると何気ない自然な行動ですが、ビジネスとしてみると、
一件あたり数十万かけていたような商談獲得がほぼコストゼロでできている
ことを意味しています。
B2Bソフトウェア企業にとって最も高額なコストである顧客獲得費用が劇的に削減されることのインパクトはすさまじいです。
(広告費用はもちろん、マーケティングやインサイドセールスの人件費にかける費用も劇的に下がります)
100件、1000件で換算すると、数千万、数億円に及ぶ差を生むわけで、
ワンストップセールスが確立されれば、根本的・構造的な競争優位をつくることができます。
ちなみに、実は、このようなワンストップセールスの経営的利点をフル活用しているのは、経営品質の高さで有名な歴史ある日本企業が多いです。
おそらく課題解決型のワンストップセールスで最も有名な企業は、おそらくキーエンス(時価総額約17兆円/2024年5月時点)でしょう。
他にも、オービック(時価総額約2.1兆円)、大塚商会(時価総額約1.1兆円)なども、代表的なワンストップセールス企業だと思いますが、いずれも長期に渡って凄まじい業績を出し続けています。
これらの会社は営業利益率は5割近くの会社もあり、凄まじい利益率を誇っていますが、それは中長期的にワンストップセールスが機能し、マーケティング費用や人件費をさほどかけずに、毎年、受注を量産できているからです。
(たとえばキーエンスは、結果としての社員一人当たり生産性の高さ、給与の高さは有名ですね。)
最近(2024年5月)も、大塚商会さまの以下のような記事が出ていました。
高品質のワンストップセールスは、お客様本位の高品質の営業体験をつくることで、結果的に、凄まじい経営成果をうみだせる手法なのです。
ワンストップセールスで築けるキャリア・市場価値
ワンストップセールスは、これからの時代のキャリアパスとしても非常に魅力的な選択肢になると思っています。
誤解を恐れずにいえば、たとえるならば、投資銀行家、戦略コンサルタント、士業のようなキャリアにも近い。
高度専門職としての腕力と市場価値が身につく職能であると思います。

ワンストップセールスのキャリアとしての魅力・厳しさの両方を表すのが、
「一人当たり成果のアップサイドが凄まじく大きく、個の力次第で大きな市場価値/給与の向上が狙える」
という点です。
ひとつの顧客に、実に多様な製品をクロスセルできるので、営業の工夫次第で、一人当たり成果を大きく高められるアップサイドが極めて大きい。
前述したとおり、ワンストップセールス体制は、全体的な経営効率の大きな向上につながるため、社員一人当たり生産性は非常に高い数値を狙うことができます。
また、マーケティングやインサイドセールスに完全には依存しきらずに商談創出していく面もあり、「自ら売上をつくれるビジネス総合力」が骨の髄まで鍛えられます。
コンパウンド戦略をとるスタートアップにおけるワンストップセールスは、投資銀行家、コンサルタント、士業のような職能にも似た高度専門職キャリアといってもよいかもしれません。
(実際、これらのキャリアでは、キャリアを重ねるほど、知識よりも、営業スキルこそが最も高く評価される構造になっています。)

また、高い一人当たり生産性は、給与アップ/キャリアアップを描きやすい、ということも意味しています。
HQも、まだ2プロダクト体制ですが、Bizチーム一人当たりの獲得粗利益(ARR)は、日本の平均的なSaaS企業と比較すると、少なくとも数倍の数値を既に出せています。
今後プロダクト数が増えていくにつれ、極めて高い一人あたり生産性数値が狙えることが保守的に試算できており、数値を見れば見るほど、ワンストップセールス体制の持つポテンシャルを感じています。
たとえば一人当たりの創出売上/利益が5倍であれば、
給与のアップサイドも少なくとも5倍以上あるということを意味します。
(これは非現実的な前提ではありません。たとえば、実際に、米国SaaS企業のエンタープライズセールスの平均年収は約3,500万円(出所Glassdoor:https://www.glassdoor.com/Salaries/enterprise-sales-salary-SRCH_KO0,16.htm)ですし、キーエンスの2023年3月期における平均年収は2,279万円(出所:有価証券報告書)です。)
一方で、ワンストップセールスは、楽して儲かるお得なキャリアパスではなく、求められることが高い険しい道です。
ワンストップセールスとして成長し続けるには、多様なスキルセットの獲得が必要であり、長期的な自己研鑽が求められる難易度の高い道だとも思います。
「プロダクト営業」X「ソリューション営業」という挑戦
ワンストップセールスは、販売するプロダクトの数が増えるだけかと勘違いしてしまうと間違いなく痛い目をみるでしょう。
ワンストップセールスの職能としての難しさは、
「課題解決型ソリューションセールス」と「プロダクト営業」の両方
を究めなければいけない点にあります。
課題解決型ソリューションセールス:顧客のニーズを理解して、本当に必要なソリューションを案内する
プロダクトセールス:完全カスタマイズのコンサルティングではない形で、自社プロダクトに精通したうえで、磨き上げた自社サービスによって顧客の課題を解決する
この両方の役割を全うせねなりません。
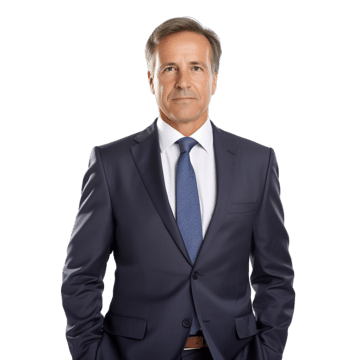
そして、顧客からすれば、「〇〇(領域名)のことなら何でもまず相談する相手」「具体的にプロダクト/解決策まで案内してくれる」という存在になりますので、期待値は当然高くなります。
専門領域の最新トレンドに精通していて当たり前。
お客様企業のことも分かっている。
もちろんプロダクトの知識も豊富でなければならない。
追加製品提供のための商談を創出するためのインサイドセールス能力も求められる。
自分の担当顧客/担当テリトリーのCEOであるようなオーナーシップが求められる重責といえます。
ワンストップセールスを支える専門サポート部隊
前述のとおり、ワンストップセールスに求められることは数多く、
さまざまなプロダクトに関する知識、ソリューションセールス力、最新のドメインナレッジなど、多岐に渡ります。
人材への要求水準は高くなりがちだからこそ、
ワンストップセールス体制をより良く機能させるための分業化、専門サポート体制構築が必要です。

サービス乱立時代の分業化、専門化が起こした弊害についても説明してきましたが、分業化、専門化それ自体は決して悪ではありません。
(The Modelの考え方自体も、決して時代遅れなものではなく、表面的な理解のもとで手段=howだけが広まりすぎたというだけとも思います。)
むしろ、ワンストップセールスだからこそ、分業化・専門化の重要性は高いです。
求められるのは、
「プロセス分解、KPIを起点とした従来型の分業」ではなく、
「顧客価値を中心とした分業化」です。
ワンストップセールスがその役割に集中するうえでは、たとえば以下のような専門サポート部隊が大きな助けになるはずです。
スペシャリストセールス:各プロダクトの詳細な知識をもつメンバー。より専門的な支援が求められたとき、営業(アカウントエグゼクティブ)と連携する。
セールスイネーブルメント:育成プログラムや営業資料の管理など
Sales Ops:KPI管理、CRM/SFA統括、目標数値やテリトリー管理
営業サポート:個社別の提案資料作成や定量分析、調査などを実施
マーケティングサポート:マーケティングやインサイドセールスが商談創出につながるツールやメッセージを供給
BDR:注力新規エンタープライズアカウントとの商談創出に向けた戦略的チーム
カスタマーサクセス:オンボーディングや効果測定、日々の運用サポートなどを担当
プロフェッショナルサービス/コンサルティング:プロダクト導入以前の戦略や実行面の支援
当社でも上記のうちの幾つかを既に仕組み化していますが、一人の営業に全てを任せるよりも、明らかに全体の生産性が高くなります。
顧客体験中心という理念に基づいた分業化・専門化を推進し、
最先端の武器・テクノロジーを活用する専門サポートチームの力をフル活用することで、
ワンストップセールスのもたらす付加価値創出をより高めることができるのです。
顧客起点を貫くスタイルで、最高峰の成果が出せる
これまで偉そうにワンストップセールスについて語ってきましたが、私たちにこのテーマを語るだけの実績があるかというと、決してそうではありません。
私が経営しているHQ社のセールスの人数は、2024年5月現在、わずか4名に過ぎませんので、
どれだけ大げさに言ったとしても、大規模組織での営業チームの仕組み化に成功したとは全く言えません。
(ただ、成績には満足しており、サービス提供開始から約2年で実質3名ほどでARR4億円を積み上げています。通常のSaaSサービスのトップセールスばかりを集めたような少数精鋭部隊になってきたと感じており、これから、更に平均値を高めていきたいと思っています。)
一方で、規模は小さくとも、「ワンストップセールス」の大きな価値を心から信じられるだけの”確かな現場実感”は毎日ひしひしと感じています。
2つ目のサービスを提供開始してすぐにクロスセスが生まれた
ちがうサービスを案内するなかで、もうひとつのサービスに興味をもたれ、当初とは違うプロダクトで成約する例が相次いでいる
会社としてのビジョンやその後の開発予定のサービスも案内することで、「ワンストップ相談窓口」と認知いただき、深い相談をしていただける
結果として、営業効率/集客効率が劇的に上がっている。
(ボトルネックは完全にセールスキャパシティとなっており、残念ながら新規の集客投資は止めているような状況)
そして、数値面以上に重要なこととして、
「お客様にとって本当に必要なものはなにか?」という問いがごくごく自然に生まれるようになり、
顧客価値をより追求するチームへと一致団結できていると感じています。
「ワンストップセールスという、顧客起点を貫くスタイルで、最高峰の成果が出せる」
そう確信しています。
もちろん、ワンストップセールスという手法それ自体はただのひとつの営業形態にすぎませんが、
次なる10年の社会からの要請に応える営業のありようであるように感じています。
ビジネスの世界では様々な手法が流行します。
より新しい役割名や組織体制、セールスの技術、マーケティングツール、集客チャネル・・・この10年で、B2B営業の世界も、一見して近代化されたかのように思います。
しかし、いついかなるときも、中心にあるべきは”顧客”だと思います。
このB2B SaaS乱立時代において、提供者視点ではなく、顧客視点で、営業のあるべき姿が問い直されるべきタイミングにあると感じています。
ワンストップセールスという手法それ自体が完璧というわけでは全くありませんが、
お客様の状況、課題を起点にして構想された”ワンストップセールス”という新しい営業によって、より良い営業体験が増えていってほしいと思っています。
【最後に・・・】
HQでは、ワンストップセールス/アカウントエグゼクティブを積極採用しています。豊富な実績を有する方はもちろんですが、一番重視しているのは”ポテンシャル”です。
本記事の営業のありように少しでも共感いただけた方は、ぜひカジュアル面談にお気軽に申し込みいただければ幸いです。
▼HQワンストップセールス /アカウントエグゼクティブ
▼カジュアル面談応募フォーム
面談申し込みフォーム
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
