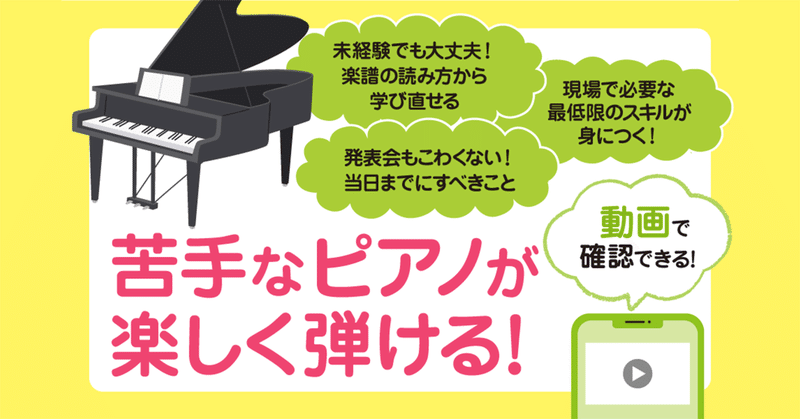
保育園で必要なのに「ピアノが苦手」な人へ、弾けるようになる基本と心構えが身につく本
保育の現場で働いている人や、保育士の資格取得を目指している人が1つの壁として感じていることの多いピアノの演奏(伴奏)。
いままで楽器を演奏したことがないと、少し鍵盤に触ってみただけで「難しそう」「できそうにない」と思ってしまいがちです。
ですが、基本から少しずつ学び、練習していけば、誰でも多かれ少なかれ弾けるようになるのものでもあります。
もし苦手意識を感じていながらも、ピアノを弾けるようになりたいと考えているなら、翔泳社の書籍『先輩が教えてくれる!保育ピアノのきほん』がおすすめです。
本書は元保育士であり、現在は日本児童教育専門学校で専任講師を務める今泉良一さんによる、初めてピアノを練習する保育士のための入門書です。
楽譜の読み方、実際にピアノを弾く方法、表現力豊かな弾き方のコツ、さらに合唱の発表会の準備まで、順序立ててわかりやすく解説しています。
また、保育園におけるピアノや歌の意義、保育者として大切にしたいことなど、ピアノ演奏にまつわる心構えも学ぶことができます。
今回は本書から、「PART1 「音楽表現」について考えよう!」の一部を抜粋して紹介します。「保育と音楽について考えてみよう」や「園の方針を理解しよう」など、ピアノに触る前の準備について書かれたパートです。
これからピアノの練習をしたい方の参考になれば幸いです。
◆著者について
今泉 良一 (いまいずみ りょういち)
日本児童教育専門学校専任講師。1984年生まれ。東洋大学大学院ライフデザイン学研究科ヒューマンライフ学専攻博士後期課程満期退学。(修士)社会福祉学。保育園や認定こども園などでクラス担任、主任保育士を務めたのち、2017年より現職。保育者養成とあわせて、保育雑誌などに記事を執筆中。著書に『0・1・2歳児の連絡帳 選べる書き方&文例集 potブックス』(チャイルド本社)などがある。
保育と音楽について考えてみよう
ピアノの練習を始める前に、まずは子どもたちの活動場面をイメージしてみましょう。保育中に、どんな音楽表現の場面が思い浮かぶでしょうか?
保育の計画立案は、子どもたちの姿を予測することから始まります。ピアノの練習より前に、まずは子どもたちが音楽表現に触れる場面にはどのようなものがあるかをイメージしてみましょう。
保育におけるピアノは、ピアノの技術のみを身につければよいわけではありません。日頃から、「子どもたちは、どのようなことに興味を示すのか?」「保育者はどのような環境を構成したらいいのか?」という視点を持つことが、結果的に保育におけるピアノの豊かさにつながります!
子どもが歌う場面
子どもは、うたを歌うことを好みます。保育者のピアノ伴奏に合わせて歌うことはもちろん、イメージをしてみれば、室内遊びの場面や散歩中にも自然とうたを口ずさんでいることなどにも気が付くでしょう。
子どもが楽器を演奏する場面
カスタネットやタンバリンなどリズム楽器を使って音を鳴らしたり、鍵盤ハーモニカやブームワッカーなどで曲を奏でたり。また、日々の演奏だけでなく、生活発表会などで保護者に向けてみんなで合奏を披露したり、運動会でマーチング(鼓笛)を披露したりすることもあるでしょう。
子どもと音楽表現のかかわり
しかし、子どもの音楽表現の場面は本当にそれだけでしょうか? たとえば「保育所保育指針」では「表現」の項目の中に、子どもたちが「風の音や雨の音」など、自然の中にある音に気付くようにすることで豊かな感性が養われると書かれています。
風も雨も、風速や雨量によって音が変わりますね。子どもたちがそんな音にも興味が持てるように、保育者も感性を研ぎ澄ましていきたいですね。そう、保育におけるピアノの存在は、そうした体験の連なりの中にあるのです。
また、ままごと遊びでボウルをカチャカチャと鳴らしてかき回す仕草をしたり、なわとびやかくれんぼの時に「いーち、にーい、さーん…」と、ふしをつけて数を数えたりする様子も、音楽的な表現に感じませんか? 他にはどんな場面があるでしょうか。考えてみましょう!
エクササイズ
子どもたちが保育の中で行う音楽的な表現活動には、どのようなものがあるでしょう?
大人のかかわり
三項関係という言葉を知っていますか? たとえば子どもがチューリップを見かけたとき、そこにはチューリップと子どもの一対一の関係があるのみです。しかし、そこに大人が「チューリップだね」と声をかけてかかわっていくことで、子どもは一対一の関係をこえ、共通理解やコミュニケーションなどを獲得していきます。
これは音楽についても同様のことが言えるのではないでしょうか。子どもたちと音楽の間に、大人がどのようにかかわっていくのかという視点を大切にしたいですね。
自分の苦手ポイントを知ろう
ピアノを弾くにあたって、「あー、だるいな」「めんどくさいな」と思うことはありますか? どんなところに難しさを感じるでしょうか?
ピアノに限ったことではありませんが、保育の仕事は多岐にわたるので、どれもこれもバランスよく実行しようしても、どうしても負担のあるものに関しては面倒で後回しにしてしまいがちですよね。
「つまらないこと」「分からないこと」はなかなか気分が上がらないもの。言い換えれば「楽しく」「分かりやすく」できれば、より行いやすくなります! これから少しずつ、なるべく分かりやすく説明していくので、一緒に徐々にピアノを楽しめるようになっていきましょうね。
まずは、自分がピアノの、どんな部分に苦手意識を持っているのかを把握するところからスタートです!
ニガテ① 楽譜を読むのが大変
ピアノは、「楽譜を読む」ことからスタートします(まれに聞いた音を弾ける人もいますが……)。子どもたちが、字が読めるようになると読書を楽しめるようになることと一緒で、楽譜を読むことに慣れてくると、ピアノを弾くことがもっと楽しくなりますよ! 楽譜の読み方は後ほど紹介するので、無理のないペースで覚えていきましょう。
ニガテ② 指が思うように動かない
たとえば、サッカー部でも合唱部でも、最初の練習は基礎的なトレーニングから始めますね。ピアノも同じで、自分の思い通りに指を動かせるようになるには、基礎練習が有効的です。とはいえ、独学だと何が基礎なのか、どう練習したらよいのか分からないかもしれません。本書でも練習方法を紹介していきますので、少しずつ身につけていきましょう!
ニガテ③ 緊張してしまう
ピアノを弾くことの難しさとして、「緊張してしまう」ということも要因の1つとしてあげられるかも知れません。たとえば、発表会や卒園式など保護者の前でピアノを弾く場面などでは、いつも以上に緊張しますよね。
緊張には「いい緊張」と「よくない緊張」があると思います。集中して弾くためにはある程度の緊張感が必要です。練習で上手に弾けるようであれば、本番前にはピアノの椅子に座るところからイメージトレーニングしておくといいでしょう。
逆に練習不足による緊張は、余計に慌ててしまって、ボロボロの演奏になるかも……。でも、自分で納得のいくまで準備しておけば自信をもって弾けることでしょう!
即効性のある「緊張しなくなる方法」はないかもしれませんが、たとえば「前日は勝負めし(かつ丼とか?笑)を食べる」とか「本番前にお茶を一杯飲む」とかなど、自分なりの“おまじない”を用意しておくのもいいかも?

園の方針を理解しよう
音楽活動の捉え方は園によって様々です。まずは自分の園の保育方針などをよく理解していきましょう。
保育方針は?
同じ音楽活動でも、園によって、どこに力を入れているか異なります。たとえば普段の遊びの中で音楽に触れる機会を多めに設けている園や、マーチングに力を入れている園、わらべうたを積極的に取り入れている園など。
また、キリスト教系の園や仏教系の園では歌われる曲も変わってくるかも知れません。保育方針によってもピアノの必要度が変わってきますね。
あなたの意見は?
保育には「ねらい」や「意図」が大切です。それらがないと、「ただ歌うだけ」「ただ弾くだけ」になってしまい、子どもの育ちに無意味な内容になってしまうかもしれません。
自分の園の保育方針を理解した上で、あなたはどんな音楽活動を取り入れていきたいと思っていますか? また、ピアノに対してはどのような意見を持っていますか? 自分の思いをまとめ、必要に応じて園の保育者たちと話し合ってみましょう。そうすることで、自分が練習すべき内容や目指すべき姿が、より明確になるはずです!
園の方針と楽器
伴奏ができる楽器はピアノだけではありません。園にある楽器はなんですか? グランドピアノ? アップライトピアノ? 電子ピアノ? オルガン?
私が勤務していた園では3歳以上児クラスの各保育室にアップライトピアノが設置してありました。また、ギターやアコーディオンなどピアノ以外の楽器で伴奏をする園もありますね。どんな楽器を備え付けているのかも、園の音楽に対する方針を表しています。一度、園内にどんな楽器があるのかを確認してみましょう!
担当者を確認する
行事などのピアノ担当は、あらかじめ全職員が割り当てられる場合と、ピアノの得意な職員が担当する場合とがあります。それも園の方針や慣習によるものが多いですが、全職員が意思統一ができているか確認してみるのもいいでしょう。

うたを歌うのはどうして?
歌うことの意味はどこにあるのでしょう? 子どもたちは、なぜ歌うのでしょう? 一緒に考えてみましょう!
人はどんなときに、うたを歌う?
カラオケでストレスを発散したり、学生時代に合唱を通して友達と感動をともに味わったり。うたを歌う背景は人それぞれです。いずれにしても楽しいから人はうたを歌うのですよね。
では子どもの場合はどうでしょう? 保育者の伴奏に合わせて子どもが歌う場面はすぐに思い浮かぶと思いますが、ほかにも散歩に出かけたときや、ままごと遊びで「カレーライスのうた」を歌ったり、お片付けの際に「おかたづけのうた」を歌ったりなど、うたは子どもたちにとって、とても身近な存在だと考えられます。
唱(とな)え歌として
それだけではありません。たとえば子どもたちは歌うときだけでなく、コミュニケーションの場面においても、自然な「ふし」や「リズム」をつけて、言葉を口ずさんでいます。
「あーそーぼー (かーしーてー)(いーれーてー) いーいーよー」(遊ぶとき)
「いーち、にーい、さーん」(数を数えるとき)
「もーういいかーい?」(かくれんぼのとき)
「いーけないんだいけないんだー せーんせーにいっちゃーおー」(注意するとき)
子どもはなぜうたを歌うのでしょうか?
私が感じることに、1つ目は「手のひらをたいように」「勇気100%」などの曲のように「自分を励ますため」というのがあるのではないかと思います。うたを歌うと気分が高まり、楽しい気持ちになりますね。
2つ目は、「一年生になったら」「バスごっこ」など、歌の主人公になれるからではないかと思います。
3つ目は、「おばけなんてないさ」「おもちゃのチャチャチャ」など想像の世界へワープできることが挙げられます。非現実的な内容を歌の中で味わえるのだと思います。あなたは、子どもはなぜ歌をうたうと思いますか?
このように、「なぜ?」という視点で物事を捉えると、一面的にしか見えてなかったものが、より幅広い視点で考えられるようになりますね。視野が広がることで、保育者のスキルもアップし、子どもとのかかわりも、音楽表現も、より豊かになることでしょう。
保育の中で歌う活動があるのはなぜでしょうか?
日本における幼稚園に関する単独の勅令として初めてのものである『幼稚園令』(大正15年)の保育内容にも、「唱歌」の項目が示されています。このように保育には常にうたが傍らにあり、子ども向けの新しいうたもどんどん作り出されてきました。
では、なぜ保育の中に歌う活動があるのでしょうか? 「子どもの表現の芽生えを促すから?」「自分の気持ちを表に現わす経験になるから?」先生たちで話し合って挙げてみましょう。
◆本書の目次
PART1 「音楽表現」について考えよう!
PART2 楽譜を読めるようになろう!
PART3 練習しよう!
PART4 表現力を磨こう!
PART5 音楽で遊ぼう!
PART6 保育者として大切にしたいこと
◆「翔泳社の福祉の本」のおすすめ記事
よろしければスキやシェア、フォローをお願いします。これからもぜひ「翔泳社の福祉の本」をチェックしてください!
