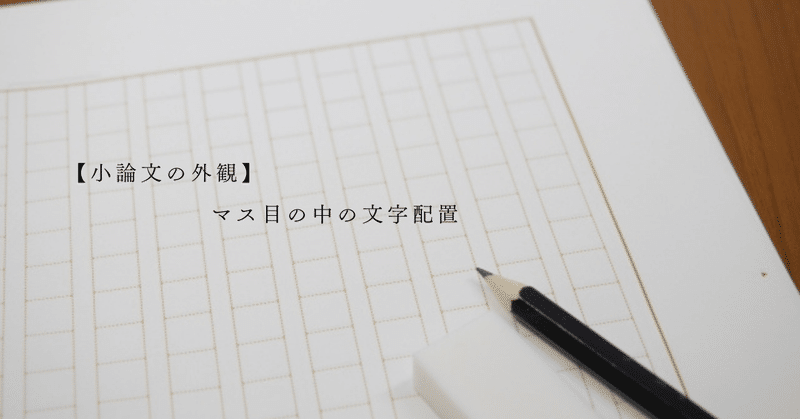
マス目の中の文字配置【小論文の外観】
アナログ形式の原稿用紙を用いる場合は、普段通りに書いていくというよりもそれなりにかしこまった形できっちりとした文字表記をしていく必要があります。そのため今回は原稿用紙のマス目に対してどのように文字を記入していくのかについて解説していきます。また、ただ単にきれいな原稿用紙に仕上げていくという観点だけでなく、制限時間、制限文字数が指定されている中での作戦としてどのように表記していくかについて詳しく説明していきます。
【1】 マス目の中で左寄せで書かない

手書きで書く以上、横書き原稿用紙の場合、左から右にペンを進めていきます。そのため、目先のことを思ったまま書いていく発想で、マス目に対して左寄りで文字を書いていく方がいらっしゃいます。基本的にデジタル文字の状態が最も読みやすい状態であり、その場合は当然真ん中に表示されるものですから、左寄せでも右寄せでもなく、やはり真ん中に書いて文字と文字の間のバランス、原稿全体のバランスを平行に保っておくのが好ましいですね。当たり前のようなことですが、実際にペンを走らせていくと、目の前の「書く」という作業に集中しすぎてしまい、左から左からどんどん書いていってしまうようですから、もう少し俯瞰で見て全体のバランスを整えるようにしましょう。
【2】 マス目の真ん中に小さく書かない

最近ではスマートフォンやパソコンを利用して文字を書くことが多くなり、鉛筆やペンを持たない習慣が身に付いてしまっているためか、正しい筆記用具の持ち方、握り方、走らせ方、圧力のかけ方がわかっていないような文字が多く見受けられます。添削指導をしている中で特にここ5年くらいでそのような事例が急増しているように感じられます。そのため特に鉛筆の場合、力の弱さからか文字が非常に薄くなっている状態も多く見られます。同様に、力強いしっかりとした文字を書くことができず、非常に小さく、できる限り手を動かさなくても書ける状態の文字を書く人が増えています。
文字が小さいからといってそれ自体が減点の対象になるわけではありませんが、文字が小さいことにより、さらにそれが薄い文字であればあるほど、採点者としても単純に文字が読み取れない状態になりかねません。眼鏡をかけたり虫眼鏡を使ったりして真剣に見れば必ず見れるような大きさの文字だとしても、そもそもそのように採点者に苦労をかけること自体が好ましくありません。失礼か失礼ではないかという以前に、論文を読んでいく中で採点者の頭の中が一時的に停止してしまうことを意味しますから、その方が受験者としてはよほど大きな問題です。
普段手を動かして書くことにあまり慣れていないとしても、意識的に自分の中で少し大きめの文字を書くようにしておきましょう。
【3】 マス目いっぱいに大きく書かない

近年は先ほどのように小さな文字で書かれることが多いわけですが、逆に細かい作業自体が不得意で、大きすぎる文字を書く方も増えています。大きな文字は小さな文字よりも読みやすいことが多いわけですが、大きすぎる文字を書く方は大半がマス目を超えてというよりもむしろマス目を無視したような形で自由に書き進める状態が多く見られます。
マス目はある意味で採点者が回答者に課す1つの制限でありルールであるわけですから、その指示にもきっちりと従うようにしておきましょう。その範囲の中で表現するように求められているわけですから、当然にその範囲を厳守しなければなりません。
【4】 マス目のどこにどの大きさで書くべきか

では実際にどの位置にどのような大きさで書くべきでしょうか。やはりヒントはデジタル文字(パソコン・スマートフォンの文字)にあります。おおよそデジタル文字の場合、すべてが枠の真ん中に配置されているわけではなく、むしろ「下寄せ」の状態で下線に沿って文字が進んでいきます。初めて英語のアルファベットの書き方を勉強した頃を思い出してみてください。英字の中でも特に小文字の場合、上に長く出ていたり(b, d, f, h, k, l, t)下に長く出ていたり(g, j, p, q, y)と上下に出っ張ってしまう中で、基準となるのは下線部分でした。それと同じ様な感覚で日本語の文字も下の線を基準として意識をしながら、漢字とひらがな・カタカナ、稀に英字や数字をバランスよく配置していくのが良いでしょう。特に最近はカタカナや英字、数字を用いることが多くなっていますから、そのバランスから考えても、下線を中心に意識した形で、マス目の面積に対して70%から80%程度の大きさで書いておくと良いでしょう。
【5】 なぜ90%ではないのか

【3】のように枠に対して100%以上で書くのは好ましくないとして、なぜ90%ではなく70%から80%なのでしょうか。それは次の【6】とも関連してきますが、小論文試験での制限時間を意識して、出来る限りスピーディーに文字を書き進めていくためです。
文字を大きく書くということは、それだけ大きく手を動かし、それなりの筆圧をかけて書いていくことを意味します。ごくわずかではあるものの、大きく手を動かして筆圧を多くかけていくことは、小さく手を動かし筆圧を少なくかけていくよりも時間を要します。1文字に対してはごくわずかの時間だとしても、全体で600字以上も書いていく小論文においてはトータルでなかなかの時間になります。また人間ですから書き進めていく中でも大きく手を動かすことで疲れも溜まってきます。それによってさらにスピードが落ちてしまうことになります。
ですから、マス目に対していっぱいに書きすぎず、だからといって採点者が目を細めるような小ささでもない、70%から80%程度で書いていくのが好ましいといえます。
【6】 速美書写法:スピーディ&綺麗に書くコツ

制限時間が決められている小論文試験において、スピードという要素は非常に重要です。ただし、それだけを優先し読めないような文字を書いていてはなかなか印象が悪いものです。印象が悪いだけならまだしも、文字が全く読めないようでは得点になりません。そのため、スピーディーかつ綺麗な文字を書いていく必要があります。一見それは相反する事象のように思われるかもしれませんが、ちょっとしたコツを意識して訓練していけば、スピーディーかつ綺麗な文字を書いていくことができるようになります。それが「速美書写法」です。
この速美書写法については下記の記事で詳しく説明しております。ご興味のある方はぜひご覧ください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
