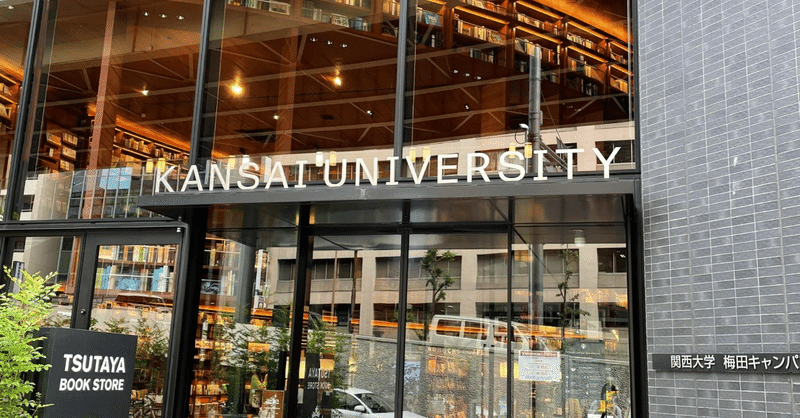
併願受験校を減らすべきでない5つの理由
私立大学の合否発表がほとんど終わり、国公立大学の後期発表を待ったのち、追加合格や二次募集が行われる時期になっています。
最近の受験傾向として、推薦や総合選抜で早期に合格を勝ち取る生徒が増える一方、私立大学は難化し、合否が3月後半まで確定しないというケースも増えています。
併願受験校の数を減らすトレンド
そうした厳しい状況にもかかわらず、近年は受験先を減らす生徒が増えています。
さすがに国公立一本というケースはまれですが、私立大学の併願先を2、3校で考えている生徒は決して少なくありません。
以前はダイヤモンド型受験などと言い、第一志望のレベルを頂点に少数、順当校を複数校、滑り止めを少数校受験し、最低ラインは確保するというスタイルが一般的でした。
しかし、近年はピラミッド型と呼ばれる形の通り、滑り止め校を受験しないケースが増えています。
確かにレベルの低い大学が受験者数の減少でボーダーフリー化していることがあるため、合格を簡単に勝ち取れると考える気持ちは分からなくはありません。
保護者の立場からしても、受験費用を抑えるために滑り止めを減らす感覚は理解できます。
ところが、それはリスクを背負った選択でしかありません。そこでここでは受験校は決して減らすべきではない理由を上げていきたいと思います。
併願受験校を減らすべきではない理由
1.試験は水物である
大学受験の一般入試の場合、国公立大学は共通テストと2次試験という2回の合計で、私立大学は筆記試験の1回の結果のみで合否を判定します。
国公立大学の場合は試験が複数回あること、共通テストの結果を受けて出願先を決定することもあり、結果発表で大きな波乱が起きることは比較的少ないでしょう。
しかし、私立大学の場合は基本的には一発勝負であり、問題との相性、体調、他大学の日程などでその結果は大きく変動します。
そのため、ここは楽勝だ、と思っていた大学に落ちて計画が崩れるケースが頻繁に発生します。
したがって、複数回の受験を確保し、想定しない状況に対応できる準備をすることはとても重要です。
2.試験の訓練の意味合いがある
大学入試を受験に際しては多くの想定しない状況が発生します。
遠方での実施、宿泊、試験地までの交通手段、試験場の環境など考えもしていないトラブルが発生します。
また、近年の高校生は遠方まで一人で出かけるという機会が少ないということもあります。
(これは都会よりも田舎の方が顕著です。子供だけで簡単に利用できる交通手段が少ないためです。)
第一志望の大学に向けて、そうした慣れない環境、状況での試験に際して予行演習としての受験は重要です。
また、本番の空気感を味わうことで、緊張に慣れる意図もあります。
加えて、国公立大学志望者の場合は、共通テスト後の中だるみを防ぐ意味でも、私大の試験を時期を分けて複数回受験することは効果的でしょう。
3.一般入試は偏差値の低い大学でも合格者数を絞っている
現在、多くの私立大学は定員数確保のために総合型選抜や推薦型選抜の募集人数や入学者に占める割合を増やしています。
(もちろん、適切なマッチングをする意味もあります)
そのため、必然的に一般入学者の割合が減少し、以前なら一般合格していた生徒が不合格になるケースが増えています。
これはいわゆるボーダーフリーと呼ばれる大学でも同様の傾向であり、かつては誰でも合格していた大学が確実にボーダーラインを引いているような印象を受けます。
(当然、総合型、推薦型選抜の基準は甘くなっていますが)
そのため、順当に合格できるだろうという大学と安易に考えて受験した場合、足元をすくわれることがあります。
そういった点でも、自分の滑り止め大学に関してもある程度は実力よりも下の大学もカバーする必要があるでしょう。
4.同日併願と受験料減免の制度を活用できる
受験校を増やすデメリットは主に日程と費用の二つの問題が考えられます。
日程の問題に関しては、私立大学の同日併願制度を利用すると一回の試験で複数学部を併願することが可能です。
関東の一部私立大学では学部ごとにしか試験を行わない大学もありますが、関西系の大学を中心に広がっている制度となっています。
また費用に関しても共通テスト利用入試の場合は個別試験よりも大幅に安く受験できます。また、併願制度による受験料減免制度のある大学も多く、受験する学部を増やすほど一回当たりの受験料は低下します。
5.追加合格の可能性が上がる
3.で触れたように、近年は一般入試の合格者数を絞る傾向が全国的に見られます。
そのため、入学者確定段階で誤差が出るケースが多発していて、3月末に受験者に追加合格の連絡が来ることは少なくありません。
こうした追加の連絡は試験ごとに出ているのか、まとめて不合格者に声をかけているのかは不明ですが、間違いなく試験を複数受験した方が追加合格になる可能性は向上します。
定員厳格化が緩められてはいますが、依然として定員超過に関するペナルティから一般合格者の数を制限している以上は、追加合格の数は今後しばらくは減ることは無いでしょう。
併願受験の数の目安
一般的には国公立大学志望者の場合は5校前後、私大専願者の場合は10校前後を考えて間違いない、という指導を私は行っています。
もちろん、単純に受験校数を増やせば試験のスケジュールが詰まってしまい、第一志望の対策がおろそかになる可能性はあります。
そうならないためにも、共通利用や同日併願などを上手く利用して、手厚い態勢で受験校を揃え、進路の選択を最後にできる状況で受験を終えるのが理想だと思います。
とはいえ、合格するかどうかは努力の結果だけではなく、運の要素も絡むことになり、実力や戦略だけでは解決しないのも事実です。
まずは現在の時点で合格や進学先が決まっていない受験生の幸運を祈りたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
