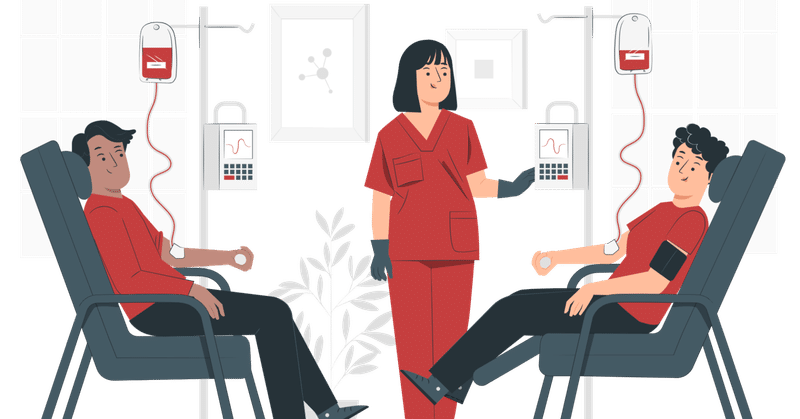
骨髄ドナー(骨髄提供)体験レポート
はじめに
有料部分やアフィリエイトへの誘導,患部の写真はございませんので,どなたでも最後までお読みいただけます。
一つの記事で完結した内容としています。
献血やドナー登録,助成金,保険等についてのURLを「参考」と「個人的な話」に貼っているので,興味のある方は先に目を通されて下さい。
提供日時・場所
ドナーのためのハンドブック(以下ハンドブック)より,提供日時・場所など,患者さんとドナーであるお互いが特定される可能性のある情報の掲載を禁止されていることから,それぞれの内容がわからないようなレポートとしています。
また,この注意から,参考とされる場合は最新の情報源として骨髄バンクのコーディネーターさんや骨髄バンク公式サイトを第一とされてください。
提供に関することを不特定多数の人の目に触れる媒体【テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、書籍等の出版物、SNS(ツイッター、インスタグラム、フェイスブック、ユー チューブ、ラインなど)、電子メール、SMS、ホームページ、ブログなど】で紹介するときは、提供日時・場所など、お互いが特定される可能性のある情報(写真・動画のほか、移植後の患者との手紙交換の内容も含みます)の掲載/公表を禁止し ています。 ※特定のグループや友人など公開先が限定される場合も含みます。
Ⅳ.ドナーと患者のプライバシーを守るために
2 情報の公表について
用語
確認検査から実際の骨髄採取と採取後健康診断までを含めてコーディネートと呼び,骨髄バンクからサポートしてくださる方をコーディネーターさんとお呼びしています。
また,レポートでは執筆時(2023年)のハンドブックに用語や情報を合わせています。
レポートの雰囲気
私が骨髄ドナーについて調査した際,コーディネートについて一気通貫して出来事を述べていくようなレポートが少ないように感じたため,ドナー選定の通知から助成金の受け取りまで淡々と出来事を述べていくようなレポートとしています。
飽きるかもしれませんが,ぜひ白血病や骨髄ドナーに興味のある方,選定されたが悩んでいる方の参考となればと思います。
本編

確認検査以降のスケジュール
1.ドナー候補者のメール
ドナー登録をしていた電話番号宛てのSMSに,ある患者さんとのHLA型(白血球の型)が一致したという連絡が届きました。
内容はスパムのような怪しさを感じるものでしたが,電話番号が骨髄バンクであることを確認し,案内に従ってWEB問診に答えました。
問診票は郵送でも届きますが,WEB問診で回答された場合,こちらからの返送は不要でした。
回答後,一週間以内に骨髄バンク担当者から電話連絡があると案内され,電話対応可能な時間帯を入力しました。
同時期にオレンジの封筒が届きました。
ただ,内容はドナー候補の通知でメールと同じものでした。
返信用封筒で返答してもいいですが,メールのURLでも返答してもいいと思います。
正直なところ,WEB問診を手書きで答えると辛い量です。
WEB問診(または通知)に返答すると黄色い封筒が届きました。
これはコーディネーターさんや調整医師さんについてのお知らせでした。
また,コーディネートが終わるまでは献血をしないように注意がありました。
ちなみに、骨髄ドナーの適合通知が来ているのに献血の依頼が同時期に来ることもあります。
2.親の同意と診察
コーディネーターさんから電話があり,そこで親の同意について簡単に確認がありました。
また,ここで病院での確認検査について日程を決めました。
私は電話から二週間後辺りの日程で診察を決めました。
事前にコーディネートについて質問を送れましたが,電話の際に交通費などについての質問は行いました。
電話から数日経った頃に,黄色い封筒で確認検査と面談日について案内が届きました。
確認検査はスケジュールにおいて始めの段階であり,この結果を踏まえて最終同意へと進んでいきます。
実際にコーディネートを経験された方のレポートやコーディネーターさんの話によると,コーディネートは患者さんの容態を優先して進められるため,通知が来た際や検査の段階では提供が確定しているわけではないようです。
最終同意の後でも中止となることもあるようでした。
確認検査日についての案内には,検査日と時間,場所,担当調整医師,持参物(ドナーのためのハンドブック・印鑑・本人確認書類)等が記載されており,交通費の請求に必要なものとして印鑑がありました。
実際には必要のない物もありますが,詳しくは下のセクションをお読みください。
3.確認検査
前日に電話で集合場所や時間,持ち物について確認がありました。
病院内では,まずコーディーネーターさんからコーディネートのスケジュールや提供方法,二種類の提供方法(末梢血幹細胞/骨髄提供)それぞれの副作用の内容やその実例等についての説明,検査結果の情報管理についての同意が行われました。
ハンドブックにある内容が基本だとは思いますが,コーディネーターさんの経験からお話しいただく内容は,自分が実際にコーディネートを行うことと関係無く非常に興味深い話が多かったです。
この際には,交通費をいただきましたが,郵便で受けた案内とは違い印鑑は不要でした。
タブレット上でのサインと申告で交通費をいただけました。
その後,身長,体重,血圧測定,医師による問診,血液検査がありました。
問診では,自身や血縁者の過去の疾病や手術経験等についての確認がありました。
コーディネーターさんからの説明でお話いただくことかと思いますが,自分のために問診時には正直に過去の疾病や心配ごとについて話した方が良いです。
説明から確認検査までは全体で一時間半ほど掛かりましたが,医師の問診待ち等で左右されると思います。
4.確認検査の結果
個人差はあるようですが,一週間程度で血液一般検査結果のお知らせ,血液一般検査結果報告書が届きました。
骨髄バンクの基準で末梢血幹細胞の提供基準,骨髄提供の基準に外れている項目があるか,問題はないかが示されています。
確認検査時に選択した採取方法(末梢血幹細胞/骨髄提供)と確認検査の結果により,コーデイートが続行されるかが決まります。
ただし,ここでも注意が必要ですが,続行となっても採取に繋がるとは限らず,数日から数ヶ月後かけて担当医師が採取実施を検討します。
5.ドナー選定の電話と通知
検討の結果,骨髄提供が決定されたことが電話で伝えられました。
その日に速達で郵便による通知も来ており,その内容は後述します。
電話では,これからの流れ
自分と親の最終同意面談
↓
(親が遠方の場合,遠方で親が最終同意面談を行うのも可能)
↓
健康検査
↓
自己血貯血1回目,2回目(骨髄提供の場合)
を確認し,最終同意面談の期日と入院日についてある程度決定しました。
上記の流れは前後入れ換えができず,自分と親が離れて最終同意面談を受ける場合,入院日や病院の受け入れ時間によっては非常にタイトな日程になりそうでした。
入院日はほとんど特定の日程で指定され,それに合わせて他の日程も決めていったので,人によっては電話から一週間後に最終同意面談行わなければならず,仕事や生活の日程が調整しにくい方は骨髄ドナーは難しいように思いました。
ただ、入院日数や入院のタイミングについては事前説明でコーディネーターさんからお話しいただくように,週末等できるだけ都合の良い日程になるようにはされていました。
また,後日連絡がありコーディネーターの変更がありました。
届いた通知については,黄色い封筒にドナー選定のお知らせ,海外渡航自粛についてのお願い,新型コロナウイルス・季節性インフルエンザを含む感染症についてというお知らせがありました。
ドナー選定のお知らせについては最終的なドナー選定について,また最終同意面談の案内がありましたが、基本的に電話で受ける説明と同様でした。
海外渡航自粛についてのお願いは、採取日の一ヶ月前からの海外渡航の自粛について理解と協力を求める文書でした。
海外渡航を行う場合は地区事務局へ連絡すること,帰国後に体調確認を行うこと,ウエストナイルウイルスに関する調査について書かれていました。
新型コロナウイルス・季節性インフルエンザを含む感染症については,新型コロナウイルス・季節性インフルエンザを含む感染症の疑いがあるような体調不良が見られたとき,また濃厚接触者に該当した場合や新型コロナワクチン接種の予定が決まった場合の連絡について書かれていました。
後日また通知がありました。
ただ,内容はほぼ確認検査の通知と同様で,最終同意面談日の案内や提供方法,日時,場所,担当調整医師,担当コーディネーター,本人確認について,骨髄提供に関する予定通知でした。
確認検査の時と同様に,最終同意面談の日程確認の電話もありました。
また,健康診断と二回の自己血貯血(骨髄採取の場合),採取に伴う入院の日程と場所の通知がありました。
すべて電話やメールで確認されたことですが,文書で改めて通知がありました。
6.最終同意面談
コーディネーターさん,弁護士さん,調整医師さんの立ち会いのもと,ハンドブックに沿って説明を受け,最終同意のサインと連絡先の記入を行いました。
全体として一時間半程でした。
弁護士さんや医師さんと同時に接する機会はあまり無いので緊張はしましたし,最終同意も頻繁には無い厳かな手続きなので堅苦しく感じますが,それほど任意で全身麻酔等の治療を受けることを再確認する良い機会でした。
同意書については一部控えとして受けとりました。
また,この際初めて印鑑を用いましたが,指印でも良かったです。
この際に骨髄採取量と自己血貯血の準備量についてより詳しい説明や,弁護士さんから個人情報の取り扱いについて通知がありました。
骨髄提供とあまり直接の関係はありませんが,「骨髄・末梢血幹細胞提供者由来の遺伝学的情報を含む臨床的意義のある情報開示に関するご意志の確認について」の内容が興味深かったです。
こちらは後日郵送で回答しました。
最終同意面談から数日後に封筒が届きました。
こちらには骨髄・末梢血幹細胞ドナー手帳,採取予定日と施設についての案内,交通費の請求書と郵送用の封筒が入っていました。
ドナー手帳は骨髄提供のしおりみたいな物でした。
案内は確認検査の案内などと同様の物です。
交通費の請求書と郵送用の封筒については,同意面談の際に以降の通院費や入院時の支度金(入院時の洗面具等の経費として入院時に受領又はこの請求書により請求できる経費であり,金額は5,000円)は別で請求するよう伝えられていたので,それを請求するための請求書と封筒でした。
最終同意面談まではその場で受け取っていました。
支度金は実際には現金支給でした。
7.術前検査・診察と自己血貯血
内科にて手術と自己血貯血・輸血について説明を受け,それぞれの同意書にサインしました。
また,この際に入院の申し込みや退院後検診の予定(確認検査等と同様に予定通知が後日届きました)を組みました。
その後,心拍や血圧の確認,触診を行い,骨髄提供の位置を確認しました。
ここで,血液検査,尿検査,胸部のレントゲン検査,心電図検査,肺機能検査,自己血貯血を行いました。
自貯血貯血は一度目だったので,点滴をうちながら400ml程度とりました。
同様の自己血貯血は手術までにもう一度行いました。
麻酔検診では全身麻酔と術前術後の流れの説明が行われ,同意書にサインしました。
最後に鉄剤を処方されました。
骨髄提供では1L以上採る予定だったのと自己血貯血がもう一度あったのでそのためです。
鉄剤で気分が悪くなった場合は点滴でいれることもできるそうでした。
自己血貯血等でこの日は三時間半ほど掛かりましたが,人によってはこれらを別日に分割して行う場合もあると思います。
8.入院と採取前日
手術の前日の午前に入院しました.
通常の入院と同じかと思いますが,血圧や身長体重の計測,酸素飽和度や脈拍と体温の測定,アレルギーや食事についてのアンケートを行いました。
これらは後日の入院中にも行っています。
その日の食事は病院食やコンビニの食事と水分を摂り,夜24時からは食事を採らないよう指示があったため水分のみを摂りました。
明日の手術のため,午前六時からは水分も摂らないよう指示がありました。
入院時の支度金として5,000円を受け取ったので,洗面具や食事で用いました。
前述の通り,この支度金は現金で受け取る場合と,後日交通費とまとめて請求する場合がありそうです。
シャンプーリンスーやボディーソープ,水2L,箱ティッシュ,お箸,ボディーペーパーで1,700円程度ですから,タオルやパジャマを家から持っていけば支度金は余るぐらいだと思います。
また,この日は採血も行いました。
以下の内容は、これまでの内容よりも個人の状態や病院によって違いが大きいと思います。
特に採取部の痛みとその対応はかなり違うと思います。
また,なんとか記憶に残っていることだけを書いていることにご注意ください。
9.採取当日
私は午前八時過ぎから手術があり,朝は六時頃に起床し,七時頃に前日の排尿とお通じの回数確認や酸素飽和度と体温の測定を行い,手術着に着替えました。
八時頃に病室を出発し,11時頃には病室に戻りました。
手術では仰向けのまま血圧測定等を行い,点滴を打ち,マスクを付けたあたりで麻酔により意識は無くなりました。
手術後は採取部に分厚い湿布のような止血があり,シャワー浴ができませんでした。
場合によっては医師の方から防水カバーを着けて頂いてシャワー浴ができるかと思いますが,そのままでも洗顔や歯磨きぐらいは無理せずできました。
病室に戻ってからは酸素投与のマスクと心電図を付け,点滴を打ったままで一時間おきに体温と呼吸,血圧の確認,採取部の痛みや喉の違和感の確認を行いました。
一時間後あたりには採血をしたように思います。
自分は麻酔のためか14時まで上記の確認以外の時間は寝ていました。
体のだるさが強く,夕食までスマホをいじる程度の作業もできませんでした。
手術日の夜にこれらの記録を取りましたが,正直なところ後日にはほとんど記憶に残っていませんでした。
昼食は無く,パンと牛乳を14:30頃に取ることができました。
夕食はありました。
15:30頃に点滴は外れました。
この日は着替えることも可能でしたが,心電図を繋げたままの状態では看護師さんのサポートが必要でした。
トイレは自力で行けましたが,採取直後の買い物は近場に売店がないと難しいと思いました。
なので,事前に食料や水分関係は買っておくか,面会で人を呼ぶと良いと思います。
また,トイレを含め何かしら術後に行動をするときは看護師さんに確認をしたほうがいいと思います。
水分は大きなペットボトルとコップではなく,小さいペットボトルを買っておくと自力で飲みやすいと思います。
心電図は19:30ごろまで付けていました。
採取時や採取後に痛み止めを点滴していましたが,採取部に痛みが出れば別で痛み止めの錠剤をもらえるようでした。
私は痛みが出ず,心電図を取ってからは病室を出て飲み物を買いに行くぐらいには動けました。
10.採取日の次の日
この日はほとんどすることがなかったです。
採取日のお通じの回数や血圧と体温測定,酸素飽和度の確認など,基本的に通常の入院と変わらないと思います。
また,採取後の喉と採取部の痛みや違和感についての確認,麻酔について皮膚や気分に異常はないか確認がありました。
これらの検査が数回ありました。
9:30頃には分厚い止血を取って絆創膏を貼りました。
傷跡は赤い点が二つ採取部にあるだけで,ほとんど気にならないものでした。
採取部に気をつけながらシャワー浴が可能でした。
シャワー後に消毒をして絆創膏を貼りましたが,当然腰に貼るのは難しいです。
看護師さんに貼ってもらうと良いと思いますし,そう指示されることもあると思います。
また,21時頃には採取部の痛みは前かがみになったり腰を捻っても痛むこと無く,押さえれば少し痛むぐらいでした。
一日中その程度だったと思います。
11.退院日
採血や血圧測定,酸素飽和度と体温の測定がありました。
希望したわけではありませんが,痛み止めの錠剤を頂いて退院しました。
交通費は後から請求できるので,無理せずタクシーで帰ると良いと思います。
採取日を週末に調節すると公共交通機関が休みだったりするので,退院日の移動手段はうまく調整するとよいと思います。
もちろんですが,これまでの入院費は骨髄バンクの負担となっています。
12.退院日の次の日から数週間後まで
採取部用の消毒と絆創膏をいくつか頂きましたが,退院した次の日の夜には付けなくなりました。
採取部の痛みは動き回ると痛い気がする程度で,押さえない限りは気になりませんでした。
ただ,リュックを背負うと当然押さえられるので痛いです。
体力や気だるさは数日入院したり病み上がりのときと同じ程度だったので,入院前と変わらずすぐに活動するのは難しいと思います。
特に立ち仕事は辛いと思います。
二日後も状態は変わりませんでした。
一週間後辺りまでは強く押さえると痛いぐらいで,通常は全く痛くありませんでした。
二週間以上経つと押しても痛くありませんでした。
13.退院後検診
退院してから三週後辺りに退院後検診として採血と検尿,採取部の痛みなどの状態確認を行いました。
私の場合,骨髄移植前と比べて血色素(ヘモグロビン)量がまだ低く,息があがりやすい状態と言われました。検診の二日前に2km程度のランニングをしていましたが,言われてみればそのような気がする程度で,日常に支障が出るほどではありませんでした。
14.助成金の受け取りと交通費請求
通院等の証明書類として,骨髄バンクから採取前の健康診断や自己血貯血、入院の証明書(骨髄バンクの判子があり,氏名やそれぞれの日程,病院の場所が書かれた一枚の書類)を頂きました。
これらの証明書類 + 最終同意面談の証明書で助成金の限度に達していたので,退院後検診の証明書は頂きませんでした(こちらからそう伝えたわけではありませんが,採取後検診前にコーディネーターさんに証明書類の件を伝えてからすぐに書類が届いたので結果的にそうなりました)。
助成金を超えるような証明書も頂くことはできますが,助成金の限度額を超えるのであればあまり意味はないと思いますし,助成金の申請に期限があるので採取後検診が遅くなるのであれば証明書類は待たない方がいいと思います。
助成金をもらわずに保険で手当てをもらう方は採取後検診が適用内であれば申請すると良いと思います。
コーディネート中は,何が助成金の申請に必要な書類なのか分かりにくいですが,私は最後に届いた証明書と最終同意面談で届いた書類(実際は引き継ぎの関係か最終同意面談の証明書が無く,再送していただいた)のみで十分でした。
手書きで日付と時間が記入された証明書で,申請時には他の資料と区別がつきやすいと思いますが,コーディネート中は書類が多く分かりにくいです。当たり前のことですが,基本的に書類は捨てない方が良いです。
証明書と申請書を役所に提出すると,一ヶ月半後に決定通知が届き,そこから一月弱後に口座へ送金されました。
助成金申請は個人の手続きなので,通常の役所手続きのように明確な案内も無く,書類不足や手続きミスがありましたが,役所側のミスだったりしたので申請期限は延期していただきました。
郵送でもできそうだったので時間がない場合は確認してみると良いと思います。
役所で対応してくださった方が仰るには,証明書が一枚の場合と,上記のように分割されている場合があると言うことでした。
これらも自治体によることだと思います。
最終同意面談あたりで受け取った交通費の請求書に最終同意面談よりも後の交通費と口座を記入し,郵送すると,一ヶ月近く後に入金されていました。
15.骨髄提供後の献血と通知
骨髄提供を行ってからは,半年間は献血が出来ません。
これは献血RTAをされている方にとって非常に大きなロスとなるため注意が必要です。
私にとってはこれが骨髄提供の一番大きな難点でした。
また,提供から二ヶ月半ほど経った頃に骨髄バンクから通知がありました。
通知には提供への感謝や次回の提供まで少なくとも一年の保留があること,一年が経過後はドナー登録が継続となること,またDLIの説明とその同意の確認(意思がない場合はその旨を添付された書類で連絡する)が含まれていました。
三ヶ月後には「採取後・3ヵ月アンケートのお願い」が郵送されました。提供者となった動機や,コーディネートにおける説明が十分であったか,骨髄提供前後や提供時において感じた印象,現時点での採取部の痛みや体調等を解答するアンケートでした。五枚程度のアンケートであり,WEB回答の案内はありませんでした。返送用の封筒も送付されていました。
16.感謝状
地方や所属によっては,骨髄提供からしばらくして厚生労働大臣より感謝状が郵送される場合があるようです。
参考
助成金
地方により助成金は異なりますが,基本的には「検査や入院を含めてコーディネートに必要だった日数(証明書類が必要)× 二万円」(最大14万)が申請によって得られるようでした。
保険
大学の保険(学研災と付帯学総)は骨髄ドナーの入院は対象外のようでした。
一般の保険商品でも対象のものがあるようです。内容も基本的に「入院給付金日額の20倍程度を骨髄ドナー給付金として支払う」ようなイメージでした。
注意として,骨髄ドナーの入院に適用される保険に入っていると自治体の助成金は基本的に無くなるようです。
ご自身が加入されている保険について調べると良いと思います。
個人的な話
ドナー登録のタイミング
献血を普段からしていたので,その中で登録をしました。
献血で登録される情報を骨髄バンクで管理し,それを元にドナー選定も行われるようなので,登録は非常に簡単でした。
ドナー登録のきっかけ
拝聴していたラジオの中で白血病で亡くなられた方がいらっしゃったことから,普段の献血(成分献血)の一環として登録しました。
骨髄提供のきっかけ
骨髄提供においては,ドナーにとってコーディネートのスケジュールや手術でリスクを伴いますが,そのリスクを考慮しても骨髄提供を行った考えを記述します。
自分自身がこれまで健康であったことは,その状態を保てるように産み育ててくれた両親や親戚,周囲の方々のお陰であり,それを維持しようとしてきた自分の結果ではありますが,ほとんどは運が良かったのだろうと考えていました。
骨髄提供はその運を人と共有できる機会であると思い,喜んでお受けしました。
終わりに
検査や入院時の待遇はコーディネーターさんや病院によると思いますが,私の待遇は驚くほど良く,助成金を骨髄バンクや病院に寄付したいと思うほどでした。
自治体によっては保険に入っていると助成金が出ないというのはどうかと思いましたが,正直これがどうでも良くなるぐらいに病院の方々は良くしてくださいました。
ハンドブックによると,一人の患者さんに対して複数のドナーが選定されるようですが,その中で健康状態やスケジュール,本人と家族の意思から実際に骨髄移植を行うかが検討されるようです。
血縁者以外から移植を受ける患者さんの内半数程度が実際に移植に繋がっていることを考えると,選定されたドナーの内移植まで進んだ方は少ないのだと想像できます。
これまでをお読みいただいたらご理解いただけるように,骨髄移植はリスクを伴ったドナーの善意に依った手術であり,どれだけ善意があってもドナー選定から移植まで進まなかった方々もいらっしゃいますし,(最終同意面談までなら)途中で辞退された方々が責任を感じる必要は無いと思っています。
このレポートを読んで「骨髄提供って面倒くさそう」と思わせてしまったのではないかと気がかりですが,ドナー選定者を増やすためにドナー登録は気軽に行って頂ければと思います。
