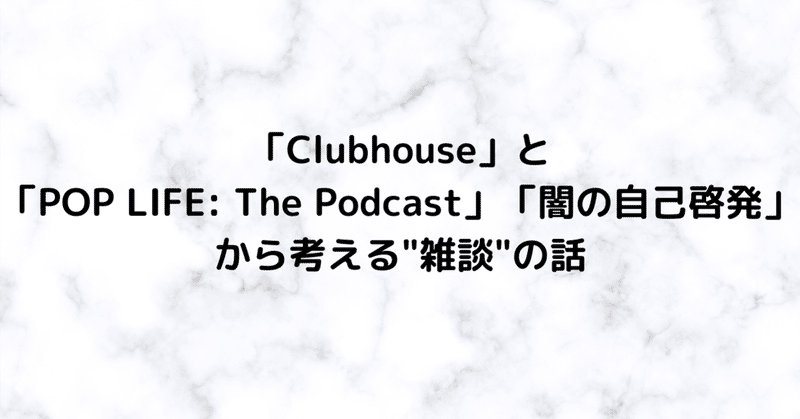
【2021/1の記憶②】「Clubhouse」と「POP LIFE: The Podcast」「闇の自己啓発」から考える"雑談"の話
先月の興味深かった記事をもとに、あえて少し時間を置いて振り返り、考えをまとめてみる企画。音楽やIT、テクノロジーなどなどの記事をベースに、ジャンルを横断した内容を目指す。
2021年1月、「Clubhouse」の衝撃
2021年1月に起きた大きな出来事の一つに、音声SNS「Clubhouse」が爆発的流行が挙げられるでしょう。そのブームのスピードはすさまじく、日本では、1/23にβ版が運用開始され、その5日後の1/28にはAppStoreの「無料アプリ」ランキングのトップになっているほどです。
Googleトレンドを見ても、1/23からの爆発的流行の具合が見て取れます。

「Clubhouse」の流行の要因や、今後どうなっていくかみたいな話もしようかとは思いましたが、それはそこかしこで行われていますので、ここでは辞めておきます。正直個人的にもアプリを使ったことがないので、あまり語るべきではない気がします。
しかし、一つだけ確実に言えるだろうと思っていることは、"雑談"というキーワードが、重要な要素を占めているということです。以下の記事でも、ここまで注目を集めた要因の一つとして、"コロナ禍で失われた“雑談”への飢え"が挙げられています。
コロナ禍で"雑談"の機会が大きく減ったことは確実で、ビジネスの場でも、"雑談"の意義が見直されつつあると感じています。
個人的にも、"雑談"のような会話からこそ、創造的な発想が生まれると感じています。テキストでのコミュニケーションでは、良くも悪くも考えすぎてしまいます。考えすぎずに、自由に、楽にアウトプット出来る場としての"雑談"には大きな可能性を感じます。"雑談"に、価値を見出しすぎるのは、そういうものでもないので良くないと思いますが、それでも、"雑談"には未来が詰まっているように思えます。
2つのコンテンツに見る"雑談"の可能性
ここでは、もう少し深く"雑談"について考えてみるために、最近自分が楽しんでいる"雑談"を二つ紹介します。
一つ目は、ポッドキャスト「POP LIFE: The Podcast」です。2019年2月にスタートしたSpotifyのオリジナルポッドキャスト番組で、田中宗一郎と三原勇希がホストとなり、毎回ゲストを迎えて、音楽や映画などなどのカルチャーを中心に、縦横無尽に語るというコンテンツです。
この番組の面白いところは、自ら“超・雑談形式”と称しており、台本なしで、自由に出演者が語っていることです。聴けば分かりますが、レジュメはあるようですが、その場その場の雰囲気で進んでいく会話は、いわゆる雑談のようなゆるさに加えて、大抵予想だにしていない展開となっていくというはらはらとした緊張感もあります。
自分自身、聴き始めたのは半年前ほどですが、ポッドキャストという形式と"雑談"の相性の良さに驚きました。特に音楽の話って、なかなか聴く機会がなかったと思います。テキストとなるとインタビューか、もしくは重厚な分析。そことは別の軸で、音楽の話を聴く場としてのポッドキャストは、音楽体験を豊かにしてくれています。音楽のポッドキャストは他にも「TALK LIKE BEATS」などもあり、いつも楽しみにしていますが、どちらも結構深く音楽の話をするので、もっと浅く、軽く"雑談"する番組も面白そうだなと思います。日常生活を考えれば、音楽の話をするときは、まさしく"雑談"だと思いますから。
「POP LIFE: The Podcast」については、以下の記事で、田中宗一郎本人が語っています。とても興味深いので是非。
二つ目は、1/21に発売された『闇の自己啓発』という本です。この本は、江永泉が主催している読書会「闇の自己啓発会」の内容をまとめた以下のnoteが元となっています。
ここで語られる内容は、どれもこれも、一見すると分かりやすいものではなく、これが"雑談"か?とも思いますが、SF作家の樋口恭介氏による書評にもある通り、これは確かに"雑談"だと思います。ただし、それは異常な濃度のものですが。
雑であること。予定調和を拒否すること。それが本書を貫徹する態度であり、雑談という生命を生み出し続ける四人の話者たちに、あらかじめ共有された思想である。
加えて、ここでは"雑談"の先の可能性も感じるエピソードがあります。それは、この読書会の記録の作成方法にあります。以下の記事によると、読書会の記録にボイスレコーダーが使われることはなく、記録されるのは言葉の断片のみ。そこから、後日、当日の会話が再構築されていくというのです。
加筆と追記は新たな加筆と追記を呼び、収拾のつかなくなったテクストは肥大と変形を重ね、あの日に起こったはずの、出来事としての読書会からかけ離れた、異形のテクストが生成された。
"雑談"について、正確な記憶が残っているのは稀でしょう。そういえば、あの時こんな話をしたような気がするな、ぐらいの記憶がほとんどな気がします。いやむしろ、話したことすら忘れることがほとんどかもしれません。しかし、それは"雑談"したことが、なかったことになるわけではありません。昨日の、あの"雑談"は、まさしく「闇の自己啓発会」と似た形式で、記憶として、経験として、堆積され、それは非常に長いスパンを経て、"なにか"に繋がっていくのだと思います。
これからの"雑談"
紹介した二つの"雑談"は、それ自体がコンテンツとなりえる、価値がある"雑談"です。しかし、改めてちゃんと気を付けておきたいのは、"雑談"に価値を見出すことばかりが正解ではないだろうということです。記憶の彼方に飛んで行ってしまうような、言ってしまえば無駄な時間と化した"雑談"だってあります。我々の"雑談"の大部分は、そのような無駄な"雑談"です。この"雑談"がどのような役割を担っているのか、改めて考える必要があるでしょう。
「Clubhouse」に話を戻すと、今は有名人の会話を聴くツールとしての側面が大きそうですが、その手軽さは、そのような無駄な"雑談"をする場として、適しているんじゃないかと思っています。それは、以下の記事で「常時接続のSNS」と表現されていることとほぼ同義かもしれません。
このコロナ禍を経て見直されつつある、"雑談"。2021年は、2020年の経験を経て、さらに違った視点・観点、もしくはより本質的に"雑談"が語られ、またその先を見る試みが多くなされるのではないか、と個人的には考えています。自分も引き続き考えてみたいと思います。
"雑談"とは何か。その先には何があるのか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
