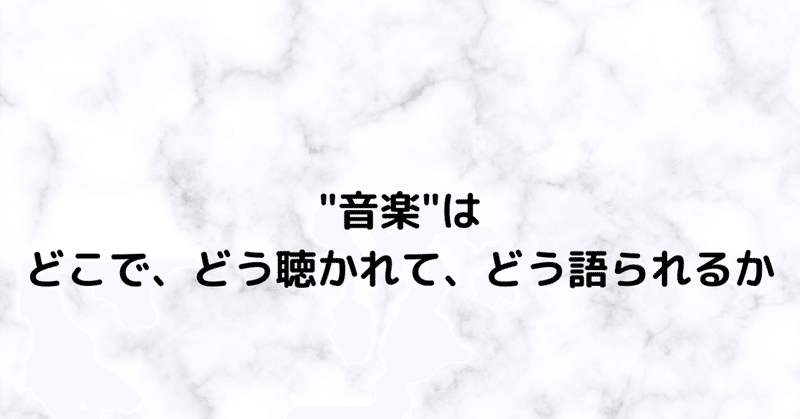
【2021/1の記憶⑤】"音楽"はどこで、どう聴かれて、どう語られるか
YOASOBIの音に関するツイートが、色々と物議をかもしましたが、自分としても考えさせられるものでした。
このツイート自体にどうこう言うつもりはないのですが、"音圧"ってなんでしょうね。なかなかまだ分からないです。確かに言っていることは分からなくもないです。そんなに面白い音ではないとは思いますが、それは"ショボい"のか、そこが世間での許容云々と関係があるのかはまた話が別なのだろうと思います。
話はさっぱり変わりますが、最近初めてまともなスピーカーを買ってみました。Twitterで話題になっていたので、ブラックフライデーでのセール時に思い切って買ってみました。
先日、3か月ほど待った末に、漸く届いたので、さっそく設置して聴いてみましたが、流石にそれなりの値段するだけはありますね。音がくっきり聴こえますし、音量を絞っても一つひとつの音が潰れずにしっかり届く印象です。左右に配置する形のスピーカーは初めて買ったので、立体感ある音像にも感動を覚えました。
ただ、やはりこれで失ったものもあるなと思っています。それは普通の人と同じ音質で音楽を聴く機会です。今まで適当にスマホやPCで流していた音楽も、すべてこの良いスピーカーを通した解像度の高い音楽となることで、何か見えなくなったものがあるように思っています。
この感覚は、言うまでもなく、ただの自分の思い込みです。そもそも外出時はAirPodsで音楽を聴きますし、たまたまTVから流れてくる音楽は、今までと同じ解像度です。そもそも、元々AirPods以外で音楽を聴く機会など大して多くなかったはずです。
こんな話もあります。おっしゃる通りだと思いました。
ーーあと、いわゆるAKB48を中心にした女性アイドルシーンに関しては、秋元康さんの影響力が強いというのはあるかもしれないですね。僕は直接インタビューで聞いたことがあるんですけれど、秋元康さんは音域に関しての持論があって。原体験が鹿児島の漁港のスピーカーだ、と。
後藤:僕もその話、聞いたことがあります。トシちゃん(田原俊彦)ですよね。
ーーそうそう。田原俊彦の「NINJIN娘」が鹿児島の漁港の割れそうなスピーカーで鳴ってるのを聴いて「これがポップスなんだ」と実感した、と。だからAKB48の制作でもエンジニアとかディレクターに「いい低音が鳴ってるでしょう」って言われると僕は全部下げるんだ、って言っていた。
後藤:それに関しては明確な反論が一個だけあって。今や漁港のスピーカーで音楽を聴いてる人はほとんどいないんですよ。鹿児島の漁港であっても、今の人はiPhoneにイヤホンで聴いてるから。もちろん、かつてはそういう時代もあったかもしれない。80年代にはラージスピーカーとラジカセを両方使ってチェックしていたと聞きました。でも、今はそういう時代じゃなくなってきちゃった。
ーーですよね。安価で高音質なイヤホンも増えたし、ポップミュージックの最終的なアウトプットのあり方が変わってきた。
後藤:そうです。回線の速度によっては解像度が低いかもしれないけれど、僕らがスタジオで聴いてる音と、音域のレンジがかなり近くなりましたね。だから、逆にヘッドフォンとかイヤホンでトラックを作ってる人の方がフラットな音響を獲得してて、バンドがスタジオで録るよりも音がよかったりする。特に日本だったら、ヘッドフォンでやってる子達が先に革命を起こしてるんじゃないかな。僕らは遅れてたんです。まずリスナーとしての自分がそれに気付いた。Spotifyで聴いたら違いがわかるわけで。「あれ?」みたいな。ひょっとしたら、みんな同じようにハッて気付いたのかもしれないけど。
なので、自分が上に書いたことは、やはりただの勘違いなのだと、自分でも思うのですが、ここには重要な視点が残っているように思えてしょうがないのです。
例えば、YOASOBIを良く聴くような人たちは、どのような環境で、どのように聴いているのでしょうか。YOASOBIもTikTok発と表現されることが多いですが、TikTokのヘビーユーザーは、どのような環境で、どのように聴いているのでしょうか。音の解像度ではなく、このような場面の解像度を上げて考えることは、今後の音楽の在り方を考えるうえで、何か興味深い視点となりえるのではないかと思っています。
こんな動画も気になって観てみました。
ツイートの内容で言わんとしていることには賛同したうえで、レコード会社がこの音を認めて世に出していること自体には疑問があるということで、おっしゃっていることはその通りだなぁと思いつつも、やはり何かすっきり来ないのが正直なところ。
常日頃思うのですが、”音楽"を言葉にすると、零れ落ちていくものが多すぎる。"音圧"という言葉一つとっても、人それぞれの捉え方、感じ方があります。それを言葉にすれば、そもそもの感じ方がそれぞれなのに、さらに解像度が下がってしまうのはしょうがない。これが"音楽"を語る時の難しさだなと思っています。
しかし、だからこそ、"音楽"をいかに語るか、についてはまだ可能性があるようにも思います。
音楽ライターの方たちのように深く音楽を分析して、的確に言葉にすること。友達と適当に好きな音楽について、あれが良いとかあれは良くないとか話すこと。その間にある、"音楽"の語り方。ここには可能性があるのではないのでしょうか。具体的なことは、全く言えません。ただの感覚です。でも、そういう視点を持って、語りが出来るようになれたら、面白いんじゃないかなぁと思っている、今日この頃です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
