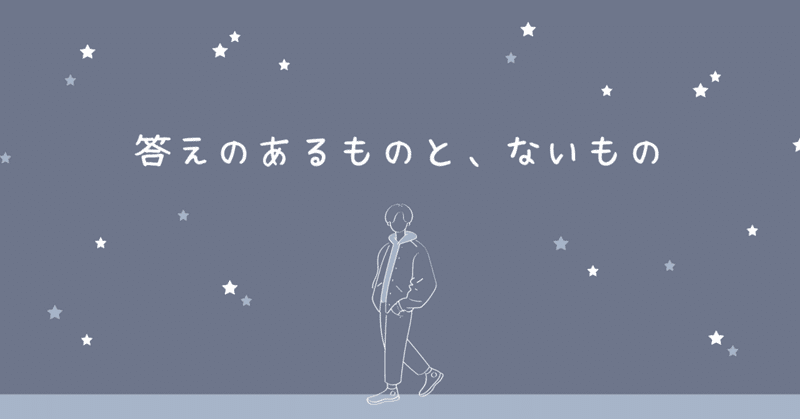
答えのあるものと、ないもの
学生時代、答えのある科目が好きだった。
解を求めるために試行錯誤するのが、難解なパズルを解いているようでとにかく楽しくてたまらなかった。我ながらクレイジーなほど片っ端から解きまくっていた。
逆に、明確な答えのない科目はあまり好きではなかった。
曖昧で、よくわからなくて、興味が持てなくて、その面白さがまったくわからなかった。
しかし不思議なことに今の僕は、明確な答えのない”解釈はご自由に”といったもののほうが好きだ。
映画や本でもそう。
派手なアクションものや、謎を解くもの、至るところに張り巡らされた伏線を回収していくものよりも、ただ人が生きているというだけの(別に人じゃなくても、生きていなくても良いが)、取り立てて何にも起こらないような話が好きだ。
こちらの心境次第でどうとでも取れるものや、最後まで観てもはっきりとした結末が描かれないような、読み手の想像力に任せるような話を好んで選んでいる。
音楽の聴き方も変わった。
ただ”聴く”ようになった。音楽をシンプルに”感じる”ようになったと思う。
誰かの(時にアーティストご本人のものであっても)詳しい解説や、込められた想いや背景などの情報にそれほど惹かれない。
ただ、いいなと思ったら聴いている。それを何度も聴いて、勝手に空想している。
答えのあるものばかり好んでいたはずの僕は、いったいいつからどうしてこうなったのだろう?実はよくわからない。
しかしなにもこのような作品に限ったことではないが、僕は色々なものに対して、わからないことをわからないままにしておくのもいいんじゃないかと思っている節がある。
全てがはっきりしてしまったらそれはそれでつまらないのかもしれない、と思うのだ。
そんなことを思いながら、今もぼんやりとイヤフォンで音楽を聴いている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
