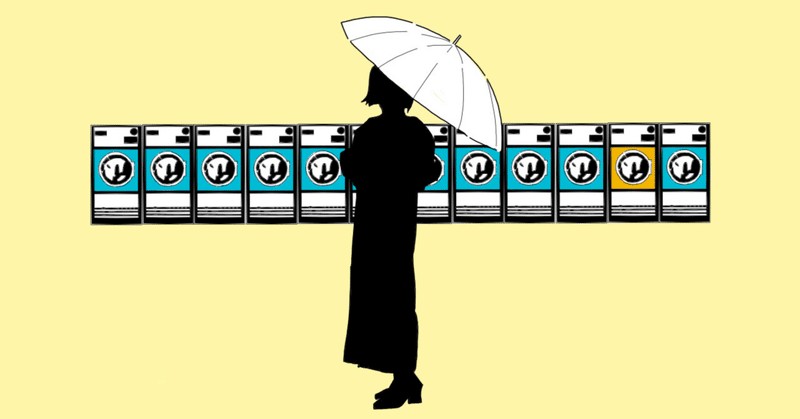
【ピリカ文庫】可逆性セレナーデ弍號機
深夜だと言うのに、コインランドリーには人がいた。
四車線の大通りに面したガラス張りの店内、中央のベンチに女性が一人座っている。洗濯が終わるのを待っているのだろう、傍らに大きな袋を置き、スマートフォンで動画を見ているようだった。
この時間なら誰もいない、と高を括っていたところ、失敗した。今から他の店舗に行こうにも、時間がかかる。何より外は雨。入ってきた扉側、無数の水滴が張り付いた全面ガラスを見やり、これ以上は勘弁、と心が折れた。
仕方がない。やるしかない。
私は濡れた傘を傘立てに入れ、手持ちのミニトートを両手で抱く。ドラム式洗濯機の透明な円がタコの吸盤のように並ぶ中、できるだけ女性と離れた位置にある一機を選び、手前まで歩を進めた。
トートの口を開ける。白いビニール袋に詰められた、小さな膨らみ。片手を中に入れ、縛り目を指で解くと、泥に塗れた息子の服が顔を出した。
ざりり、と罪悪感が胸を引っ掻く。やるしかない、そう決意した直後だと言うのに、容易く揺れる自分が悔しい。しかし、公共の場でこんなものを洗う、その非常識極まりない行動を思うと、やはり自責の念に駆られてしまう。
どうして、誰のせいでこうなったのだろう。
雨続きの中、いくら午前中に晴れ間が見えたとは言え、ぬかるむ足場で外遊びをさせた保育園か。
節操なく水溜りに飛び込み、遊び回った無邪気な息子か。
それとも毎晩帰りが遅く、育児や家事に参画できていない夫か。
黒い染みが心に拡がっていくのを感じ、慌てて思考を打ち切る。いけない、他の誰かや何かを責めては。
誰が悪いか。決まっている。
責任を放棄した、この私だ。
泥や砂をそのまま入れ込んでは、洗濯機の故障に繋がる。洗面台にお湯を張り、何度も何度も揉み洗い。際限なく出てくる汚れに挫けず、濁った水が透き通るまで、それを続ける。
そういうものだとわかっていたし、幾度もやったことがある。だけど、今夜はできなかった。ようやく寝かしつけが終わり、散らかった部屋、積み上がった洗い物をやっつけ、あぁそう言えばと服の存在を思い出したときには、もう駄目だった。そこから手を動かし、砂汚れと対峙する気概が、どうしても湧かなかった。
いっそコインランドリーでやっちゃえばいいよ。
息子と同じクラスのママ達。お迎えのとき、自然と聞こえた会話の断片が、甘い響きを持って脳を過った。家の洗濯機だと壊れちゃう。いっそお金で解決を。身勝手な、と嫌悪を覚えたはずのそれが、魅惑的なアイデアに思えた。
息子を一人残すわけにはいかない。夫が帰って来るのを待ち、ろくに事情を説明せぬまま、入れ違いで外に出た。真夜中、傘を差し。冷静に考えれば、こちらの方が時間も労力も高コストであるところ、しかし、冷静にはなれなかった。とにかくこれ以上、手を動かしたくない。働かされたくない。その一心で突き進んだ。
そんな暴走する思考の片隅で、やはりこれはまずいのでは、と警鐘を鳴らす自分もいた。マナー違反が過ぎる。誰かに見咎められでもしたら。煌々と光るガラス張りの店舗にたどり着く頃には、「やってしまえ」と「やってはいけない」が同じぐらいの勢力を持ち、胸の中でせめぎ合っていた。
そして、今もなお。
こうして洗濯機を前にしながらも、葛藤は止まず、動き出せない。
ここまで来て、こんなところで、一体私は何をしているのだろう。
つん、と鼻の奥に痺れるものを感じ、慌てて目を瞑る。息を止め、溢れ出ようとしてくるものを堪える。
ほんの数ヶ月前までの日々が恋しい。
私はまだ育休中で、夫の仕事にも余裕があった。日中は息子と公園に出掛け、お昼寝の間に食事を作って。晩御飯には三人揃い、お風呂は夫と交代で入れた。
職場復帰し、夫の部署異動があったこの春から、そんな余裕はとんとない。時短とは言え、私だって働いている。その隙間に息子の世話や保育園のあれこれ、家の作業を詰め込んで。不安やトラブルがあったとしても、残業続きの夫とは相談できる暇がない。話せるとしたら週末だが、最近はお互い疲れ果て、苛立ちをぶつけ合うことが多くなってきた。
環境の変化に翻弄され、それでも時は待ってくれない。
息つく間も無く過ぎゆく日常に、身体も心も追いつかない。
恋しい。
平穏を味わえていたあの日々が、恋しくて仕方がない。
「あの」
ふと声をかけられ、目を開けた。振り向くと、先客としてベンチに座っていたあの女性が、一メートルほどの距離に近づいてきていた。
「大丈夫ですか」
溢れかけている涙を拭おうとして、しまった、と気づく。先にミニトートの中身を隠すべきだった。しかし時すでに遅く、女性は私の荷物に目をつけ、それが何であるかを認識したようだった。
「うわぁ、すごい泥」
駄目だ。見つかった。
「お子さんのですか」女性は近づき、不躾にも中を覗き込んでくる。見せたくはなかったが、後ろめたさを露呈させるようで、隠すこともまた憚られた。観念し、私は自らミニトートの口を開け、女性へと向けた。
咎められるだろう、と身構えていたところ、意外にも女性は顔を綻ばせ、私を見た。
「ここのところ雨続きだものねぇ」
遠目からはわからなかったが、女性の口元には皺が寄り、ノーメイクの肌にはシミがいくつか浮いていた。私より二十は歳上だろうか。茶色く染めた髪の隙間に、白いものがちらちらと見えた。
この女性も、私と同じような道を通ってきたのだろうか。向けられた笑みには、こちらの苦悩を心得ているかのような苦味があった。
「あ……」
無言で伝わるそのシンパシーに、心が融解した。抑え込んでいた涙と共に、堰き止めていた想いが溢れ出した。
「あの……私……」
「うん」
止まらない。
「すみません、私、もう嫌になっちゃって……」
「うん」
「だって早く洗わないとシミになるし、でも明日も私、仕事があるし。だから良くない、駄目だってわかっていても、もうここで洗っちゃおう、って……私……」
「うん」
大変だよねぇ。唐突な告白に驚く様子もなく、女性は頷き、どこか能天気な相槌を打つ。立ち入るでも遠のくでもなく、ただただ側で。その距離から伝わる温もりが、雨に濡れた私を温めていく。
「そう言えば」
言って、女性はおもむろにスマートフォンを取り出した。先ほどまで見ていた動画はアニメだったらしく、ロボットらしきものの戦う画像がちらりと覗く。女性はその画面を閉じ、違うブラウザを立ち上げて、何やら検索を始めた。
ちらりと左手薬指に指輪が見えた。一瞬、息が止まる。しかし、芽生えた疑念が育ち始める前に、女性の明るい声がそれを摘み取る。
「そう、これこれ。今、こんなのあるらしいわよ」
女性が見せてくれた画面には、白いバケツのようなアイテムが映っていた。説明を見ると小型の洗濯機らしく、汚れがひどい洗い物に、との謳い文句が書かれていた。
「泥だらけの服とか靴とか、これでいけちゃうんだって。私もネットでたまたま知って。今は便利なものがあるわぁ、って羨ましかったから、覚えていたの」
どう、”弐號機”として。
先ほどまで見ていたアニメの影響だろうか、おどけた言い回しで、女性は言う。
「”弐號機”……」
「あぁ、でもこれ一万近くするわ」急に商品を勧められ面食らう私を前に、「いっそ新しい服買った方が安上がりか」再び画面を見て、女性。
「思い切って、しばらくヘルパーさん雇うとか。いっそ仕事の方を休んじゃうとか。子供の服なんてシミだらけなもん、と割り切っちゃうのもひとつだし、旦那の顔面にその服投げつけてやってもいいかも」
目線を上に、つらつらと列挙した後、女性は悪戯っぽい顔を私に向けた。
「いっぱいあるわね、”弐號機”」
瞬間、乾いた風を感じた。
女性の言葉が、雲間から差し込む陽射しのように、真っ直ぐ私の胸底を照らす。
いっぱいある。
私を救う光も。私が進む未来も。
女性から目を逸らし、前を見る。こちらを捉える瞳のような、ドラム式洗濯機の透明な円。
違う。
これは私の”弐號機”じゃない。
こんなものを乗りこなしたとして、あの恋しい日々は取り戻せやしない。
先ほどまでの逡巡が、嘘のように消え去っていた。拡がった黒いシミが、見る影もなく漂白されていた。
「ありがとうございます」
再び女性の方を向き、ミニトートを胸に頭を下げる。「何が?」嘯きつつも、女性は手を振り応えてくれる。
会釈をして、私は入り口の傘立てへ。女性も元いたベンチの方へ。
傘立てから傘を抜き、ガラス戸に手を当てたところ、思いとどまり、振り返った。女性は最初見た時と同じ位置に座り、イヤフォンを耳に挿そうとしていた。
「……あの」
思い切って声をかける。
女性が手を止め、顔を上げた。
目線が合う。
「あなたは、どうしてここで?」
このまま、清らかになった心で帰ればよかった。しかし、先ほど見えた指輪の存在が、どうしても気になった。
この時間、この場所で、それをしっかり嵌めている女性が、
この時間、この場所で、一体何をしているのか。
どんな事情で。どんな思いで。
訊かずにはいられず、訊いた以上は逃げるわけにもいかず。ただただ私は相手を見つめる。
しかし、女性は多くを語ることはなく、
「私の"弐號機"」
ただ一言そう答え、くしゃりと顔に皺を寄せた。
湿り気を帯びた表情。
白く洗われたばかりの心に、またひとつシミができる。
何色ともつかないそれが、どんどんと拡がっていく。
女性がイヤフォンを耳に挿し、再びスマートフォンの操作を始める。私は今一度頭を下げ、ガラス戸を押し開けた。
地面を叩く雨音が、ボリュームを上げる。
聞いたばかりの答えと、その背後に渦巻く得体の知れない何かを思い、胸がざわめく。
戻れるのだろうか。
あの人が恋しく思う日々は、あの人の側にまだあるのだろうか。
身体が濡れ始めていることに気づき、慌てて傘を広げる。空から降り続くそれは、まだまだ止む気配がない。
「いっぱいある」
言い聞かせるように小さく呟き、私はコインランドリーを後にした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
