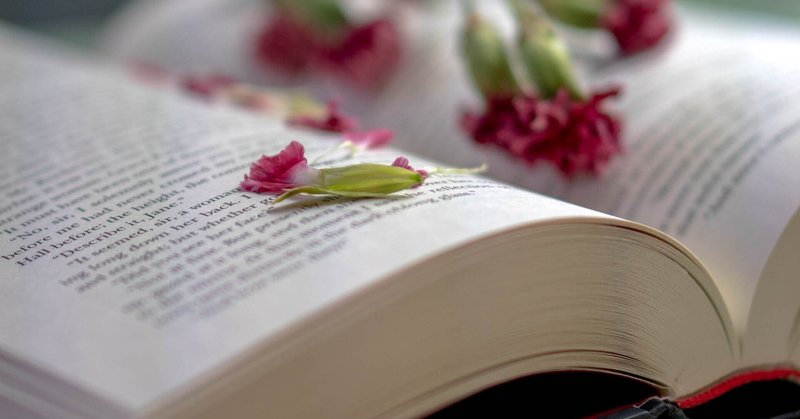
二度のリストラと保活失敗を経て今思うこと
これまでの人生で転換点となった二つの出来事がある。
二度のリストラと、保活の失敗だ。
これらの出来事は私の人生に少なからぬ打撃を与えた。そのたび私は生き方の変容を迫られた。
私は現在、会社員として働きながら教育ライターとして活動している。「書くことを通して本や学びの素晴らしさを発信する」をミッションに、様々な活動に携わっているが、軸は全て「本」と「学び」に関することだ。
現在の生き方にはある程度満足しているが、ここへ辿り着くまで随分と遠回りをした。
今回そんなことについて振り返りたくなったのは、日経COMEMOのテーマ企画を目にしたからだ。
このテーマ企画では、若い世代を応援するメディア「NIKKEI STYLE U22」と連動し、#あなたが変身した話 というテーマでエピソードを募集している。コロナ禍に社会に飛び出していく若い人々にとって、私の経験がどれほど参考になるかは分からないが、誰か一人にでも届けばと書き起こしたくなった。
そんなわけで、今日は私が幾度かの危機を乗り越えて「変身」を遂げた過去について、お話ししたいと思う。
リーマンショック禍で経験した二度のリストラ
私は元々書くことが好きな子どもだった。本を読むことも好きだった。しかしそれでは飽き足らず、自作の絵本やマンガを描いては友達に見せたりしていた。
高校生の時、そんな私に「書くことを仕事にしたら」と言ってくれた友人がいた。それを真に受けて、いつしか言葉に関わる仕事を夢見るようになった。大学は文学部へ進み、ジャーナリズム研究会に入ろうとした。そんな折、ある人から言われた言葉で私は冷静になった。
「公に対して何かを発信するときは、慎重になった方がいいよ」
私のことを思って忠告してくれた言葉だった。しかしこの言葉に私は怖気づいてしまった。
自分の文章は果たして人目に触れる価値があるものなのか?
そのような価値ある視点や覚悟が自分に備わっているか?
自分にはいずれも備わっていないと判断した。ジャーナリズム研究会への入部は見送った。その後の就職活動でも、新聞や出版など活字系の業界は一切避けて通った。
一方で表現への憧れは捨てきれず、新卒では映像業界に入った。充実した日々を送っていたが、同時に何かがしっくりこない感覚も抱いていた。そこに激務が重なり、しまいには体調を崩してしまった。連日の深夜残業で体への負担を強いたのは事実だが、精神的な葛藤も大きな要因をなしたと思う。不調がピークだった頃は、路上でところかまわず寝込んだり、その辺のベンチで寝込んだりしてしまうようなありさまだった。
潮時と判断し、二年目に入るタイミングで環境を変えた。心機一転、桜の時期に新しい仕事がスタートした。入社から10日ほど経ったある日のことだった。出社早々、社長室に呼び出された。開口一番に告げられたのは、解雇だった。理由ははっきりしなかったが、とにかくその日のうちに荷物をまとめて出て行かなければならないということだった。あまりのことに唖然と立ち尽くした。その日どうやって帰宅したか、記憶にない。数日後、テレビのニュースでその企業が倒産したことを知った。
次に拾われたのはとある不動産会社だった。しかしそこでの日々も長くは続かなかった。時はリーマンショックの翌年。不動産業界全体が甚大なダメージを受けていた。入社から約一年が経ったある日のこと。勤務していた営業所の閉鎖が発表された。再び解雇を告げられた日、どうやって自宅まで帰り着いたか、やっぱり記憶に残っていない。
一年あまりの間に経験した二度のリストラにより、私はすっかり途方に暮れてしまった。金銭的にも、精神的にも、路頭に迷ってしまった。そんなある日、スマートフォンを見るともなしに見ていたら、ある企業の求人広告が目に留まった。ある出版社の人材募集だった。いいなぁ、とぼんやり思った。かといって何かアクションを起こせるほどの気力すら残っていなかった。その求人広告は見送った。と、思っていた。
翌朝目覚めると、メールが届いていた。開いてみると、前日に見た出版社から面接の誘いが来ていた。無意識のうちに応募ボタンを指で押すなどしたのだろうか。もはや思考停止していて記憶にないのだが、とにかく面接に誘われていることは事実のようだった。そんなわけで面接に赴き、縁あって正社員として採用された。
私の転身① 会社員×妻×学生、3足のわらじ生活へ
念願の出版社で大好きな本に囲まれながら働く日々は、夢のようだった。無我夢中で仕事にのめりこんだ。
一方で仕事に夢中になるにつれ、ひとつの葛藤を抱くようになっていた。新しい勤務先は学術出版社で、お客様の大半は教育関係者だった。それらの方々に対応していくには、商品知識だけでなく、教育そのものに関する深い知識が必要となる。教職課程すら取らなかった私にとって、教育という分野は未知の領域だった。
悩んだ末、一念発起して大学院で教育を学びなおすことにした。しかし決意こそしたものの、フルタイムで働く既婚者の私にとって、夜間や週末の通学はハードルが高い。やはり仕事や家庭を持ちながら学び続けることは難しいのだろうか。そんな思いがよぎる中、またもやある検索広告が目に留まった。海外大学のオンラインコースの案内だった。調べてみると、海外ではオンラインで完結できる修士課程コースが数多く開講されているようだった。その日たまたま私が見つけたのは、イギリスのユニバーシティ・カレッジ・ロンドンという大学の教育学コースだった。UCLの略称で知られ、QS世界大学ランキング等でも教育分野において毎年世界一位の評価を受ける大学だ。過去には伊藤博文や夏目漱石なども留学した、歴史ある名門大学でもある。
仕事と並行しながら出願準備を進め、2014年夏、はれてUCLの教育学修士コースに入学した。そこから二年間、日本で働きながらイギリスの大学院に「オンライン留学」する生活が始まった。ビジネスパーソンであり、妻であり、学生でもあるという三足のわらじ生活が始まった。想像を超えた目まぐるしい生活だったが、とても充実した日々でもあった。
オンラインによる大学院生活を経て、自分の成長を実感し、仕事も軌道に乗りはじめた。任せてもらえる仕事の幅が広がり、仕事がどんどん楽しくなっていった。
一方で、自分の内ではまた新たな葛藤が芽生え始めていた。教育出版はまさに変革のさなかで、紙からデジタルへのパラダイムシフトが起こり始めていた。デジタル教育についてきちんと学ばなければ、いつかまた壁にぶつかるかもしれない。そんな課題意識は、デジタル教育について学びたいという純粋な思いへといつしか変わっていった。
当時まだ20代と若く、柄にもなく思いつめがちな部分があった。一方で、それが自分にとって必要な経験だという、何か確信みたいなものも感じていた。教育の実務経験を積みながら、デジタル教育について学べる機会はないだろうか。模索していたところ、大学院の先生がある選択肢を紹介してくれた。フランスの大学院への進学だった。フランスなどヨーロッパの一部の国では、大学院の課程の中で数か月のインターンシップを義務付けていることが多い。私の指導教官が勧めてくれたのは、フランス・パリ大学のデジタル教育分野の修士課程だった。デジタル教育について一年間研究を行いながら、後半の半年間は教育現場で実習経験を積む。まさに願ってもない機会だった。
しかしここでまた悩みが頭をもたげた。フランスに行くとしたら、今度こそ夫と別居しなくてはならない。さすがに誰にも相談できず、人知れず胃に穴が開くほど悩み続けた。しかしこの機会を逃したら、もう二度とこんな機会は訪れないだろう。もはや、離婚を切り出されても仕方ない。覚悟し、主人に話をした。彼は背中を押してくれた。彼の中にも、とても大きな葛藤があったと思う。それにもかかわらず背中を押してくれたことを、今でも心から感謝している。
30歳の夏、フランスに一人降り立った。フランスではデジタル教育の世界にどっぷりと浸かり、ひたすら知識や情報を吸収した。念願の教育現場での実習も経験した。パリ市内のインターナショナルスクールで、世界65ヵ国から集まった子どもたちと半年間を過ごした。先生として校内を駆け回った日々は、今でも人生の輝かしい思い出として残っている。
一年間の留学を終え、帰国後は出版社に復職した。様々な仕事を経験させて頂いた。お客様対応の仕事だけでなく、イベント企画やプロモーション、編集に関わる仕事など、様々なことを経験させて頂いた。
コロナ禍での保活惨敗、そして復職の延期
充実した日々を送る中、第一子を妊娠した。慣れない子育てに没頭しながら、あっという間に日々が過ぎて行った。
復職に備えて少しずつ準備を進めていた2020年春。コロナ禍が忍び寄る中、保育園に落選した。感染拡大の脅威が広がる中、一から保活を再開した。
このまま復職できなかったらどうしよう。
コロナ禍でまた仕事を失ってしまったら、今度こそどうすれば良いのか。
不安に苛まれる日々が始まった。原因不明の胃痛や過呼吸にも苦しんだ。
三月半ばのある日、近所の認可外保育園からついに受け入れの電話がかかってきた。タイミング的に、恐らく三次募集くらいだったと思う。首の皮一枚でキャリアがつながることになった。
しかしそんな中、緊急事態宣言が発令。保育園こそ確保できたものの、今度は会社側との調整により復職が延期されることとなった。復職が延期された間、育児休業手当の支給もストップし、私の収入は途絶えた。復職予定も定まらないまま、何もかもが宙ぶらりんになってしまった。
仕事を失うかもしれないという事が自分にとってこれほど重いことだという事実に、私はここで改めて向き合うこととなった。リーマンショックで二度リストラを経験したときにも、このような危機には直面してきたはずだった。しかし当時気づいていなかったのは、仕事を失うということに関する金銭面以外での意味合いだ。リーマンショック当時、私は社会に出たばかりの独身者で、失業とはすなわち生きる糧を失うことに直結した。一方、既婚者である現在は、夫の収入もある。私が職を失ったからといって、すぐに生活が立ちいかなくなるわけではない。それにもかかわらず、仕事を失うということに対して抱く、この絶望的な感情は何だろうか?
つまり、私は職業を持ち続けたいのだ。
さらに言えば、微力でもいいから書くことで私は世の中に貢献したい。
言葉に関わる仕事を通して、活字文化を微力ながらも下支えするという、そのこと自体に私は何か生きる意味のようなものを見いだしてきたのだ。
転職を視野に求人サイトを日夜眺める中、あることに気づいた。「ライター」や「編集者」といった言葉に関わる仕事ばかりを、気づけばいつも目で追っていた。これまで活字の素晴らしさを一人でも多くの人に伝えることが自分の使命だと信じて働いてきた。それ自体は決して間違いではない。しかしそこには一つの重要な視点が抜け落ちていた。「書くことによって」という、手段(How)の部分だった。
私の転身② 「パラレルキャリア × 学び直し × 発信」で人生を立て直す
自分は結局書きたいのだ。
幼い頃からの原点にようやく立ち戻った。私は「書くこと」を軸に次の一手を考え始めた。しかしそこで厳しい現実にぶちあたった。何か行動を起こしたくても、一歩を踏み出すことが難しいという現実だ。
これまで「出版」と「教育」に軸を定め、自己研鑽に励んできた。働きながら大学院に通ったり、海外で教育実習を積んだりなど、常に学び続けてきた。結果、様々な知識やスキルが身につき、圧倒的に仕事がやりやすくなった。周囲からも評価され、目標がどんどん広がり、仕事もますます楽しくなっていった。しかしそれらはあくまで現職の中での話だ。
会社の看板を外したら、はたして自分に何が残るのか?
社外での実績や居場所づくりを怠ってきたことに今更気づいた。要するに、会社の看板を外したら何もできない状態になっていたのだ。いくら知識やスキルを仕入れたところで、見える形での実績がなければ、社会の中で仕事を任せてはもらえない。実績のない者にいきなり仕事を任せてもらえるほど、世の中甘くはない。
実績がないならどうすればいいか。
作ればいい。
自分の現状を冷静に見つめ直した。結果、自分には三つのものごとが欠けていると判断した。一つはとにかく何をおいても社外での実績。もう一つはそれを支える新たな学び。最後に発信力だ。
まずはとにかく最初の実績を作らなければならない。有償か無償かは置いておいて、とにかく目に見える最初の実績を作る。タイミングよく、知り合いの起業家の方が絵本を英訳できる人手を求めていた。これが最初の実績になった。それを弾みに、次はバレエスクールを開業した友人からウェブサイトの翻訳依頼を引き受けた。とにかくもらえるチャンスは何でも引き受けることにした。何がその先に繋がるか分からない。
執筆につながる実績が増えてきたことで、知り合いの輪を飛び越えて仕事をもらえるようになっていった。外部メディアへの寄稿を少しずつ増やし、教育をテーマにした記事などを書かせて頂けるようになった。
ボランティア(プロボノ)にも積極的に挑戦した。雇用や契約といった金銭上のみの関係性にとらわれない、社会との新たな関わり方を模索する必要性を感じ始めていた。元から手伝いをしていた都内の大学で、オンラインによる学生メンタリングのボランティア募集が始まった。すかさず手を挙げた。以来、現在もオンラインによる学生との個別面談や、学内イベントへの登壇など、様々な形でお手伝いをさせて頂いている。
こうして私のパラレルキャリア生活は軌道に乗り始めた。そのタイミングで、私はライティングを改めて学びなおすことにした。何か新しい活動を始めるにあたっては、それを支える新たな学びが必要となる。これまで十年以上出版社に勤めてきたが、自身で原稿料を頂いて何かを書く経験をしたことはなかった。今こそ学び直す時だと思った。
最後に、自分に決定的に欠けているものは何かと問えば、それは発信力だ。発信力を強化すべく、noteのアカウントを作って発信をしはじめた。いきおいで日経新聞が主催するオンラインサロンにも参加した。ここでの活動が良い起点となった。最初のひと月で5本の記事をアップした。それらがきっかけとなり、後々メディアからインタビューを受けたり、大学から講演依頼を頂いたりなど、思いもよらない展開が起こり始めた。ゆっくりと回転しはじめたメリーゴーラウンドのように、人生がまた音を立てて回り始めた。
2020年6月末、緊急事態宣言が解除された。保育園の再開に伴い、あわただしく復職が決まった。
現在私はワーキングマザーとして仕事と子育てを両立しながら、空いた時間で執筆と講演活動を行うというライフスタイルに落ち着いている。コロナ禍以前は想像もしなかった生活だが、今となっては必然だったと感じる。
変身は必要か
今回日経COMEMOでは、「人生において変身は必要か」「変身するには何が必要か」といった問いを投げかけている。私個人の経験からU22世代の方々へお伝えたいのは、これから始まる長い社会人生活の中で、そういう時期も何度か訪れるだろうということだ。
社会はより不確かな方向に進んでいて、変化の速度も速くなっている。終身雇用は、私たちの親世代をもって実質終わりを告げた。会社が個々人のキャリアプランを管理してくれる時代でもない。定年まで勤め上げる意思があっても、そこまでの道のりはある程度自分で考えなければならない。さらに、人生100年時代においては老後も長い。65歳以降も何らかの形で職を持つことが一般的になっているかもしれない。そうなると人生のどこかのタイミングで二度や三度の転身は避けては通れないだろう。このあたりのことについては、日経をはじめ様々なメディアが論じている通りだから、今更私が言うまでもない。
一方で、「変身」とは非常に強い言葉だ。あたかもこれまでの人生を捨てて、誰か違う人にならなければならないかのようなニュアンスを感じる。そのため「変身」を怖いと思ったり億劫だと思ったりする人もいるだろう。
私自身、これまでリストラや保活失敗といった危機的状況を迎えるたび、「このままではいけない、新しい自分にならなければならない」ともがいてきた。自分を根本的に変えなければそれらの変化には到底対応しきれないと考えていた。ある意味「別人」になる道を模索し続けてきたこれまでの半生と言ってもいい。
一方で、そんな日々を振り返って気付くのは、別人になろうともがけばもがくほど、なぜか自分自身の軸により近づいていったという逆説的な事実だ。例えば、私は二度のリストラを経験したあと、憧れながらも敬遠していた出版の道にあえて飛び込んだ。さらに保活の失敗を経て、ついに書くことを仕事にした。人生の危機に瀕し、何かを変えなければならないと思えば思うほど、私はむしろ自分の本心へと近づくような行動を取っていった。
私のケースは、不幸中の幸いが続いたという見方もできるかもしれない。確かにラッキーなこともたくさんあった。しかし結局それらの道を歩み始めたきっかけは、自分自身がそれらを追い求め、行動に移したことが起点となっている。
だから「変身」という言葉に恐怖や抵抗を感じる人々に伝えたいのは、それを自分の軸に立ち戻るためのチャンスと捉えてはどうかということだ。自分の本来の望みに近づくための「変身」と考えれば、恐怖心も少しは和らぐかもしれない。
変身するためにはどうすれば良いか
ここで改めて断っておきたいのだが、私は全ての人が「やりたいこと」を軸に仕事を探すべきだとは思っていない。得意なことで探してもいいし、職場環境で探してもいい。安定性やお給料で探したっていい。100人いれば100通りのキャリア選択の基準があるはずだ。
しかし私自身はやりたいことでないと続かない人間で、これを読んでくださるU22世代の人たちの中にも、私と似たような人がいるのではないかと思う。そのような方々に向けて、一つお伝えしたいことがある。
もしもあなたが好きなことを仕事にしたいと考えるなら、「やりたいこと」の種を探すために、なるべく頭は使わないほうがいいということだ。
興味があることというのは、別にわざわざ考えなくたって、気付けば目で追ったり考えたりしているものだ。私自身、気付けばライティング関係の仕事ばかりを目で追っていたように、無意識の行動の中にこそ、好きの種が隠れているように思う。
日常の中で気付けば欲しているものや考えていることがあれば、そういうものの中にやりたいことの種が隠れているかもしれない。だからもしもあなたが今好きなことを模索している段階にいるのなら、脳みそを使うのはしばらくお休みしてみてはどうか。この点の重要性について、ブルース・リーほど端的に表現した人を私は知らない。Don't think, Feel. それが第一歩になると思う。
やりたいことの種が見つかったら、次はそれをいかに仕事につなげるかだ。U22世代の方々は、春から就職活動を始める人もいるかもしれない。社会人の中にも、複業や起業といった新たな働き方を模索されている人もいるだろう。
やりたいことを仕事につなげるために、私がいつも意識している視点がある。
「やりたいこと」×「社会のニーズ」×「収益性」
という三つの視点だ。
やりたいことが見つかったら、まず社会に存在するニーズとの接点を探す。私の場合、「書きたい」という気持ちがまず先にあって、そこに「本」や「教育」というテーマ(=社会のニーズ)が合致した。その両者が重なる点を見いだせたら、最後に収益性について考える。私の場合は、本や学びをテーマに記事を書いて原稿料を頂くなどがある。こんな風に「やりたいこと」「社会のニーズ」「収益性」の3点が重なるところを見つけられれば、そこがスイートスポットになる。
余談だが、日ごろ社会人メンターとして大学生からの様々な相談に応じていると、この順番を逆に行こうとする人がとても多いことに気づく。まず収益性や社会のニーズについて考え、最後に自分のやりたいこととマッチするかどうかをチェックする。自分のやりたいことについて考えるときも、とかく頭でっかちに考えてしまう人が多い。しかしそのやりかたでは、本来の自分の気持ちと乖離した方向へ行ってしまうリスクがある。だから順番としては、あくまで「やりたいこと」→「社会のニーズ」→「収益性」の順がいい(そもそも社会にニーズがあれば、収益性について考えることはさほど難しいことではない)。
ここまで考えたら、後は行動あるのみだ。既に職業として確立されているなら、それを目指せばいいから話は早い。具体的な職業としてイメージできない場合は、関連する業界や企業にまずは潜り込むという方法があると思う。
複業などスモールスタートから始める場合は、よりハードルが下がる。私のように、最初は友人から仕事をもらって実績につなげるという方法もある。またクラウドソーシングやスキルマーケットに登録してみるという手もある。例えばスキルマーケット大手の「ココナラ」では、200種類以上のサービスカテゴリに30万以上のスキルが出品されているそうだ(※2020年時点)。どのようなスキルに需要があるかわからない。とにかく何でも行動に移してみることから、現実的な路線が見えてくるのではないだろうか。
コロナ禍で社会に飛び出すU22世代の人たちは、今とても大きな不安を抱えていると思う。リーマンショックの年に社会に飛び出した私もそうだった。もちろんリーマンショックとコロナ禍では、社会の変化の度合いは比較にならない。安易に比較して語るべきではないとは思う。ただ、同じく未曾有の危機のなか社会に飛び出した者として、何か一言伝えたくなり筆を執った。
これから始まる長い社会人生活の中で、生き方の変容を迫られるタイミングは幾度となく訪れるだろう。きっかけは必ずしもポジティブなものではないかもしれない。それまでの人生を否定されるような物事も起こるかもしれない。でも、変身自体は決して悪いものではない。むしろ、そこからより自分らしい生き方を紡ぐきっかけとなるかもしれない。そんなふうに考えて、果敢に新しい世界へ飛び込んでほしいと思う。
なんて、柄にもなくアドバイスめいたことをぶちまけてしまい、少々こっぱずかしい気持ちになっているのだが、春の気配というのは何か人にそういう気持ちを起こさせるのだろうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
