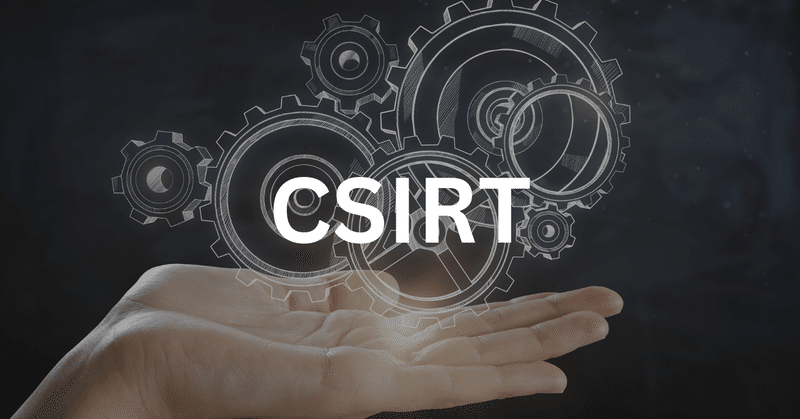
1分で分かる!?インシデントに速やかに対応「シーサート(CSIRT)」
はい、こんにちは。松井真也です。『ゼロトラスト用語辞典シリーズ』と題してブログを更新しております
今回、第2回目のテーマは「CSIRT」です。「SOC」は、脅威がないかシステムを24時間365日に監視することが役割の中心でしたね。他方、「CSIRT」は、インシデント発生時にSOCと連携しつつ対応にあたるのが主な役割です。両者の連携プレーが脅威への対応の決め手です!
では、CSIRTとはどのように活躍するのか?早速、見てみましょう!
CSIRTとは何か?
まずは、CSIRT(読み方はシーサート)とはどんなものか概要を掴みましょう。
サイバーセキュリティの脅威が日増しに増加するなかでは、セキュリティインシデントがあれば、それに効果的に対応するの専門組織が不可欠ですね。
そこで注目されるのが「CSIRT(Computer Security Incident Response Team」というわけです!
これは、簡単にいうと、インシデントが発生した際に迅速かつ的確に対応するための専門チームです。企業内外のステークホルダーと調整し、経営的な意思決定に深くかかわりますから、企業内に設置されることが一般的です。一方、SOCは外注されることが多いです。
ということで、CSIRTの主な任務は、インシデントが発生した際に、その詳細を収集し、分析を行い、被害を最小限に抑えるための対応をとることにあります。

CSIRTの具体的な業務内容
概要が分かったところで、もう少しCSIRTの仕事を深掘りしましょう!
CSIRTの業務は多岐にわたりますが、主に以下のような活動を行います。緊急時対応だけでなく、平時でも活動をしているのがポイントです。
インシデント対応:セキュリティインシデントが発生した場合、SOCと連携して迅速に対応を行い、被害の拡大を防ぎます。これが「1丁目1番地」の仕事です。
情報収集と注意喚起:最新のセキュリティ関連情報を取集します。それを関連部署や他のCSIRTとの情報共有します。さらに、これに合わせて、自社のセキュリティ状況を評価して対策を講じておくことも重要です。
セキュリティポリシーや対応手順の策定:CSIRTは、様々な種類のセキュリティインシデントに対する対応手順を事前に定めておきます。これには、インシデント発生時の初動対応、関連部門への報告フロー、技術的な対応手段などが含まれます。
教育と訓練:平時のセキュリティ意識の向上とスキルアップを図るために、社員を定期的な教育や訓練します。CSIRTメンバー自身のトレーニングも、もちろん必要です。

運営上の課題
最後にどんな課題があるか、整理してみましょうか。
CSIRTの運営には高度な技術と専門知識が求められられます。CSIRTは、原則自社で設置する、と述べましたが、自社だけでは十分な態勢が整えられないかもしれません。多くの組織ではセキュリティベンダーと協力して運用を行っています。
また、インシデント発生時には社内のさまざまな部門との調整が必要となり、これが大きな課題となることもあります。このように、効果的な運用を進めるためには、定期的なレビューと改善が不可欠です。
最後は、やはり企業文化の構築が課題になりましょう。効果的なCSIRTを構築するためには、組織全体でのセキュリティ文化の醸成が大事です。具体的には、従業員一人一人がセキュリティに対する正しい理解と意識を持つこと、技術的な対策だけでなく、人的な対策も強化することが求められます。

はい、本日はここまで!今回はインシデント対応チーム「CSIRT」についてお話ししました。この機会に、皆様の会社のアンサング・ヒーローである「CSIRT」にご注目ください!
では!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
