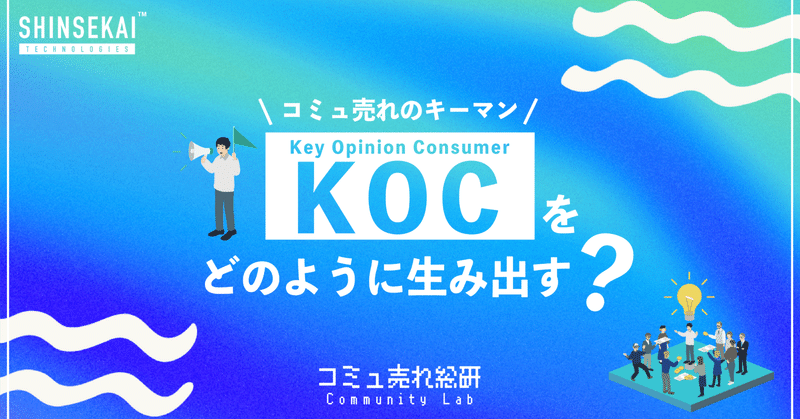
コミュ売れのキーマン、KOCをどのように生み出す?
こんにちは!コミュ売れ総研 主任研究員のSHINです!
このコミュ売れ総研ではコミュニティを”科学”することによって、データに基づく再現性の高い手法で、企業や団体のマーケティングやコミュニティ運営の成果に繋げる方法を模索しています。
第4回目では、第2回目にお話ししたコミュニティマーケティングのキーパーソンであるKOCをどのように生み出していくのかについてお話しします。
前回は顧客が継続購入するためにも重要な考え方、コミュニティファネルについてお話ししました。
コミュニティファネルに則った環境でユーザー同士が、またはユーザーと企業がコミュニケーションをとり、愛のあるコミュニティを作っていきます。その鍵となるのがKOCです。ただ、このKOCはどのような環境だと生まれやすいのでしょうか?
その答えは「熱量の高い」コミュニティです。熱量が高いというのは、コミュニティメンバーがその商品やコンテンツに関する情報を自発的に発信したり、他人に紹介したりするという、アクティブな状態のことです。
そこで今回はKOCが生まれやすくなるためのコミュニティ設計とはどのようなものかについて詳しく解説していきます。
KOCが定着するまでの流れを把握しよう
KOC(Key Opinion Consumer)とは、自身も消費者でありながら、商品の良し悪しを的確に伝えて、周りの消費者に影響を与える人です。KOCについては第2回の「【時代はKOLからKOCへ】コミュニティマーケに重要なKOCって何?」で詳しく記載しましたので、まだご覧になっていない方は参考にしてください。
KOCも自然に発生すれば良いのですが、なかなかそうも行きません。コミュニティ担当者は、KOCを生み出すために①KOCになりうる人の心について理解し、②正しくコミュニティを設計し、③その活動を継続してもらう環境を用意する必要があります。それぞれについて、解説していきましょう。
①KOCになりうる人の深層心理
KOCになりうる人(潜在的なKOC)は、少なからず「自分の好きなモノ・コト」について発信し、同じ熱量やマインドを持つ人たちとつながりたいという欲求を持っています。

ですが、SNSのような不特定多数とオープンに繋がっている場では自分の好きなモノやコトについて発言した際に批判や否定などが飛んでくる可能性があります。ただ自分の好きなモノについて語っているだけなのに思わぬところからの攻撃が来たり、ちょっとした発言で炎上が起こったり。それをを恐れ、発信することが嫌になってしまうかもしれません。
潜在的なKOCには、そんな経験がある、もしくはそういうリスクを懸念して、不特定多数とつながっているオープンなSNSでは自分の好きなことについて堂々と語りづらい、という深層心理があることが多いです。発信をし始めたばかりの頃は特にそうでしょう。だからこそ、そういう人には共通の趣味や好きなものについて、同じような温度感の人たちともう少しクローズドに話したいという欲求が存在します。
そういう気持ちを拾い上げて内部で増幅させるのが、コミュニティです。ユーザー同士の双方向コミュニケーションの中で、「好き」の相乗効果を生み出していくことで、そうした情報を積極的に発信していくKOCが生まれ、育っていきます。つまり、「コミュニティ内で発言しやすい環境」を作っていくことこそが、KOCを作るために最も重要な要素となります。

②コミュニティファネルを活用したサポート
では、どのようにコミュニティ内で発言しやすい環境をつくっていくのでしょうか?
ここで前回説明した「コミュニティファネル」が登場します。「VISIT」「FRIEND」「VALUE」の3つのステップを経て、ライトなユーザーがロイヤル化してKOCになるまでの心理変化を、コミュニティ設計と照らし合わせて見ていきましょう。

まず、VISITのステップは初めて商品を購入し、コミュニティに入る段階です。ここではまだ何もわからず、不安が大きいので心理的安全性を与えることが大事になります。自己紹介エリアを作ってお互いのことを知れるようにしたり、コミュニティモデレーター(MOD)が積極的に声をかけたり、共通の話題を見つけやすい動線をつくったりと、新しいメンバーが発言しやすい環境を整えます。そんな中で、その人にも徐々に価値観の合う友達ができ、コミュニティを訪れるのが楽しくなってきます。
次に、FRIENDのステップはコミュニティが日常化し、メンバーとのコミュニケーションが増える段階です。コミュニティ内でできた友人からのメッセージや、KOCを中心に流れてくる会話テーマやコンテンツを楽しむ中で、毎日コミュニティに来るのが習慣になってきます。その中でお互いの「好き」を伝えあって増幅したり、自分の意見を積極的に発信したりしたいと思うようになります。
最後にVALUEのステップはコミュニティに来るのが習慣化し、能動的に会話やアクションを行うようになる段階です。いわゆる「KOC化」する段階です。運営側からメンバーに意見を求めたり、さらに小さなコミュニティを作って役割を与えたりすることで、ユーザーがコミュニティを軸とした行動をするようになり、自然と好きなものを人に紹介したりと、コミュニティのための行動を無意識的にしてくれます。
ここで重要なのは、能動的な発信や行動をしてもらうためには「余白」が必要だということです。
コミュニティ内のコンテンツに関して、運営側が全てを決めて決定事項だけを連絡してしまうと、KOCがアイデアやUGCを作ろうと思う余地がありません。みんなで掛け声を考えてみたり、コミュニティで使うスタンプのデザインを募集したりするなど、「ユーザーと一緒に」コミュニティを作るきっかけ、つまり「余白」が必要です。その余白があることで、ユーザーはコミュニティのために何かを成して、ほかの人に称賛され、さらにコミュニティに貢献しようという気持ちになってくれるでしょう。

③KOCの活動を習慣化させるサイクル
コミュニティファネルに基づいたコミュニティ設計をすることで、商品やコンテンツを愛し、自発的に発信してくれる「KOC」が増えていきます。そしてひとたびKOCとなると、その後はKOCが自身で一層KOC化していく「正のフィードバックループ(習慣化)」が起きるのです。
「①消費→②おすすめ→③UGCの作成→④再購入→①…」といったループの中で自身の行動が習慣化されるということです。
どういうことか、ハンドクリームを例に説明していきます。
①まず、新しいハンドクリームを購入したKOCは、②「いい香り」や「保湿効果」など、使用してよかった感想を日常の会話の中で人に話すことで自然とその商品をおすすめします。③そして、よりわかりやすく伝えたいと思って、「おすすめのハンドクリーム」という記事や推しポイントをまとめた画像のようなUGCを作成してコミュニティ内やSNSに発信します。④おすすめや発信を通して商品に一層愛着を持ち、購入したものをある程度消費したら再び購入して使用する、というループです。

もちろん、日常的に購入できる商品以外でも上記のループは起こります。音楽アーティストであれば新曲やライブなどがきっかけになりますし、画家であれば新作の販売や個展の開催などでしょうか。ゲームコミュニティでも得点を競うイベントや新キャラの発表、新機能のアップデートなどが該当します。何らかのきっかけから人に自然と伝え、自分ごととしてUGCなどを発信していく、そのサイクルによってKOCは一層KOCとして醸成されていきます。
さらに、こうした行動を繰り返しているうちに、他の人もその人の行動を真似るようになり、新たなKOCが生まれます。新陳代謝をしながらKOCが増え、コミュニティ全体が活気づいていきます。
このように、商品への想いがこもった行動が伝播していく「熱量の高い」コミュニティを作ることにより、自発的にKOCが増える構造を生み出すことができます。熱量とは、まさに「好き」という気持ちです。他人におすすめしたり、UGCを作成したりするなど、ユーザーのコンテンツに対する「愛」を発信するためのきっかけと環境をつくることこそが、コミュニティ運営者のなすべきことなのです。
KOCと共に成長するために「熱量の高い」コミュニティを作ろう
ユーザーが安心してコミュニティに参加するところから始め、日々のコミュニケーションや情報発信を通じて、徐々に他人にも影響を及ぼすKOCへと成長していく、そんなフローをコミュニティ設計を通じて作り出すことで、熱量の高いコミュニティは生まれます。
そのためにもユーザーの心理変化を理解して、行動変容のきっかけを与えるコミュニティファネルによる環境設計が非常に重要なのです。
ただ、その設計がうまくいっているのかは、基準や指標といったものがなければ正しく評価をすることができません。
次回は、そうしたコミュニティを形成する際の指標はどのように設定すべきなのか?という疑問に対して、コミュニティファネルをベースにお話しします。
最後まで読んでくださりありがとうございます!スキやコメント、シェアなどをしていただけると励みになります。お待ちしています!
問い合わせのある方は下記のリンクまでお願いします。
▼ホームページ
https://shinsekai-technologies.co.jp/
▼X
https://twitter.com/shinsekai_jp
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
