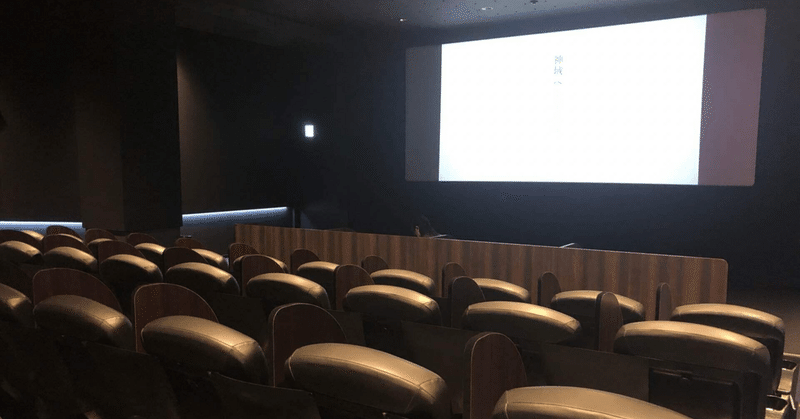
難解な映画と「補助線」、そしてヒットする作品の話。
タローさんの記事に触発されて書いてみる。これって昔のブログ文化でいうところの「トラックバック」というやつですね。懐かしい。
なお、Threadsに書いた内容の加筆修正となります。バラしちゃった。バラさなくていいのに。
難解な映画とはなんだろう。それは、平たく言えば「わかりやすい説明を省いた不親切な映画」となるだろうか。
古くは「2001年宇宙の旅」が難解と言われたし、デビッド・リンチの「マルホランドドライブ」なども難解と言われる。チャーリー・カウフマンの「もう終わりにしよう。」も難解だろう。わかりやすくない。どういう話なのかわからない。でも何か惹きつけられる映画。そんな映画が難解な映画だろう。
それらに異論はないのだけど、一つだけ言いたいことがある。
それは、映画を理解する際の「補助線」という概念だ。難解と言われる映画も、もしかすると「補助線」を一本引くだけで難解ではなくなる…とまでいくと言い過ぎだろうか。
「2001年宇宙の旅」は「物語性を排除した映像作品」という補助線で、「マルホランドドライブ」は「夢・妄想」という補助線で、「もう終わりにしよう。」は「学校の用務員の夢想」という補助線で、理解とまではいかなくとも自分の中に落とし所は見つかる気がしている。どういうものとして受け取ればいいのかがわかる。
ただ、それらもあくまで「ただの一観客が受け取るための補助」に過ぎないし、監督サイドの意図とは違うかもしれない。あくまで自分(筆者)はこう思う、という話に過ぎない。
また、映像という表現がなぜ言語でなく映像でなされているのかということを考えると、安易な言語化を許さないところがある。言葉だけで説明した方が良いのであれば、わざわざ映画など撮るわけがない。
結果、「難解な映画」を観た人の意見や解釈は分かれ、理解の階層のようなものも発生して物議を醸す。そんなんでいいの?と思うが、そんなんでいいのである。物事は簡単になどわからない。これはけっこう抽象性の高い話なのだ。映画の難解さについて語ることは、とりもなおさず、人が人を安易に理解することなどできないという人間のコミュニケーションそのものの話と相似を成しているのである。
そういう意味では大ヒットする作品というのは非常に絶妙だと言わなければならない。ヒットするというのはつまり、非常に多くの人たちに気に入ってもらわなければならないからだ。そこには当然、普段から映画(漫画もそうだ)を見慣れていない、いわばリテラシーの低い層も含まれる。となると、理解のハードルは低くなければならない。人はわからないものを好きにはなりにくいものだ。同時に、わかりやすすぎるものは魅力として映らない。その矛盾(実際には矛盾ではないのだが)を超えることが必要というのが一つだ。
そしてヒットする作品は、何より時代の精神の移し鏡である必要がある。人々が漠然と抱いている時代の気分、過去でも未来でもない「いま」の気分をテーマとして作品に落とし込めていること、それが多くの人の共感性を揺さぶるのである。そして、多くの人と同じ気持ちの、ほんの少し先を突いた表現が、皆の心を掴むのだろう。
やぶさかではありません!
