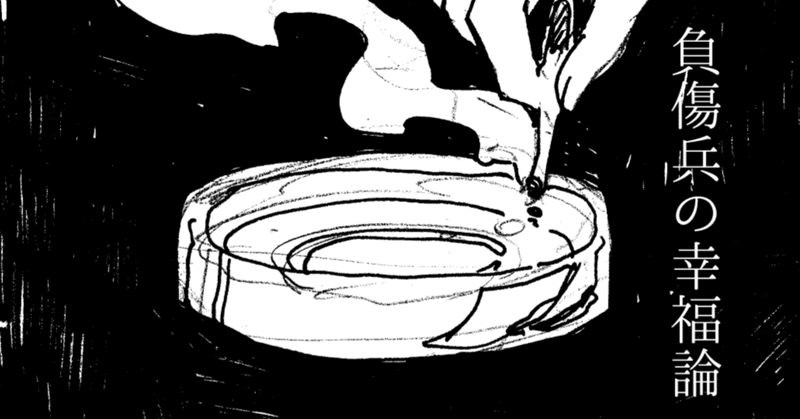
負傷兵の幸福論

幸福について考えいてる。幸せの定義なんて人それぞれだろうから、
「自分の幸福論」ということになるが…
毎日三食飯が食えれば幸せだろう。
それは確実だ。
だが、それだけでは納得できない。当然だ。
ふかふかのベッドで眠れないと、これも幸せではないだろう。
毎日、泥まみれになって眠っていると自分が人間としての尊厳を享受できているのか疑問に感じてしまうものだ。
オレはネズミじゃないし、ノミとかハエとかでもない。
最後に、信頼できる仲間であるとか家族・友人の存在だ。
これがあれば例え不幸を経験しても、乗り越えられる可能性がぐんと上がる。
人はひとりでは生きていかれない。
「できれば女がいいな。毎晩優しくしてくれる美人がいい。」
ルキアは煙草をふかしながら隣でそう言って伸び切った前髪をかきあげていた。
右手の薬指には最近購入したらしい銀の指輪をしている。
「それ、彼女さんのこと?」
オレはルキアに女ができたことを知っている。指輪をつけているから気付いた…という訳ではない。
実を言うとオレはそういうのにかなり疎いので、前情報がなければ気にもとめなかっただろう。
「なんだ…分隊の連中に聞いたか?裏切り者ども…」
ルキアは悪態をつくと、オレの目を見据えてゆっくりと恋人の存在について語りだした。
少し怠そうに見えるのはきっと薬を服用したばかりだかりだからだろう。
なにせ彼には最近までついていた左目が無い。敵兵の銃弾で目を撃たれ、後頭部に弾丸は貫通。
かなりの重症で生死を彷徨い、九死に一生を得た。彼は「奇跡の隻眼」なんて適当なあだ名までついていた。
「…まあ、そういう訳で…悪いな…お前を置いて先に家庭を築いて子供も授かって幸せに暮らそうと思います」
最後なんで敬語になった…?ルキアはたまに言葉遣いをわざとズラして気持ちを表現しようとする妙な癖があった。
先を越したとでも思っているのか、そしてそれを申し訳なく思われてしまっているのだろうか。
「あのさあ…別にいいじゃんか。後ろめたい事なんてないだろ?お前には良い出会いがあって、オレにはまだ無いってだけだ。
隠れされてる事の方がショックだったしな。分隊の連中が言ってたんだよ、お前の恋人のこと。」
それはオレ達が戦役に就いていた半年くらい前のことだった。
ヨアヒムにその事を聞かされたのはルキアが誰かと文通をしているというオレの発言が発端だった。
「ユラ、お前知らねえの?ルキアはさ、「ここ」で恋人作ったんだぜ?」
ここ、と言うのは戦場…基地のことか?そんなことってあるのか、相手は男なのだろうか。
そう質問すると、ヨアヒムは面白いおもちゃを見つけたと言わんばかりに「なんでだと思う?」と意地の悪い質問を繰り返してきた。戦場でこんなに陽気なのはこいつの天性の才能だから…ではない。
こいつは少し前から心を病んでいた。相棒としていた仲間が頭を弾丸で粉砕されたのを目の前で見てから気がおかしくなった。
精神安定剤を1日1回は服用するのだが、それを敵兵の目玉だの敵兵の脳みそだの言いながら飲み込む。
敵兵を食い殺しているという錯覚がこいつを生かしていたと言ってもいいのだろう。
ヨアヒムはひとしきりオレで遊び倒すと満足したようで、ルキアは戦場に食糧を届ける手伝いをしていた近くの町娘と恋に落ちたらしい。
自分で言うのも何だが、オレはルキアとは親しい友人同士だと思っていた。戦場におけるルキアへの信頼も厚かった。
相手も、同じように接してくれたし、そう思ってくれているものだと勝手に考えていた。
だから正直ショックではあった。だが何か理由があるのだろうと思い、タイミングを伺っていた。
「戦争が終わって、落ち着いた時に話そうとでも思っていたのか?なんですぐ教えてくれなかったんだ。」
残念ながら戦争は2年以上続いているし、終わる気配もない。
オレ達が今こうして平穏に会話をしているのは、戦場に戻れないくらい大きな負傷をしたからだ。
ここは街の大病院。オレとルキアは同じ作戦で負傷して奇跡的に生還した。現状は負傷兵の扱いになるが、いずれ退役命令がくだるだろう。
ルキアは神妙な面持ちでオレのことを見つめていた。そして重たげな口を開いた。
「恥ずかしかったんだよ。」
「…は?」
まったく予想していない言葉だった。
「彼女のことを考えてウキウキしている自分の姿を見られたくなかったんだよ。」
そこまで言ってルキアは腕を組み俯いてしまった。オレはこらえきれず大笑いしてしまう。
「そうか、相部屋だから言いたくなかったんだな。けど、残念だったな。オレはお前が時折ほくそ笑んでいるのを知っていたぜ。」
「…!!!!!」
こんなやりとりをして、何も面白い事はないはずなのに、楽しくて仕方がない。
だから独りでは生きていかれない、そう思う。
オレの左顔半分は包帯で覆われている。砲撃で飛び散った瓦礫の破片や炎を受けてぐちゃぐちゃになってしまったからだ。
左腕は切断した。火傷があまりにも酷く腐り始めていたからだと聞かされた。
こんな姿になっても、友人として接してくれるルキアには感謝している。
オレにとっては、こうして馬鹿みたいに笑ったり、時に泣いたりできる空間や時間が幸福そのものなのだろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
